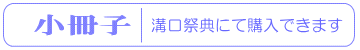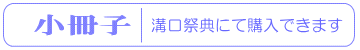丂偙偡傕偡僙儈僫乕摿暿島墘丂乲戞俀廤乴
丂丂惗偲巰偺幚憡偵偮偄偰
丂丂丂丂乕丂巹偨偪偼側傫偺偨傔偵惗傑傟偰偔傞偺偐丂乕
丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 晲丂杮丂徆丂嶰
丂丂丂The Illuminating Truth of Our Life and Death
丂丂丂丂丂乕Why Did We Come into This World?乕
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂by Shozo Takemoto
丂丂丂 恖偑恖惗偱捈柺偡傞偁傝偲偁傜備傞崲擄丄帋楙丄嬯擄丄
丂丂埆柌丄憆幐側偳傪丄懡偔偺恖偼偄傑偩偵庺偄偩偲偐恄偺
丂丂壓偟偨敱偩偲偐丄壗偐斲掕揑側傕偺偲峫偊偰偄傞傛偆偱偡丅
丂丂偱傕杮摉偼丄帺暘偺恎偵婲偙傞偙偲偱斲掕揑側傕偺偼傂偲
丂丂偮傕偁傝傑偣傫丅
丂丂丂 偁側偨偑宱尡偡傞帋楙丄嬯擄丄憆幐側偳丄偁側偨偑乽傕
丂丂偟偙傟傎偳偺嬯偟傒偩偲抦偭偰偄偨傜丄偲偰傕惗偒傞婥偵偼
丂丂側傟側偐偭偨偩傠偆乿偲偄偆傛偆側偙偲偼偡傋偰丄偁側偨傊
丂丂偺恄偐傜偺憽傝暔側偺偱偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乕丂僄儕僓儀僗丒僉儏僽儔乕丒儘僗丂乕
丂丂丂丂偼丂偠丂傔丂偵
丂 嶐擭乮堦嬨嬨敧擭乯偺偙偡傕偡僙儈僫乕島墘廤乽偄偺偪傪帨偟傒柧擔偵岦偐偭偰惗偒傞乿偼丄岾偄岲昡傪摼偰丄懡偔偺曽乆偵撉傫偱偄偨偩偔偙偲偑偱偒傑偟偨丅敪峴尦偺峚岥嵳揟偺曽傊傕丄偄傠偄傠偲偍楃偺偙偲偽偑撏偗傜傟偰丄挊幰偲偟偰傕偙偺彫嶜巕偑彮偟偱傕偍栶偵棫偭偨偙偲傪丄戝曄桳傝擄偔巚偭偰偄傑偟偨丅側偐偵偼丄嶐擭偺島墘夛偱巹偺榖傪挳偒丄島墘廤傪偍撉傒偔偩偝偭偨屻丄昦婥偱偍朣偔側傝偵側偭偨曽傕偍傜傟傑偡丅偍朣偔側傝偵側傞慜偵丄乽偙偺島墘廤傪撉傫偩偍偐偘偱埨怱偟偰巰偸偙偲偑偱偒傞乿偲巹偵懳偡傞幱堄傪楻傜偝傟偨偲偄偆偍榖傕偍巉偄偟偰丄巹偼堦弖惡傪幐偄丄偨偩恎偺堷偒掲傑傞傛偆側婥偑偄偨偟傑偟偨丅
丂 摨偠傛偆側偙偲偑丄嵟嬤丄巹偺偐側傝恎嬤側偲偙傠偱傕偁傝傑偟偨丅巹偺挿彈偺壟偓愭偺恊愂偵丄戝扟偝傫偲偄偆敧堦嵨偺曽偑偍傜傟傑偟偨丅崱擭偺惓寧偵挿彈偺壠偱怴擭夛偑偁傝丄偦偺帪偵椬傝崌傢偣偵嵗偭偰偄傠偄傠偲偍榖偟傪偍巉偄偟偨偺偱偡偑丄戝扟偝傫偼偛帺暘偑娻偵偐偐偭偰偍傝丄偁傑傝挿偔惗偒傜傟側偄偙偲傪妎偭偰偍傜傟偨傛偆偱偡丅偦偺戝扟偝傫偼巹偵丄乽愭惗偺島墘廤傪壗搙傕撉傑偣偰偄偨偩偄偰丄巰偸偺偑晐偔側偔側傝傑偟偨乿偲尵偭偰偔偩偝偄傑偟偨丅偦偟偰丄偦偺屻擖堾偝傟丄婥忎側摤昦惗妶傪懕偗傜傟偰丄弔巐寧丄嶗偺壴偺嶇偒巒傔偨偙傠丄壐傗偐偵楈奅傊偲椃棫偨傟偨偺偱偡丅巹偺帹偵偼崱傕丄惓寧偵暦偄偨戝扟偝傫偺偙偲偽偑從偒晅偄偰偄傑偡丅偦偺偙偲偽傪巚偄弌偡搙偵丄巹偼丄巚傢偢庤傪崌傢偣偨偔側傞傛偆側尩弆側婥帩偪偵側傝傑偡丅
丂 巹偼丄偙偺彫嶜巕偺側偐偱丄恖娫偼巰傫偱傕巰側側偄偙偲丄巰傫偱傕傑偨惗傑傟曄傢傞偙偲丄偄偺偪偼塱墦偱偁傞偙偲丄側偳傪壢妛幰傗尋媶幰偺尋媶惉壥傪徯夘偟側偑傜丄巹側傝偵椺徹偟偰偒傑偟偨丅偦偺巹偺彂偄偨傕偺偑丄巰傪寎偊傛偆偲偡傞曽乆偵傕偙偺傛偆側偐偨偪偱塭嬁傪梌偊偨偺偱偁傟偽丄巹偼柤忬偟偑偨偄弒尩側姶奡偵懪偨傟傞堦曽偱丄偳偆怽偟忋偘偨傜傛傠偟偄偺偱偟傚偆偐丄壗偐戝偒側廳偄愑擟偺傛偆側傕偺傕姶偠偞傞傪偊側偄偺偱偡丅乽偍傑偊偺尵偭偰偄傞偙偲丄彂偄偰偒偨偙偲偼丄杮摉偵偦傟偱傛偄偺偐丄懡偔偺曽乆傪榝傢偟偰偄傞偙偲偵偼側傜側偄偺偐乿偲丄偮偄丄帺傜偵栤偄偐偗偰傒偨傝傕偄偨偟傑偡丅
丂偦偺傛偆側巹偺摢偺側偐偵偼丄偐偮偰偼丄弶婜僉儕僗僩嫵偺偁偔側偒敆奞幰偱偁偭偨僷僂儘偺偙偲偽偑巚偄弌偝傟傑偡丅僷僂儘偼惗慜偺僀僄僗偵偼夛偭偰偄傑偣傫偱偟偨丅僀僄僗偺巰屻傕憹偊偮偯偗傞怣搆偨偪傪嫼敆丄嶦奞偟傛偆偲偟偰丄僄儖僒儗儉偐傜僟儅僗僐傊岦偐偭偰偄偨僷僂儘偼丄摴傪媫偄偱僟儅僗僐偺嬤偔偵棃偨偲偒丄撍慠丄揤偐傜偺岝偵懪偨傟偰搢傟傑偟偨丅偦偟偰丄乽傢偨偟偼偁側偨偑敆奞偟偰偄傞僀僄僗偱偁傞丅偁側偨偼側偤傢偨偟傪敆奞偡傞偺偐乿偲偄偆揤偐傜偺僀僄僗偺惡傪暦偒傑偡乮巊搆峴揱丒嬨復乯丅偦傟傪宊婡偵丄斵偺惗偒曽偼堦敧乑搙曄傢傝傑偟偨丅偐偭偰偺敆奞幰偼丄崱搙偼擬楏側僉儕僗僩嫵搆偵側傝丄僉儕僗僩嫵偺揱摴偵堦惗傪曺偘偰丄嵟崅偺揱摴幰偲偄傢傟傞傑偱偵側偭偨偺偱偡丅偦偺僷僂儘偑丄乽巰恖偺傛傒偑偊傝乿偵偮偄偰弎傋偨丄偮偓偺傛偆側偙偲偽偑偁傝傑偡丅
丂丂偟偐偟丄偁傞恖偼尵偆偩傠偆丅乽偳傫側傆偆偵偟偰丄巰恖偑傛傒偑偊傞偺偐丅偳傫側偐傜偩傪偟偰棃傞偺偐乿丅偍傠偐側恖偱偁傞丅偁側偨偺傑偔傕偺偼丄巰側側偗傟偽丄惗偐偝傟側偄偱偼側偄偐丅丒丒丒巰恖偺暅妶傕丄傑偨摨條偱偁傞丅媭偪傞傕偺偱傑偐傟丄媭偪側偄傕偺偵傛傒偑偊傝丄斱偟偄傕偺偱傑偐傟丄塰岝偁傞傕偺偵傛傒偑偊傝丄庛偄傕偺偱傑偐傟丄嫮偄傕偺偵傛傒偑偊傝丄擏偺偐傜偩偱傑偐傟丄楈偺偐傜偩偱傛傒偑偊傞偺偱偁傞丅擏偺偐傜偩偑偁傞偺偩偐傜丄楈偺偐傜偩傕偁傞傢偗偱偁傞丅
丂丂丒丒丒偝偰丄僉儕僗僩偼巰恖偺拞偐傜傛傒偑偊偭偨偺偩偲愰傋揱偊傜傟偰偄傞偺偵丄偁側偨偑偨偺拞偺偁傞幰偑丄巰恖偺暅妶側偳偼側偄偲尵偭偰偄傞偺偼丄偳偆偟偨偙偲偐丅傕偟巰恖偺暅妶偑側偄側傜偽丄僉儕僗僩傕傛傒偑偊傜側偐偭偨偱偁傠偆丅傕偟僉儕僗僩偑傛傒偑偊傜側偐偭偨偲偟偨傜丄傢偨偟偨偪偺愰嫵偼傓側偟偔丄偁側偨偑偨偺怣嬄傕傑偨傓側偟偄丅偡傞偲丄傢偨偟偨偪偼恄偵偦傓偔婾徹恖偵偝偊側傞傢偗偩丅側偤側傜丄枩堦巰恖偑傛傒偑偊傜側偄偲偟偨傜丄傢偨偟偨偪偼恄偑幚嵺偵傛傒偑偊傜偣側偐偭偨偼偢偺僉儕僗僩傪丄傛傒偑偊傜偣偨偲尵偭偰丄恄偵斀偡傞偁偐偟傪棫偰偨偙偲偵側傞偐傜偱偁傞丅(僐儕儞僩恖傊偺戞堦偺庤巻丒堦屲復)丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
丂 巹偼丄僉儕僗僩嫵搆偱偼偁傝傑偣傫偟丄傑偩怣嬄傕愺偔丄暓嫵搆偲傕偄偊傑偣傫偑丄偙偺乽巰恖偺暅妶偑杮摉偵側偄偺偱偁傟偽丄傢偨偟偨偪偼恄偵偦傓偔婾徹恖偵偝偊側偭偰偟傑偆乿偲偄偆僷僂儘偺偙偲偽偵偼丄嫮偔偙偙傠傪懪偨傟傑偡丅僷僂儘偼丄帺暘偺懱尡傪捠偟偰傕丄僉儕僗僩偺傛傒偑偊傝傪丄怣偢傞偲偄偆傛傝抦偭偰偄傑偟偨偐傜丄晄摦偺怣擮偱丄偙偺偙偲偽傪弎傋偨偺偱偟傚偆丅崱夞偺偍榖偼丄偙偺僷僂儘偺偙偲偽傪巚偄婲偙偟側偑傜丄偙偺傛偆側怣嬄偺嫮偝偵偮偄偰峫偊偰傒傞偙偲偐傜丄巒傔偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂 堦 丂怣偠傞偲偄偆偙偲
丂 僀僄僗偼丄僑儖僑僞偺媢偱廫帤壦偵偐偐偭偨屻丄梊尵偳偍傝偵暅妶偟偰丄掜巕偨偪偺慜偵尰傟傑偡丅偟偐偟丄堦擇掜巕偺堦恖偺僩儅僗偼丄偨傑偨傑僀僄僗偑巔傪尰偟偨帪偵偼丄偦偺応偵嫃傑偣傫偱偟偨丅傎偐偺掜巕偨偪偑丄暅妶偟偨僀僄僗偵夛偭偨偙偲傪姶寖偟偰揱偊傞偲丄僩儅僗偼丄乽傢偨偟偼丄偦偺庤偵揃偁偲傪尒丄傢偨偟偺巜傪偦偺揃偁偲偵偝偟擖傟丄傑偨傢偨偟偺庤傪偦偺傢偒偵偝偟擖傟偰傒側偗傟偽丄寛偟偰怣偠側偄乿偲尵偭偨偺偱偡丅峫偊偰傒傟偽柍棟偺側偄偙偲偐傕偟傟傑偣傫丅怺偔僀僄僗傪懜宧偟偰偄偨掜巕偨偪傕丄僀僄僗偑廫帤壦偵壦偗傜傟偨偲偒偵偼丄帺暘偨偪傕曔傜偊傜傟傞偙偲傪嫲傟偰丄傎偲傫偳偑摝偘塀傟偰偄傑偟偨丅廫帤壦偵壦偗傜傟丄嶰擔屻偵偼傛傒偑偊傞偲偄偆梊尵傪僀僄僗帺恎偐傜暦偄偰偼偄偰傕丄偼偠傔偼扤傕丄偦傟傪怣偠傜傟側偐偭偨偺偱偡丅
丂 暅妶偟偨僀僄僗偼丄偟偐偟丄傑偨掜巕偨偪偺慜偵尰傟傑偡丅崱搙偼丄僩儅僗傕偄傑偟偨丅僀僄僗偼僩儅僗偵尵偄傑偡丅乽偁側偨偺巜傪偙偙偵偮偗偰丄傢偨偟偺庤傪尒側偝偄丅庤傪偺偽偟偰傢偨偟偺傢偒偵偝偟擖傟偰傒側偝偄丅怣偠側偄幰偵側傜側偄偱丄怣偠傞幰偵側傝側偝偄乿偲丅僩儅僗偼丄傕偆偙偲偽傕偁傝傑偣傫丅偨偩堌傟偍偺偺偄偰丄乽傢偑庡傛丄傢偑恄傛乿偲尵偆偺偑惛堦攖偱偟偨丅偦偺斵偵岦偐偭偰丄僀僄僗偼乽偁側偨偼傢偨偟傪尒偨偺偱怣偠偨偺偐丅尒側偄偱怣偠傞幰偼偝偄傢偄偱偁傞乿偲桪偟偔桜偟偨偙偲傪丄惞彂偼彂偒婰偟偰偄傑偡丅乮儓僴僱丒擇乑復乯
丂 偙偺丄怣偠傞偐怣偠側偄偐偲偄偆偙偲偼丄巹偵偲偭偰傕丄惗偒墑傃偰偄偔忋偱偺偒傢傔偰愗幚側栤戣偱偟偨丅
丂 慜夞偺島墘偱偍榖偟偟傑偟偨傛偆偵丄巹偼堦嬨敧嶰擭嬨寧堦擔偺戝娯峲嬻婡帠審偱丄傾儊儕僇偐傜婣傞搑拞偺嵢偲挿抝傪朣偔偟偰偐傜丄懾嵼拞偺僲乕僗丒僇儘儔僀僫偱戝妛偺嫵抎偵棫偮偙偲傕偱偒偢偵擔杮傊堷偒曉偟丄偟偽傜偔偼怮偨偒傝偺昦恖偺傛偆側忬懺偱壗偐寧偐傪夁偛偟傑偟偨丅側偡偙偲傕側偔偍宱傪彞偊偰偄傞偲丄偦偺傛偆側帺暘偑偁傑傝偵傕嶴傔偱丄偮偄媰偄偰偟傑偭偨傝傕偟傑偟偨丅堦擭偑夁偓丄擇擭偑夁偓偰傕丄巹偼傑偩怺偄埮偺側偐偱欙嬦偟偰偄偨傛偆偵巚偄傑偡丅傗偑偰巹偼丄偙偺傛偆側惞彂傗暓揟側偳傪丄榤偵傕偡偑傞傛偆側婥帩偪偱撉傒巒傔傞傛偆偵側傝傑偡丅
丂 巹偼丄嵢偲挿抝偑偄側偔側偭偰偟傑偭偨偙偲偑丄偳偆偟偰傕彸暈偱偒傑偣傫偱偟偨丅嵢偲挿抝偑巰傫偩偲偄偆偙偲偼偳偆偄偆偙偲偐丅偦傕偦傕丄偄偺偪偲偼壗偐丅巹偨偪偼偄偭偨偄偳偙偐傜棃偨偺偐丅偦偟偰丄巰偲偼壗偐丅惗傪廔偊偰偐傜偼偳偙傊峴偔偺偐丅偄傗偱傕偦傟傜偺栤戣偵岦偒崌傢偞傞傪偊側偐偭偨偺偱偡丅偄偔傜峫偊偰傕傛偔傢偐傝傑偣傫丅偟偐偟丄峫偊傞偺傪傗傔傞偙偲偼弌棃傑偣傫丅傢偐傜側偄側傝偵丄擸傒偮偮丄嬯偟傒偮偮丄峫偊偰偄偔偆偪偵丄傆偲丄柍柧偺埮偵嵎偟崬傓偐偡偐側岝傪姶偠傞偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦傟偑丄偨偲偊偽丄慜夞傕堷梡偟傑偟偨偑丄亀扸堎彺亁戞屲抜偺傛偆側暥偵弌夛偭偨傛偆側偲偒偱偡丅
丂 晝曣偲偄偆偺偼丄帺暘偺晝曣偩偗偑晝曣側偺偱偼側偄丅恖娫偼壗搙傕壗搙傕惗傑傟曄傢傞偐傜丄惗偒偲偟惗偗傞傕偺偼丄傒傫側偄偮偐偺悽偱丄晝曣偱偁傝孼掜偱偁偭偨丅偩偐傜丄恊阛偼丄擮暓傪彞偊傞応崌偱傕丄尰悽偺帺暘偺晝曣偩偗偵懳偡傞岶梴偺偮傕傝偱偲側偊偨偙偲偼堦搙傕側偄丄偲偄偆偺偱偡丅
丂 恖娫偺偄偺偪偲偄偆偺偼丄偄傑惗偒偰偄傞娫偑偡傋偰偱丄巰傫偩傜偦傟偑嵟屻偩偲巚偭偰偄傞偺偲丄偄偺偪偼塱墦偵懕偄偰丄恖娫偼孞傝曉偟惗傑傟曄傢傞偺偩偲偄偆偺偱偼丄戝曄側堘偄偱偡丅偦偟偰丄偄偺偪偑塱墦偵懕偔偲偄偆偺偑杮摉偱偁傟偽丄偦傟偼丄戝偒側媬偄偱偡丅偟偐傕丄巰傫偩屻偼丄嬌妝偲偐忩搚傊偲堏傝廧傓偙偲偵側傝丄偦偺嬌妝丒忩搚偑岝偵曪傑傟偨憇楉側娊婌偺悽奅偱偁傞偲偡傞側傜偽丄巰偸偙偲偼斶偟傒偱偼側偔偰丄婌傃偱側偔偰偼側傝傑偣傫丅杮摉偵丄楈奅偲偐嬌妝丒忩搚偼偁傞偺偱偟傚偆偐丅
丂 偙偺慺杙側媈栤偵偮偄偰傕丄亀扸堎彺亁偺拞偱偼傆傟傜傟偰偄傞売強偑偁傝傑偡丅亀扸堎彺亁偺戞嬨抜偱偼丄掜巕偺桞墌偑丄恊阛偵丄乽偄偔傜擮暓傪偲側偊偰偄偰傕丄偳偆傕揤偵晳偄抧偵梮傞偲偄偆傛偆側慡恎偺婌傃偑姶偠傜傟傑偣傫丅偦傟偵丄恀幚偺妝墍偱偁傞偼偢偺忩搚傊傕丄憗偔峴偒偨偄偲偄偆婥帩偪偑婲偙傜側偄偺偼偳偆偟偰偱偟傚偆乿偲丄棪捈偵暦偄偨偺偱偡丅恊阛傕偦傟偵懳偟偰棪捈偵摎偊傑偟偨丅乽幚偼巹傕偦偺偙偲傪晄巚媍偵巚偭偰偄偨偺偩偑丄偦側偨傕摨偠偱偁偭偨偐乿偲丅偦偟偰丄偮偓偺傛偆偵帺暘偺峫偊傪弎傋偰偄傑偡丅
丂丂偼傞偐墦偄愄偐傜崱擔偵帄傞傑偱丄惗巰傪孞傝曉偟偰偒偨偙偺柪偄偺悽奅偼幪偰偑偨偔丄傑偩尒偨偙偲傕側偄嬌妝忩搚偼楒偟偔側偄偲偄偆偺偼丄杮摉偵傛偔傛偔斚擸偼嫮偄傕偺偵偪偑偄側偄丅偗傟偳傕丄偄偔傜柤巆惿偟偄偲巚偭偰傕丄偙偺悽偲偺墢偑愗傟丄惷偐偵惗柦偺摂偑徚偊傞帪偼丄偁偺忩搚傊峴偐偞傞傪偊側偔側傞丅暓偼丄媫偄偱忩搚傊峴偒偨偄偲巚偆偙偲偺弌棃側偄幰傪偙偲偺傎偐楓傟傫偱壓偝偭偰偄傞偺偩丅偦偆偱偁傟偽側偍偝傜丄戝帨戝斶偺暓偺杮婅偑棅傕偟偔丄墲惗偼娫堘偄側偄偲怣偠傜傟傞丅媡偵傕偟丄揤偵晳偄抧偵梮傞婌傃偑偁傝丄媫偄偱忩搚傊峴偒偨偄偲偄偆偺偱偁傟偽丄偦偺恖偵偼斚擸偼側偄偺偱偁傠偆偐偲丄偐偊偭偰偆偨偑傢偟偔巚傢傟偰偟傑偆偺偩乿丅
丂 巹偼丄偙偆偄偆暥復偵彮偟偢偮丄栚傪奐偄偰偄偔傛偆偵側傝傑偟偨丅偄傑丄帺暘偑廧傫偱偄傞偙偺嬯偟傒偺懡偄丄柪偄偺悽奅偵幏拝偟偰丄偁傟傎偳偡偽傜偟偄嬌妝丒忩搚傊傕偡偖偵峴偒偨偄偲巚傢側偄偺偼丄偦傟傎偳恖娫偺傕偭偰偄傞斚擸偑嫮偄偐傜偩丄偲偄偆傛偆側尵偄曽偵傕丄偦傟側傝偵彮偟偢偮丄棟夝偱偒傞傛偆側婥偑偟偰偒偨偺偱偡丅
丂 傓偐偟巹偑尒偨偁傞奜崙塮夋偺堦偮偺僔乕儞偵偮偓偺傛偆側傕偺偑偁傝傑偟偨丅儓乕儘僢僷偺偳偙偐偺娔崠偱丄堦恖偺廁恖偑丄嶰乑擭傕巐乑擭傕撈朳偵暵偠偙傔傜傟偰傛傏傛傏偺榁恖偵側偭偰偟傑偄傑偡丅榁恖偼丄撈朳偺崅偄彫偝側揤憢偐傜嵎偟崬傓岝傪嬄偄偱偼丄娔崠偺奜偺帺桼傊偺偁偙偑傟傪曞傜偣偰偄傑偟偨丅
丂 戞擇師悽奅戝愴偺枛婜偩偭偨偱偟傚偆偐丄偦偺娔崠傕偁傞擔丄寖偟偄嬻敋傪庴偗偰丄崅偄暬傕婃忎側寶暔傕曵傟棊偪偰偟傑偄傑偡丅偦偺撈朳偺榁恖偼惗偒墑傃偰丄姠釯偺側偐偐傜攪偄弌偟偰偒傑偟偨丅偦偟偰丄傛傠傛傠偲奜傊岦偐偭偰曕偒巒傔傑偡丅偟偽傜偔曕偄偰怳傝曉傝傑偡偑丄扤傕捛偭偰偔傞條巕傕偁傝傑偣傫丅栚偺慜偵偼丄峀乆偲偟偨栰尨偑峀偑偭偰偄傑偡丅偦傟偼丄榁恖偑挿偄擭寧偁偙偑傟偰偒偨帺桼偺悽奅偺偼偢偱偟偨丅榁恖偼丄傑偨彮偟傛傠傛傠偲曕偒懕偗傑偡丅偟偐偟丄偦偙偱棫偪巭傑偭偰偟傑偆偺偱偡丅傗偑偰榁恖偼丄傑偨傛傠傛傠偲丄曵傟棊偪偨娔崠傊婣偭偰峴偒傑偟偨丅
丂 帺桼偑懇敍偝傟偰傕丄屒撈偺嬯偟傒偑偁偭偰傕丄偁傑傝偵傕挿偄擭寧偦傟偵姷傜偝傟偰偟傑偄傑偡偲丄傕偆偦偙偐傜敳偗弌偡偙偲偝偊晄埨偵側偭偰偟傑偄傑偡丅忩搚丒嬌妝偑偄偐偵憇楉偱偡偽傜偟偄偲偙傠偱偁傞偲暦偐偝傟偰傕丄桞墌偑媈栤偵巚偭偨傛偆偵丄斚擸偺悽奅偵姷傟偒偭偰偟傑偆偲丄乽媫偄偱峴偒偨偄乿偲巚傢傟側偄偺傕丄柍棟偱偼側偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟丄偦傟偱偼丄偙偺斚擸偺悽奅偵惗偒偰偄傞尷傝丄埨怱棫柦偺嫬抧偵払偡傞偺偼擄偟偄偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偆偺偱偟傚偆偐丅怣怱偲偄偆偺偼丄偙偙偱栤戣偵側偭偰偔傞偺偩偲巚偄傑偡丅傑偨恊阛偵栠偭偰丄崱搙偼丄恊阛帺恎偺怣嬄偺偁傝傛偆傪傒偰傒傞偙偲偵偟傑偟傚偆丅
丂 偐偮偰恊阛偼丄忢棨偺崙乮偄傑偺堬忛導乯傪拞怱偵丄壓憤丄壓栰丄晲憼側偳偺娭搶彅崙偵丄懠椡杮婅偺擮暓傪愢偄偰傑傢偭偰偄偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦偺屻恊阛偼丄堦擇嶰屲擭丄榋嶰嵨偺崰丄娭搶傪嫀偭偰嫗搒偵婣偭偰偄偭偨偺偱偡偑丄巆偝傟偨娭搶偺怣搆偨偪偺娫偵偼丄傗偑偰怣嬄偵懳偡傞峫偊曽偺堘偄偐傜惓摑攈偲堎媊攈偵暘偐傟偰懳棫偡傞傛偆偵側偭偰偄偒傑偡丅偦偙偱丄怣怱偵柪偄傪棃偟偨恖偨偪偑丄偁傜偨傔偰恊阛偐傜捈愙偵嫵偊傪庴偗傞偨傔丄忢棨偺崙偐傜搶奀摴廫梋偐崙傪偼傞偽傞偲墇偊偰丄嫗搒傊岦偐偭偨偺偱偡丅
丂 搶奀摴偲偄偭偰傕丄姍憅帪戙偺偙偲偱偡偐傜丄峕屗帪戙偺搶奀摴屲廫嶰師側偳傛傝傛傎偳晄曋偱丄婋尟傕懡偐偭偨偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅偦偺柦偑偗偺椃傪偟偰傗偭偰偒偨怣搆偨偪傪慜偵偟偰丄恊阛偼丄乽偁側偨曽偼丄巹偑擮暓埲奜偵墲惗嬌妝傊偺摴傪抦偭偰偄傞偩傠偆偲偐丄偄傠偄傠偲宱揟埲奜偺嫵偊偵傕捠偠偰偄傞偩傠偆偲偐彑庤偵峫偊偰偄傞傛偆偩偑丄偦傟偼偲傫偱傕側偄岆傝偱偁傞乿偲愗傝弌偟傑偟偨丅偦偟偰偦偺屻偱丄恊阛偼棪捈偵偟偐偟嫮偄偙偲偽偱丄帺暘帺恎偺擖怣偺偄偒偝偮傪崘敀偡傞偺偱偡丅乽巹偼偨偩丄擮暓傪偲側偊偰垻栱懮暓偵彆偗偰偄偨偩偔偩偗偩偲丄朄慠忋恖偵嫵偊偰偄偨偩偄偨偙偲傪怣偠傞偺傒偱偁傞丅偦偺傎偐偼側偵傕側偄丅擮暓傪偲側偊傟偽杮摉偵忩搚偵峴偗傞偺偐丄偦傟偲傕抧崠偵懧偪傞偺偐丄偦傫側偙偲傕偳偆偱傕傛偄丅偐傝偵丄朄慠忋恖偵閤偝傟偰丄擮暓偟偨偁偘偔偵抧崠偵懧偪偨偲偟偰傕丄巹偼寛偟偰屻夨偼偟側偄偱偁傠偆乿偲丅
丂 偙傟偼偢偄傇傫巚偄愗偭偨尵偄曽偩偲巚偄傑偡丅娭搶偐傜偼傞偽傞柦偑偗偺椃傪懕偗偰傗偭偰偒偨怣搆偨偪偼丄偄傑屌懥傪偺傫偱恊阛偺婄傪尒庣偭偰偄傑偡丅偙偺嬞敆偟偨暤埻婥偺拞偱丄恊阛偼丄愒棁乆側帺暘帺恎偺巔傪偝傜偗弌偟偰丄怣擮傪斺鄉偟側偗傟偽側傝傑偣傫偱偟偨丅偟偐偟偙傟偼丄傑偐傝娫堘偊偽巘偲偟偰偺怣傪幐偄偐偹偢丄暓摴偺嫵偊偵傕媈栤傪書偐偣傞偙偲偵傕側傝偐偹側偄偙偲偽偱偡丅偦偺傛偆側偙偲偽傪丄妋屌偨傞怣嬄偺徹偲偟偰怣搆偺偙偙傠偵捈嵸偵偟傒偙傑偣偰偄偭偨偺偼丄偍偦傜偔恊阛偺偦偺帪偺婥敆偱偁偭偨偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅
丂 恊阛偼偝傜偵懕偗傑偡丅乽偦偺傢偗偼丄擮暓傛傝傎偐偺廋嬈偵椼傫偱屽傝傪奐偗傞偼偢偱偁偭偨偺偵丄擮暓偵懪偪崬傫偩偨傔偵抧崠偵懧偪偨偲偄偆偺側傜丄偦偺帪偼丄巘偵閤偝傟偨丄偲偄偆屻夨傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄巹偼偳偺傛偆側廋嬈傕偱偒側偄恎偩偐傜丄偳偆偣巹偵偼抧崠偑偼偠傔偐傜掕傔傜傟偨峴偒応強側偺偩乿偲丅偦偟偰丄嵟屻傪偮偓偺傛偆偵寢傃傑偟偨丅乽垻栱懮暓偺杮婅偑恀幚偱偁傞側傜偽丄庍懜偺嫵偊偵傕塕偼側偄丅庍懜偺嫵偊偑恀幚偱偁傞側傜丄慞摫戝巘偺偍愢偒偵側偭偨偙偲偵傕岆傝偼側偄丅慞摫戝巘偺偍愢偒偵側偭偨偙偲偑恀幚偱偁傞側傜丄偳偆偟偰丄朄慠忋恖偺尵傢傟傞偙偲偑嫊尵偱偁傝偊傛偆偐丅偦偟偰傑偨丄朄慠忋恖偺尵傢傟傞偙偲偑恀幚偱偁傟偽丄偙偺恊阛偺尵偆偙偲傕嬻尵偱偁傞偼偢偑側偄丅偙傟偑偮傑傝丄巹偺怣怱側偺偩丅偙偺忋偼丄擮暓傪怣偠傛偆偑丄幪偰傛偆偑丄偦傟偼偁側偨曽偺彑庤偱偁傞乿丅
丂 偙傟偑丄怣嬄偲偼偙偆偄偆傕偺偩偲丄恊阛偑寣傪揻偔傛偆側偙偲偽偱弎傋偨傑偛偙傠偐傜偺崘敀偱偟偨丅
丂擇丂丂楈奅偐傜偺儊僢僙乕僕
丂帠審偺偁偲嶥杫偱丄巹偑嵢偺桭恖偱偁偭偨楈擻幰偺惵栘偝傫傪朘偹偰丄斵彈偑巹偺挿抝偺寜揟偲岎傢偟偨夛榖偵偮偄偰暦偐偝傟偨偙偲偼丄慜夞偺島墘偱偍榖偟偟傑偟偨丅乽偁傝偑偲偆丒丒丒妝偟偐偭偨丒丒丒崱傑偱偺惗妶偑偡傋偰丒丒丒丒乿偲偄偆斵彈傊偺摎偊偑丄捈姶揑偵寜揟偺偙偲偽偩偲傢偐偭偰丄巹偼椳傪傐傠傐傠偲偙傏偟傑偟偨偑丄偦偺帪偼丄杮摉偵晄巚媍偱偟偨丅偦傫側偙偲偑杮摉偵偁傝摼傞偺偩傠偆偐偲丄屗榝偄傑偟偨丅偟偐偟丄偦偺屻壗搙傕丄偙偺傛偆側楈奅偐傜偺偙偲偽傪暦偄偰偄傞偆偪偵丄彮偟偢偮傢偐偭偰偒偨偺偱偡丅楈奅偐傜偺偙偲偽偼丄巹偵偲偭偰傕丄偩傫偩傫偲晄巚媍偱偼側偔側偭偰偄偒傑偟偨丅偄傑偱偼丄偦傟偑帠幚偱偁傞偙偲傪丄巹偼乽抦偭偰乿偄傑偡丅
丂 堦嬨嬨擇擭擇寧堦堦擔偼丄巹偵偲偭偰朰傟傞偙偲偺弌棃側偄婰擮偺擔偱偡丅偦偺帪丄巹偼僀僊儕僗偺儘儞僪儞偵偄傑偟偨丅慜擭偺巐寧偐傜丄儘儞僪儞戝妛偺媞堳嫵庼偲偟偰僀僊儕僗偵棃偰丄儘儞僪儞峹奜偺儘僠僃僗僞乕偲偄偆挰偵廧傫偱偄傑偟偨偑丄擔杮傊婣崙偡傞擔偑嬤偔側偭偰偐傜偼丄巹偼偐側傝昿斏偵丄儘儞僪儞偺戝塸怱楈嫤夛傊懌傪塣傇傛偆偵側偭偰偄傑偟偨丅戝塸怱楈嫤夛偲偄偆偺偼丄堦敧幍擇擭偺憂愝埲棃丄僀僊儕僗偺嶌壠僐僫儞丒僪僀儖傗挊柤側暔棟妛幰僆儕僶乕丒儘僢僕側偳丄懡悢偺柤巑偵傛偭偰巟偊傜傟偰偒偨悽奅揑偵桳柤側怱楈尋媶偺揳摪偱偡丅偙偺擔巹偼丄偙偺儘儞僪儞偺戝塸怱楈嫤夛偱丄楈奅偵偄傞挿抝偺寜揟偲乽嵞夛乿偡傞偙偲偑偱偒偨偺偱偡丅
丂 楈奅偐傜偺偙偲偽偵偄偔傜偐偼姷傟偰偄偨偲偼偄偊丄偙偺乽嵞夛乿偼巹偵偲偭偰偼戝曄側偙偲偱偟偨丅偦偺帪偺條巕傪丄巹偼嫮偄姶摦偲姶幱偺婥帩偪偺側偐偱丄偡偖偵搶嫗偵偄偨挿彈傊抦傜偣傑偟偨偑丄偦偺帪偺庤巻偵丄巹偼師偺傛偆偵彂偒傑偟偨丅偙傟偼傕偪傠傫丄傒側偝傫偵偍暦偒偄偨偩偔偙偲傪慡偔梊憐偟偰偄傑偣傫偱偟偨偺偱丄巹偛偲偺梾楍偵側偭偰嫲弅偱偡偑丄偁傝偺傑傑傪偍揱偊偡傞偨傔偵丄偁偊偰偦偺傑傑丄堦晹傪堷梡偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂丂擇寧堦堦擔偺峩帯廸晝偝傫偺柦擔偵偼丄嶥杫偱偼塸巕廸曣偝傫偺恊愂偺恖偨偪偑堦乑恖偔傜丂偄廤傑偭偰偔傟偨傜偟偄丅桳傝擄偄偙偲偩偲巚偭偰偄傞丅偍晝偝傫傕偙偪傜偱丄擔杮帪娫偵崌丂傢偣偰偍嫙偊傪偟丄偙偪傜偺堦堦擔偵偼丄儘儞僪儞偺戝塸怱楈嫤夛傊峴偭偨丅偄傑傑偱壗搙傕丄丂戝惃偺側偐偱偺岞奐幚尡偵嶲壛偟偰丄偍晝偝傫帺恎偑楈奅偐傜偺捠怣傪庴偗傞応崌偺弨旛傪偟丂偰偒偨偑丄嬤崰偼丄堦恖偱楈擻幰偺慜偵嵗偭偰丄堦懳堦偱捈愙榖傪挳偔傛偆偵側偭偰偄傞丅
丂丂堦堦擔偼峩帯廸晝偝傫偺柦擔偱傕偁傞偺偱丄偐偹偰偐傜丄偙偺擔傪梊栺偟偰偄偨丅楈擻幰偼丄傑偢儅儅偲寜揟偑楈奅偵偄傞偙偲傪尒敳偄偨丅偦傟偐傜丄乽偁側偨偺掜偝傫傕楈奅偵偄傑偡偹乿偲尵偭偨丅偦偺楈擻幰傾儞丒僞乕僫乕偵傛傟偽丄楈奅偱傕峩帯廸晝偝傫偺乽婰擮擔乿偵偍晝偝傫偑戝塸怱楈嫤夛偵棃偰恄柇偵嵗偭偰偄傞偲偄偆偺偱丄傒傫側偑廤傑偭偰偄偨傜偟偄丅峩帯廸晝偝傫偼丄偡偖偵弌偰偒偰丄偍晝偝傫偺墶偵棫偭偰偄偨傛偆偩丅偦偟偰丄寜揟偑弌偰偒偨丅丂寜揟偼偍晝偝傫偺慜偵棫偭偰丄旕忢偵姶摦偟偰偄傞條巕偩偲丄傾儞丒僞乕僫乕偑尵偭偰偄偨丅
丂丂偍晝偝傫偼丄偙偺楈擻幰偺傾儞丒僞乕僫乕偵戝塸怱楈嫤夛偱弶傔偰夛偭偰丄偦偺慜偵栙偭偰嵗偭偰偄傞偩偗偱丄傾儞丒僞乕僫乕偼偍晝偝傫偺偙偲偼壗傕抦傜側偄丅擔杮偐傜棃偰偄傞偙偲傕丄帠審偺偙偲傕丄壠懓偺偙偲傕丄斵彈偵偼堦愗尵偭偰偄側偄丅傾儞丒僞乕僫乕偼丄乽偁側偨偺慜偵棫偭偰偄傞偺偼偁側偨偺懅巕偝傫偱丄恎挿偼屲僼傿乕僩丒敧僀儞僠乮堦幍嶰僙儞僠乯偖丂傜偄丄憦柧側婄偮偒偵尒偊傞乿偲尵偆丅寜揟偺恎挿偼偦偺偔傜偄偩傠偆丅偟偐偟丄偦傟偩偗偱丂偼傑偩傛偔傢偐傜側偄偐傜丄偍晝偝傫偼栙偭偰偄偨丅傾儞丒僞乕僫乕偼丄傑偨尵偭偨丅乽懅巕偝傫偑丄帺暘偺柤慜偼丄僉儏僆乕僯偲偐僋儓乕僯偩偲柤忔偭偰偄傞乿丅偦偟偰丄壗搙偐丄乽僉丂儏乕僆乕僯丄僉儓乕僯丄僋儓乕僯乿偲撈傝尵傪尵偆傛偆偵偮傇傗偄偨丅
丂 偍晝偝傫偼丄偼偭偲偟偨丅偙傟偼寜揟偩丅寜揟偵堘偄側偄丅傎偐偺柤慜側傜偙偺傛偆偵暦偙偊傞偼偢偑側偄丅偟偐偟丄偦傟偱傕擮偺偨傔偵師偺傛偆偵暦偄偨丅
丂乽偦傟偼塸岅偺柤慜偐丠乿
丂乽偦偆偱偼側偄丄奜崙岅偺敪壒偱巹偵偼傛偔傢偐傜側偄偑丄偦偺傛偆偵暦偒庢傟傞偺偩乿
丂丂寜揟乮偒傛偺傝乯偲偄偆敪壒偼丄偨偟偐偵擔杮岅偵側傟偰偄側偄塸暷恖偵偼暦偒庢傝偵偔偄丅偙傟傪堦搙暦偄偰丄惓妋偵偔傝曉偡偙偲偺弌棃傞塸暷恖偼傎偲傫偳偄側偄偩傠偆丅偦偙偱偍晝偝傫偼丄巚偄愗偭偰暦偄偰傒偨丅
乽偦偺敪壒偼丄亀僉儓僲儕亁偲偼堘偆偐丠乿
丂斵彈偼摎偊偨丅
丂乽偦偆偩丄僉儓僲儕偩丅僉儓僲儕偲尵偭偰偄傞乿
丂 挿抝偺寜揟偺柤慜傪偙偺傛偆偵尵傢傟偨偙偲偼丄巹偵偲偭偰偼戝曄側偙偲偱偟偨丅巹偼丄柡偵偼偁傑傝嫮偄巋寖偵側傜偸傛偆偵丄堄恾揑偵丄偁傑傝姶忣傪崬傔偢偵扺乆偲偙偺庤巻傪彂偄偨偮傕傝側偺偱偡偑丄幚嵺偵偼丄巹偺怱偺拞偼寖偟偔梙傟摦偄偰偄傑偟偨丅帠審屻丄挿偄擭寧丄壗擭傕壗擭傕嬯偟傒懕偗偰偒偰丄偄傑弶傔偰丄堦偮偺戝偒側嶳傪墇偊傛偆偲偟偰偄傞丅偦偺傛偆側巚偄偑寖偟偔偙偙傠傪梙偝傇偭偰偄偨偺偱偡丅
丂 偙偺庤巻偼傑偩懕偒傑偡丅傕偆彮偟丄堷梡偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅
丂丂丒丒丒傑偨丄傾儞丒僞乕僫乕偼偮偓偺傛偆偵傕尵偭偨丅
丂乽懅巕偝傫偼丄偁側偨偺嵍懌偵 scar乮彎愓乯偑偁傞偲尵偭偰偄傞乿
偍晝偝傫偼丄偙偺傊傫偱偐側傝嬞挘偟偰偄偨丅尵偭偰偄傞偙偲偼傛偔傢偐偭偰偄偨偑丄嵍懌偵偼彎愓偼側偄丅偩偐傜乽巹偺嵍懌偵偼彎愓偼側偄乿偲丄棪捈偵摎偊偨丅側偤偦傫側偙偲傪尵偆偺偩傠偆偲丄晄怰偵傕巚偭偨丅偟偐偟丄傾儞丒僞乕僫乕偼嫰傑側偐偭偨丅乽偦傟偼屆偄彎愓偱丄傕偆徚偊偐偐偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅昁偢偁傞偼偢偩偐傜扵偟偰尒傛乿偲尵偆丅偄偔傜偦偆尵傢傟偰傕丄帺暘偺偙偲偼帺暘偑堦斣傛偔抦偭偰偄傞丅柍偄傕偺偼柍偄丄偲偍晝偝傫偼巚偭偨丅偦偙偱偪傚偭偲幐朷偟偰丄偦偺擔偺柺愙偼廔傢偭偨丅
丂 偦偺偁偲丄壠傊婣傞偨傔偵償傿僋僩儕傾墂偺曽傊備偭偔傝曕偒側偑傜丄撍慠偼偭偲偟偰棫偪巭傑偭偰偟傑偭偨丅傾儞丒僞乕僫乕偺乽scar乿偲偄偆偙偲偽偱丄偍晝偝傫偼偮偄丄恘暔偺彎愓偺傛偆側傕偺傪楢憐偟偰偟傑偭偨偺偩偑丄傗偗偳偺愓傕乽scar乿偱偼側偄偐丅偦傟側傜偍晝偝傫偵偼丄巕嫙偺帪偵丄搾偨傫傐偱傗偗偳偟偨彎愓偑戝偒偔偄傑傕偼偭偒傝偲巆偭偰偄傞丅偦傟傪抦偭偰偄傞幰偼丄寜揟傪娷傔偰壠懓偟偐偄側偄丅偨偩傂偲偮丄堘偭偰偄傞偺偼丄偦偺傗偗偳偺彎愓偼丄嵍懌偱偼側偔丄塃懌偩丅偟偐偟偙傟傕丄慜偵棫偭偰偄偨寜揟偐傜偼丄偍晝偝傫偺塃懌偼丄嵍懌偵側傞丅
丂 寜揟偼丄傗偼傝偁偺帪丄偍晝偝傫偺慜偵棫偭偰偄偨丅帺暘偺柤慜傪崘偘丄偍晝偝傫偺懌偺彎愓傪尵偄摉偰傞偙偲偱丄偦傟偑娫堘偄側偔寜揟偱偁傞偙偲傪堦惗寽柦偵偍晝偝傫偵慽偊傛偆偲偟偰偄偨偺偩丄怺偄姶摦傪婄偵昞偟側偑傜丅偍晝偝傫偑傗偭偲偙偙傑偱棃偰偔傟偨偙偲傪丄偦偟偰丄寜揟傗儅儅偑乽杮摉偵傑偩惗偒偰偄傞乿偺偩偲偄偆偙偲傪偍晝偝傫偑棟夝偟巒傔偨偺偑婐偟偐偭偨偺偩傠偆丅
丂帠審屻傑偩嶥杫偵偄偨偲偒丄惵栘偝傫傪捠偠偰偺楈尵偱丄寜揟偐傜乽偄偮傑偱傕尦婥偑側偄丒丒丒偍晝偝傫偼壗偱傕弌棃傞恖偱偼側偄偐乿偲尵傢傟偨偙偲偑偁傞丅偦偺偍晝偝傫偑傗偭偲偄傑丄彮偟偢偮棫偪捈偭偰偒偨丅壗傛傝傕丄寜揟傗儅儅偑尦婥偱惗偒偰偄傞偙偲偑傢偐偭偰丄偁偺傛偆偵寜揟傗儅儅偨偪偺慜偵嵗傞傛偆偵側偭偨丅偙傟偐傜偼丄傕偭偲傕偭偲乽懳榖乿偑偱偒傞傛偆偵側傞丅偩偐傜丄寜揟偼姶摦偟偰偄偨偺偱偁傠偆丅偍晝偝傫傕姶摦偟偰偄偨丅
丂 巹偺偙偲偼壗傕抦傜側偄弶懳柺偺僀僊儕僗恖偐傜丄傂偲偙偲傕巹傗壠懓偺偙偲偼榖偟偰偄側偄偺偵丄嵢傗挿抝偑楈奅偵偄偰丄挿抝偺柤慜偐傜巹偺懌偺彎愓偺偙偲傑偱崘偘傜傟傞丄偲偄偆傛偆側偙偲偼丄晛捠偱偼偁傝摼側偄偙偲偱偟傚偆丅偦傫側偙偲偑偁傟偽丄偦傟偼婏愓偲偟偐巚偊傑偣傫偑丄偦偺乽婏愓乿偑尰幚偵巹偵婲偙偭偨偺偱偡丅偦偺屻丄寜揟偲偼丄壗搙偐乽夛偄乿丄擇寧擇巐擔偺嵢偺抋惗擔偵偼丄嵢偲傕乽夛偄乿傑偟偨丅偦偟偰丄擔杮傊婣崙偟偰偐傜傕丄枅擭榋寧屲擔偺寜揟偺抋惗擔偵偼丄傾儞丒僞乕僫乕傪捠偠偰丄寜揟偲暥捠傕懕偗偰偒傑偟偨丅巹偵偼丄偙偺傛偆側嵢偲挿抝偲偺乽懳榖乿偑偄傑傕丄惗偒偰偄偔忋偱偺嫮偄偙偙傠偺巟偊偵側偭偰偄傑偡丅
丂 嶰 丂楈奅偲偼偳偆偄偆偲偙傠偐
丂 巹偺嵢偲挿抝偑丄楈奅偱尦婥偵曢傜偟偰偄傞偙偲傪巹偼抦偭偰偄傑偡偑丄楈奅偲偄偆偺偼丄慡懱偲偟偰偼丄偙偺抧忋偺惗妶偲斾傋傕偺偵側傜側偄傎偳丄柧傞偔桖偟偄偲偙傠偱偁傞傛偆偱偡丅偦偺楈奅偐傜偺捠怣偼丄墷暷傗擔杮偱婰榐偵巆偭偰偄傞偩偗偱傕偍傃偨偩偟偄検偵偺傏偭偰偄傑偡丅偦偟偰丄楈奅偑偡偽傜偟偄岝柧偺悽奅偱偁傞偙偲偼丄傎偲傫偳偺捠怣偑堦抳偟偰弎傋偰偄傞偲偄偭偰傛偄偱偟傚偆丅偩偄偨偄丄帡偨惈奿偺恖偨偪丄庯枴偺嫟捠偟偰偄傞恖偨偪丄摨偠傛偆側嵥擻傪帩偮恖偨偪偑婑傝廤傑偭偰丄擸傒傗嬯偟傒偲偼柍墢偺丄惗偒惗偒偲偟偨惗妶傪憲偭偰偍傝丄偄傑偝傜抧媴偺抧忋惗妶偵偼栠傝偨偔側偄偲峫偊偰偄傞恖偑傎偲傫偳偺傛偆偱偡丅
丂 慜夞偺島墘偱偼丄僐僫儞丒僪僀儖偑乽巰傫偱乿偐傜傕丄楈奅偐傜捠怣傪憲傝懕偗偨偍榖傪偟傑偟偨丅斵偼丄乽壗搙傕孞傝曉偟傑偡偑丄巹偨偪偼巰屻偺悽奅偱偄傑尰嵼丄惗偒偰偄傑偡丅偙傟傪杮摉偵恖椶偵棟夝偟偰傕傜偄偨偄偺偱偡乿偲尵偭偰偄傑偟偨丅偦偟偰丄懡偔偺楈奅捠怣傪憲偭偰偒傑偟偨偑丄偦偺側偐偵偼丄楈奅偺偙偲傪偮偓偺傛偆偵丄揱偊偰偄傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅丂丂
丂丂巹偼丄偙偲偽偵尵偄昞偡偙偲偺弌棃側偄傎偳旤偟偄悽奅偵偄傑偡丅偙偺尰幚傪丄抧忋偵偄傞巹偺桭恖偨偪偵揱偊傞偙偲偑巹偺嵟戝偺婅偄偱偡丅巹偑傗偭偰偒偨偙偺楈奅偑偳偺傛偆側傕偺偱偁傞偐傪棟夝偟偰傕傜傢側偗傟偽丄偙偺傛傠偙傃傪暘偐偪崌偆偙偲偑弌棃傑偣傫丅偱偡偐傜巹偼丄巰岅偺悽奅偵偮偄偰偺恀幚傪峀偔抦傜偣側偗傟偽偲偄偆徴摦傪丄偙偪傜傊棃偰傑偡傑偡嫮偔姶偠偰偄傞偺偱偡丅嘆
丂 偙傟偑丄僐僫儞丒僪僀儖偺偙偲偽偱偡偑丄楈奅偲偄偆偺偼丄偦傟傎偳傑偱偵慺惏傜偟偄偲偙傠側偺偱偟傚偆偐丅偙偺楈奅偺條巕傪丄巹偑偄傑丄悢懡偔偺捠怣椺偐傜慖傫偱奆偝傫偵偍揱偊偡傞偺偼丄偁傑傝梕堈偱偼偁傝傑偣傫丅傑偢丄扤偑偳偺傛偆偵偟偰憲偭偰偒偨捠怣偱偁傞偐傪嬦枴偟側偗傟偽側傝傑偣傫偟丄岥挷傗昳埵側偳傕榖偡撪梕偲偲傕偵栤戣偵側傝傑偡丅偦偆偄偆偙偲傪娷傔偰丄偦偺恀幚惈偼丄寢嬊丄奆偝傫偵敾抐偟偰偄偨偩偔傛傝偟偐偨偑側偄傛偆偱偡丅偙偙偱偼丄巹偑儘儞僪儞偵偄傞偲偒偵東栿偟偨丄僔儖僶乕丒僶乕僠偲柤忔傞崅埵楈偐傜偺捠怣暥偺堦晹傪偛徯夘偟傑偟傚偆丅偦傟偵偼丄偮偓偺傛偆偵弎傋傜傟偰偄傑偡丅丂
丂丂巹偺廧傓楈奅偱偼丄偡傋偰偑嵤傝朙偐偵婸偄偰偄傑偡丅偙偙傠偼惗偒傞婌傃偵偁傆傟丄恖乆偼偡傋偰妝偟偄巇帠偵懪偪崬傫偱偄傑偡丅寍弍妶摦傕惙傫偱丄恖乆偼偄偮傕懠偺恖偵曭巇偡傞偙偲傪峫偊偰偄傑偡丅帺暘偺帩偭偰偄傞幰偼帩偭偰偄側偄恖偵暘偐偪梌偊丄抦傜側偄恖偵偼嫵偊丄偙偙傠偺埫偄恖傪摫偄偰偄偙偆偲偟偰偄傑偡丅慞峴偺偨傔偺擬怱偝偲婌傃偲婸偒偵枮偨偝傟偰偄傞偺偱偡丅
丂 恖娫偺堦恖堦恖偼恄偺暘恎偱偁傝丄恄偺傕偮尷傝側偄戝偒側壜擻惈傪暘偗梌偊傜傟偰偄傑偡丅扤傕偑丄偙偺悽偱惗偒偰偄偔崲擄傪忔傝墇偊偰偄偔偨傔偺楈姶偲擻椡傪帺暘偺側偐偵帩偭偰偄傞偺偱偡丅偟偐偟抧忋偱偼丄偙偺塱墦偺帠幚偵偮偄偰抦偭偰偄傞恖偼彮側偄偟丄帺暘帺恎偺偡偽傜偟偄桪傟偨嵥擻傪堷偒弌偡偙偲偺弌棃傞恖傕懡偔偼偁傝傑偣傫丅偦偟偰抧忋偺懡偔偺恖乆偼丄楈奅偱偼偙偺抧忋傛傝傕傕偭偲尰幚枴偺偁傞朙偐側怓嵤傗桪偟偝偵枮偪偨惗妶偑弌棃傞偙偲傕抦傜偢偵丄柍枴姡憞側抧忋偺惗妶偺曽偑偄偄偲巚偄崬傫偱偟傑偭偰偄傞偺偱偡丅
丂 巹偼丄帺暘偑尒偰偒偨楈奅偲丄偄傑棦婣傝偟偰偒偨偙偺抧忋偺悽奅偲傪斾傋偰丄偁傝偺傑傑傪榖偟偰偄傑偡丅杮摉偼丄偁側偨曽偺偙偺抧忋偺悽奅偼丄楈奅偺懢梲偺岝偺塭偱偁傞偵偡偓傑偣傫丅偙偺悽奅偼偄傢偽嬻嫊側妅偱偁偭偰尰幚偱偼側偄偺偱偡丅暔幙偺悽奅偵偼丄傕偲傕偲丄惓恀惓柫偺尰幚側偳偼偁傝偊側偄偺偱偡丅暔幙偺懚嵼帺懱偑楈偺嶌梡偵傛傞傕偺偩偐傜偱偡丅偦傕偦傕丄暔幙偲偄偆偺偼丄尰幚偺楈偺悽奅偑弌偡攇摦偺傂偲偮偺昞尰偱偁傞偵偡偓傑偣傫丅
丂丂偙偺抧忋偺悽奅偺恖偨偪偑丄傕偟巹偨偪楈奅偺恖娫偑抦偭偰偄傞偙偲傪抦傞偙偲偑弌棃偨側傜丄堄婥徚捑偡傞偙偲傕側偗傟偽丄偆側偩傟偰偄傞偙偲傕側偄偱偟傚偆丅恖乆偼傒側丄惗婥傪庢傝栠偡偱偟傚偆丅偦傟偼丄偁傜備傞椡偺崻尦偑楈偵偁傝丄楈奅偺塱墦偺晉傪庤偵擖傟傞傎偆偑丄嬯楯傗怱攝偺庬偵側傞暔幙揑側傕偺傛傝偢偭偲戝愗偱偁傞偙偲傪棟夝偟偼偠傔傞偐傜偱偡丅巹偼丄偙偺抧忋偱丄杮摉偵懡偔偺恖乆偑帺暘偨偪偺僄僱儖僊乕傪巊偆偵抣偟側偄偝傑偞傑側偙偲偱擸傫偩傝丄嫲傟偨傝丄怱攝偟偨傝偡傞偺傪尒偰偒傑偟偨丅椡傪擖傟傞傋偒応強傪娫堘偭偰偄傞偺偱偡丅尒摉堘偄偺搘椡傪偟偰偄傞偺偱偡丅偄偮偐偼夵傔傜傟側偗傟偽側傝傑偣傫丅嘇
丂 偙偺僔儖僶乕丒僶乕僠偲偄偆偺偼丄儘儞僪儞偺僴儞僱儞丒僗儚僢僴乕丒儂乕儉僒乕僋儖偲柤晅偗傜傟偨岎楈夛偱丄堦嬨擇乑擭戙屻敿偐傜屲乑擭偁傑傝傕抧忋偺恖娫偵嫵孭傪岅傝懕偗偰偒偨崅埵楈偱偡丅楈擻幰傪捠偟偰岅傜傟偨朿戝側婰榐偼丄塸岅埲奜偵傕悢偐崙岅偵東栿偝傟丄悽奅奺抧偵偄傑傕懡偔偺擬怱側怣曭幰傪帩偮偲偄傢傟偰偄傑偡丅嘊
丂 偙偺僔儖僶乕丒僶乕僠偼壖偺柤慜偱丄抧忋帪戙偺杮柤偼丄壗搙恞偹偰傕杮恖偼柧偐偦偆偲偼偟傑偣傫偱偟偨丅乽恖娫偼柤慜傗尐彂偒偵偙偩傢傞偐傜偄偗側偄偺偱偡丅傕偟傕巹偑楌巎忋桳柤側恖暔偩偲傢偐偭偨傜丄巹偑弎傋偰偒偨偙偲偵堦抜偲敁偑偮偔偲巚傢傟傞偺偱偟傚偆偑丄偦傟偼傛偔側偄嶖妎偱偡丅慜悽偱巹偑墹條偱偁傠偆偲岊怘偱偁傠偆偲丄戝晉崑偱偁傠偆偲搝楆偱偁傠偆偲丄偦傫側偙偲偼偳偆偱傕傛偄偺偱偡丅巹偺尵偭偰偄傞偙偲偵丄側傞傎偳偲擺摼偑偄偭偨傜恀棟偲偟偰怣偠偰壓偝偄丅偦傫側攏幁側丄偲巚傢傟偨傜丄偳偆偧怣偠側偄偱壓偝偄丅偦傟偱偄偄偺偱偡乿偲丄摎偊偰偒偨偦偆偱偡丅
丂 岎楈夛偱偼丄帺桼偵幙栤傕偱偒傑偟偨偐傜丄暦偒偨偄偙偲偼側傫偱傕暦偔偙偲偑弌棃傑偟偨丅巹偨偪偺慡偔枹抦偺悽奅偺偙偲傪偄傠偄傠暦偔傢偗偱偡偐傜丄慺杙側幙栤傕懡偄偺偱偡偑丄偦傟傜偵懳偟偰丄僔儖僶乕丒僶乕僠偼偳偆摎偊偰偄傞偐丄偦傟傪偄偔偮偐丄偮偓偵敳偒弌偟偰傒傞偙偲偵偄偨偟傑偟傚偆丅嘋丂
丂丂乽巰幰偨偪偵傕帪娫偑偁傞偺偱偟傚偆偐丄巰幰偨偪偼偳偺傛偆側巇帠傪偟偰偄傑偡偐丠乿
丂丂偁側偨曽偺帪娫偼丄曋媂忋偙傑偐偔嬫暘偝傟偨傕偺偱偡丅偮傑傝抧媴偺帺揮傗懢梲偲偺娭學偵婎偯偄偰丄偁傞帪偺棳傟傪壗擔偩偲偐丄壗昩偩偲偐丄偁傞偄偼壗帪娫偩偲偐壗暘偩偲偐偄偆傆偆偵寛傔傜傟偨傕偺偱偡丅巹偨偪偵偼栭傕拫傕偁傝傑偣傫丅巹偨偪偺岝偼丄偁側偨曽偺岝偲偼惈幙偑堘偆偺偱偡丅偩偐傜丄巹偨偪偵偼偁側偨曽偑偄偆帪娫偲偄偆傕偺偼偁傝傑偣傫丅巹偨偪偑帪娫傪偼偐傞婎弨偼丄楈偺忬懺偵傛偭偰寛傑傝傑偡丅偄傢偽丄妝偟傒偺検偲偟偰帪娫傪姶偠傞偺偱偁偭偰丄巹偨偪偵偲偭偰偺帪娫偼惛恄嶌梡偺傂偲偮側偺偱偡丅
丂 巇帠偺傗傝曽偼丄屄恖屄恖偱堘偄傑偡丅幙栤偝傟偨曽偑丄暔棟揑側広搙偱楈揑側彅宱尡傪棟夝偟傛偆偲偝傟傞偲丄崲擄傪姶偠傜傟傞偐傕偟傟傑偣傫丅偙偪傜偺悽奅偵偼丄怱偲楈偵娭楢偡傞悢偊愗傟側偄傎偳懡偔偺巇帠偑偁傝傑偡丅偦傟傜偺巇帠偼丄偁側偨曽偺暔幙悽奅偵偁傞偺偲摨偠傛偆側暥壔揑側傕偺傕偁傝丄嫵堢揑側傕偺傕偁傝丄偦傟偧傟栚揑傪帩偭偰偄偰丄暔幙悽奅傊摥偒偐偗傞傕偺傕偁傝傑偡丅偦傟傜偺巇帠偵丄巹偨偪偼帺暘偺岲偒側偩偗偄偮偱傕庢傝慻傓偙偲偑弌棃傞偺偱偡丅
丂 乽楈奅偱偼丄堦恖堦恖偑帺暘帺恎偺壠傪帩偭偰偄傞偺偱偡偐丠乿
偦偺捠傝偱偡丅壠偑梸偟偄恖偼壠傪帩偭偰偄傑偡丅壠偑梸偟偄偲婅偭偰丄壠傪庤偵擖傟傞偺偱偡丅偟偐偟丄壠傪梸偟偑傜側偄恖傕偄傑偡丅傑偨丄恖偵傛偭偰偼丄帺暘偺岲傒偺寶抸條幃偱壠傪寶偰偨偑傝傑偡偟丄偁側偨曽偵偼抦傜傟偰偄側偄岝偺巚憐傪嬶懱壔偟偨壠嶌傝傪峫偊傞恖傕偄傑偡丅偦傟傜偼傑偭偨偔丄楈奅偺廧柉偺憂憿擻椡偵婎偯偔屄恖偺庯枴偺栤戣側偺偱偡丅
丂 乽楈奅偵偼丄壒妝夛傗寑応丄偁傞偄偼攷暔娰偺傛偆側傕偺偼偁傝傑偡偐丠乿
丂丂壒妝夛偼偄偮偱傕奐嵜偝傟偰偄傑偡丅旕忢偵懡偔偺壒妝壠偑偄偰丄偟偐傕偦偺懡偔偑丄壒妝偺戝壠側偺偱偡偑丄斵傜偼偄偮傕丄帺暘偨偪偺壒妝偑弌棃傞偩偗懡偔偺恖乆偵妝偟傫偱傕傜偊傞偙偲傪朷傫偱偄傑偡丅寑応傕丄偄傠偄傠側庬椶偺傕偺偑戲嶳偁傝傑偡丅偁傞寑応偼墘寑偺偨傔偩偗偺傕偺偱偡偟丄暥壔揑側栚揑偱巊傢傟傞寑応傗丄嫵堢栚揑偱巊傢傟傞寑応側偳傕偁傝傑偡丅
丂 偁側偨曽偺悽奅偱帩偭偰偄偨嵥擻傗媄擻丄庤榬側偳偼巰偵傛偭偰廔傢傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅偐偊偭偰巰屻偼丄懇敍偐傜夝曻偝傟偰丄嵥擻偱傕媄擻偱傕庤榬偱傕丄傛傝戝偒偔敪婗偱偒傞傛偆偵側傞偺偱偡丅
丂 楈奅恖偺攷暔娰偲偄偆偺偼丄恖椶偺慡楌巎傪捠偠偰偺抧忋惗妶偵娭偡傞偁傜備傞庬椶偺捖楍昳偑暲傋傜傟偰偄傑偡丅傑偨丄楈奅惗妶偺嫽枴怺偄僐儗僋僔儑儞傕偁傝傑偡丅偨偲偊偽丄楈奅偵偼抧忋偱偼嶇偐側偄傛偆側壴偑偁傝傑偡偟丄偁側偨曽偵偼抦傜傟偰偄側偄帺慠惗妶偺條乆側條幃傕偁傝傑偡丅
丂 乽楈奅偵偼丄怴暦傗儔僕僆偑偁傝傑偡偐丠乿
丂丂僐儈儏僯働乕僔儑儞偺庤抜偑堘偄傑偡偐傜丄儔僕僆偼偁傝傑偣傫丅捠忢偍屳偄偺娫偱梡偄傜傟傞偺偑僥儗僷僔乕偱偡丅偟偐偟丄偦偺応偵偄側偄懡偔偺恖偵岦偐偭偰捠怣傪憲傞偙偲偑弌棃傞恖傕偄傑偡丅偨偩偦偺応崌傕丄偁側偨曽偺儔僕僆偺尨棟偱捠怣偝傟傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅
丂 傑偨丄偁側偨曽偺悽奅偱偺怴暦偺傛偆側傕偺偼偁傝傑偣傫丅偦傟偼丄偁側偨曽偺傛偆偵丄偄傠偄傠側弌棃帠傪婰榐偟偰抦傜偣傞昁梫偑側偄偐傜偱偡丅昁梫側忣曬偼丄偦傟傪憲傞偙偲傪巇帠偵偟偰偄傞恖偑偄偰丄抦傜偣側偗傟偽側傜側偄憡庤偵偼愨偊偢忣曬傪憲偭偰偄傑偡丅偱傕偙傟偼丄偁側偨曽偵偼棟夝偟偵偔偄偱偟傚偆丅
丂 偨偲偊偽丄巹偺抦傜側偄偙偲傪巹偵抦傜偣偨偄帪偵偼丄巹偑偦偺偙偲傪抦傞傋偒偩偲峫偊偰偄傞恖偵傛偭偰憐擮偑巹偵憲傜傟傑偡丅偦偺傛偆側憐擮傪憲傞偙偲傪怑嬈偲偟偰偄傞恖乆偑偄傞偺偱偡丅偦偺偨傔偵摿暿偺孭楙傪庴偗偨恖偨偪偱偡丅
丂
丂 乽杮偩偲偐丄偁傞偄偼杮偵憡摉偡傞傕偺偑楈奅偵偼偁傝傑偡偐丠乿
丂丂悢偊愗傟側偄傎偳偺戲嶳偺杮偑偁傝傑偡丅偁側偨曽偺悽奅偱抦傜傟偰偄傞杮偼偡傋偰偙偪傜偵傕偁傝傑偡丅偦傟偵丄偁側偨偺悽奅偵偼側偄楈奅偩偗偺杮傕戲嶳偁傝傑偡丅偡傋偰偺妛栤丄寍弍偺偨傔偺嫄戝側寶暔傗巤愝偑偁偭偰丄暥妛愱栧偺恾彂娰側偳傕妋曐偝傟偰偄傑偡丅偁側偨曽偵嫽枴偺偁傞偳傫側壢栚偵偮偄偰傕抦幆傪偊傜傟傞傛偆偵側偭偰偄傞偺偱偡丅
丂
丂 偙偺傛偆側幙栤偲夞摎傪娷傔偨孭榖偑丄屲乑擭偁傑傝傕懕偗傜傟偨傢偗偱偡偐傜丄偦偺憤検偼朿戝偱丄偙偙偱偼偦偺堦抂偵偟偐怗傟傞偙偲偑偱偒傑偣傫丅偙偺曈偱廔傢傜偣傞偙偲偵偟傑偟傚偆丅僔儖僶乕丒僶乕僠偼丄偁傞擔偺岎楈奅偱丄帺暘偺巇帠傗丄巹偨偪抧忋偺恖娫偺側偡傋偒偙偲偵偮偄偰丄偟傒偠傒偲岅偭偨偙偲偑偁傝傑偟偨偑丄偦傟傪嵟屻偵偍揱偊偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂丂懡偔偺偙偲偑側偝傟偰偒傑偟偨偑丄傑偩偟側偗傟偽側傜側偄偙偲傕戲嶳巆偭偰偄傑偡丅巹偼丄巹偨偪偑彮偟偱傕偍栶偵棫偰傞傛偆側恖乆偺偲偙傠傊帺桼偵峴偗傞傛偆偵丄杺朄偺鉕焴偱傕偁傟偽偄偄偲巚偄傑偡傛丅傑偨暿偺杺朄偺鉕焴偑偁傟偽丄偙偺楈奅偱丄偐偭偰巹偨偪偑偍栶偵棫偰偨恖乆偑偙偪傜偵棃偰偄傞偺傪憑偡偙偲偑弌棃傞偐傕偟傟傑偣傫丅偦偆偡傟偽丄巹偨偪偺偟偰偒偨巇帠偑丄昞柺偵尰傟偰偄傞傛傝偢偭偲戝偒側傕偺偱偁傞偙偲傪巹偨偪傕擣幆偱偒傞偱偟傚偆丅
丂 巹偼丄偄傑傑偱偳傟偔傜偄偺巇帠傪偟偰偒偨偐偲峫偊傞偙偲偼偟傑偣傫丅偦傟偼巹偨偪傒傫側偺巇帠偱偡偑丄偙傟偐傜傕懕偗偰偄偐側偗傟偽側傜側偄巇帠傪慜偵偟偰丄巹偼忢偵偙偙傠偐傜尓嫊偱偁傝偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅偁側偨曽傕丄偱偡偐傜丄婤慠偲偟偰摢傪忋偘丄恄惞側栚揑偺偨傔偵曭巇偟偰偄傞偙偲傪帺妎偟偰壓偝偄丅偦偟偰丄偁側偨曽偺恖惗偱傆傟崌偭偨恖乆偵丄偁側偨偑偟傛偆偲偟偰偄傞偙偲偑壗偱偁傞偐傪抦偭偰傕傜偊傞傛偆側惗偒曽傪怱偑偗偰偄偒傑偟傚偆丅偁側偨曽偲傆傟崌偭偨恖乆偵丄偄偮偱傕弌棃傞尷傝偺曭巇傪偟傑偟傚偆丅偦傟傜偺恖乆傪丄弌棃傞尷傝崅傔偰偄偒傑偟傚偆丅婡夛偑偁傟偽偄偮偱傕丄摫偄偰偄偭偰偁偘傑偟傚偆丅曭巇偙偦偑偡傋偰側偺偱偡丅傎偐偺偡傋偰偺偙偲偑朰傟嫀傜傟偨帪偱傕丄悽懎揑側偡傋偰偺帩偪暔偑朅偺偛偲偔徚偊嫀偭偰偟傑偭偨屻偱傕丄偙偺悽偺嵿嶻偺偡傋偰偑怓偁偣媭偪壥偰傞偙偲偵側偭偰傕丄偁側偨偑恖乆偺偨傔偵恠偔偟偨曭巇偩偗偼丄偁側偨曽偺恖暱傪帵偡塱墦偺曮愇丂偲側偭偰婸偒懕偗傞偙偲偱偟傚偆丅嘍
丂 巐丂丂偐偄傑尒傞巰屻偺悽奅
丂 偙偺傛偆側楈奅偺桳傝條傪丄偐偄傑尒偨偲峫偊傞恖偨偪偑擔杮偺傒側傜偢悽奅拞偵懡偔偄傑偡丅偄傢備傞椪巰懱尡偺徹尵幰偨偪偱偡丅椪巰懱尡偲偄偆偺偼丄帠屘傗昦婥側偳偱巰偵偐偐偭偨恖偑嬨巰偵堦惗傪摼偰丄堄幆傪夞暅偟偨偲偒偵岅傞乽偁偺悽乿揑側懱尡偺偙偲偱偡偑丄嶰搑偺愳傪尒偨偲偐丄岝偺僩儞僱儖傪弌偰旤偟偄偍壴敤偺拞傪曕偄偨偲偐丄偁傞偄偼丄嵃偑擏懱偐傜敳偗偩偟偨丄巰傫偩擏恊偵夛偭偨丄偲偄偭偨堦楢偺嫟捠偟偨僷僞乕儞偑偁傝傑偡丅嬤擭偱偼丄堛妛偺敪払偺偍偐偘偱丄巰偵偐偐偭偨恖傕巰側偢偵偡傫偩傝丄偄偭偨傫偼怱憻偑巭傑偭偰乽巰傫偩乿恖傕惗偒曉偭偨傝偡傞帠椺偑憹偊偰偒偰偄傑偡偐傜丄偙偺庬偺懱尡幰偺悢偼偐側傝懡偔側偭偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅
丂 偄傑偐傜巐擭傎偳慜偺偙偲偱偡偑丄埱椦戝妛堛妛晹偺恅溲嵠嫵庼偺僌儖乕僾偑摨戝妛晅懏昦堾偺媬媫奜棃偵塣傃崬傑傟偨堄幆晄柧偺姵幰偺偆偪丄偦偺屻慼惗偟偰抦揑忈奞傕帩偨側偐偭偨恖嶰嶰恖偵暦偒庢傝挷嵏傪偟偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偦偺寢壥丄堦擇恖偑椪巰懱尡傪偟偰偄偨偦偆偱偡丅懱尡棪偐傜偄偆偲嶰榋僷乕僙儞僩偺崅棪偵側傝傑偡丅偟偐偟丄幚嵺偵偼丄朰傟偰偟傑偭偰巚偄弌偣側偄偲尵偆恖側偳傕偄偨傝偟偰丄巰偵偐偗傞恖偺敿暘埲忋偼椪巰懱尡傪偡傞偺偱偼側偄偐偲偄傢傟偰偄傑偡丅嘐
丂 嵟嬤偱偼丄椪巰懱尡偺曬崘偼懡偔偺杮偵側偭偰弌斉偝傟偰偄傑偡偐傜丄偍撉傒偵側偭偨曽傕懡偄偲巚偄傑偡偑丄偙偙偱偼丄棫壴棽偝傫偑庢嵽偟偨丄曻憲昡榑壠偺巙夑怣晇偝傫偺懱尡択傪傒偰傒傞偙偲偵偟傑偟傚偆丅
丂 巙夑偝傫偼丄堦嬨敧堦擭偺榋寧偺偁傞擔丄夛崌傪廔偊偰壠偵婣傞搑拞丄僞僋僔乕傪廍偍偆偲偟偰摴楬傪嬱偗懌偱搉偭偨偲偒偵丄僞僋僔乕偵偼偹傜傟傑偟偨丅堦嶰儊乕僩儖傕偼偹旘偽偝傟偰摴楬偵偨偨偒晅偗傜傟丄堄幆傪幐偄傑偟偨丅偦偺帪偵椪巰懱尡傪偟偨偺偱偡丅巙夑偝傫偼丄偦偺帪偺條巕傪奊偵昤偒側偑傜師偺傛偆偵岅偭偰偄傑偡丅
丂
丂丂僶傾乕僢偲丄偙偺偔傜偄偺懢偝偐側丄幍怓偺岝偺懇偑偁傞偺偱偡丅偦偺岝偺拞傪丄傏偔偑僗乕僢偲忋偑偭偰偄偔傫偱偡丅偦傟偑偲偰傕婥帩偪偄偄傫偱偡丅傎傫偲偵壗偲傕偄偊偢偄偄婥帩偪偱偟偨丅偦偟偰忋偵忋偑傞偲丄偦偙偼幣惗傒偨偄側丄壴墍傒偨偄側応強偱丄恀柸偱偱偒偰傞傒偨偄偵丄廮傜偐偔偰丄僼傽乕僢偲偟偰偄偰丄偦偙偵墶偵側傞偲丄婥帩偪偄偄偺偑偝傜偵婥帩偪傛偔側偭偨傒偨偄偱偟偨丅丒丒丒側傫偲傕偄偊偢偄偄婥帩偪偱偡丅偙傟傑偱枴傢偭偨偳傫側偄偄婥帩偪傛傝偄偄婥帩偪偱偡傛丅斾傋傛偆偑側偄偱偡丅揤崙偵峴偭偨傛偆側偲偄偆偐丄湌崨偺嫬抧偱偡偹丅偦偟偰枮偪懌傝偰偄傞傫偱偡丅壗傕偄傜側偄丅廩懌搙昐僷乕僙儞僩偲偄偆姶偠偱偡偹丅偁傟偽偐傝偼丄堦夞懱尡偟偰傕傜傢側偄偙偲偵偼愨懳傢偐偭偰傕傜偊側偄偲巚偆丅嘑
丂 偙偺巙夑偝傫偼丄棫壴偝傫偑乽椪巰懱尡偵傛偭偰帺暘偑曄傢偭偨偙偲偲偄偆偺偼壗偐偁傝傑偡偐乿偲恞偹傞偲丄乽傗偼傝巰傪偍偦傟側偔側偭偨偙偲偱偟傚偆偹丅巰偲偄偆偺偼丄偁偁偄偆晽偵撍慠廝偭偰偔傞傕偺偱丄恖娫偺椡偱偳偆偙偆偟傛偆偨偭偰偳偆偵傕側傞傕偺偠傖側偄丅巰偵掞峈偡傞側傫偰僶僇偘偨偙偲偩偲丅偦傟偵丄巰偸偭偰偄偆偺偼嬯偟偄偙偲偱偼側偄丅偲偰傕婥帩偪偑偄偄傕偺偩偲丅傕偆堦夞傗偭偨偭偰偄偄偲巚偭偰傞傫偱偡丅栠偭偰偙側偔偰傕偄偄偔傜偄偱偡傛丅偮傑傝丄惗偒傞巰偸偵偙偳傢傜側偔側偭偨傫偱偡丅恖娫堦惗寽柦惗偒偰偄傟偽丄偄偮巰傫偩偭偰偄偄傫偱偡丅偳偆偭偰偙偲側偄偱偡傛丅惗巰偵偮偄偰擸傓昁梫偼側偄丅偦偆偄偆怱嫬偵側偭偰丄偁傫傑傝傑傢傝偺偙偲偑婥偵側傜側偔側傝傑偟偨乿偲摎偊偰偄傑偡丅
丂 廆嫵妛幰偲偟偰挊柤側嶳愜揘梇偝傫傕丄偙偺傛偆側椪巰懱尡傪傕偭偰偄傞傛偆偱偡丅嶰乑嵨偺崰丄妛惗偨偪偲庰応偱庰傪堸傫偱偄傞偲偒丄撍慠戝検偺揻寣傪偟偰堄幆晄柧偵側傝丄媬媫昦堾偵偐偮偓崬傑傟傑偟偨丅庒偄偲偒偵姵偭偨廫擇巜挵捵釃偑嵞敪偟偨偺偱偟偨丅
丂嶳愜偝傫偼丄堄幆傪幐偆偲偒丄懱偑傆傢偭偲晜偒忋偑傞傛偆側晜梘姶傪姶偠傑偟偨丅偡傞偲丄栚偺慜偵丄偄偭傁偄屲怓偺僥乕僾傪悂偒棳偟偨傛偆側丄岝傝婸偔擑偺傛偆側岝偑峀偑偭偰丄帺暘偺懱傪曪傒傑偟偨丅岝偵曪傑傟偰晜偒忋偑傝側偑傜丄乽偙偺傑傑巰傫偱偄偗傞側傜妝偩側丅巰傫偱偄偭偰傕埆偔偼側偄側乿偲巚偭偨偦偆偱偡丅嬯偟偝偼壗傕姶偠側偐偭偨偲弎傋偰偄傑偡丅嘒
丂 偙偺傛偆側椺偼杮摉偵柍悢偵偁傝傑偡偑丄偦傟偱傕擔杮偱偼傑偩丄偙偺傛偆側椪巰懱尡傪恀柺栚偵庢傝忋偘偰尋媶偟傛偆偲偄偆晽挭偼嫮偔偼偁傝傑偣傫丅偦傫側傕偺偼僆僇儖僩傔偄偨柉娫揱彸偺椶偱偁傠偆偲丄暦偒棳偟偰偟傑偆恖乆傕彮側偔偼側偄傛偆偱偡丅偟偐偟傾儊儕僇偱偼丄堦嬨幍乑擭戙偵擖偭偰偐傜丄儗僀儌儞僪丒儉乕僨傿攷巑傗僉儏僽儔乕丒儘僗攷巑側偳偺堛妛幰偺尋媶傪偒偭偐偗偵偟偰丄椪巰懱尡傪妛栤揑尋媶偺懳徾偵偟傛偆偲偄偆摦偒偑峀偑偭偰偒傑偟偨丅
丂 尰嵼偱偼丄怱棟妛幰丄惛恄丒恄宱堛丄擼惗棟妛幰丄廆嫵妛幰丄暥壔恖椶妛幰丄揘妛幰側偳懡曽柺偺妛幰偑偙偺尋媶偵娭怱傪婑偣丄崙嵺揑側尋媶抍懱偑慻怐偝傟丄尋媶帍傕敪姧偝傟偰偄傑偡丅偙偺傛偆側孹岦偼丄儓乕儘僢僷偱傕椺奜偱偼偁傝傑偣傫丅僀僊儕僗丄僼儔儞僗丄杒墷側偳偱傕椪巰懱尡偺尋媶偼惙傫偵側傝丄堦嬨嬨乑擭偵偼丄儚僔儞僩儞偺僕儑乕僕僞僂儞戝妛偱丄堦嶰偐崙偐傜嶰昐恖傕偺尋媶幰傗懱尡幰傪廤傔偰丄椪巰懱尡尋媶偺戞堦夞崙嵺夛媍偑奐偐傟傞傑偱偵側傝傑偟偨丅嘓
丂 偙偺墷暷偵偍偗傞椪巰懱尡尋媶偺憪暘偗偺堦恖偱偁傞儉乕僨傿攷巑偼丄堦屲乑椺偺椪巰懱尡傪傕偲偵偟偰丄偦傟傜偺懱尡撪梕傪暘愅偡傞偙偲偐傜尋媶傪巒傔傑偟偨丅偦傟偱傢偐偭偨偙偲偼丄巰偵昺偟偨帪偺忬嫷傗丄巰傪懱尡偟偨恖乆偺僞僀僾偑懡庬懡條偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄懱尡偺撪梕偦偺傕偺偵偼嬃偔傎偳偺嫟捠揰偑偁偭偨偲偄偆偙偲偱偡丅偦偺嫟捠揰偼旕忢偵偼偭偒傝偟偰偄偰丄堦屲傎偳偺梫慺偵暘椶偱偒傑偡丅偦偙偱攷巑偼丄偦傟傜偺堦屲偺嫟捠梫慺傪偡傋偰娷傫偩椪巰懱尡偺偁傝傛偆傪丄棟榑揑側儌僨儖偲偟偰師偺傛偆偵慻傒棫偰丄亀偐偄傑尒偨巰屻偺悽奅亁偲偄偆杮偺側偐偱敪昞偟傑偟偨丅
丂丂巹偼昺巰偺忬懺偵偁偭偨丅暔棟揑側擏懱偺婋婡偑捀揰偵払偟偨偲偒丄扴摉偺堛巘偑巹偺巰傪愰崘偟偰偄傞偺偑暦偙偊偨丅帹忈傝側壒偑暦偙偊巒傔偨丅戝偒偔嬁偒搉傞壒偩丅憶乆偟偔偆側傞傛偆側壒偲偄偭偨傎偆偑偄偄偐傕偟傟側偄丅摨帪偵丄挿偔偰埫偄僩儞僱儖偺拞傪丄栆楏側懍搙偱捠傝敳偗偰偄傞傛偆側姶偠偑偟偨丅偦傟偐傜撍慠丄帺暘帺恎偺暔棟揑擏懱偐傜敳偗弌偟偨偺偑傢偐偭偨丅偟偐偟偙偺帪偼傑偩丄偄傑傑偱偲摨偠暔棟揑悽奅偵偄偰丄巹偼偁傞嫍棧傪曐偭偨応強偐傜丄傑傞偱朤娤幰偺傛偆偵帺暘帺恎偺擏懱傪尒偮傔偰偄偨丅偙偺堎忢側忬懺偱丄帺暘偑偮偄偝偒傎偳敳偗弌偟偨暔棟揑側擏懱偵慼惗弍偑巤偝傟傞偺傪娤嶡偟偰偄傞丅惛恄揑偵偼旕忢偵崿棎偟偰偄偨丅
丂 偟偽傜偔偡傞偲棊偪拝偄偰偒偰丄尰偵帺暘偑偍偐傟偰偄傞婏柇側忬懺偵姷傟偰偒偨丅巹偵偼偄傑偱傕乽懱乿偑旛傢偭偰偄傞偑丄偙偺懱偼愭偵敳偗弌偟偨暔棟揑擏懱偲偼杮幙揑偵堎幙側傕偺偱丄偒傢傔偰摿堎側擻椡傪傕偭偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅傑傕側偔暿偺偙偲偑巒傑偭偨丅扤偐偑巹偵椡傪偐偡偨傔偵夛偄偵棃偰偔傟偨丅偡偱偵巰朣偟偰偄傞恊愂偲偐桭払偺楈偑丄偡偖偦偽偵偄傞偺偑側傫偲側偔傢偐偭偨丅偦偟偰丄偄傑傑偱堦搙傕宱尡偟偨偙偲偺側偄傛偆側垽偲抔偐偝偵枮偪偨楈乕岝偺惗柦乕偑尰傟偨丅偙偺岝偺惗柦偼丄巹偵帺暘偺堦惗傪憤妵偝偣傞偨傔偺幙栤傪搳偘偐偗偨丅嬶懱揑側偙偲偽傪夘嵼偝偣偢偵幙栤偟偨偺偱偁傞丅偝傜偵丄巹偺惗奤偵偍偗傞庡側弌棃帠傪楢懕揑偵丄偟偐傕堦弖偺偆偪偵嵞惗偟偰傒偣傞偙偲偱丄憤妵偺庤彆偗傪偟偰偔傟偨丅
丂丂偁傞帪揰偱丄巹偼帺暘偑堦庬偺忈暻偲傕嫬奅偲傕偄偊傞傛偆側傕偺偵彮偟偢偮嬤偯偄偰偄傞偺偵婥偑偮偄偨丅偦傟偼暣傟傕側偔丄尰悽偲棃悽偲偺嫬栚偱偁偭偨丅偟偐偟丄巹偼尰悽偵栠傜側偗傟偽側傜側偄丅崱偼傑偩巰偸偲偒偱偼側偄偲巚偭偨丅偙偺帪揰偱妺摗偑惗偠偨丅側偤側傜丄巹偼崱傗巰屻偺悽奅偱偺懱尡偵偡偭偐傝怱傪扗傢傟偰偄偰丄尰悽偵栠傝偨偔偼側偐偭偨偐傜偩丅丂寖偟偄娊婌丄垽丄傗偡傜偓偵埑搢偝傟偰偄偨丅偲偙傠偑堄偵斀偟偰丄偳偆偄偆栿偐丄巹偼嵞傃帺暘帺恎偺暔棟揑擏懱偲寢崌偟丄慼惗偟偰偟傑偭偨丅
丂偦偺屻丄偁偺帪偺懱尡傪傎偐偺恖偵榖偦偆偲偟偨偗傟偳丄偆傑偔偄偐側偐偭偨丅傑偢戞堦偵丄憐憸傪愨偡傞偁偺懱尡傪丄揔愗偵昞尰偡傞偙偲偽偑慡慠尒偮偐傜側偐偭偨丅偦傟偵丄嬯楯偟偰榖偟偰傕丄暔徫偄偺庬偵偝傟偰偟傑偭偨丅偩偐傜傕偆扤偵傕榖偝側偄丅偟偐偟丄偁偺懱尡傪偟偨偍偐偘偱丄巹偺恖惗偼戝偒側塭嬁傪庴偗偨丅摿偵丄巰偲偄偆偙偲偵偮偄偰丄拞偱傕丄巰偲恖丂惗偺偲娭學偵娭偡傞巹偺峫偊曽偵戝偒側塭嬁傪庴偗偨丅嘔丂
丂 妋偐偵丄椪巰懱尡偺婎杮揑側僷僞乕儞偼屳偄偵旕忢偵傛偔帡偰偄傑偡偐傜丄儉乕僨傿攷巑偺偙偺儌僨儖偼傛偔傢偐傝傑偡丅偟偐偟丄傛偔帡偨婎杮揑側峔憿傪帩偪側偑傜傕丄懱尡椺偺嬶懱揑側撪梕偼丄偦傟偧傟恖偵傛偭偰堘偄傑偡偟丄柉懓傗暥壔偵傛偭偰傕堘偄傑偡丅偦傟偵丄慜復偱弎傋偰偒偨丄楈奅偺桳傝條偲偺傊偩偨傝傕姶偠傜傟側偄偙偲偼偁傝傑偣傫丅偦傟傪偳偺傛偆偵庴偗巭傔偰偄偗偽傛偄偺偱偟傚偆偐丅
丂 偙傟偵偮偄偰丄僉儏僽儔乕丒儘僗攷巑偼丄椪巰忬懺偱懱尡偡傞偺偼巰屻偺悽奅偦偺傕偺偱偼側偔偰丄惗偐傜巰傊偺堏峴夁掱偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傑偡丅椪巰懱尡幰偲偄偆偺偼丄杮摉偵巰傫偱偟傑偭偨恖偱偼側偔偰丄傑偨惗偒曉偭偨恖偽偐傝偱偡丅巰屻偺悽奅偺擖傝岥傑偱峴偭偨偩偗偱丄姰慡偵拞傑偱擖傝崬傫偱偟傑偭偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偩偐傜丄椪巰懱尡幰偲偄偆偺偼丄巰屻偺悽奅偐傜尒傞偲丄惗傑傟偨偽偐傝偺丄傊偦偺弿傪偮偗偨忬懺偺愒偪傖傫偺傛偆側傕偺偩偲偄偆偺偱偡丅
丂 傊偦偺弿傪偮偗偰偄傞偐傜丄傑偩抧忋偺悽奅偲偮側偑偭偰偄傞丅偩偐傜栠傞偙偲偑弌棃傞丅杮摉偺巰傪懱尡偡傞偺偼丄偦偺傊偦偺弿偑愗傜傟偰偐傜偱丄椪巰懱尡幰偑岅傞撪梕偲偄偆偺偼丄偩偐傜丄偁偔傑偱傕傊偦偺弿晅偒偺忬懺偱惗偲巰偺嫬奅椞堟傪偝傑傛偭偨偲偒偺懱尡偩偲丄攷巑偼弎傋偰偄傑偡丅嘕
丂 偟偐偟丄椪巰懱尡偑楈奅偺擖傝岥傑偱峴偭偰婣偭偰偒偨傕偺偱偁偭偨偲偟偰傕丄僉儏僽儔乕丒儘僗攷巑偼丄楈奅偺懚嵼傪寴偔怣偠偰偄傑偡丅慜夞偍榖偟偟傑偟偨傛偆偵丄斵彈帺恎偑椪巰懱尡幰偱傕偁傞偐傜偱偡丅攷巑偼丄偦偺楈奅偺懚嵼偵妋怣傪帩偮傛偆偵側偭偨偄偒偝偮傪丄師偺傛偆偵岅偭偰偄傑偡丅
丂丂巹偼傕偲傕偲壢妛幰偲偟偰孭楙傪庴偗偨恖娫偱偡丅暔棟揑帠幚埲奜偺傕偺偵懳偟偰偼媈偄偺栚傪岦偗傞傛偆偵孭楙偝傟偨恖娫偱偡偐傜丄楈嵃傗怱楈揑側悽奅偵偮偄偰岅傞偙偲偵偼掞峈偑偁傝傑偟偨丅壢妛幰偲偐堛幰偼丄偦偆偄偆椞堟偵懌傪摜傒擖傟偰偼側傜側偄傕偺偲偝傟偰偄傑偟偨丅偦偆偄偆椞堟偺尰徾偼丄婎杮揑偵徹柧偡傞偙偲傕妋擣偡傞偙偲傕弌棃側偄偙偲偩偐傜偱偡丅偟偐偟丄尰幚偵懱尡幰偺榖傪師乆偵暦偄偰偄偔偲丄媡偵丄偦偆偄偆尰徾偵栚傪岦偗傛偆偲傕偣偢丄帹傪孹偗傛偆偲偟側偄傎偆偑壢妛幰偲偟偰岆傝偩偲巚偆傛偆偵側偭偨偺偱偡丅偦偟偰丄堛幰偑尪妎偩偲偐惛恄堎忢偲偄偆儗僢僥儖傪揬傞偩偗偱丄偦傟埲忋憡庤偵偟側偄姵幰偺榖傪恀柺栚偵暦偄偰傒傞偲丄偦偺拞偵柍帇偟偑偨偄恀幚偑偁傞偲偄偆偙偲偑傢偐偭偰偒傑偟偨丅偟偐偟丄偦傟偑杮摉偵恀幚偱偁傞偲傢偐偭偨偺偼丄傗偼傝帺暘帺恎偱椪巰懱尡傪偟偰偐傜偱偡丅嘖
丂 偙偆偟偰僉儏僽儔乕丒儘僗攷巑偼丄椪巰懱尡偺帠椺傪擇枩審傕廤傔偰丄楈奅偑幚嵼偡傞偙偲丄恖娫偲偄偆偺偼巰傫偱傕巰側側偄偺偩偲偄偆偙偲傪丄峀偔悽奅偺恖乆偵揱偊偰偄偔偺偑帺暘偺巊柦偱偁傞偲峫偊傞傛偆偵側傝傑偟偨丅堦嬨榋嬨擭偵亀巰偸弖娫亁傪弌斉偟丄堦桇悽奅拞偵偦偺柤偑抦傜傟傞傛偆偵側偭偰偐傜偼丄暥帤捠傝揱摴幰偲側偭偰悢懡偔偺杮傪彂偒丄傎偲傫偳媥傒柍偔悽奅拞傪旘傃夞偭偰島墘偟丄僙儈僫乕傪庡嵜偟懕偗傑偟偨丅擔杮傊傕棃偨偙偲偑偁傝傑偡丅偦偺攷巑偼丄乽偡傋偰偺嬯擄偼丄偁側偨偵梌偊傜傟偨惉挿偺婡夛偱偡丅惉挿偙偦丄抧媴偲偄偆榝惎偵惗偒傞偙偲偺桞堦偺栚揑偱偡丅偁側偨偑旤偟偄掚偵嵗偭偰偄傞偩偗偱丄嬧偺嶮偵偺偭偨崑壺側怘帠傪扤偐偑塣傫偱偔傟傞偺偩偲偟偨傜丄偁側偨偼惉挿偟側偄偱偟傚偆丅偱傕丄傕偟昦婥偩偭偨傝丄偳偙偐偑捝偐偭偨傝丄憆幐傪宱尡偟偨偲偒偵丄偦傟偵棫偪岦偐偊偽丄偁側偨偼昁偢惉挿偡傞偱偟傚偆丅捝傒傪丄庺偄偲偐敱偲偟偰偱偼側偔丄摿暿偺栚揑傪傕偭偨恄偐傜偺憽傝暔偲偟偰庴偗擖傟傞偙偲偑戝愗偱偡乿偲弎傋偰偄傑偡丅嘗
丂 堦嬨嬨幍擭堦寧丄擼懖拞偺敪嶌傪婲偙偟偰偦偺屻堚徢偵嬯偟傫偱偄偨幍堦嵨偺攷巑偼丄昦彴偱斵彈帺恎偑乽偙傟偑愨昅偵側傞乿偲弎傋偰偄傞杮傪彂偒懕偗偰偄傑偟偨丅巰傪彮偟傕嫲傟偢丄傓偟傠婌偽偟偄偙偲偲峫偊偰偄傞攷巑偼丄堛幰偱偡偐傜帺暘偺堄巙偱乽懱偐傜棧傟傞乿偙偲傕偱偒傑偡丅乽傕偭偲傑偟側悽奅乿偮傑傝楈奅偱丄乽傕偭偲傑偟側曢傜偟乿偑偱偒傞偙偲傕廫暘偵抦偭偰偄傑偟偨丅偦傟偱傕攷巑偼丄偙偺抧忋惗妶傪懖嬈偡傞慜偵梌偊傜傟偰偄傞嵟屻偺嫵孭傪妛傇婡夛偲偟偰丄晄夣傗嬯捝傪擡懴嫮偔庴偗擖傟偰偄傑偟偨丅偦偺斵彈偑丄偙偺偍偦傜偔偼嵟屻偵側傞偲巚傢傟傞偙偺杮傪丄師偺傛偆側撉幰傊偺偙偲偽偱掲傔偔偔偭偰偄傑偡丅
丂 巰偼晐偔側偄丅巰偼恖惗偱傕偭偲傕偡偽傜偟偄宱尡偵傕側傝偆傞丅偦偆側傞偐偳偆偐偼丄偦偺恖偑偳偆惗偒偨偐偵偐偐偭偰偄傞丅巰偼偙偺宍懺偺偄偺偪偐傜偺丄捝傒傕擸傒傕側偄暿偺宍懺傊偺堏峴偵偡偓側偄丅
丂丂垽偑偁傟偽丄偳傫側偙偲偵傕懴偊傜傟傞丅偳偆偐傕偭偲懡偔偺恖偵丄傕偭偲懡偔偺垽傪梌偊傛偆偲偙偙傠偑偗偰傎偟偄丅偦傟偑傢偨偟偺婅偄偩丅塱墦偵惗偒傞偺偼垽偩偗偩偐傜丅嘙
丂
丂丂屲丂丂側偤惗傑傟偰偔傞偺偐
丂 巹偨偪偼側偤偙偺悽偵惗傑傟偰丄偄傑惗偒偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅傑偨丄恖娫偼側偤惗傑傟曄傢傝傪孞傝曉偡偺偱偟傚偆偐丅偦傟偼丄偙偺悽偺惗妶偺拞偱丄偄傠偄傠偲宱尡傪愊傒側偑傜妛傫偱偄偔偨傔偱偡丅妛傃巆偟偨晹暘偼傑偨惗傑傟曄傢偭偰妛廗傪懕偗傑偡丅偄傢偽丄偙偺悽偼丄巹偨偪偺嵃偺惉挿偺偨傔偺妛峑側偺偱偡丅僉儏僽儔乕丒儘僗攷巑傕丄乽偄偺偪偺桞堦偺栚揑偼惉挿偡傞偙偲偵偁傞乿偲偟偽偟偽孞傝曉偟偰偄傑偡丅偦偟偰丄恖惗偵偍偗傞偡傋偰偺嬯擄丄埆柌丄帋楙偼偦偺惉挿偺偨傔偵恄偐傜梌偊傜傟偨憽傝暔偩偲傕弎傋偰偄傑偡丅偦傟傜偼丄巹偨偪偺嵃偺惉挿偺偨傔偺戝愗側嫵嵽偩偐傜偱偟傚偆丅
丂 嫵嵽偲偄偆偺偼丄彫妛峑偐傜拞妛傊丄崅峑偐傜戝妛傊偲丄妛廗儗儀儖偑忋偑傟偽忋偑傞傎偳擄偟偔側偭偰偄偒傑偡丅偙偺応崌丄擄偟偄戝妛偺嫵嵽偲庢傝慻傓偺偼丄傗偝偟偄彫妛峑偺嫵嵽傪梌偊傜傟傞傛傝乽晄岾偱婥偺撆乿偲偄偆偙偲偵側傞偱偟傚偆偐丅偟偐傕偦偺嫵嵽偼丄帺暘偑儅僗僞乕偱偒側偄傕偺傪梌偊傜傟傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅擄偟偔崲擄偲巚偊傞嫵嵽偱傕丄偦傟傪忔傝墇偊傞擻椡偑偁傞偐傜偙偦丄梌偊傜傟傞偺偱偡丅戝偄側傞嬯擄丄怺偄斶偟傒丄廳偔偺偟偐偐傞帋楙側偳偼丄傑偝偵偙偺乽戝妛儗儀儖偺嫵嵽乿偲偄偭偰傛偄偺偱偟傚偆丅偙傟傜偺嫵嵽偵庢傝慻傓偙偲偼丄偩偐傜丄恑曕偟偨擻椡偺偁傞嵃偵梌偊傜傟偨摿尃偱偁傞偲偝偊偄偊傞偲巚偄傑偡丅恑曕偺戙彏偼忢偵帋楙偲崲擄偩偐傜偱偡丅
丂 恖娫偑惗傑傟偰偔傞偺偼嵃偺惉挿偺偨傔偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼丄慜夞偺島墘偱弎傋偨戅峴嵜柊偵傛偭偰傕丄悢懡偔偺旐尡幰偺徹尵偐傜柧傜偐偵偝傟偰偒傑偟偨丅偨偲偊偽丄僇僫僟偺僩儘儞僩戝妛偺庡擟惛恄壢堛偱偁偭偨僕儑僄儖丒俴丒儂僀僢僩儞攷巑偺尋媶偑偦偆偱偡丅攷巑偺尋媶偺傕偭偲傕拲栚偡傋偒揰偼丄惗傑傟曄傢傞慜偺傑偩楈奅偵偄傞偆偪偵丄懡偔偺恖乆偑師偺恖惗傪寁夋偡傞偲偄偆帠幚傪扵傝弌偟偨偙偲偱偟偨丅
丂 儂僀僢僩儞攷巑偺尋媶偱偼丄堦恖堦恖偺嵃偼丄帺暘偺慜悽偱偺懱尡偵偮偄偰偺昡壙傗斀徣傪傕偲偵丄偮偓偺揮惗偱偼偳偺傛偆側懱尡傪偡傞偐傪帺傜寛傔偰偄偔偙偲偑傢偐偭偰偒傑偟偨丅偨偩偟偦偺応崌偵傕堦恖堦恖偵巜摫楈偑偮偄偰偔傟偰丄偦偺屄乆偺嵃偵偳偺傛偆側僇儖儅偺晧嵚偑偁傞偐丄惗傑傟曄傢偭偰偳傫側揰傪妛傇昁梫偑偁傞偺偐傪傆傑偊偰丄暆峀偄彆尵傪梌偊偰偔傟傞偺偩偦偆偱偡丅
丂 偨偲偊偽丄攷巑偺旐尡幰偺偁傞彈惈偼戅峴嵜柊偺側偐偱丄乽巹偼偳傫側崲擄偑恖惗偺搑忋偵惗偠偰傕偦傟偵棫偪岦偐偭偰偄偗傞傛偆丄偮偓偺恖惗傪寁夋偡傞偺傪彆偗偰傕傜偭偰偄傑偡丅巹偼庛偄恖娫側偺偱丄愑擟傪夞旔偡傞偙偲偽偐傝峫偊偰偄傑偡偑丄忈奞傪忔傝墇偊傞偨傔偺壽戣傪帺暘偵壽偝側偗傟偽側傜側偄偙偲偼傢偐偭偰偄傑偡丅巹偼丄偮偓偺恖惗偱偼傕偭偲堄幆傪崅傔偰嫮偔側傝丄偝傜偵恑曕偟偰愑擟傪壥偨偟偰偄偐側偗傟偽側傝傑偣傫乿偲丄岅偭偰偄傑偡丅傑偨丄暿偺旐尡幰偼丄乽慜悽偱廫暘側埖偄傪偟偰傗傜側偐偭偨恖偨偪偑偄傞偺偱丄傑偨偙偺悽偵栠偭偰庁傝傪曉偝側偔偰偼側傝傑偣傫丅偙傫偳斵傜偑巹傪彎偮偗傞斣偵側偭偰傕丄嫋偟偰傗傞偮傕傝偱偡丅傑偨偙偺屘嫿偺楈奅傊婣傝偨偄堦怱偩偐傜側偺偱偡丅偙偙偑屘嫿側傫偱偡偐傜乿偲偄偆傆偆偵傕弎傋偰偄傑偡丅嘚
丂 楈奅偱偼偙偆偄偆傆偆偵丄帺暘偺慜悽偱偺惗偒曽傪斀徣偟偨傝丄偝傜偵廋峴偟偰楈惈偺岦忋傪栚巜偡寁夋傪偨偰偨傝偟側偑傜丄婷梸傪梷偊搟傝傗嫲晐傪捔傔丄垽傪崅傔偰丄揮惗偺奒抜傪堦偮偢偮徃偭偰偄偔偙偲偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅偦偟偰丄嵃偑偁傞儗儀儖傑偱惉挿偡傞偲丄忣弿柺偱偺惉挿偺偨傔偺揮惗偼昁梫偑側偔側傝丄崱搙偼丄懠偺恖傪捈愙彆偗傞偨傔偵帺傜巙婅偟偰惗傑傟曄傢傞偐丄偁傞偄偼丄楈奅偵偦偺傑傑偲偳傑偭偰丄楈奅偐傜偙偺抧忋偺恖乆傪彆偗傞偙偲傪慖傇偙偲偑弌棃傞傛偆偵側傝傑偡丅嘜
丂丂偄偢傟偵偟偰傕丄戅峴嵜柊偵傛偭偰偁偺悽偺婰壇傪傛傒偑偊傜偣偨旐尡幰偨偪偺徹尵偼丄婎杮揑偵偼傒側摨偠偱偁傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅偦傟偼丄乽偄傑偺偙偺悽偱丄帺暘偑偳偺傛偆側嫬嬾偵惗傑傟丄偳偺傛偆側恖娫偲偟偰惗偒偰偄傞偐偲偄偆偙偲偼丄偡傋偰帺暘偺愑擟偱偁傞丅側偤側傜丄帺暘帺恎偑偦傟傪慖傫偩挘杮恖偩偐傜乿偲偄偆偙偲偱偡丅偦傟傪儂僀僢僩儞攷巑偼丄乽偨偲偊尰忬偑偄偐偵崲擄偱傕丄偙偺尰忬偵変偑恎傪偍偄偨偺偼帺暘帺恎側偺偩丅恖偼偦傟偧傟丄帋楙傗嬯擄偺拞偵偙偦妛傃惉挿偡傞偨傔偺嵟戝偺婡夛偑偁傞丄偲棟夝偟偨偆偊偱偦偺帋楙傗嬯擄傪扵偟弌偟偰偄偔偺偱偁傞乿偲寢榑偯偗偰偄傑偡丅嘝
丂 偙偺乽帺暘偱慖傇恖惗乿偵偮偄偰偼丄傎偐偺尋媶幰偵傛傞戅峴嵜柊偺徹尵偵傛偭偰傕悢懡偔棤晅偗傜傟偰偍傝丄柕弬偼偁傝傑偣傫丅偨偲偊偽丄儅僀傾儈戝妛堛妛晹嫵庼偺僽儔僀傾儞丒俴丒儚僀僗攷巑傕丄戅峴嵜柊偺側偐偱旐尡幰偵懳偟偰弎傋傜傟偨巜摫楈偺偙偲偽傪偮偓偺傛偆偵徯夘偟偰偄傑偡丅
丂 偁側偨曽偼丄嫮梸傪崕暈偡傞偙偲傪妛偽側偗傟偽側傜側偄丅傕偟偦傟偑偱偒側偄偲丄偦偺嫮梸側惈奿偼懠偺傕偺偲堦弿偵師偺恖惗偵帩偪墇偝傟傞丅偦偟偰丄偦偺廳壸偼傑偡傑偡戝偒偔側偭偰偄偔偺偩丅堦夞堦夞偺恖惗偱僇儖儅傪曉偟偰偄偐側偄偲丄偦偺屻偺恖惗偼傑偡傑偡崲擄側傕偺偲側傠偆丅傕偟堦偮偺恖惗偱僇儖儅傪曉偟偰偟傑偊偽丄師偺恖惗偼傕偭偲梕堈側傕偺偲側傞偺偩丅偳傫側恖惗傪憲傞偐偼丄偁側偨偑帺暘偱慖戰偟偰偄傞丅偩偐傜偁側偨偼丄帺暘偺恖惗丂偵昐僷乕僙儞僩偺愑擟偑偁傞丅帺暘偱慖戰偟偨傕偺偩偐傜偩丅嘠
丂 偙偙偱偄傢傟偰偄傞乽傑偡傑偡戝偒偔側偭偰偄偔廳壸乿偼丄偙偺悽偱偺廋峴偺偨傔偺偄傑偟傔偲峫偊偰偄偄偱偟傚偆丅廳壸偦偺傕偺偼丄乽戝妛儗儀儖偺嫵嵽乿偲摨偠偱丄昁偢偟傕儅僀僫僗偽偐傝偱偼側偄偐傜偱偡丅偟偐偟丄廳壸偑儅僀僫僗偽偐傝偱偼側偄偲偄偭偰傕丄偨偲偊偽丄廳偄惛恄昦傗擏懱揑側忈奞側偳偺傛偆偵怺崗側栤戣傪帩偮偙偲偼偳偆側偺偱偟傚偆偐丅儚僀僗攷巑偑偍偙側偭偨戅峴嵜柊偺旐尡幰偺徹尵偵傛偭偰丄攷巑偼偙偺栤戣偵偮偄偰傕偮偓偺傛偆側摎偊曽傪偟偰偄傑偡丅
丂 忈奞傗崲擄偺崕暈偑丄楈揑側惉挿傪懀恑偡傞偲偄偆偙偲偼杮摉偱偡丅廳偄惛恄昦傗擏懱揑側寚娮側偳偺傛偆偵怺崗側栤戣傪帩偮偙偲偼恑曕偺偟傞偟偱偁偭偰丄戅曕傪堄枴偟偰偼偄傑偣傫丅巹偺尒夝偱偼丄偙偆偟偨廳壸傪攚晧偆偙偲傪慖傫偩恖偼丄戝曄偵嫮偄嵃偺帩偪庡偱偡丅傕偭偲傕戝偒側惉挿偺婡夛偑梌偊傜傟傞偐傜偱偡丅傕偟丄晛捠偺恖惗傪妛峑偱偺堦擭娫偲偟偨傜丄偙偺傛偆側戝曄側恖惗偼丄摨偠妛峑偱傕戝妛堾偺堦擭偵憡摉偟傑偡丅戅峴嵜柊偱嬯偟偄恖惗偺曽偑偢偭偲懡偔尰傟偰偔傞偺偼丄偙偺偣偄偱偟傚偆丅埨妝側恖惗丄偮傑傝媥懅偺帪偼丄晛捠偼偦傟傎偳堄枴傪帩偭偰偄側偄偺偱偡丅嘡
丂 偙偺傛偆偵丄嵃偑帺傜偺惉挿偺偨傔偵丄帪偵偼忈奞偺偁傞恎懱偱丄偁傞偄偼丄摿暿偺廳壸傪攚晧偭偰偙偺悽偵惗偒傞偙偲傪婅偆偙偲傕偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅帺暘偑愝掕偟偨栚昗傪払惉偡傞偨傔偵昁梫側娐嫬傪帺傜憂傝弌偡偨傔偱偡丅偙偺応崌丄暔棟揑側堄枴偱偼乽晄棙側乿棫応偵偍偐傟偰偄傞傛偆偵尒偊偰傕丄楈揑側栚偱尒傟偽丄揑妋偱姰帏側娐嫬偑慖偽傟偰偄傞丄偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆丅
丂 偙偺嵃偺庡懱揑側慖戰傪棟夝偟側偗傟偽丄巹偨偪偼偟偽偟偽丄偄偺偪偺帩偮堄枴偵偮偄偰傕廳戝側岆夝傪朻偟偰偟傑偆偙偲偵側傝偐偹傑偣傫丅堦偮偺椺傪偁偘偰傒傑偟傚偆丅
丂 堛妛敪払偺楌巎偺拞偱丄堦嬨幍乑擭戙偵擖傞偲丄挻壒攇偵傛傞戀帣恌抐傪捠偟偰丄弌惗慜偵戀帣偺愭揤揑側昦婥偺壜擻惈偵偮偄偰傕恌抐偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偨偲偊偽丄愭揤惈怱幘姵傪偲傕側偆僟僂儞徢偑敾柧偟偨応崌偵偼丄偦偺戀帣傪弌嶻偡傞偐偟側偄偐偲偄偆惗柦偺慖戰傕壜擻偵側偭偨偺偱偡丅恄屗巗偺曐寬壽偱偼丄傢偞傢偞懳嶔幒傑偱愝偗偰丄乽晄岾側巕嫙傪嶻傑側偄塣摦乿傪巒傔傑偟偨丅
丂 偙傟偵懳偟偰偼丄忈奞幰偺抍懱偑嫮偔斀敪偟傑偟偨丅忈奞傪帩偭偰惗傑傟偰偔傞巕傪丄偼偠傔偐傜乽晄岾側巕乿偲寛傔偮偗偰偟傑偭偰偄傞偺偼曃尒埲奜偺側偵傕偺偱傕側偄偲偄偆棟桼偐傜偱偡丅偙傟偼丄偒傢傔偰惓摉側斀墳偱偁偭偰丄楈揑師尦偱尒傟偽丄乽晄岾側巕嫙傪嶻傑側偄塣摦乿偼丄忈奞傪帩偭偰惗傑傟傞偙偲傪乽帺暘偱寁夋偟偰寛傔偰偒偨乿嵃偵懳偡傞旕忣側枙嶦峴堊偵側偭偰偟傑偄偐偹傑偣傫丅
丂 忈奞傪帩偭偰惗傑傟偰偔傟偽丄偨偟偐偵丄廃埻偺曃尒偵偝傜偝傟傞偩偗偱側偔丄條乆側晄帺桼傗惗妶傊偺廳埑摍偵傕懴偊偰偄偐偹偽側傜側偔側傝傑偡丅偟偐偟丄偦傟偑忈奞傪帩偭偰惗傑傟偰偔傞偙偲偺堄枴側偺偱偡丅摨帪偵偦傟偼丄傑傢傝偺恖偨偪偵丄偄偺偪偺恀幚偵栚妎傔偝偣丄恖娫垽偺偁傝偐偨傪懱摼偝偣傞婱廳側婡夛傪採嫙偡傞偙偲偵傕側偭偰偄偒傑偡丅恄屗巗偼丄嫮偄斀懳偵偁偭偰丄巐擭偱偙偺懳嶔幒傪攑巭偟傑偟偨偑丄偦傟偼摉慠偺側傝備偒偱偟偨丅
丂 偙偺忈奞幰栤戣傪峫偊偝偣傜傟傞丄傂偲偮偺奿岲偺帠椺偑偁傝傑偡丅亀屲懱晄枮懌亁偲偄偆杮偱偡丅乽忈奞偼晄曋偱偡丅偩偗偳丄晄岾偱偼偁傝傑偣傫乿偲昞巻偺懷偵彂偐傟偨偙偺杮偼丄偄傑嶰昐枩晹傪挻偊傞戝曄側儀僗僩僙儔乕偵側偭偰丄擔杮拞偱撉傑傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅挊幰偼憗戝惗偱丄壋晲梞嫥孨偲偄偆擇嶰嵨偺庒幰偱偡丅偛懚偠偺曽傕懡偄偲巚偄傑偡偑丄斵偵偼椉庤傕椉懌傕偁傝傑偣傫丅愭揤惈巐巿愗抐偲偄偆忈奞偱偡偑丄側偤偙偺傛偆側忈奞偑婲偙傞偺偐尨場偼偄傑偩偵傛偔傢偐偭偰偄側偄偦偆偱偡丅壋晲孨偼乽偲偵偐偔儃僋偼丄挻屄惈揑側巔偱抋惗偟丄廃埻傪嬃偐偣偨丅惗傑傟偰偒偨偩偗偱價僢僋儕偝傟傞側傫偰丄搷懢榊偲儃僋偔傜偄偺傕偺偩傠偆乿偲偙偺杮傪彂偒弌偟偰偄傑偡丅
丂 壋晲孨偼丄帺暘偺懱偵楎摍姶傪帩偮偳偙傠偐丄帺暘偵庤懌偑側偄偙偲傪丄扤偵傕晧偗側偄傎偐偲偼堘偆帺暘偺挿強偩偲巚偭偰偄傞傛偆偱偡丅偦偟偰丄乽懡偔偺恖偑寬忢幰偲偟偰惗傑傟偰偔傞側偐丄偳偆偟偰儃僋偼恎懱偵忈奞傪帩偭偰惗傑傟偰偒偨偺偩傠偆丅偦偙偵偼偒偭偲壗偐堄枴偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐乿偲峫偊偨斵偼丄乽忈奞幰偵偼弌棃側偄偙偲偑偁傞堦曽丄忈奞幰偵偟偐弌棃側偄偙偲傕偁傞偼偢偩乿偲偄偭偰丄暉巸妶摦偵忔傝弌偟偰偄偔偺偱偡丅偙偺寬峃側庒幰偵偼丄壗偺埫偝傕偠傔偠傔偟偨偲偙傠傕側偔丄斵偺巔偼偄偮傕柧傞偄岝偺拞偱婸偄偰偄傞傛偆偱偡丅
丂 斵偼丄杮偺拞偱丄彫妛峑帪戙偺巚偄弌偵怗傟偰師偺傛偆偵傕彂偄偰偄傑偡丅
丂丂忈奞傪帩偭偰偄傞巕偑僋儔僗偵偄傞偲丄偦偺僋儔僗偼昁偢偲尵偭偰偄偄傎偳丄偡偽傜偟偄僋儔僗偵側傞傛偆偩丒丒丒
栚偺慜偵偄傞憡庤偑崲偭偰偄傟偽丄側傫偺柪偄傕側偔庤傪戄偡丅忢偵懠恖傛傝傕桪傟偰偄傞偙偲傪媮傔傜傟傞尰戙偺嫞憟幮夛偺側偐偱丄儃僋傜偼偙偆偄偭偨偁偨傝傑偊偺姶妎傪幐偄偮偮偁傞丅
丂 彆偗崌偄偑偱偒傞幮夛偑曵夡偟偨偲尵傢傟偰媣偟偄丅偦傫側乽寣偺捠偭偨乿幮夛傪嵞傃峔抸偟偆傞媬悽庡偲側傞偺偑丄傕偟偐偡傞偲忈奞幰側偺偐傕偟傟側偄丅嘢
丂 偙偺垽偡傋偒庒幰偼丄惗傑傟偰偔傞慜偵楈奅偱寁夋偟偨娐嫬傪偦偺捠傝偵帺傜憂傝弌偟偰丄偦偺側偐偱丄崲擄偲晄帺桼傪柧傞偔忔傝墇偊丄傑傢傝偺恖偨偪偵垽偲婓朷偺岝傪搳偘偐偗偰偄傞偙偲偵側傞偺偱偟傚偆丅偙偺悽偱戝偒偔惉挿偟偮偮偁傞丄楈奅偺桪摍惗岓曗偲偄偭偰傛偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅
丂丂丂 偍丂傢丂傝丂偵
丂 壗擭偐慜偺偙偲偵側傝傑偡偑丄乽挬擔怴暦乿偺撉幰棑偵丄乽恖偑怣偠傜傟側偄乿偲戣偡傞搳峞偑嵹偭偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅椦旤榓偝傫偲偄偆堦嬨嵨偺僼儕乕傾儖僶僀僞乕偐傜偺搳峞偱偡丅偮偓偺傛偆偵彂偐傟偰偄傑偡丅
丂丂偍晝偝傫丄偍曣偝傫丄偁側偨曽偼妶帤偵側偭偨巹偺暥復傪撉傫偱堦懱偳偆巚偆偩傠偆偐丅偒偭偲壗偲傕巚傢側偄偩傠偆丅巵柤傪尒偰傕乽挿彈偲摨惄摨柤偺恖偑偄傞乿偖傜偄偵偟偐巚傢側偄偩傠偆丅
丂 偁側偨曽偼巹偺偙偲傪恖娫偩偲偼巚偭偰偄側偄丅帺暘偨偪偺惂嶌偟偨儘儃僢僩偖傜偄偵偟偐巚偭偰偄側偄丅偁側偨曽偼偄偮傕巹偵偙偆尵偭偰偄偨丅乽巕嫙偺偔偣偵恊偺尵偆偙偲偵岥摎偊傪偡傞偺偐乿乽偍慜側傫偐拞愨偟偨傎偆偑傛偐偭偨丅崱偐傜偱傕巰偹偽偄偄傫偩乿丒丒丒
丂 偦偆偄偄側偑傜丄偁側偨曽偼巹傪墸傝偮偗丄偗偲偽偟丄惛恄揑丄擏懱揑偵彎偮偗傞偙偲偵傛偭偰僗僩儗僗傪夝徚偟偰偄偨偺偱偟傚偆丅偁側偨曽偵偲偭偰垽偡傋偒巕嫙偼堦恖懅巕偺掜偨偩傂偲傝偱偁傝丄巹偼昁梫側偐偭偨偺偱偟傚偆丅昁梫偺側偄巕嫙側傜丄偳偆偟偰嶻傫偩偺偱偡偐丅偳偆偟偰堢偰偨偺偱偡偐丅巹偼拞愨偝傟偰傕丄僐僀儞儘僢僇乕偵幪偰傜傟偰傕崷傫偩傝偼偟側偐偭偨偺偵丒丒丒丂偍偦傜偔丄巹偼堦惗撈恎偱偄傞偩傠偆丅巹偵偼壠懓偼廥偄傕偺偲偟偐巚偊側偄丅
丂 偍晝偝傫丄偍曣偝傫丅巹偑偁側偨曽偐傜嫵傢偭偨偙偲偼丄恖偼怣偠傜傟側偄偲偄偆偙偲丅恖傪憺傓偲偄偆偙偲丅恖娫偼廥偄傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲丅偦偟偰丄偙偺悽偵惗傑傟偰偔傞偺偼嵟戝偺晄岾偱偁傞偲偄偆偙偲乕乕偨偩偦傟偩偗偩偭偨丅
丂 偙偺搳彂偼戝偒側斀嬁傪傛傃丄偄傠偄傠側恖偑偄傠偄傠側宍偺斀墳傪怴暦偵婑偣傑偟偨丅偁傞榋堦嵨偺妛堾挿偼丄乽椳偑億僞億僞偲怴暦巻偺忋偵棊偪偰偟傑偄傑偟偨丅棟桼偑傢偨偟偵傕傢偐傜側偄偺偱偡乿偲彂偒丄椦偝傫偲摨偠堦嬨嵨偺彈巕妛惗偐傜偼丄乽巹傕梒偄崰偐傜墸傜傟偰堢偪傑偟偨丅巹偑晝偵峈媍偡傞偲丄帞偄將偵偐傑傟偨帪偺傛偆偵媡忋偟偰朶椡傪傆傞偄傑偟偨丅巹偼拞妛偺崰偐傜帺嶦偡傞偙偲偽偐傝峫偊偰偄傑偟偨乿偲丄摨忣偺偙偲偽傪弎傋偰偄傑偟偨丅傑偨丄偁傞屲幍嵨偺庡晈偼丄乽偁側偨傕傕偆撈棫側偝偭偰偄傞偺偱偡偐傜丄側偤帺暘偑慳奜偝傟偨偺偐丄揙掙揑偵偍恞偹偵側傞傋偒偩偲巚偄傑偡丅暅廞偲尵偆偙偲偱偟偨傜丄傏偗側偄慜偱丄恊偑擭傪偲傝庛偔側偭偨帪偵栤偄媗傔傞偙偲偱偡丅偍慜偨偪偺惈偺塩傒偑側偗傟偽巹偼惗傑傟側偐偭偨偺偩偲丄偼偭偒傝尵偭偰偍傗傝側偝偄乿偲丄寖偟偄偙偲偽傪暲傋偰偄傑偟偨丅
丂 偙偺傛偆側栤戣偼丄偳偺傛偆偵峫偊偰偄偗偽傛偄偺偱偟傚偆偐丅堦偮偩偗偼偭偒傝偟偰偄傞偙偲偼丄扨側傞椳傪棳偡偩偗偺摨忣傗丄暅廞偺偡偡傔偩偗偱偼丄彮偟傕栤戣偺夝寛偵偼側傜側偄偲偄偆偙偲偱偡丅偦傟偱偼丄椦偝傫偼棫偪捈傟傑偣傫丅偙偺椦偝傫偑媬傢傟傞偲偡傟偽丄偳偺傛偆偵偟偰媬傢傟偰偄偔偺偱偟傚偆偐丅偦傟偼丄偙偙傑偱榖偟傪暦偄偰偔偩偝偭偨奆偝傫偵偼丄傕偆傛偔偍傢偐傝偺偙偲偲巚偄傑偡丅
丂 戝愗側偙偲偼丄乽抦傞乿偙偲偩偲巚偄傑偡丅恖娫偼丄抦傜側偄偲庛偄偟丄柪偄嬯偟傒傑偡丅媡偵丄抦偭偰偄傞偲丄恖娫偼嫮偄偟丄柪偄傕嬯偟傒傕偁傝傑偣傫丅婌傃偲婓朷傪帩偭偰億僕僥傿僽側惗偒曽偑偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅愄偐傜恖娫偼屽傝傪奐偔偨傔偵丄擄峴嬯峴傪偟偨傝丄嵋憐偵傆偗偭偨傝丄婩傝嶰枂偺惗妶傪懕偗偨傝偟偰偒傑偟偨丅偦傟偼偦傟偱懜偄偙偲側偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄側偐側偐杴恖偵偼恀帡偑弌棃傑偣傫丅巹偼丄傗偼傝乽抦傞乿偙偲偑戝愗偩偲巚偄傑偡丅偦偟偰偦傟偼丄扤偵偱傕偱偒傞偙偲側偺偱偡丅
丂 嵟屻偵丄傕偆堦搙偔傝曉偟偰尵傢偣偰偔偩偝偄丅乽抦傞乿偲偄偆偙偲偑戝愗偱偡丅恖娫偼扤偱傕岾偣傪柌尒傑偡丅偟偐偟丄恖娫偵偲偭偰岾偣偵惗偒傞偨傔偵昁梫側偙偲偼壗偱偟傚偆偐丅嵿嶻偱傕側偄丄柤梍偱傕側偄丄幮夛揑抧埵偱傕偁傝傑偣傫丅寬峃傗屲懱枮懌偱傕側偄偲偝偊偄偊傞偱偟傚偆丅恖娫偵偲偭偰岾偣偵惗偒傞偨傔偵昁梫側偙偲偼丄帺暘偲偼扤偐傪抦傞偙偲偱偡丅帺暘偑側偤偙偺悽偵惗傑傟偰偒偨偺偐傪抦傞偙偲偱偡丅楈奅偺恖偨偪偼丄偦傟傪堦惗寽柦偵巹偨偪偵揱偊傛偆偲搘傔偰偒傑偟偨丅暓嫵偺嫵偊傕丄偦傟傪巹偨偪偵抦傞偙偲傪孞傝曉偟懀偟偰偒傑偟偨丅恄摴傕庲嫵傕丄僀僗儔儉嫵丄僸儞僘乕嫵側偳傕偍偦傜偔傒傫側偦偆偱偟傚偆丅偦偟偰偦傟偼丄僉儕僗僩嫵偱傕椺奜偱偼偁傝傑偣傫丅
丂 惞彂偺拞偵偼丄惗偲巰偺幚憡偵怗傟偨恀棟偺偙偲偽偑偪傝偽傔傜傟偰偄傑偡偑丄僉儕僗僩偺嫵偊偱嵟傕戝愗側偙偲偼丄巹偨偪偑塱墦偺偄偺偪傪摼傜傟傞偩傠偆偲偄偆偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅巹偨偪偵偼塱墦偺偄偺偪偑偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅巹偨偪偼恄偺傕偲偱孼掜偵側傞偩傠偆偲偄偆偺偱偼偁傝傑偣傫丅巹偨偪偼恖庬丒崙壠傪挻偊偰偡偱偵孼掜偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅巹偨偪偑媮傔傟偽梌偊傜傟傞偩傠偆偲偄偆偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅偡偱偵梌偊傜傟偰偄傞偺偱偡丅昁梫側偙偲偼偦傟傪抦傞偙偲丄偨偩偦傟偩偗偱偡丅
丂 偛惔挳傪丄偳偆傕桳傝擄偆偛偞偄傑偟偨丅
丂拲
嘆 傾僀償傽儞丒僋僢僋亀僐僫儞丒僪僀儖亁乮戝撪攷栿乯島択幮丄
丂丂堦嬨嬨巐擭丄堦榋乑暸丅
嘇 Tony Ortzen, ed., The Seed of Truth--More Teachings
丂丂from Silver Birch--, Psychic Press, London, 1989,丂Chapt
丂丂1 偺東栿傛傝丅
嘊 擔杮偱偼丄傾儞丒僪僁乕儕乕曇亀僔儖僶乕丒僶乕僠偺楈孭亁
丂丂乮嬤摗愮梇栿乯丄挭暥幮丄堦嬨敧敧擭丄偑乮堦乯乣乮堦擇乯偺
丂丂堦擇姫杮偵側偭偰弌斉偝傟偰偄傑偡丅
嘋 偙傟傜傕巹偑東栿偟偨丄Tony Ortzen, ed., The Seed of Truth
丂丂丂--More Teachings from Silver Birch--, Psychic Press,
丂丂丂London, 1989, Chapt 1 偺堦晹偱偡丅
嘍 拲係偲摨偠丅
嘐 棫壴棽亀徹尵丒椪巰懱尡亁暥寍弔廐丄堦嬨嬨榋擭丄屲暸
丂丂嶲徠丅
嘑 棫壴棽丄慜宖彂丄巐堦乣巐巐暸丅
嘒 棫壴棽亀椪巰懱尡亁乮忋乯丄暥寍弔廐丄堦嬨嬨巐擭丄擇嶰暸丅
嘓 棫壴棽丄慜宖彂丄嬨乣堦乑暸嶲徠丅
嘔 儗僀儌儞僪丒儉乕僨傿亀偐偄傑尒偨巰屻偺悽奅亁乮拞嶳慞擵栿乯丄
丂丂昡榑幮丄堦嬨敧嶰
丂丂擭丄嶰堦乣嶰擇暸丅
嘕 棫壴棽丄慜宖彂丄巐擇嬨暸嶲徠丅
嘖 棫壴棽丄慜宖彂丄巐嶰乑乣巐嶰堦暸丅
嘗 僄儕僓儀僗丒僉儏僽儔乕丒儘僗亀巰偸弖娫偲椪巰懱尡亁
丂丂乮楅栘徎栿乯丄撉攧怴暦幮丄堦嬨嬨幍擭丄幍嬨暸丅
嘙 僄儕僓儀僗丒僉儏僽儔乕丒儘僗亀恖惗偼傑傢傞椫偺傛偆偵亁
丂丂乮忋栰孿堦栿乯丄妏愳彂揦丄堦嬨嬨敧擭丄嶰幍屲暸丅
嘚 僕儑僄儖丒俴丒儂僀僢僩儞亀椫夢揮惗亁乮曅嬎偡傒巕栿乯丄恖暥
丂丂彂堾丄堦嬨敧嬨擭丄榋屲乣榋榋暸丅
嘜 僽儔僀傾儞丒俴丒儚僀僗亀慜悽椕朄亁嘇乮嶳愳峢栴丒垷婓巕栿乯丄
丂丂俹俫俹尋媶強丄堦嬨嬨榋擭丄堦擇幍暸丅
嘝 僕儑僄儖丒俴丒儂僀僢僩儞丄慜宖彂丄堦堦屲暸丅
嘠 僽儔僀傾儞丒俴丒儚僀僗亀慜悽椕朄亁嘆乮嶳愳峢栴丒垷婓巕栿乯丄
丂丂俹俫俹尋媶強丄堦嬨嬨榋擭丄擇堦巐暸丅
嘡 僽儔僀傾儞丒俴丒儚僀僗丄慜宖彂嘇丄擇堦幍暸丅
嘢 壋晲梞嫥亀屲懱晄枮懌亁島択幮丄堦嬨嬨嬨擭丄嬨巐乣嬨屲暸丅
丂丂杮峞偼丄偙偡傕偡嵵応嶰奒戝儂乕儖偱堦嬨嬨敧擭屲寧擇巐擔偵峴側傢傟偨乽偙偡傕偡僙儈僫乕乿丂摿暿島墘偺撪梕偵壛昅廋惓傪壛偊偰傑偲傔偨傕偺偱偡丅杮峞偱傕丄堷梡売強偵偼偡傋偰拲傪偮偗偰丄塸彂偵偮偄偰偼曋媂忋丄栿杮柤偱弌揟傪柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟偨丅
丂丂慜夞偲摨條丄巹偺島墘偺撪梕傪偱偒傞偩偗懡偔偺曽乆偵峀偔抦偭偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆庯巪偱丄幮夛偵懳偡傞曭巇妶摦偺堦娐偲偟偰丄偙偺傛偆側彫嶜巕偺敪峴傪婇夋偟偰壓偝偭偨峚岥嵳揟丒峚岥彑枻幮挿偺偛崅攝偵丄偙偙傠偐傜岤偔偍楃怽偟忋偘傑偡丅
丂幱丂帿 丂
丂慜擭搙偵堷偒懕偒丄嶐擭偼屲寧擇巐擔偵丄暰幮偺嶰奒戝儂乕儖偱乽偙偡傕偡僙儈僫乕乿摿暿島墘夛偑奐嵜偝傟傑偟偨丅偙偺彫嶜巕偼丄偦偺島墘撪梕傪島巘偺晲杮徆嶰愭惗偵傑偲傔偰偄偨偩偄偨傕偺偱偁傝傑偡丅
丂愭惗偼丄偄偺偪偲偼壗偐偲偄偆廳戝側栤戣偵恀惓柺偐傜庢傝慻傒丄楈奅捠怣丄椪巰懱尡丄戅峴嵜柊側偳偺暘栰偱墷暷偺堛幰傗壢妛幰偨偪偵傛偭偰柧傜偐偵偝傟偰偒偨帠幚傪丄巹偨偪偵傕傢偐傝傗偡偔擬怱偵偍榖偟偔偩偝偄傑偟偨丅夛応偱恀寱偵帹傪孹偗偰壓偝偭偨悢懡偔偺挳廜偺曽乆偺姶摦偲偙偙傠偺桙偟傪丄偙偺彫嶜巕偐傜傕偔傒庢偭偰偄偨偩偔偙偲偑偱偒傟偽丄島墘夛偺庡嵜幰偲偟偰傕戝曄桳傝擄偔懚偠傑偡丅
丂恖惗偵偮偄偰偺恀棟傪妛傇偙偲偼丄巹偨偪憭嵳傪嬈偲偡傞幰偵偲傝傑偟偰偼丄偲傝傢偗廳梫側偙偲偱偁傝傑偡丅憭媀偲偄偆偺偼丄傕偲傛傝丄扨側傞斶偟傒偺媀楃偱廔傢傞傕偺偱偼側偔丄側偵傛傝傕丄偦偺恀棟偵棤晅偗傜傟偨傕偺偱側偗傟偽側傝傑偣傫丅偦偺忋偱丄懡偔偺婱廳側恖惗宱尡傪愊傑傟偰埨傜偓偺傆傞棦傊婣偭偰峴偐傟傞曽乆傪丄偙偙傠偐傜偺宧堄傪傕偭偰尩弆偵偍尒憲傝偡傞偺偑杮棃偺憭媀偱偁傠偆偲怱摼偰偍傝傑偡丅偦傟偩偗偵巹偨偪傕丄偙偺島墘偺偍榖傪娞偵柫偠偰丄巹偨偪偺惤堄偲恀怱傪丄偙傟偐傜偺偛曭巇偵妶偐偟偰偄偒偨偄強懚偱偁傝傑偡丅
丂偙偺彫嶜巕偑丄堦恖偱傕懡偔偺曽乆偵撉傑傟傞偙偲傪婩擮偟側偑傜丄晲杮愭惗側傜傃偵偙偺島墘夛偵偛弌惾偔偩偝偭偨懡偔偺奆條曽偵丄偁傜偨傔偰拸怱傛傝岤偔偍楃怽偟忋偘傑偡丅
丂丂堦嬨嬨嬨擭榋寧屲擔
丂丂丂丂丂丂姅幃夛幮 峚岥嵳揟丂丂戙昞庢掲栶 峚丂岥丂彑丂枻
丂 |