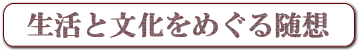ものの見方の違いについて
ー生活と文化をめぐる随想(57)ー (2007.07.01)
むかし、私がロンドンに住んでいた頃、クリスマス休暇をパリで過ごしたことがあります。モンマルトルのサクレクール寺院から階段を下りていく途中で、ふと見ると、若い女性のまわりにスズメが二十羽近くも群がって、差し伸べた手のひらから餌を食べていました。頭にも肩の上にも順番待ちをしているスズメが鈴なりになっているのです。日本では考えられないこのようなスズメの姿を、私はロンドンの郊外でも見たことがあります。これは、一般にイギリスやフランスを含めて西ヨーロッパ(以下、ヨーロッパといいます)では、そんなに珍しくはない情景ですが、なぜスズメは、人をあまり怖がらないのでしょうか。
日本では、スズメは大切な稲を食い荒らす害敵ですから、農家の人たちはスズメを見れば目の敵にして追い払ってきました。それが何百年も続けられると、スズメの方も、人間が近づいてきただけで怖がって逃げるようになります。スズメにとっては、人間は、いわば、何よりも恐ろしい天敵のようなものです。
ヨーロッパでスズメが人間をあまり怖がらないのは、日本の農耕・稲作文化とは違って、ヨーロッパが、伝統的に「スズメの害」とは無関係な、牧畜・肉食文化だから、といえそうです。ヨーロッパでは、古来、水(降雨量)と熱(気温)に恵まれず、土地も痩せているという厳しい自然環境の中で、農業生産性が極めて低いのが特徴的です。つまり、農業では食べていけないから、仕方なく羊や豚などの家畜を飼育することで命をつないできたわけで、その厳しい生存条件がもたらした肉食文化の伝統が、いまもヨーロッパの文化に色濃く残されているといっていいでしょう。
ロンドンから高速道路で北へ四時間ほど走ったところに、イギリスの古都ヨークがあります。このヨークの街の北端にひときわ高く聳え立っているのが、イギリス最大の中世建築として有名なヨーク大聖堂で、信仰と観光の中心地になっています。大聖堂の南に広がるヨークの街は、周囲の城壁がいまもほぼ完全に保存されていて、中世の面影を色濃く残していますが、石畳の似合う街の通りは狭く、特に、木骨造りの家々に挟まれた路地や路地裏に入り込むと、数百年の昔にタイム・スリップしたような気持ちになります。
日本でも大きな寺院・名刹には、門前市のような賑やかな場所がありますが、ヨーク大聖堂のすぐ南側にも、そのような一角があって、いつも大勢の国内、国外の観光客が跡を絶ちません。その一部にシャンブル(Shambles)と呼ばれる通りがあります。両側のくすんだ色調の木骨造りの店舗は、一階よりも二階、二階よりも三階が道路にせり出しているほぼ完全な中世の様式です。この繁華街は、実は、昔は軒並み家畜処理業者の店が並ぶ肉屋さんの街でした。「シャンブル」というのも、「家畜処理場」という意味です。
大聖堂からほど近い繁華街の一部が、家畜処理業者の店で占められていたというのも、肉食文化の名残で興味深く思われます。稲作文化の伝統が生きていた昔の日本では、家畜処理業者に対する偏見が強く、お寺の前の繁華街に店を構えるなどということは、全く考えられないことでした。いまでもその傾向は、「被差別部落出身者」への陰湿な、根強い差別・偏見となって尾を引いているようです。
しかし、イギリスを含めてヨーロッパでは、家畜を処理するというのは、主食を提供するということで、何よりも重要な職業のひとつでした。日本でなら、さしずめ、米屋さんということになるでしょうか。
日本人にとっては米は大切で、その大切な米を扱う業者が軽蔑されるようなことは決してありませんでした。それと同様に、ヨーロッパでは、家畜は何よりも大切な食料源で、それを処理する業者は、軽蔑されるどころか、しばしば、その土地の名士となって、地位と富と名誉を手にすることさえできたのです。
このような、ヨーロッパ人が家畜を何よりも大切にしてきた伝統は、彼らの動物愛護の精神の伝統にも表れてきました。日本人は、彼らが血のしたたるようなビフテキを食べながら動物愛護を説くのは矛盾だと言ったりします。しかし、これも、彼らが血のしたたるようなビフテキを「食べながら」ではなく、「食べるから」動物愛護を説く、と考えるべきなのでしょう。
その彼らも、逆に、日本人がスズメを焼き鳥にしたり、魚を「活き作り」にして食べるというのを聞いたりすると、日本人はなんと残酷か、と言ったりします。ものを見る場合、やはり、ひとつの狭い視野からだけでは、真実はなかなか見えてこないようです。特にグローバル化する今日の世界では、誰にとっても、多くの視点から広い視野でものを見ることが、大切な資質になるのかもしれません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
般若心経の「色即是空」をめぐって
―生活と文化をめぐる随想 (56)― (2007.07.01)
むかし、私がロンドンに住んでいた頃、ヴィクトリア駅裏側のビルの一室で開かれた仏教の会に参加したことがあります。京都で修行を積んだというイギリス人の尼僧が主宰する会で、その尼さんの講話があって、それが終わると、みんなで一斉にローマ字で書かれた般若心経を日本語読みで唱えました。
ローマ字は漢字などの表意文字とは違って、音声記号に過ぎませんから、カタカナで書かれた般若心経を読むようなものですが、それでも、日本語はほとんど理解しないであろうと思われるイギリス人の男女四十人ばかりが、尼さんに従って一斉に読み続けたのです。
その時の尼さんの話では、般若心経というのは真理のことばで、意味がわからなくてもそれを声に出して読むことが大切なのだということでした。ちょうど、意味がわからなくても写経が精神的な修行になるというのと同じようなことかもしれません。
しかし、この「意味がわからなくても」というのには、どうも少しひっかかるものを感じます。日本では、玄奘(げんじょう)が漢文に訳した般若心経を日本語読みで読んでいる人は数多くいますが、私たちに馴染みの深い漢字で読んでも、どれくらいの人が、その意味を本当に理解しているのでしょうか。仏教集団などで多くの信者が集まって般若心経を一斉に唱えているという情景は、日本でも決して珍しくはありません。でも、私には、その集団の姿は、ロンドンの仏教の会で、ローマ字で書かれた般若心経を意味もわからず斉唱しているイギリス人たちの姿と重なって見えてしまいます。
般若心経の二百六十余文字は、もっとも短い仏典として、古来、日本人にはひろく親しまれてきました。本の売れ行きに悩むことの多い出版社でも、般若心経の本だけはよく売れるといわれているようです。なぜ、この難解で意味が取りにくい漢語訳の般若心経が、日本ではこれほど人気が高いのでしょうか。それを探ろうとして、かつて、宗教に造詣の深かった山本七平氏が、『色即是空の研究』(日本経済新聞社、一九八四年)という本を出したことがあります。
山本氏はその本を書くために、「般若心経」と名のつく本を片っ端から読み始めたのだそうです。しかし、氏は二十数冊で読むのを止めてしまいました。「わかったのか、わからないのか、それがさっぱりわからない奇妙な状態になったからだ」と氏は書いています。
なんとかこの般若心経をわかりやすく訳せないものか。多くの人がそう考えて、夥しい数の翻訳書、解説書が出回ってきました。最近では、柳沢桂子さんの、心訳般若心経『生きて死ぬ智慧』(小学館、二〇〇四年)がNHKにも取り上げられて、ベストセラーになり、いまでも版を重ねているようです。このなかでは、「色即是空」はつぎのように「心訳」されています。
《形のあるもの、いいかえれば物質的存在を、私たちは現象としてとらえているのですが、現象というものは、時々刻々変化するものであって、変化しない実体というものはありません。実体がないからこそ形をつくれるのです。実体がなくて変化するからこそ、物質であることができるのです》
この訳は「科学的解釈で美しい現代語」と銘を打たれていますが、これで般若心経の心髄といわれている「色即是空」が、多くの読者に理解できるのでしょうか。やはり、「わかったのか、わからないのか、それがさっぱりわからない」と感じる人も少なくないように思われます。
さらに最近では、芥川賞作家の新井満氏が『自由訳・般若心経』(朝日新聞社、二〇〇五年)を出して評判になっています。新井氏は、「何百回読経してもよくわからなかった謎が、ついに解けた。瞬間、迷いが晴れ、不安が消えた・・・」と書いていますが、その新井氏の「色即是空」の「自由訳」は、こうです。
《この世に存在する形あるものとは、喩(たと)えて言えば、見なさい、あの大空に浮かんだ雲のようなものなのだ。雲は刻々とその姿を変える。そうして、いつのまにか消えてなくなってしまう。雲がいつまでも同じ形のまま浮かんでいるなどということがありえないように、この世に存在する形あるものすべてに、永遠不変などということはありえないのだ・・・》
しかし、これでもまだ、どうも分かるようで分かりにくいのです。私自身は、「色」とは眼に見える物質的なもので、「空」とは眼に見えない霊的なもの、と捉えると、少し分かり易いのではないかと考えています。
「色即是空」というのは、「形のあるものはすべて実は霊であって、霊であるからこそ形あるものとして存在できる。そして、形は不断に変わっていっても、その霊は不変で生まれることも死ぬこともなく永遠なのだ」ということを意味しているのではないでしょうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
死んでも生き続けるいのち
―生活と文化をめぐる随想(55)― (2007.05.01)
私たちは死んだらどうなるのでしょうか。死んだら灰になってそれで終わりになる、無に帰するだけだ、と考えている人もいます。一方、死んだら霊界へ行く、あるいは天国へ行って生き長らえると仏教やキリスト教では教えます。どちらが正しいのでしょうか。
仏典の、例えば、仏説阿弥陀経などには、極楽浄土の壮麗な美しさが詳しく述べられていますし、聖書のヨハネ伝十一章などには、「わたしはよみがえりであり、命である。私を信じるものはたとえ死んでも生きる。また、生きていてわたしを信じるものは、何時までも死なない」などとあります。
これらのことばどおりに、本当に、私たちが死んでも霊界や天国で生き続けるのであれば、死に対して抱いている根強い恐怖心も和らぐはずですし、たいへん心強いのですが、少し気にかかるのは、釈迦やイエスが自身で書き残したものは何もないということです。
仏典も聖書も、釈迦やイエスが言ったことを「私はこのように聞いた」とか「主はこのように言われた」などと、弟子たちがそれぞれのことばでまとめたもので、それらのことばは、長い年月を経て人から人へ、国から国へと伝えられていくうちに、翻訳の誤差を重ねながら、脚色され変容させられてしまうということもなかったわけではありません。
もしも、二千五百年前の釈迦のことばを直接聞けたら、二千年前のイエスの教えを直接耳にすることができたら、と思うのは無理というものでしょうか。釈迦やイエスでなくても、せめていま、現実に霊界や天国にいて、そこで生きている人に、「あの世」の正確な情報を知らせてもらうことが出来たら、と考えるのは全く荒唐無稽で、夢のまた夢でしょうか。実は、そうとばかりはいえないようです。
真剣に求めていきさえすれば、そのような極めて貴重な情報も、案外、少なくないことが分かってきます。ただ、「検証できない」と考えられている世界のことですから、贋宗教や金銭目あてのお告げの類もはびこっていることも否定できません。やはり私たちは、私たち自身のいのちに関わる重要な問題には、理性をはたらかせ、真偽を判断できる真実を見る目を持たなければならないのでしょう。
霊界にいて、霊界の情報を現代の私たちに伝えてくれている高位霊は、何人か居ますが、そのうちもっともよく知られているのがシルバー・バーチです。霊界で三千年を生き、地上人類を教化するために、五十年以上にも亘って、膨大な霊界の情報を伝えてきました。その教えは霊媒のモーリス・バーバネルの声帯を通してであるとはいえ、シルバー・バーチ自身の荘厳な現代英語で一語一句そのままを、いまテープで聞くことさえ出来ます。これは「世紀の奇跡」といっても決して誇張ではないかもしれません。
その地上人類への無償の愛と高遠な教えは、日本を含めた世界中の数百万人の信奉者を深く惹きつけてきました。そのシルバー・バーチは、霊界の壮麗な美しさについてこう述べています。
《私たち霊の世界の生活がどうなっているか、その本当の様子をお伝えすることはとても困難です。霊の世界の無限の豊かさについて、あなた方は何もご存知ありません。その壮大さ、その無限の様相は、地上のどの景色を引き合いに出されても、どこの壮大な景観を引き合いに出されても、それに匹敵するものはありません。》(『シルバー・バーチの霊訓 (8)』七六頁)
それでは、私たちのいのちについてはどうでしょうか。シルバー・バーチは、「人が死ぬということはありえないのです」と断言するのです。そして、次のように述べました。
《死は霊の第二の誕生です。第一の誕生は地上へ生をうけて肉体を通して表現しはじめた時です。第二の誕生はその肉体に別れを告げて霊界へおもむき、無限の進化へ向けての永遠の道を途切れることなく歩み続けはじめた時です。あなたは死のうにも死ねないのです。生命に死はないのです。》(『霊訓(11)』二〇二頁)
霊界にいて、いのちの真実を一生懸命に私たちに伝えようとしているシルバー・バーチは、私たちがいつまでも死の恐怖に捉われていることが歯がゆくてならないようです。テープでその声を聞いていますと、おかしみをかみ殺したような言い方で、このあと、こう続けています。
《「そもそも死というのは少しも怖いものではありません。死は大いなる解放者です。死は自由をもたらしてくれます。皆さんは赤ん坊が生まれると喜びます。が、私たちの世界ではこれから地上へ生まれて行く人を泣いて見送る人が大勢いるのです。同じように、地上では人が死ぬと泣いて悲しみますが、私たちの世界ではその霊を喜んで迎えているのです。》(『霊訓(11)』二〇八頁)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
極端に偏在する世界の富
―生活と文化をめぐる随想(54)― (2007.03.01)
一京(けい)四千三百六十八兆円という数字があります。「京」というのは「兆」の一万倍ですから、天文学的な数字になりますが、これは、ヘルシンキに本部がある国連大学世界開発経済研究所が発表した二〇〇〇年当時の世界個人資産の総額で、世界のGDP(国内総生産)の約三倍に当たるということでした。この数字をドルに換算すると、約一二五兆ドルになります。少し古いデータなので、いまならもっと大きな数字になっていることでしょう。
この報告書で驚かされるのは、世界のたった一パーセントの人が、この個人資産総額の四〇パーセントを保有し、上位一〇パーセントでは、その占有率は八五パーセントにもなるということです。しかも、その「上位一パーセント」に属しているのは米国(三七パーセント)と日本(二七パーセント)が突出しています。つまり、アメリカと日本には、途方もない大金持ちがいることになります。
この世界個人資産の総額を、世界中の人々に公平に分配すると仮定すると、一人当たり二万五千ドルになるようです。しかし、世界の貧しい地域では、例えば、コンゴ(旧ザイール)が一人当たり百八十ドル、エチオピアは百九十三ドルにしかなりません。
これに対して、日本は平均すると、一人当たりの資産が十八万一千ドル(約二千万円)もあって、米国の十四万四千ドルを抜いて世界一というデータもあるようです。ただ、物価水準を考慮した購買力平価で計算すると、日本はスイスや米国、英国を下回るのだそうですが、いずれにしても、私たち日本の個人資産は、一人当たりの平均でさえ、コンゴやエチオピアに比べれば、その格差は千倍規模の大きさなのです。(「朝日」’06.12.06、「佐賀」12.12)
日本人は世界のトップクラスの個人資産を持っているといわれても、日本国内でも最近は大きな個人資産の格差がありますから、一般の庶民にとっては、あまり実感が伴わないのが普通です。しかし、それでも、私たちはこの世界的に見た千倍規模の格差のうえで、少なくとも物質的には、あまり不自由なく生きていることは否めないでしょう。
二〇〇〇年九月に開かれた国連ミレニアム・サミットでは、世界の貧困撲滅という目標を掲げ、当時十億人以上が直面している悲惨で非人道的な極度の貧困状態から解放するため、「二〇一五年までに、一日の所得が一ドル以下の人口の比率、及び飢餓に苦しむ人口比率を半減すること、また同期日までに、安全な飲料水を入手できず、またはその余裕がない人口比率を半減することを決意する」という、ミレニアム開発目標を世界に向かって公約しました。しかし、それから六年経ったいまも、世界の貧困や飢餓は改善されるどころか、ますます悪化しているようです。国際的なNGOの告発によれば、一日一ドル以下の生活を送る人は十二億人。満足な食事にありつけない人は八億人。極度の貧困により命を落とす人の数は一日に三万人。およそ三秒に一人が絶対的貧困・飢餓で死んでいます。
そのような悲惨な状況とは裏腹に、日本やアメリカなどの先進国では、一部の大金持ちたちがさらに資産を激増させているという形で、好景気が謳歌されているようです。例えば、株価高騰や大規模な企業合併等で好況に沸くアメリカの証券業界では、ゴールドマン・サックスなどの大手が軒並み過去最高益を記録するなど活況が続き、ボーナスも極端に跳ね上がりました。ゴールドマン・サックスのロイド・ブランクファイン最高経営責任者のボーナスにいたっては、その額は実に約五千三百万ドル(約六十三億円)、ウォール街の史上最高額になったと、アメリカのメディアも一斉に報じたほどです。(「朝日」’06.12.21)これも資本主義のルールでは正当なのかもしれませんが、やはり、どこかに何か大きな間違いがあるような気がしてなりません。
九・一一テロをきっかけに、米国をはじめとする先進国は、「テロとの戦い」を最重要の国際的課題と位置づけるようになりました。そのために、アフリカをはじめとする多くの国々の絶対的貧困・飢餓の問題、さらには地球規模での環境問題は、すべて後回しにされてしまっています。しかし、千倍規模の世界的な貧富の極端な格差を是正しようともせず、さらにその格差が広がりつつある現状が放置されているかぎり、世界から憎しみや暴力・テロが無くなることはないのかもしれません。
人類はすべて同胞ですし、それだけに、私たちの耳には高位霊シルバー・バーチの次のようなことばが、いまは、ことさらに強く響いてくるように思えてならないのです。
《物的存在物はいつかは朽ち果て、地球を構成するチリの中に吸収されてしまいます。ということは物的野心、欲望、富の蓄積は何の意味もないということです。一方あなたという存在は死後も霊的存在として存続します。あなたにとっての本当の富はその本性の中に蓄積されたものであり、あなたの価値はそれ以上のものでもなく、それ以下のものでもありません。》(潮文社『シルバー・バーチの霊訓6』)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
霊界探訪を繰り返す人たち
―生活と文化をめぐる随想(53)― (2007.01.01)
浄土真宗のお経の中に、「仏説阿弥陀経」というのがあります。お釈迦様が大勢の弟子たちを前にして、西の方はるか彼方に、極楽という世界があることを教えているお話です。そこでは阿弥陀仏が今も法を説き続けている。その極楽というのは光り輝く壮麗な世界で、人は誰でも、阿弥陀仏の名号を唱えることによってその極楽に往生できる。そしてそのことは、東西南北上下の六法世界の数多くの諸仏によっても証明されているのだ、というような内容だと思います。私は、一九八三年に妻と長男を一度に亡くした辛い経験をもっていますが、当時、このお経をよんでいて、「これは嘘ではない、本当のことなのだ」と何度も何度もくり返して述べられていることばに、わずかながらも心を癒されたような気持ちになったことがありました。
それでも、「はるか西の彼方に極楽がある。これは嘘ではない」と言われても、つい「本当だろうか?」と思ってしまいます。地球は球形で一回りすると約四万キロです。今は飛行機で割合簡単に地球を一周できますから、日本から飛んで西へ西へと行けば、またもとの場所、つまり日本に戻ってきてしまいます。極楽はどこにあるのでしょうか。地球の上ではなくて、それは、西の空のかなたにあるのだ、と言われても、そこには無限の大空が宇宙の果てまで広がっているだけです。極楽とはその空の彼方にあるのでしょうか。それこそ何か、雲を掴むような話で、どうも実感が湧かないような気がするのが普通なのかもしれません。
しかし、二、三十年前から、アメリカのキュブラー・ロス博士の臨死体験をはじめとする死後の世界の調査や研究がいろいろと発表されてきて、いまでは霊界の様子も、ある程度、より具体的なイメージで描くことが出来るようになってきました。なかでも注目させられるのが、体外離脱の研究と実践で知られるアメリカのモンロー研究所の霊界探訪に参加して、直接、自分の目で霊界を見てきたという日本人も増えてきていることです。
その口火を切ったのが、二〇〇三年に、「臨死体験」を超えるといわれる『死後体験』(ハート出版)を書いた坂本政道さんでした。彼は、この本の最後に、「ひとつだけもう一度言っておきたいことがある。それはわたしは超能力者ではない、ごく普通の人間だということだ。そういう人でも好奇心と熱意さえあれば、死後の世界を探索し、未知を既知に変えることができる」と書いています。
この坂本さんは、東京大学、カナダのトロント大学大学院で学んだハイテク・エンジニアです。死後の世界への好奇心から、二〇〇一年以来、アメリカのバージニア州にあるモンロー研究所を度々訪れ、体外離脱や死後体験を重ねてきました。
このモンロー研究所には、二〇〇五年の時点で世界中からすでに一万人以上の人びとが訪れているそうですが、そのなかには、坂本政道さん以来、何人もの日本人も含まれているようです。坂本さんと同じように、大学では電子工学を学んだ森田健さんもそのうちの一人です。
森田さんも「超能力者ではないごく普通の人」ですが、彼もまた、モンロー研究所で何度も霊界訪問を繰り返して、霊界では、亡くなった長男や父、祖母と会って、いろいろと助言や教えを受けたりしてきました。彼は、その記録を『「私は結果」原因の世界への旅』(講談社、二〇〇五年、α文庫)などに書いています。
結局、霊界とはこの地球を含めた宇宙のことであると考えると分かりやすいかもしれません。つまり、霊界の人たちも私たちも裏腹の関係でこの同じ宇宙に住んでいるわけです。地上は霊界の一つの影であるに過ぎません。
この地上で鈍重な肉体を具えた人間は、さまざまな欲望に捉われて、いわば、粗くて重い波動のなかで生きていますが、肉体から開放されて魂が自由になり、利己的な欲望から離れていけばいくほど、そして、他人に対する優しさや思いやりの気持ちが高まっていけばいくほど、波動は細かく軽くなり、宇宙の高いところへ登っていくことになります。
この世の波動は一〜二一で、「見える」世界です。波動が二三になると見えなくなりますが、これが幽界で、肉体を離れた後はまずここへ行くことになります。二四〜二六までは、まだまだ囚われの世界で、やすらぎの霊界は、二七あたりから始まるようです。そして、冒頭の阿弥陀経に描かれている世界は、おそらく、波動三五以上の太陽系や銀河系をも越える世界で、これがいわゆる「極楽」と考えていいのでしょう。霊界というのは、厳然たる界層社会ですから、私たちが、この地球上で生きているうちに示した生き様によって、波動が粗くも細かくもなり、霊界へ行ってからの住む世界を決定すると考えてよいようです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
無限に広がる魂のふるさと
―生活と文化をめぐる随想 (52)― (2006.11.01)
福岡県直方(のおがた)市の須賀神社には、落下が目撃された隕石のなかでは世界最古といわれるものが、木箱に入れられた状態で保存されています。木箱のふたには貞観(じょうがん)三年と書かれていて、これは西暦にすると八六一年ですから、この隕石が落ちてきたのは今から千百四十五年前のことになります。
この直方隕石の落下の時から、千百三十一年経った一九九二年に、今度は、島根県美保関(みほのせき)町の民家の屋根に、別の隕石が落ちてきました。ところが、この隕石は、その成分を調べてみますと、直方隕石と同じ母体から六千万年前に宇宙空間に飛び出した「双子」であることがわかったというのです。当時の新聞では、「六千万年漂いわずか千百年の差で落下」などと報道されました。(「朝日」93・5・15)
このニュースは、その頃、「六千万年も宇宙を漂った後、広い太陽系では、極めて小さな点にしか過ぎない地球上の、しかもほぼ同じ場所に、千百年を隔てて二つの隕石が落ちたことになる。ものすごい偶然だ」などと言われたりしていました。直方と美保関町との間の距離は、約三百キロですが、これは、宇宙の尺度では、「ほぼ同じ場所」です。「千百年を隔てて」というのも、宇宙の尺度では、「ほぼ同時に」ということになるでしょう。
現在、地球上の科学の目で捉えられている最も遠い、従って最も古い銀河は、百二十八億八千万光年彼方にあるといわれています。国立天文台や東京大学の研究チームが、ハワイのすばる望遠鏡で観測したもので、ついこの間、その映像が公開されました。(「朝日」06・9.14) 光速は、いうまでもなく、一秒間に三十万キロの光の速さを基準にしていますから、この銀河は、この光の速さで測って、百二十八億八千万年かかるところにあるということです。宇宙そのものは、百三十七億年前のビッグ・バンにより誕生したという説がいまのところ有力です。すると、この銀河は、宇宙誕生の「わずか」八億二千万年後の古い姿が捉えられていることになるわけです。
これとは逆に、二〇〇四年末には、これまで見つかった中では最も幼い赤ちゃん銀河の画像が、アメリカの宇宙望遠鏡科学研究所によって公表されていました。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したもので、その年齢は、「たった五億歳」ということでした。(「朝日」04.12.2)
このように、宇宙にはいろいろな銀河がありますが、その総数はどれくらいになるのでしょうか。宇宙誕生直後では一万個くらいと推定されたりしていました。それが、一九九九年一月七日に米天文学会で発表された宇宙望遠鏡科学研究所の記録では、約千二百五十億個だそうです。これは、それまで推測されていた八百億個よりも六割近くも多くなっていますから、今なら、もっと増えているのかもしれません。それにしても、この宇宙の想像を絶する広大な広がりには、ただただ圧倒される思いです。しかし、実は、この宇宙が私たちの魂の本来の故里(ふるさと)ではないでしょうか。
ところで、「私は宇宙へ行きたい」という民間人の夢を叶えてくれる宇宙旅行は、いま、現実のものになろうとしているようです。(「朝日」06.9.16) たとえば、「ソユーズで行く月旅行」というのがあります。旅行代金は百二十億円で、ソユーズロケットを使い、ブースターの力で月に接近し、裏側をも回る、というもので、早ければ再来年の二〇〇八年には、打ち上げ予定といわれています。それよりも少し安い宇宙ステーション滞在の二四億円コースというのもあるようです。九日間の日程で地表から四百キロの上空まで上がり、国際宇宙ステーションに滞在する予定で、すでに三名が体験しているという触れ込みです。
二四億円は払えないが、二千万円くらいなら何とか、という人のためには、地上百キロを越えた大気圏外に飛び立つ「宇宙弾道ツアー」というのもあって、これには、日本人も五名ほど、予約している人がいるようです。往復二〜三時間のフライトの間に約二五分間宇宙空間に滞在し、数分間の無重力状態も体験できるといいます。地球はまん丸には見えなくても、緩やかな曲線を描く青い輪郭が漆黒の宇宙空間から堪能できるということです。
日本を外国から見るということは、視野を広げるという意味でも非常にいい勉強になりますが、これはもう、いまでは当たり前のようになってきました。一歩進んで、このように地球を外から見るというのも、確かに、それ以上にいい体験になるのでしょう。しかし、宇宙旅行といっても、それはあくまでも地球の尺度での話であって、宇宙の尺度では、それこそ、「地上旅行と同じ」ということになってしまうのかもしれません。私はむしろ、私たちが霊界へ「里帰り」する時にこそ、宇宙の尺度での「宇宙旅行」を無料で体験できるのではないかと、密(ひそ)かに考えたりしています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
富者が負う社会的責任
―生活と文化をめぐる随想 (51)― (2006.09.01)
聖書の「マタイ伝」19章に、ある資産家の若者の話が載っています。若者がイエスに近寄ってきて、「永遠の生命を得るためには、どんなよいことをしたらいいでしょうか」と訊きます。それに対してイエスは、「殺すな、盗むな、姦淫するな、父母を敬え、隣人を愛せよ」という戒めを説いたのです。すると青年は、「それはみな守ってきました。ほかに何が足りないのでしょう」と重ねて訊きました。イエスは、こう答えました。「もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人びとに施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして、わたしに従ってきなさい」。
その若者は、このことばを聞くと、悲しみながら立ち去っていきました。沢山の資産を持つ金持ちであったからです。そのときにイエスが弟子たちに言ったことばが、よく知られている「らくだと針の穴」の譬えです。
イエスは、「富んでいる者が神の国にはいるのは、むずかしいものである」と言ったあと、「富んでいる者が神の国にはいるよりは、らくだが針の穴を通る方が、もっとやさしい」と続けたのです。(23-24)
アメリカはキリスト教が盛んな国で、一部とはいえ、このようなイエスの教えがいまも生き続けている社会と言っていいでしょう。
かつて、アメリカの伝説的な鉄鋼王アンドリュー・カーネギーは、「子孫に美田を残すのは愚行でしかない」と述べて、莫大な私財の多くを、社会活動につぎ込んだことが知られています。その後も、アメリカンドリームを実現した多くの成功者がその蓄積した富を社会に還元し、福祉や教育、文化の担い手になってきました。その風潮は、一般市民にも及んで、たとえば、アメリカの大学の特徴の一つは、数多くの校舎や寄宿舎が、個人からのそのような寄付金で建てられ、日本に比べれば桁違いに多くの学生たちが、寄付金による奨学資金の恩恵を受けて勉強を続けていることでしょう。
いまのアメリカで、ビル・ゲイツ氏といえば、世界一位の市場占有率をもつマイクロソフト・ウィンドウズを開発したマイクロソフト社の創業者で、個人資産では、世界一の金持ちといわれています。アメリカの雑誌「フォーブス」の一昨年の長者番付によると、資産総額は推定で四百八十億ドルといいますから、日本円ではざっと五兆四百億円くらいでしょうか。ちょっと、想像もつかないような大金持ちです。
そのビル・ゲイツ氏も熱心な慈善事業家で、巨額の私産を投入して、奥さんのミリンダさんとともに「ビル・アンド・ミリンダ・ゲイツ財団」を設立しました。世界の貧困対策や途上国支援に積極的に取り組み、アフリカの貧困と疾病の救援を訴えながら、子供たちに予防接種を広める組織への
七億五千万ドル(約七百七十億円)の寄付をするなど、幅広い慈善活動を継続しています。
ビル・ゲイツ氏に次ぐ世界第二の金持ちは、ウォーレン・バフェット氏というアメリカ人実業家で、株式投資と企業買収で巨額の財を築き上げた立志伝中の人物として有名です。この間、そのバフェット氏が、自分の資産の大半にあたる三百七十億ドル(約四兆三千億円)を、ゲイツ氏の慈善財団に寄付することが報じられました。(「朝日」06.7.4)
その金はすべて、世界の貧しい子供への医療や教育に使われるのだそうです。バフェット氏も、「子孫に美田を残す」のは愚かであると考えているようで、金持ちの相続税負担軽減などにも反対してきました。「富んでいる者が神の国に入るのは難しい」ことをよく理解している賢者といえるのかもしれません。
もちろんアメリカにも、強欲な富者が決して少なくはありません。特に一九八〇年以降は、経営者が法外な報酬を得る傾向が強まり、貧富の差をますます拡大させて、アメリカ社会に暗い影を落としてきました。そして、その傾向はいま日本でも広がろうとしています。
インサイダー取引で莫大な利益をあげて逮捕された村上被告が、「金もうけ、悪いことですか」と開き直った発言は、先にライブドア事件で逮捕された堀江被告の「カネで買えないものなどあるはずがない」と同様、聞く者のこころに寒々としたものを感じさせました。
最近では、一部の富者たちが、税負担を嫌って海外へ住所を移すという、こころの貧しさを露呈しているような事例がいくつも報道されています。「貧しきを憂えず、等しからざるを憂う」のが、長い間、日本の社会の在り方だとされてきましたが、それも、徐々にくずれてきて、いまは、社会も荒れ、モラルの低下も、至るところで目につくようになってきました。弱者に対する思いやりと優しさを失って、日本の社会はこれから一体、どこへ向かおうとしているのでしょうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
No,1〜No,10へ
No,11〜No,20へ
No,21〜No,30へ
No,31〜No,40へ
No,41〜No,50へ
|