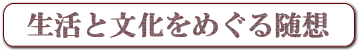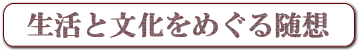|
オリオン座ベテルギウスの最後の大爆発
―生活と文化をめぐる随想 (80)―
私たちの住む地球は、一周すると約4万キロもあり、その上には現在、69億6500万人もの人間が住んでいますから確かに広大です。私たちはこの地球からはみだして住むことはできませんから、現実的な感覚ではこの地球が極大であるともいえるでしょう。しかし、これほど大きな地球も、宇宙から眺めると、ほんの粟粒一つ、米粒一つにもならないような、ちっぽけな存在になってしまいます。極大も、見方によれば極小です。そして、どれほど地球が小さいか、ということは、どれほど宇宙が大きいか、ということでもあります。
その宇宙の大きさを測る尺度が光速ですが、これはいうまでもなく、秒速30万キロメートルです。一秒間に地球を7.5回もまわるほどのものすごい速さを基準にしてそれが1年間に進む距離を1光年として測っていくわけで、この速さで測ると、月からの光が地球に届くまでの時間は、わずかに1秒、太陽からは8分です。これは「光年」に換算するとゼロに近くなり、その意味では、ほとんど地球に密接しているといえないこともありません。宇宙全体から見れば、太陽の周りを回っている水星、金星、地球、木星、土星等を含めて広大無辺に思える太陽系そのものでさえ、みかん一つ、りんご一つほどの大きさに縮小されてしまうのです。
私たちが地球から見上げる夜空には、様々な無数の星を見ることができます。晴天で条件のよい山中などでは、すぐ頭上に星が一面に広がって、降るように輝いていることもあるでしょう。しかし、そのほとんどは、地球からは気の遠くなるような彼方にあります。一番近くにある恒星でさえ光の速さで4年、ベガからは25年、ある種の銀河からは何十億年もかかります。いまは天体望遠鏡のめざましい進歩もあって、クエーサーという光度が銀河系全体の一万倍もあるような天体まで、観測できるようになりました。そのなかには120億光年の彼方に位置するものもあると聞いたりしますと、もう想像を絶するというほかはありません。
これを書いている現在も、NHKのBS放送では「Cosmic Front」のタイトルで、さまざまな宇宙の姿を続き物にして放映していますが、先月のはじめには、オリオン座の肩の部分に位置するベテルギウスという星を取り上げていました。これは私たちの肉眼では点にしか見えませんが、直径が最大で14億キロメートルもあって、太陽の1000倍の大きさです。地球からの距離は640光年で、光の速さで640年もかかるわけですから、かなり遠いように思えます。しかし、これも宇宙の尺度では、「至近距離」になるのだそうです。問題は、この星がその生涯の99.9パーセントを終えて、いままさに死を迎えようとしていることです。それが超新星爆発で、その大爆発を起こす「死」の直前には、太陽の3億個分の明るさで輝くといいますから、その至近距離にある地球でも、このベテルギウスの死は、有史以来の大ニュースになることは間違いないでしょう。
この地球で人間が生まれては死んでいくように、そしてまた、死んでは生まれてくるように、宇宙の星も、やがて寿命がくれば爆発を起こして死んでいき、そしてまた、爆発で宇宙に飛び散ったガスやチリが集まって、やがて新しい星が誕生していきます。星が爆発する場合には、その明るさが急激に増大しますが、その明るさの特に大きいものが超新星です。その最も遠いものは、1987年に観測された超新星1987Aで、それは、16万年光年の彼方で起こった大スペクタルでした。そのほかの超新星爆発では、1万6千光年のケプラー新星、7千8百光年のティコ新星、6千5百光年のかに星雲などがあります。これらに比べれば、ベテルギウスの640光年というのは、確かに、文字通り桁違いに近いことが分かります。
そのベテルギウスは地球から「至近距離」にあるだけに、夜空を見上げれば、オリオン座の一角で光っているのが、肉眼でもよく見えます。それが最後の死の瞬間には、真っ赤に膨れ上がって大爆発を起こし、温度が急上昇するために色が青く変わるといいます。1時間後にはその輝きは、どの星よりも大きくなり、3時間後には、満月のおよそ100倍にもなるといわれていますから、昼間でさえ、青空のなかで明るく煌いている状態になるようです。しかも、その状態が3か月も続くそうですから、世界中でこの「天変地異」は大きな驚愕をもたらすことでしょう。
ブリタニカ百科事典には、「超新星は多量の宇宙線を放出する。もし太陽から数百光年離れた場所で超新星爆発が起これば、地球上の生物は死ぬか、生物進化の過程に大きな影響を残すと思われる」などと書かれていますが、他人事ではありません、ベテルギウスの大爆発はまさにこれに当てはまります。危険なのはガンマ線で、その直撃にあうと地球のオゾン層が破壊されてしまいます。その結果、地上の生物はすべて有害な紫外線に曝され、69億6500万人もの地球人口もその生存を脅かされてしまうことになります。
この問題については、NHKの番組では、世界各地で天文学者たちが真剣に観測や計算を続けてきて、ガンマ線を放出するベテルギウスの自転軸が地球に対して20度ずれていることがわかったと伝えていました。2度以内なら危険なのですが、20度ずれておれば、影響はないということになっているようです。粟粒一つにもならないようなちっぽけな地球だから、ガンマ線の束も命中せず、なんとか難を逃れられそうだといえないこともありません。
安全であることがわかって、いま世界中の天文学者、地球物理学者たちは、このベテルギウスが99.9パーセントの生涯をすでに終えていることが分かっているだけに、いつ大爆発を起こすかと固唾を呑んで見守っています。日本の岐阜県飛騨山中の地下千メートルにある宇宙線観測施設「スーパー・カミオカンデ」も、爆発の直前に飛び出してくるはずのニュートリノを捉えるために「臨戦状態」で、目が放せない状況にあるようです。その大爆発が、来年の2012年に起こると予測している学者もいるようですが、もしその予測が当たるとすれば、私たちも、世界中の人々と共に、有史以来の壮大なドラマを目撃できることになります。
しかし、実際には、おそらくベテルギウスは、もう大爆発を起こしてしまっているのでしょう。オリオン座のあの場所にはもう存在していないかもしれません。至近距離とはいえ、ベテルギウスは640光年の彼方にあります。つまり、私たちがいま夜空で見ているベテルギウスは640年前の姿で、紀元1360年頃の映像がいま地球に届いているのです。日本では足利尊氏が開いた室町幕府がまだ続いていて、ヨーロッパでは14世紀の半ばにペストが大流行して全人口の3人に1人が犠牲になった後遺症がまだ色濃く残っている頃です。
大宇宙のなかでは粟粒一つにもならないような地球の上に住んで、そのちっぽけな尺度でものを見たり判断したりすることに慣れきってしまいますと、この宇宙の広さを理解していくのはなかなか容易ではありません。2011年10月現在、空を見上げますと確かにあのオリオン座の一角にベテルギウスが見えますが、すでに述べたようにあれは実は640年前の姿で、いま現在の本当のベテルギウスの姿を見るためには、私たちはさらに640年も待たねばならないことになります。2651年のその時の人類が夜空を見上げてオリオン座を眺めたとしても、これも繰り返しになりますが多分ベテルギウスはもうそこにはなく、おそらく大爆発を起こした後のガスやチリが渦巻いていて、また再生に向かっての壮大な誕生のドラマを展開しているのかもしれません。
(2011.10.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
闇夜のバルト海で見た赤い飛行物体の真実
-生活と文化をめぐる随想 (79) -
もう8年前になりますが、私はこの随想集(No.34)に、「闇夜のバルト海にて」という文を載せています。2003年11月1日のことです。そこでは、「去る9月28日の夕方、私は北欧スウェーデンのストックホルムから、フィンランドのヘルシンキへ向かう三万五千トンのフェリー・ガブリエラ号に乗っていました。六階の海側の個室の窓から見えていたバルト海は、曇天で六時頃には真っ暗になって、どこまでも深い闇がひろがっていただけです」と、私は書き出しています。
翌日の忙しい行程に備えて、私は午後10時過ぎにはもうベッドに横になっていましたが、夜中のちょうど12時に私はふと目を覚まし、船室のカーテンを開けて、夜のバルト海に目を向けてみました。その時に不思議な光景が眼に飛び込んできたのです。船から遠く、おそらく百メートルも二百メートルも離れた海上に、鳥のように見える物体が赤く光りながら、水平に、そして左右に、三本、四本、五本の線になって、素早く飛んでいました。
しかし、赤色に光って飛ぶ鳥などというものは、常識で考えても、とてもあり得るとは思えません。あまりに不思議なので、私は、幻覚ではないかと何度も思ったりしましたが、何度見直しても、やはり間違いはありません。念のために、目覚ましを三時にセットして、三時に起きあがり、もう一度、窓の外を眺めてみました。外は相変わらず、漆黒の闇でした。そしてやはり、赤い光を発する物体が、左右に速い速度で飛んでいました。ちょうど流れ星が横に流れているような感じで、鮮明に目に映ります。
翌日、私は現地の人に、「この海ではこういう光景が見られるのか」と訊いてみようと思いましたが、どう考えても幻覚だと一笑に付されそうで、やめました。帰国してから、山科鳥類研究所へ電話し、手紙も出して、その実体を知ろうとしましたが、やはり、「鳥が赤い光を出して飛ぶことはあり得ない」ということで、その実体を探索する道は絶たれてしまいました。それでも、事実は事実として否定することはできません。私は、その時のこのエッセイを、「いま、私の頭に残っているのは、あの赤いいくつもの鮮明な光の線と、そして、それが決して幻覚ではなかったという、ゆるぎない確信だけです」と書き終えています。
私は、80年を超える生涯で、二度、三度、奇跡的に命を救われたり、燦然と輝くみ仏の姿に見守られたりしたことを含めて、少なからずいろいろと貴重な体験をしてきました。いまでは、それらの体験は何であったか、なぜ、そのような体験をしたのかを、そのほとんど全部について自分なりに理解し納得することができます。しかし、このバルト海での体験については、私はいくら考えてもわかりませんでした。最近では、この体験だけは、遂に最期まで、わからないままこの世を去ることになるのだろうか、と考えたりしていました。
この間、思い切って、霊能者のA師に、この問題を持ち出してみました。バルト海で私が見たあの物体は何か、なぜ飛んでいたのか、私にだけ見えた現象なのかを、霊視で見てもらおうとしたのです。私は何とか知りたい一心でA師に縋りついたのですが、A師にとっては、別に難題でも不思議でもなかったようです。A師は、よどみなく、つぎのように答えてくれました。
∵ ∵ ∵ ∵ ∵ ∵ ∵ ∵
他の人にも見えることがありますが、でも、全員が見えるということではありません。人の中の何割かが見えるという程度です。その実体は何かというと、生命体です。霊界のみ霊そのものではありませんが、生命の要素が光って飛んでいるものです。物理的なものでなく、生命の発光体です。北方の寒冷の地で、しかも大海原で、生命の気が、或いは要素が、海上に沢山うごめいています。生命の要素は赤く発光することがあります。その生命の要素は、たとえば魚の霊とか、魚だけでなく魚介類など、そういった生命の要素が発光体として光ります。
人間の亡くなったみ霊というより、大自然の、特に、陸地よりも海に関わる生命の要素が沢山、寒冷の地の澄んだ大気の中で、特に夜は、生命の要素が真っ暗がりで目立つので、ちょうどオーラのように光るのです。それと似たものとしては、日本の墓地などで、浮遊霊が火の玉のように飛んでいることに近いです。墓地に昔見えた火の玉は、主に遺体の骨の燐の部分が発光して光っているものでした。最近は火葬が徹底しているし、密閉するようになったのでほとんど見受けなくなりました。
あなたがバルト海で見たのは、人間の霊ではなく、生き物たち、特に海系の生き物たちの生命の気です。また、あなたの心が澄んでいて、生死を乗り越え、達観視してきていたのです。自分では無我夢中で現実に対応してきたのですが、何時しか自分が実感している以上に達観して澄んだ心境になったので、余計あなたには目立って見えたのです。地球は生命に満ちあふれていて、生命は光り輝いていることをあなたに見せたのです。あなたは生命について、今生で苦しい体験を以って会得しました。普通には得がたいことでした。それがあなたに今生で与えられた贈り物です。
(2011.08.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
宇宙の摂理の中で生かされているいのち
―生活と文化をめぐる随想 (78)―
1983年の大韓航空機事件で妻と長男を亡くして以来、私は何年も嘆き悲しんでいましたが、ある時ふと、空海のことばが目に留まって、それからは、そのことばがいつも消えることなくこころのなかで反芻されていました。それは、つぎのようなことばです。
生まれ、生まれ、生まれ、生まれて
生の始めに暗く、
死に、死に、死に、死んで
死の終わりに冥(くら)し。
これは空海の『秘蔵宝鑰』(ひぞうほうやく)という本に残されていることばです。人間は生まれては死に、死んでは生まれて、何度も何度も輪廻転生をくり返すものですが、いったい何度生まれ変わったら、この生と死の真理が理解できるようになるのだろうという、空海の嘆きが伝わってくるようなことばです。私は、このことばは、私自身に対して言われているような気がしていました。そして、いつになったら、このことばを理解し乗り越えられるだろうと考えたりしながら、無明の日々を過ごしていました。
それから二十数年を経て、いまでは、このことばは私なりに理解することができます。「生の始め」もわかるような気がしていますし、「死の終わり」にも暗くはなくなりました。それは、実は、単純で明快な、いのちの真理を知ることができたお陰です。その、いのちの真理とは、何でしょうか。それは、私たちは本来が霊的存在で、宇宙の摂理のなかで生かされているということです。
いのちの真理は、ただ、それだけです。それ以上でも、それ以下でもありません。このように単純ではありますが、しかし、これは極めて重大な真理です。明快ですから、誰にでもわかります。もしかしたら、あまりにも単純明快であるがゆえに、かえって、誰にもわかりにくいのかもしれません。
私たちは、人間には霊魂が宿っているなどと言ったりします。しかし、私たちは霊的存在として肉体をまとっているのであって、肉体が霊を伴っているのではありません。また、私たちは、死んだら霊魂があの世へ旅立つ、などと聞いたりもしています。しかしこれも、私たちは、死んでから初めて霊になるのではなくて、いま現在、生きているうちから霊なのです。霊であるからこそ、生きていけるのです。
では、霊であることの意味はなんでしょうか。霊は不死であり永遠で、私たちは、死んでも死なない、ということです。現実には、人は死ねば、火葬場で燃やされて灰になってしまいますから、世間の常識では、死んでも死なない、ということは一般には信じられていません。ただ、辛うじて、霊魂の存在はあるような気が少しはしていますから、ほとんど慣習的に、葬儀場でも僧侶にお経を上げてもらったり、亡くなった後も法要を行ない、お墓参りに行ったりしているだけです。しかし、肝心のその僧侶自身が、人は死んでも死なないことを、知らなかったりすることが決して珍しくはないようです。
世間の常識のなかでは、生と死の間には、巨大な壁が立ちはだかっています。自分の肉体が自分だと信じているとすると、その肉体は、数十年、長くても百年もしないうちに朽ち果ててしまいますから、自分のいのちはそれで終わりということになります。長くても百年しか生きられないとすると、その短い人生を人々はどのように生きていこうとするでしょうか。他人を押しのけてでも、出来るだけ富を蓄え、できるだけ贅沢をし、できるだけ楽しみたいと考える人々が増えてもおかしくはありません。ちょうど、百メートル競走に出て、疾走するようなものです。勝つためにはスタートでちょっと遅れても致命的です。つまずいたりしたら、もうそれだけで敗者です。他人より一秒でも早く、前に出て走らなければなりません。
しかし、もしそれが百メートル競走ではなくて、42キロ(正確には42.195キロ)のマラソンであったとすれば、どういうことになるでしょうか。マラソン競争であるのに、それを百メートル競走と勘違いして、スタートと同時に疾走を始めれば、最初の百メートルくらいは、誰でもトップを切って走ることはできます。しかし、それは勝者ではなくて明らかに敗者です。百メートルで精力を使い果たし、それでも勝者になったつもりで満足感を味わいながらしゃがみこんでいるところを、42キロを走る予定のマラソン走者に次々に追い越されていくことになります。だいたい、マラソン競争で、最初から他人を押しのけてでも先頭に出て全力疾走をしたりすれば、それは滑稽以外の何ものでもないでしょう。
42キロというのは、4万2千メートルです。百メートルを百年とすれば、42キロは、4万2千年です。仮に、マラソンのように、4万2千年の人生があるとして、それを百年の人生と勘違いして、少しでも多くカネを、人を押しのけてでも富を、と物欲のとりこになってあくせくしていくとすれば、それも、マラソン競争を百メートル競走と勘違いするのと同じで、たいへん滑稽です。深刻であるのは、これは単なる比喩ではないということです。もっと深刻であるのは、人のいのちが、4万2千年どころか、永遠であるということです。
世間の生と死の常識には、このように深刻な「勘違い」があります。これが生と死の間に立ちはだかっている巨大な壁です。それを空海は、冒頭のことばのように、人のいのちは永遠で死んでも死なないという真理を、何度生まれ変わったら理解できるようになるのであろうか、と嘆いているのです。
私は、何年も何年も、妻と長男の行方を捜し求めているうちに、人は死んでも死なないことが分かるようになりました。妻と長男がいまも生き続けていることを、いまの私はよく知っています。ずいぶん沢山、手紙のやりとりもしてきました。ですから、いまの私は、人生を百メートル競走のように勘違いすることはできません。転んでも、つまずいても、慌てずに起き上がって、またゆっくりと走りつづけるでしょう。まわりに倒れている人がおれば、手助けして起こしてあげる余裕もあるかもしれません。
私たちは、肉体を持ってこの世に生まれ、肉体を脱ぎ捨ててふるさとの霊界へ帰り、また肉体をもってこの世に生まれるという輪廻転生を繰り返しています。それが分かると、ものの見方、考え方も随分変わってきます。例えば、いのちの長さがこの世での数十年だけであれば、その数十年のなかで、いのちがすべて公平に扱われることは決してないでしょう。公平どころか、この世では不公平だらけです。世の中には、自分の境遇について不公平を嘆いたり、悲しんでいる人々が無数にいますが、それも数十年だけのいのちと考えてのことであれば、同情できないことではないのかもしれません。
このように、世の中が不公平だと嘆いている人は、実は、いのちの永遠性がまだわかっていないからだと思います。永遠のいのちのなかでは、不公平はありません。百年のなかでは不公平であっても、永遠の中では、必ず、その不公平は是正されて公平の天秤が保たれるからです。それが、宇宙の摂理です。私たちは一人の例外もなく、その宇宙の摂理が一分一厘の狂いもなく働いているなかで生かされています。そして、私たちは一人の例外もなく、完全に公平な扱いを受けています。
ただ、その宇宙の摂理のなかの公平とは、おしなべて機械的に公平であるというのではないでしょう。あくまでも、その人にとっての公平です。つまり、一分一厘の狂いもない尺度で測られ、善悪の因果を含めて、受けるべき値のものを必ずそれだけ受けとるということです。その点では決して不公平はありませんが、受け取れるものが何かについては、それぞれに差があります。現に、霊界というのは厳然たる階層社会ですから、一人ひとりのそれまでの霊的進歩の程度によって、住む界層が違ってきます。光に近いところから、闇に近いところまで、それぞれに、その人の霊的進歩に応じた界層に、完璧に「公平に」割り当てられると考えてよいでしょう。
実は、私たちがこの世に生まれてくるのも、この霊的進歩のためです。「五濁悪世」の物欲が横行する世の中だからこそ、正邪ともども、学ぶべき教材はふんだんに周りにはあります。悲しみがあり、苦しみがあり、喜びもあります。絶望の淵もあり、希望の光もあります。それらを様々に経験しながら、霊性を高めていくのが、この世に生まれてきた目的でしょう。私たちが口にする一つのことば、一つの行為、一つの思考など、すべて霊的に記録されて、霊性の向上に役立ったり、或いは逆に、霊性を貶めたりもします。そのことにも、なるべく早く気がついて、謙虚に素直に、他人に対する愛と奉仕の生活を心がけるのが、正しい生き方といえるのかもしれません。
さらに、永遠のいのちの視点から見ると、偶然というものもなく、事故や不幸な出来事などもないことがわかってきます。起こっていることは、すべて自分の霊的進歩にとって必要だから起こっているのです。だから、本当は、それらは、自分にとって「悪いこと」ではないでしょう。それも、宇宙の摂理です。
私自身も、大韓航空機事件で、家族を失いましたが、その事実も、私にとっては起こるべくして起こったことで「必要」であったことがわかるようになりました。必要だから起こった以上、それも私にとっては「悪いこと」ではなかったのです。私は、今度出版した『天国からの手紙』(学習研究社)のなかで、かつての「悲劇」を、むしろ「神の恵み」であったと書きました。そして私は、これまでの人生のすべてを「神の恵みと宇宙の摂理のなかで生かされてきた」、とも付け加えています。
(2011.06.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東日本大震災をどのように捉えるか
-生活と文化をめぐる随想(77) -
先月の三月十一日午後二時四十六分ごろ、東日本大地震が起こった。深刻な原発事故まで発生して、私たちがかつて経験したことのないような、未曾有の大災害である。二週間を経た現在の時点で、すでに死者は一万人を超え、避難者は約二十五万人に達している。数多くの行方不明の人たちの消息も、まだ掴めていないようである。被災者の方々はお気の毒で、胸が締めつけられる思いがする。
新聞やテレビも、連日、目を背けたくなるような被災地の惨状を、いまも報道し続けている。官民あげての懸命な救助活動のなかで、多くのボランティアたちも被災地に入り込み、悲嘆と困窮にあえぐ多くの避難者たちを慰め、優しさを届けている。
世界各国も、すばやく援助の手を差し伸べてきた。米国、ドイツ、韓国、中国、台湾、ロシア、英国、トルコ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド等々、五十六か国以上の国々からの救援チームが、つぎつぎに日本へ乗り込んできた。
有難いことである。救われる気持ちである。どういうものか、そのようなボランティアたちや救援チームの映像を見ていると、涙がひとりでに、あふれてくる。ボランティアの人たちも、海外からの救援チームも、あたたかい隣人愛を、誰に言われなくても率先して実践している。これが、人間の行為の最も美しい情景なのであろう。
しかし、それにしても、これほどの大災害がどうして起こったのであろうか。もちろん、地震のメカニズムはよくわかっている。太平洋岸の海底のプレートが日本の陸のプレートの下にもぐりこんでいき、陸のプレートのひずみが限界に達したとき、プレートの端が跳ね上がって地震になるのである。だから、大地震でも、その結果引起される大津波でも、数十年に一度、あるいは、何百年に一回、必ず起こるというのは、わかる。しかし、それだけであろうか。
東京都の石原慎太郎知事は、大震災への国民の対応についての感想を問われて、「日本人のアイデンティティーは我欲。この津波をうまく利用して我欲を一回洗い落とす必要がある。やっぱり天罰だと思う」と発言した。世論の厳しい批判を浴びて、都庁には、抗議の電話やメールが殺到したらしい。遂に石原氏も、「添える言葉が足らず、被災者、国民、都民の皆様を深く傷つけたことから、発言を撤回し、深くおわびします」と記者会見で述べた。(「朝日」2011.3.16など)
これは、難しい問題である。石原氏は「被災者の方々はかわいそうですよ」とも言っているから、「天罰」は特に被災者に対して言っているわけではない。日本人全体に対して言っているのである。しかし、このような大災害の真っ只中では、これは、やはり誤解されやすい発言であった。「寒さや恐怖に耐えている被災者の心を踏みにじる発言で、不謹慎きわまりない」と、都知事選候補の一人も、感想を洩らしている。
つくづく思うのであるが、地上でのごく狭い視野のなかでは、ものごとの真実というのは捉えにくい。目の前の現象だけを見て、不運、不幸、天災のレッテルを安易に貼り付けようとする。やはり、実相を見極めるためには、視野を無限に広げて、霊的な永遠の視野で見ていかねばならないはずだが、その霊的視野のなかでは、この大震災はどのような意味をもつのであろうか。
まず、指摘しなければならないのは、石原氏の言う「天罰」は、正しくはないであろう。「津波をうまく利用して我欲を一回洗い落とす必要がある」のは、日本人全体であっても、神は、天罰を下すことはない。警告として受け止めるべきである。
石原氏のいう現在の「日本人の我欲」は、確かに目に余る。世界中にはびこるカネとモノに憑かれた利己主義の蔓延もそうであるが、いまでは、神の警告を受けなければならない状況にまで立ち至っているのではないか。石原氏でなくても、こころある人はみんな気がついているのだが、その我欲と利己心の流れは、止まるところをしらないようにみえる。「一回洗い落とす必要がある」というのも、あながち根拠のない発言ではない。
このような地上の状況は、霊界からはよく見えているらしい。地上の世界で人々が我欲や利己心に流され、霊的存在としての人間本来の生き方から離れてしまっていることに対しては、霊界では高位霊たちも心配しているようである。霊能者には、霊界の指導霊などから、そういう情報を受け取ることもあるらしい。私には霊能力はないが、その私のところにも、東京のすぐれた霊能者のYさんから、3月24日、長男の潔典からのメッセージを伝えてきた。そのうちの一部には、こう述べられている。
《お父さん、地震では大変でしたね。また停電と続き、不便な思いをしていらっしゃることでしょう。人類が起こしたカルマは、途方もない大きさとなり人々を襲ってきています。神々は何とかそれを最小限に抑えるべく努力を日夜なさっているのです。僕たちはそのお手伝いをしています。そして多くの人々を救うために努力し、自らを高めるべく努力をも続けています。》
このような「心配」は、決して無視してはならないであろうが、しかし、それとは別に、いまはまず、被災者の方々が立ち直っていくために一番必要なものは何かを考えていかなければならない。もちろん、それは、食べ物であり、水であり、燃料であり、住む家である。しかし、それだけでは、人は生きていけない。こころの拠り所が必要である。
やはり、被災者の方々が立ち直っていくために大切なことは、この苦しみのなかで、このホームページでも繰り返してきたような、宇宙の摂理を理解していくことであろう。このような際に、そんなことを、といわれるかもしれない。分かってもらえず反発だけが返ってくるかもしれない。しかし、それが一番大切である。宇宙の摂理のなかで、事故は決して偶然に起こるのではない。それを、こういうときだからこそ、日本だけではなく世界中の人々が学んでいくべきである。シルバー・バーチは、それをこう教えている。
《すべての事故は因果律によって起こるべくして起きているのです。その犠牲者―この言い方も気に入りませんが取り敢えずそう呼んでおきます―-の問題ですが、これには別の観方があることを知って下さい。
つまり、あなたがたにとって死はたしかに恐るべきことでしょう。が私たち霊界の者にとっては、ある意味でよろこぶべき出来ごとなのです。赤ちゃんが誕生すればあなたがたはよろこびますが、こちらでは泣き悲しんでいる人がいるのです。反対に死んだ人は肉体の束縛から解放されたのですから、こちらは大喜びでお迎えしています。》
(『霊訓4』 p.84)
私たちは、この地上世界で、狭い、短い、物的な尺度でしかものをみないが、その尺度では、この世は、不公平だらけである。特に、今度の大震災では、その不公平感が、最大限に拡大されていてもおかしくないように思える。しかし、宇宙の摂理のなかでは、決して不公平はない。地上生活は永遠の生命から見れば、ごく短い、一瞬でしかないから、そこでは不公平に大きく傾くことがあっても、霊的な永遠の天秤では、やがて必ず平衡を取り戻すのである。
シルバー・バーチは、それについても、「神は絶対に誤りを犯しません。もしも誤りを犯すことがあったら宇宙は明日という日も覚束ないことになります」といい、つぎのように続けている。
《時として人生が不公平に思えることがあります。ある人は苦労も苦痛も心配もない人生を送り、ある人は光を求めながら生涯を暗闇の中を生きているように思えることがあります。しかしその観方は事実の反面しか見ておりません。まだまだ未知の要素があることに気づいておりません。
私はあなた方に較べれば遥かに長い年月を生き、宇宙の摂理の働き具合を遥かに多く見てきましたが、私はその摂理に絶対的敬意を表します。なぜなら、神の摂理がその通りに働かなかった例を一つとして知らないからです。こちらへ来た人間が“自分は両方の世界を体験したが私は不公平な扱いを受けている”などと言えるような不当な扱いを受けている例を私は一つも知りません。》 (『霊訓1』 p.47)
最後に、もう一つの大切な霊的真理がある。愛する家族を失って嘆き悲しんでおられる多くの被災者の方々には、涙を禁じえないが、それらの方々に、敢えて私は申しあげたい気がする。愛するあなた方の家族は、決して「死んで」はいない。私の愛する家族が死んでいないように。本来人間は霊的存在であって、霊的存在であるが故に、肉体は滅びても、いのちは永遠に生き続ける。そのことも私は、繰り返し、このホームページで、検証を続けてきた。
(2011.04.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
見えないものが見える霊能者の眼
―生活と文化をめぐる随想 (76) ―
藤沢周平原作の映画『蝉しぐれ』は、日本の映画史上に残る名作の一つだと思いますが、Mさんは、その映画のプロデューサーであった人です。もう知り合ってから20年くらいになりますが、初めてお会いしたのは、川崎市多摩区のご自宅でした。
その時は、奥さんのお母さんである石原淳子さんが主宰するスピリチュアリズムの懇談会でお訪ねしたのですが、玄関に出てこられたのがMさんでした。初対面のような気がしなかったものですから、「どこかでお会いしませんでしたか」と私が言いますと、Mさんは、ちょっと間をおいて、「ええ、イスラエルでお会いしました」と答えられました。
この「イスラエル」というのは、現代のイスラエルではありません。Mさんは、二千年前のイスラエルのことを言っているのです。Mさんは、知る人ぞ知る極めて優れた霊能者で、ご自分の過去世のことも、いろいろと思い出すことができます。はっきり思い出せるのと、ぼんやりしているのもあって、そのうちのはっきり思い出せるものの一つが、私とのイスラエルでの出会いだそうです。
Mさんは、二千年前のイスラエルのエルサレムで、ロバ2頭に小間物を積んで、街の隅々まで歩きまわり、小間物を売っていました。その当時の地理に詳しかったものですから、何年か前に、エルサレムへ行ったときには、現地のガイドさんに、昔の道路のことなどをいろいろ質問したりして、相手を驚かせたこともあったそうです。自分が住んでいた商人の住む街の一画も思い出せたと言っていました。
イエス・キリストが群集に向かって説教しているのを、ロバを牽きながら遠くから聞いたこともあるそうです。当時のイスラエルは、ローマ帝国の統治下にあって、第5代のユダヤ属州総督であったポンテオ・ピラトが反ユダヤ的な強圧政治を行なっていました。Mさんは、イエスのことばを耳にして、あんなことを言っていたら、いまに殺されてしまうぞ、と内心思っていたそうです。
Mさんによれば、私はその当時、ローマ帝国の執政官でした。ただ、執政官というと、ジュリアス・シーザーなどがそうであったように、古代ローマでは毎年二人が選ばれる国家最高の政務官のことが頭に浮かびます。しかし、この頃の執政官は、職名として残っていたもので、私は、イスラエルの総督ピラトの補佐役であったと考えられます。もしそうであれば、イエス・キリストの処刑とも無関係ではないはずで、どうも、あまりいい気持はしないのですが、当時の私は、総督府の壁の中にいて、ピラトと共に、反ユダヤ的立場にあったようです。
それでも、これはMさんの贔屓目だと思いますが、私は、ユダヤ人に理解があるほうで、総督府のなかのローマ人としては、一般民衆から好かれていた、といいます。Mさんは、小間物を売り歩くための許可証を申請するために、何度か総督府の壁の門をくぐったのですが、その許可証をもらう際に、実際に私とも会ったことがある、というのです。これが、二千年前のエルサレムで、Mさんが私と会ったという、いきさつです。Mさんは、私に、「一度エルサレムへ行かれてはいかがですか、何か感じるかもしれませんよ」と言ってくれているのですが、私はまだ、それを実行することができないでいます。
Mさんが、もうひとつ、私と会った記憶をもっているのは、1700年代のイギリスにおいてです。その時は、私がロンドンにいて、裁判官で、Mさんは、ヨークシャーにいて弁護士をしていたそうです。私は厳格な裁判官で、何度か法廷で顔を合わせたことのあるMさんも、手を焼いていた、と言っていました。
この1700年代のイギリスでの私の前世については、別の優れた霊能者による、かなりくわしい「記録」があります。初めに言われたのが、「1700年代半ばから、1800年代初頭にかけて、ヨーロッパの地に住んでいました。主にイギリスに生きていたのです。あなたはイギリスの王家と多少つながりがある家系に生まれ、イギリスの王立協会のメンバーでした」というようなことです。
その当時の私は、「ロバー卜・ジェイムズ・ハンプトン」といったような名前で、おそらく1678年くらいに生まれ、1754年くらいまで生きていたことになっています。「言語学者であり、いまでいう文化人類学に近いことも研究していました。専門は言語学です。現在の職業は、このすぐ最近のイギリスでの職業の続きであります」ともいわれました。ですから、Mさんのいわれる裁判官というのは、ここでは結びつきません。
ただ、別のところで、その頃の私は、「学者でした。法律そのものではなかったのですが、法学と文学の方面での仕事をしている研究者でした。英国学士院と、それから、英国の宮廷に関わるアカデミー、王立のアカデミーでしょうか、そこの会員でした」ともいわれていますから、ここでいう「法学と文学の方面での仕事」が、もしかしたら、Mさんのいう裁判官といくらかは関係があるかもしれない、と思えるだけです。過去世を読むのは非常に難しく、年代を含めて、優れた霊能者でも、多かれ少なかれ、誤差が生ずるのは避けられないということでしょうか。
このMさんから、Mさんのお母さんのむかしの葬式の時のことを、何度か聞かされたことがあります。臨終になって、ご家族がみんなまわりに集り、嘆き悲しんでいましたが、Mさんだけは、悲しんでいませんでした。病気の苦痛から解放されたお母さんは、若々しくとても元気に見えたそうです。「お母さん、綺麗だね」とMさんが声をかけますと、「まあ、そんなことを言って」と、ちょっと照れたように微笑んでいた、ということでした。ただ、最後の出棺で、家族のみんなが、自分の遺体に花を投げ入れながら泣いているのをみている時には、それを見ているお母さんも、目に涙を浮かべていたそうです。
Mさんは、その後、山梨県八ヶ岳の清里へ移られましたので、義母の石原淳子さんが主宰する懇談会も、清里で行なわれるようになりました。私も泊りがけで、何度か、この懇談会に参加しました。石原淳子さんは、前世では、Mさんの妹であったことがあるそうです。イエス・キリストの教えが地中海地域に広まり始めた2千年前には、当時はまだキリスト教徒の弾圧を続けていたローマ帝国の禁を犯して、キリスト教の集会に出かけたこともあったと、言っていました。
その石原淳子さんが、昨年(2010年)11月10日に、C型肝炎の症状が悪化して、82歳で亡くなられました。Mさんが信頼する千葉県袖ヶ浦市の乗蓮寺の服部大空ご住職に清里まで来ていただいて、近親者だけで、家族葬が行なわれました。私は出席できませんでしたが、Mさんやご住職を含めて、みんな死とは何かをよく知っている人ばかりでしたから、家族葬は明るく賑やかで、笑い声が絶えなかったそうです。その時、浄土宗のお経をあげてくださった服部ご住職が、後に、こんな話をしてくれました。
家族葬の簡素な祭壇の正面奥には、阿弥陀如来の掛け軸がかけてありました。ご住職がお経をあげ、拝礼して、ゆっくり頭を上げていくと、阿弥陀像の足もとからだんだん上へ視線が移って、阿弥陀さまのお顔のところで、止まることになります。その日も、当然、そうなるはずでした。ところが、ご住職が拝礼を終えて、ゆっくり顔をあげながら、阿弥陀像の足もとから視線を移していくと、阿弥陀さまのお顔のところには、石原淳子さんの微笑んでいる顔が入れ替わっていたというのです。ご住職もちょっと驚いた、と言っていました。私は、石原さんが、茶目っ気をだして、いたずらしてみたのかな、と思ったりしました。
去る、1月23日には、石原淳子さんの納骨式と「お別れ会」が、袖ヶ浦の乗蓮寺で行われました。私も含めて、石原さんに親しかった15人ほどの人々が、みんな喪服ではなく、平服で参加しました。Mさんは、Gパン姿で私たちを迎えてくれました。
納骨が終わって、近くの懐石レストランで「お別れ会」になりました。石原さんの微笑んでいる写真を前にして、みんなで賑やかに、石原さんの思い出話などを語りあったのですが、ちょうど、清里の石原さんのご自宅で、懇談会をしているのと同じような雰囲気になりました。その時に、Mさんは、こんな話をしてくれました。
石原さんは、臨終の前から、何度か、霊界へ散歩に行っていたそうです。Mさんには、散歩に行っている間は、「留守」になっているのがわかりますから、散歩から帰ってきたときに、「どうでしたか」と聞きますと、「とってもいいところよ」とにこにこしながら答えて、ちょっとはしゃぐように、ダンスの真似などをしたそうです。そして、Mさんの話では、最後に霊界へ旅立つ時がくると、石原淳子さんは、自分の体から抜け出して、足元の上のほうから自分の体に向かって、「長い間、有難うございました」とお礼を言いながら、深々と頭を下げていた、ということです。
(2011.02.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私達がなるべく早いうちに知っておくべきこと
-生活と文化をめぐる随想(75)―
最近、「朝日新聞」が、日本人の死生観についての全国世論調査を実施しました。その結果、目を引くのは、「安らかな最後」への願望で、苦痛や苦悩をできるだけ少なくして死んでいきたいという思いが色濃く表れた、と同紙は伝えています。(2010.11.04)
沢山の質問項目の中には、「死が怖いですか。怖くないですか」 というのがあります。これに対して、「怖い」と答えた人は55パーセントで、「怖くない」と答えた人は、35パーセントでした。死が怖くないと考えている人が、3人に1人はいるということで、これは、かなり大きな数字ではないかと思われます。そして、これは、「人間は死んだ後も、霊魂が残ると思いますか。そうは思いませんか」 という別の質問に対する回答と深く関係していることになるとも思われます。
「霊魂が残る」と答えた人は、46パーセントで、「そうは思わない」は、42パーセントでした。さらにこの質問に関連するものとして、「あなたは、この世とは違う死後の世界や『あの世』があると思いますか。『あの世』はないと思いますか」では、「あると思う」が49パーセントで、「ないと思う」が43パーセントになっています。ほぼ、2人に1人の割合で、人は死んでも霊魂は残り、あの世へ行く、と考えていることが分かります。そして、「あの世があると思う」と答えた49パーセントの人が持っている「あの世」のイメージは、永遠=16パーセント、無=14パーセント、生まれ変わり=33パーセント、やすらぎ=29パーセント、などとなっていました。このなかで、「あの世」があると考えていても、そのイメージが「無」であるとしている人が14パーセントいるということは、やはり、まだ、「あの世」についての理解が不確かで揺れ動いているということでしょうか。
私は生と死の問題を考えるために、何年か前からこのホームページで、シルバー・バーチの教えを紹介してきました。それだけに、このような世論調査の数字には強い関心があります。いうまでもなく、シルバー・バーチは、このように重要な生と死の問題については、自分自身のことばで、極めて明快な答えをだしてくれています。それがどれほど有り難いことか、私のように、生まれて60年近くも生と死については全く無知のままに過ごしてきた者にとっては、ただ頭が下がるばかりです。しかもシルバー・バーチは、三千年前から霊界にいて、この地上世界のことも霊界のことも知り尽くしている高位霊ですから、その誠実で謙虚なことばの信憑性には、一片の疑いをも挟む余地はありません。シルバー・バーチのことばに日々親しんでいる多くの方々も、きっと同じような思いでおられることでしょう。
試みに、初めにあげた世論調査の項目に対応するシルバー・バーチの教えをあげるとすると、「死の恐怖」については、つぎのようなことばがあります。
《あなた方はまだ霊界の楽しさを知りません。この地上世界では、霊界の生活と比べられるものは何もないのです。肉体の束縛から解放され、身体の牢獄から逃れ、行きたいところへは何処へでも自由に行くことができます。考えたことは形となって現われ、こころの赴くままに何でもすることもでき、お金の悩みなども一切ありません。このような霊界の生活の楽しさを、あなた方はまだ何も知りません。
物質に包まれてしまっているあなた方には、本当の美しさは分かりません。あなた方はまだ、霊界の光、色彩、景観、木々、鳥たち、川の流れ、小川のせせらぎ、山々、花などを、見ていません。それでいて、なお、死を恐れるのです。》(霊訓原文118)
これは、「あの世があるか、ないか」の質問の明快な答えにもなっていますが、この文はさらに、次のように続きます。
《死は人々のこころに恐怖心を呼び起こします。しかし、あなた方は、死んで初めて生きていくことになるのです。あなた方は生きているつもりでしょうが、本当は、死んでいるようなものです。霊的な事柄については何も知らず、なんと多くの人々が死んだ状態でいるのでしょうか。小さな生命の光が弱々しい体の中でわずかに点滅しているだけです。霊的なことにはなんの反応も示そうとはしません。》 (霊訓原文119)
調査項目の二つ目にあげた「霊魂が残るか、残らないか」 については、シルバー・バーチを少しでも読んだ人であれば、あまりにも幼稚な質問のように感じられるかもしれません。残るも残らないもなく、私たちは霊そのものだからです。「残らない」と答えた42パーセントの人々も、それでいて、法事やお墓参りをし、先祖の霊が帰ってくるというお盆の行事を繰り返したりしているのではないかと思われますが、それらはただの「世間的慣習」として割り切っているのでしょうか。たとえ慣習としてでも、残っていることには意味があるはずですが、やはり霊魂のことについては自分自身のものを見る目を曇らせてしまっている人々が少なくはないようです。これについては、シルバー・バーチはこう述べました。
《いったいあなたとは何なのでしょう。ご存知ですか。自分だと思っておられるのは、その身体を通して表現されている一面だけです。それは奥に控えるより大きな自分に比べればピンの先ほどのものでしかありません。
・・・・・つまりあなた方は本来が霊的存在であり、それが肉体という器官を通して自己を表現しているのだということです。霊的部分が本来のあなたなのです。霊が上であり身体は下です。霊が主人であり身体は召使いなのです。霊が王様であり身体はその従僕なのです。》 (学びの栞A54-a)
世論調査の質問のなかには、「宗教を信じることにより、死への恐怖がなくなったり、やわらいだりすると思いますか。そうは思いませんか」 というのもありました。これに対する回答は、「死への恐怖がなくなったり、やわらいだりする」
が26パーセント、「そうは思わない」が68パーセントでした。「宗教を信じても死への恐怖がなくなったり、やわらいだりすることはない」 と否定的に考えている人が68パーセントもあるのですが、これには考えさせられます。これでは、宗教は宗教本来の役割を果たしていないことになってしまいそうですが、これはどう捉えていけばよいのでしょうか。
仮に、この質問を、シルバー・バーチにしてみるとすれば、その答えは、どのようなものになるか、容易に想像がつくような気がします。きっと、「それは、宗教の定義による、あるいは、宗教が教義として何を教えているかによる」というような答えが返ってくることでしょう。宗教は、何よりも、人間が本来、霊的存在であり、永遠の生命をもつ神の子であるという真理を教える場であるはずでした。ですから、その真理から離れてしまった宗教は、もはや、宗教の名には値しないのです。しかし、現実では、多くの宗教は、大きな寺院や多くの信者を抱えていても、この真理からは遠いところにあります。シルバー・バーチが厳しくキリスト教を批判しているのもそのためでしょう。そして、これは、ひろく仏教についてもいえることで、日本の仏教も決して例外ではありません。
ある時、ふとまわしたテレビのチャンネルに、多くの著作を持つある尼僧が、お寺の境内で法話をしている場面が出ていました。聴衆の一人が、「先生、人間は死んだらどうなるのですか」と、尼僧に訊いたのです。その尼僧は「私にはわかりません。死んだことがありませんから」 と答えていました。正直といえば正直なのかもしれませんが、いつものことながら、このような僧職者であるつもりの人々のことばには失望させられます。はっきり言えることは、このような人々の教える宗教では(宗教といえればの話ですが)、その宗教を信じても、「死への恐怖がなくなったり、やわらいだりする」ことは、ありえないでしょう。この調査の回答で、68パーセントもの人々が、宗教に対して否定的であるのも、このような宗教の実体が、いまの日本でも、広く見られていることと決して無関係ではないはずです。
私は、この原稿のタイトルを、「私達がなるべく早く知っておくべきこと」としました。生きていくための大切な真実をできるだけ早く知っておきたい、という気持ちからですが、迷いの多い人生ではあっても、求める心がありさえすれば、迷いのない確たる指針がはっきり示されていることを、多くの方々と確認しあっていきたいという思いが、私には強くあります。妻と子を失って悲嘆と絶望の淵に沈みながらも、仏典を読んでも分からず、聖書を読んでも最後まではついていけず、迷いに迷って、やっと私が掴みえたのは、シルバー・バーチが教える単純明快な人生の指針でした。それは、「私たちは、本来、霊であって、一分一厘の狂いもない宇宙の摂理の中で生かされている」という短いことばにして集約することができると思われます。
霊である以上、いのちは永遠です。死ぬことはありません、というより、死ぬことはできません。私たちは永遠のいのちを生きながら輪廻転生を繰り返し、様々な経験を積み学びを重ねて、霊性を磨いていきます。宇宙の摂理に従って、霊界からの指導や加護をうけながら、一歩一歩、光に向かって歩み続けます。一人の例外もなく、一切の区別もなく、人間はみんなそうなのです。ただ、歩みの速い人と遅い人がいます。かなり進んで光に近づいている人もいれば、遅れてまだ光の陰に隠れている人もいるかもしれません。しかし、みんな兄弟姉妹で、みんな同じ家族の一員です。さらには、それぞれのいのちは、もっと大きな宇宙を包含するいのちの一部です・・・・・これが、真実ではないでしょうか。そして、これは、できれば生きているうちに、「なるべく早く知っておくべきこと」と私が言っても、おそらく、私の独りよがりにはならないでしょう。
仮に、上に上げた質問の「宗教を信じることにより、死への恐怖がなくなったり、やわらいだりすると思いますか」の、「宗教」を真実のことばを表す「真理」におきかえ、この真理の意味も理解していくことができれば、その設問に対する回答は大きく変わっていくことになるはずです。お金はいりません。地位、名誉も関係ありません、不老不死の特効薬を捜し求める必要もありません。ただ一つ、単純明快な真理を知ることにより、死への恐怖は、間違いなく 「なくなったり、やわらいだりする」 ようになるでしょう。必ず、そうなるでしょう。このことの重大な意味を、私はやはり、機会があるたびに繰り返し強調しておかないではおれないのです。
(2010.12.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本文化と外国文化の違いをどう捉えるか
ー生活と文化をめぐる随想 (74)ー
グローバル時代とよばれるようになってすでに久しく、国際間の動きは、情報や物だけではなく、人の交流も、観光旅行者などを含めて、近年ますます増加の傾向にあるようにみえる。そして、それとともに、日本の文化とは異なる外国の文化についても、庶民レベルで、見たり聞いたり、或いは、体験することが多くなってきた。それらの文化の違いを、客観的には、どのように捉えていけばよいのであろうか。それを、日本と中国・韓国との「朋友」の違いをとりあげて、考察していくことにしたい。
国によって文化がどう違うか、なぜ違ってくるのか、を考える場合、一つの指標になるのが言語の違いである。言語とは、それがどの言語であれ、話し手のものの見方や考え方、いわば世界観がそのまま体系的にあらわされていると考えられるから、言語は文化そのものでもある。そして、その言語の違いは、文化の違いでもあるといってよい。
たとえば、英語と日本語の違いは、英米文化と日本文化の違いに色濃く反映される。英語とはいうまでもなく印欧系の言語で、系統をもたず東アジアに孤立した独特の言語である日本語とは、お互いにかなり異質である。自己主張の強い特性をもつ英語では、必ず主語があって、次には重要品詞の動詞がくる。一方の日本語では、主語はあいまいにされることが多く、語順も英語とは反対で、動詞は最後にくる。このことは、当然、さまざまなものの考え方、生活習慣、対人関係の違いになってあらわれてくる。語彙自体も、相互に対応しないものが決して少なくはない。明治開国以来の翻訳の氾濫で、或いは、その文化の違いまで水準化されているように思われているところもないではないが、それでも、文化の本質的な違いは、消し去られていることはない。
それでは、中国語、韓国語と日本語の違いはどうであろうか。中国語は系統的にはチベット語、ビルマ語、タイ諸語と共にシナ=チベット語族を構成するといわれていて、言語学的には日本語とは異質である。ただ、日本では、中国から漢字を輸入し、漢字を媒介に多数の借用語がひろがって現在でも通用している。日本が漢字文化圏の中に含まれていることもあって、中国語と日本語の間には、決して小さくはない親近性がみられるのである。それはそのまま、中国と日本との文化の差についてもいえるであろう。韓国語も、同じ漢字文化圏のなかで、中国語の影響を強く受けてきた点では、日本語と同じである。しかも、韓国語は、語順や接辞による膠着語的性格などの文法構造が日本語と酷似していて、系統論的には日本語と同系ではないかといわれたこともあった。したがって、日本語への親近性はさらに強い。このことは、文化の差についても、欧米文化との差に比べるとはるかに小さいことを予想させるだろう。
ここで、一つのことばを中心に、日本語と英語、それに、日本語と中国・韓国語との差をみてみることにしよう。ある新婚夫婦の妻が夫に甘えてダイヤモンドの指輪をねだったと仮定する。夫はそれに対して、今度ボーナスが出たら買ってあげると答えるとする。その状況は、日本語では、つぎのように表現することができる。
妻:「ねえ、買って」
夫:「うん、今度ボーナスが出たらね」
日本語というのは、本来、内輪の世界の言語である。話し手も受け手も、話の内容は、通常は当事者同士で熟知されているのが普通だから、このような「主語」も「目的語」も「数」もない形でも、会話は十分に成り立つ。しかし、これは、英語では表現できない。英語であるためには、少なくとも、誰が、誰に、何を、いくつ(数、量)、買うのかを明記することが必要になる。
もっとも、日本語でも、例外的な言い方がある。仮に、親しみあった新婚夫婦が、今度は倦怠期を経て離婚寸前になり、慰謝料を請求するような険悪な関係になったと考えてみよう。この場合には、あいまいな文言は極力排除されなければならない。日本語のことば遣いも、そのなかに、主語、目的語、数を明記して、つぎのように言うだろう。いや、ことばだけではまだ信用できないから、こう書くだろう。
妻:「私・藤山花子は、貴君・藤山一郎に対して、ダイヤモンドの指輪1個、100万円相当のものを、何年何月何日までに、買い求めることを要求する」
これは、離婚調停書などに用いられる日本語であって、通常の生活で使われることはない。いわば日常から離れた「異常な」日本語である。しかし、英語ではこれは少しも異常ではない。つまり、英語とは、この日本語の「異常」を「正常」として日常的に使われている言語なのである。その根底にあるのは、対人不信感で、それが、ものの見方、考え方、対人関係等を含め、欧米文化の一つの大きな特質になっているといえるであろう。
さらに、この新婚夫婦にみられるような「甘え」というのは、土居健郎『甘えの構造』で詳しく分析されているように、実は、日本語独特といってもよいことばである。英語にはこのことばはない。和英辞典などで、「甘え」をひいても、そこには、「甘え」の対応語はなく、説明があるだけである。そして、このことは、欧米には、甘えの文化もないことを意味する。
それでは、中国語と韓国語の場合はどうか。私は中国語を知らないので、中国語に、日本語と英語の「正常」と「異常」の関係があるかどうかはわからない。多分ないだろう。あるとしても、少なくとも「日本語寄り」であろう。辞書を見ると、日本語の「甘え」に対応する中国語があることも、そのことを想定させる。韓国語については、前述のように、日本語とは同系ではないにしても、文法構造が酷似している。これは、日本語と英語の基本的な相違が日本語と韓国語には見られないということだろう。「甘え」についても、日韓辞典には、対応語が記載されている。つまり、言語の観点から見る限りでは、日本語と韓国語の差は小さく、それだけ日韓両国の文化には、類似性があるということになる。
日本と外国の文化を比較する場合の、もう一つの重要な指標は、風土的背景である。日本と西欧との風土比較では、かつて和辻哲郎が『風土』のなかで、「ヨーロッパには雑草がない」と書いた。このことばの意味するところは重大で、ヨーロッパでは、人間の生存に必要な農業生産性が極めて低い。地勢的特徴を表すものとして、私もかつて、『英語教育の比較文化論』のなかで、「(日本語の)山は、(イギリス英語の)
mountainではない。川はriverではない」と書いて、その違いを論じた。
例えば、イギリスをとってみても、位置が北に偏り、夏でも温度があまり上がらず、肝心の降雨量も少ないうえに、土壌も悪い。これでは、農業生産に不可欠な「熱、水、土」がいずれも充足されず、三重苦にさらされているようなものある。だから、農業生産では食べていけずに、豚、羊、牛などを飼ってそれらを食料源とする牧畜に頼らざるを得なかった。これに対して、日本は名だたる山国で、急斜面の川の流域にひろがる平地は肥沃である。水もふんだんにあって、太陽はさんさんと照る。まことに「豊葦原の瑞穂の国」で、農業生産性もずば抜けて高い。イギリスを含めてヨーロッパが、人間の生存にとっては極めて厳しい環境であったが故に牧畜文化を育ててきたのに対し、自然に恵まれた生存環境のなかで、日本では、豊かな米作文化が栄えた。
それでは、中国・韓国の風土的背景はどうであろうか。
中国は面積が960万平方キロもあって、東は太平洋北西部の縁海に接し、西はアジア大陸中部のパミール高原に及ぶ。日本の約38万平方キロに比べると25倍もある大国である。年平均気温だけをとってみても、熱帯の海南島では摂氏25度、亜寒帯の黒竜江省ではマイナス5度で、30度もの違いがみられる。平均標高4000メートルを超える南西部のチベット高原から、標高200メートル以下の東北平原、華北平原、長江中・下流平原、東南丘陵などを含めて、地勢も変化に富んでいるから、これだけの国土を簡単に締めくくることは難しい。風土差の文化に及ぼす影響を考える場合には、したがって、中国のどの地域かを特定して考えていく必要がある。
一方、韓国は、朝鮮半島の南半分を占める現在の面積が約10万平方キロと小さい。これは、北海道と四国を合わせたくらいの広さである。東海岸に沿って太白山脈が連なり、支脈の広州山脈、車嶺山脈、小白山脈などが分岐して、南岸、西岸に達し、多くの島嶼を形成している。国土が山がちであるのは日本に似ているが、最高峰は南端の済州島のハルラ山で1951メートルである。本土の太白山脈系ではほぼ1500メートル以下で、沖積平野は少ない。このことは土壌の肥沃さにも影響する。南部の全羅北道全州を中心とする湖南平野が最大の穀倉地帯といわれているが、日本の越後平野、庄内平野などの豊かさには、比べるべくもないだろう。
地勢としては、海に囲まれて半島状に位置しているものの、顕著な大陸性気候である。寒暖の差は激しく、南部や東部沿岸部を除いて、1月の平均気温は氷点下になり、特に最低気温が低くなる。半島部の緯度は日本の静岡県や大阪府中部から宮城県と同じだが、冬は大陸からの季節風の影響を受け、日本の同緯度の地域に比べるとかなり寒冷である。当然、農業生産性の点では日本より落ちるが、それでも、イギリスなどよりは、かなり「日本寄り」といってよさそうである。従って、風土的な背景では、それが、日本文化とは異なる文化を醸成していく大きな要因になるとは考えにくい。
以上、文化比較の場合に指標となる、言語と風土という二つの指標をとりあげ、それらが、中国・韓国文化と日本文化を比較する場合にも有効か、ということを考えようとしてきた。それを、さらに、具体的な事例でみていくことにしよう。
かつての日本の教育勅語のなかに示された十二徳のなかに、「朋友の信」というのがある。この「朋友」が、中国、韓国ではどう受け止められているか。日本と違うとすれば、どのように違うか、ということについて、中国、韓国の二人の学者の対談があった。中国側は、石平(せき・へい)氏で、中国四川省生まれ。評論家で、拓殖大学客員教授という肩書きである。韓国側は、呉善花(お
そんふぁ)氏で、女性評論家。韓国済州島生まれで、現在は、拓殖大学教授と紹介されている。対談は、明治神宮社務所発行の雑誌「代々木」平成22年春号に掲載された。(pp.8-15)
ついでに付け加えておくと、私がいまこれを書いているのは、その対談内容について、比較文化の観点から、意見を求められているからである。
対談では、まず、呉氏がいう。「韓国では、友達とはものすごく深い関係です。家族主義ですので、血縁関係を最優先するんですね。家族同様の友達がいかに作れるか。兄弟みたいな関係にならないと、本当の友達だといえないのですね」と。ここで強調されているのは、友達というものは「ものすごく深い関係」だということである。どのくらい深い関係かというと、「兄弟みたいな関係にならないと本当の友達だといえない」ともいっている。当然、この言い方の裏には、友達というのは、「日本とは違って」、或いは、「日本よりは」ものすごく深い、という認識があり、日本では、兄弟みたいな関係にならなくても「本当の友達」とされているという判断がある。そして、これに対しては呉氏も同調して、中国での友達のあり方を、「すごく家族関係を大事にしていますから、家族の絆に準ずるレベルでないと、本当の友達とはいえないのですね」と発言している。
友達のあり方については、中国と韓国はほぼ一致しているのに日本はそうではない。この違いが客観的に判断できれば、それはまさしく、中国・韓国と日本との文化の違いの一つに数えられるであろうが、これだけではおそらく、異論が出かねないだろう。日本でも、友達との関係を「ものすごく深いもの」として捉え、「家族同様に」考えることが決してないわけではないからである。だから、この違いが、どの程度の普遍性を持つかということが重要な判断基準になってくる。
例えば、石氏は、三国志時代の、劉備と張飛、関羽の故事をあげている。本来は君主と臣下の関係なのに「兄弟のような関係」になり、後に関羽が隣国の呉に攻められて殺されると、劉備は弟分の敵をとるために国を挙げての戦争をして負けてしまった。その結果、劉備の蜀の国は大いに傾いたのは、中国的朋友関係のよくない面だという。この「義兄弟」の故事はわが国でもよく知られているが、だから中国では朋友関係はみんなこれほど「深い」というのでは説得力が弱い。劉備と張飛、関羽の故事は、いわば「政略的な」兄弟であって、日本の戦国時代にも、大名間の政略結婚が数多く行なわれ、「深い兄弟関係」を、或いは、それ以上の家族的関係が意図されたことは少しも珍しいことではなかった。
欧米と日本に関する限りでの文化比較ならば、さまざまな文化の相違を、言語や風土の違いから、説得力のある議論を展開することができる。例えば、自己主張が強い、他人を警戒する、過ちを認めようとしない(謝らない)、子どものしつけが厳しい、家族でも他人的である、「沈黙は金」ではない(多弁を尊ぶ)等々から、食料を盗むことをあまり悪いこととは思わない傾向がある、というようなことにいたるまで、検証することは、そんなに難しくはない。しかし、中国・韓国との文化比較になると、すでにみてきたように、風土的な相違については、まだ考察の余地が残されているとしても、言語的な相違が及ぼす影響については、あまり大きいとは思えない。第一、この対談の主題に用いている「朋友」という漢字そのものが、中国の五経の一つである「易経」からきていて、それが韓国のみならず日本でも借用語として今も使われているのである。同じ漢字文化圏のなかで使われている「朋友」についての文化の差を浮かび上がらせるには、したがって、言語、風土だけではなく、別のさらに細かい指標が必要である。ここでは、「朋友」そのものよりも、まず、中国・韓国と日本との間の人間関係の違い、生活慣習の違いなどに的を絞って見つめ直してみることにしよう。
呉氏がいう。「よく言われるのは、お葬式での当事者の態度。韓国も中国も、家族を亡くしたら、みんなの前でワーワー泣くのが、自然の発露。日本人はお客さんの前では、なるべく凛として、抱え込むんです。ひとつの美学。」この人前でも「ワーワー泣く」のは、たしかに社会的慣習としてそうである。中国・韓国のみならず、東南アジア諸国ではだいたいその傾向が強い。悲しいはずの時に泣かなければ格好がつかないので、わざわざ「泣き女」を雇って派手に泣いてもらったりもする。しかし、この点では、日本人は明らかに抑制している。これは、かなりはっきりしている社会慣習、つまり文化の相違といってよい。
この人前でも感情を抑制しない態度は、普段の対人関係でもよくみられることである。悲しみを抑制しないが、喜びも抑制しない。賑やかにしゃべるだけでは足らずに、歌い、体を動かし、踊りだす。中国の各地では、朝の公園などで大勢の人が集まって、合唱したり、踊ったりしているのを私も何度も見てきているが、これだけをみても、人前で派手に自己表現することを抑制しがちな日本人との違いは、普遍的であるといってもいいかもしれない。そして、韓国人の場合も、喜怒哀楽の感情をあからさまに表現するという点では、葬式の例で呉氏があげているように、おそらく、中国人にかなり近い。
中国・韓国人のこのような抑制のない感情表現の仕方が、中国・韓国の人間関係を濃厚にしている傾向とは決して無関係ではないだろう。しかし、問題は、なぜ日本人とは違って、中国・韓国人は喜怒哀楽の感情をあからさまに表現し、濃厚な人間関係を持っているのか、ということである。これに対する、石氏のつぎのことばは極めて示唆に富んでいて、違いの根拠の一面に迫っているという点で、私も同調する。
「韓国的、中国的な人間関係の濃厚さ、これは社会環境の厳しさとも関係しているかもしれない。韓国にしても中国にしても、内乱、戦争の脅威にさらされていて、結局人間が孤独で生きるのは大変ですから、できるだけ強い絆をつくる。生きていく知恵かもしれません。日本のほうが平和で穏やかで、ベタベタしなくとも生きていける気がします。」
ここでいわれている「社会環境の厳しさ」については、私はもっと分かり易く、「生存環境の厳しさ」といったりするが、これは、どの国であれ、自国にいるだけではわかりにくい。どの国においても、程度の差はあれ、生存環境は厳しい、と思うものだからである。厳しいか、厳しくないか、それは、客観的に他国の生存環境と比較してみて初めて明らかになる。その客観的な指標の一つがその国の社会における安定度で、それを測るのには、例えば、戦争、騒乱の回数が有効な尺度としてあげられるだろう。
ヨーロッパと日本との間での戦争の回数比較では、かつて竹山道雄氏が1480年から1941年までの間の回数として、イギリス78回、フランス71回、ドイツ23回をあげている。日本はこれに対して9回である。栗栖弘臣は、過去500年間のデータとして、イギリス100回、フランス70回、ドイツ24回、日本は9回であったという。いずれも、日本の戦争回数というのは桁違いに少ない。(前掲・拙著第5章「歴史的背景」などを参照)
ただ、このような戦争回数の比較は、戦争をどう定義するかによって変わってくるから、問題がないわけではない。中国と韓国の戦争回数についても、年代を区切りながら対照的に調べていくのも、やはり、なかなか単純ではなく、いまはその余裕はない。司馬遼太郎『街道をゆく』(1)のなかでは、朝鮮が、有史以来、外敵の侵入を受けた回数が「五百数十回」と述べられているところもあるが、その根拠は明らかではない。しかし、容易に予想されることは、おそらく、日本よりははるかにヨーロッパ寄りであるということである。逆の見方をすれば、日本が、世界史のなかでも圧倒的に戦争の少ない国で、中国・韓国にくらべても、社会の安定度が継続的に高かったということになる。これは重要な要点なので、少し詳しく論じておかねばならない。
まず、この日本がいかに平和な国であったかについては、「内」からではなく、「外」からみなければ気がつきにくい。「日本にも、戦国時代があった、戦乱相次ぐ百年があったではないか」というような反論がすぐにでてきたりするからである。かつて、イザヤ・ベンダサンは『日本人とユダヤ人』のなかで、日本の戦国時代について、「あの程度のことなら、中東では実に3千年も続いた状態のうち、比較的平穏だった時代の様相に過ぎない」と書いた。つぎのような叙述もある。
「まず日本の歴史に記載されている戦争を検討してみよう。保元の乱、平治の乱などはク-デタ-であって戦争ではない。この程度のク-デタ-なら、二十世紀の今日でも、ユ-ラシア、アフリカ、南アメリカでは日常の茶飯事であって、事件の中にすら入らない。日本最大の内乱といえば関ケ原の戦いだが、この決戦が何と半日で終わっている。戦争というより、大がかりな騎士団のト-ナメントである。第一、戦う前に、自分の系図一巻をお互いに暗証し合うなどということは、ト-ナメントの礼儀であっても、戦争の作法ではない。」
『日本人とユダヤ人』の文は、ヨ-ロッパの戦争と比較したものではないにしても、日本人の戦争に対する考え方の甘さを、いやというほど感じさせる。このように書いてきて、ここでちょっとわき道に逸れるが、第二次世界大戦で、日本は原爆を落とされ、多くの都市が焦土と化すなど、大きな被害を受けた。死者も外地に展開した軍人の戦死者を含めて総数は300万を超える。それだけに、この「考えが甘い」という言い方には反発があるかもしれない。しかし、外から見れば、加害者の立場でありながら300万だけではないか、と思われているかもしれない。例えば、中国は1、000万以上といわれている。内からと外からでは、見方が違うのである・・・・・。それを付け加えて元に戻る。ここでは、『日本人とユダヤ人』の著者は、いささか誇張しているのであろうか。だが、この著者は次のようにも述べて、そうではないことを、確信的に伝えようとした。
「さらに、当時日本に来たイエズス会宣教師の手紙をごらんになればよい。西欧も中東もインドも中国も(ということは当時の世界の殆どすべてを)直接に見たか間近かに見てきたこれらの人びと、当時には珍しい、ほぼ世界中を直接に見聞した人びとが、戦国の日本のことを何とのべているか。その手紙とパレスチナ周辺の農民とを比べてみれば、少なくとも次のように言えることは確かである。戦国時代の日本は、当時の世界で、最も平和で安全な国の一つであったと。」
どうやら何か大きな違いがあるようだが、それでは、なぜ日本がこれほどまでに平和で安全な国であったのであろうか。これは、この種の中国・韓国との文化比較では重要なので、しっかりと見極めておきたい。対外的には、国土の周囲を荒海で囲まれ、太平洋の片隅に孤立している地理的条件がその大きな要因になってきたことは否めないであろう。しかし、日本人が戦争でなく平和を、危険ではなく安全を享受できたもう一つの大きな理由は、日本の風土が豊かであったことに尽きるといってよい。実際、日本人は、古来豊かな食料と平和に恵まれ、ぬくぬくと育ってきた「苦労知らずのお坊ちゃん」であった。
こう書くと、ここでも、「それでも日本には、歴史に暗い影を落としてきた多くの飢饉があったはずではないか」とまた反論を受けそうである。なるほど確かに多くの飢饉はあった。飢饉の回数を調べてみると、六世紀後半、欽明天皇28年から明治2年までに大小225回あったことになっている。江戸時代に入ってからも、享保、天明、天保の三大飢饉は有名である。しかし、これらの飢饉はヨ-ロッパ的な意味での飢饉とは決して同じではない。日本の場合は、国土が豊かで、人間が増えすぎていたからこそ起こった飢饉であって、ヨ-ロッパ並の風土であれば、飢饉は当たり前となって人間も増えず、日本的な飢饉は起こりえなかったに違いないのである。
イギリスの経済学者ト-マス・マルサスが1789年に著した『人口の原理』によると、人口は幾何級数的に増加する傾向があるのに対して、食料は、算術級数的にしか増産できない。このギャップが、貧困、飢え、病苦をもたらせ、人口の増加を抑制するわけである。たとえば、江戸時代の日本の人口は2600万から2700万を超えることがなく、それ以上の人口の増加は、堕胎、間引き、嬰児殺しなどによって阻止されていた。豊かであっても、食料生産に見合う限度いっぱいまで増え続けた人口は、そこで抑制されることを示している。高い食料生産性のメリットも人口の増加によって相殺されるから、やはり飢饉の脅威からは逃れられなかったのである。
要するに、日本は、世界でもまれにみる平和で安全な国であった。個々の人間の生存が脅かされることが少なく、誰にでも平穏な生活が保障されているようなところがあった。社会の安定度は抜群であったといってよい。中国・韓国と日本との間の平和や社会の安定度の比較を試みようとする前に、日本は、むしろ、世界的には「異常なほど」例外的に平和で安全な国であったことに留意することで、その差は浮き彫りにされる。
少し詳しく、比較の一方の対象である日本の特殊な情勢について述べてきたが、この辺で、主題の中国・韓国と日本との「朋友の違い」に戻っていきたい。石氏の「韓国にしても中国にしても、内乱、戦争の脅威にさらされていて、結局人間が孤独で生きるのは大変ですから、できるだけ強い絆をつくる。生きていく知恵かもしれません」ということばが、ここで大きな意味を持ってくる。社会の安定度が低ければ、いざというときに頼れる者をもたなければならない。他人には頼れないから、頼れる「朋友」に対しては自然に重い関係が生まれてくる。これが、呉氏のいう「ものすごく深い関係」「家族同様の友だち」になっていく背景であろう。
日本には、たしかに、石氏がいうように、人間関係が「ベタベタ」と濃厚にならないところがある。家族には頼るが、友だちには普通多くは頼らない。多くを頼らないのが友だちで、友だちは家族とは違うのである。このように、中国・韓国の友だちと、日本の友達が離れていった要因には、儒教の影響も考えなければならないであろう。
儒教も漢字文化と同じく、中国から韓国(朝鮮)と日本にもたらされた。日本では、4世紀に招来されてからは、大化改新の律令制の理念に大きな影響を与え、それは、江戸時代の林羅山や山鹿素行らの儒学にまで受け継がれてきた。日本社会の道徳を律する精神的支柱であり続けたが、しかし、その影響は、明治以降の欧米志向の高まりとともに、徐々に衰えをみせて現在に至っている。いまでも、家族関係などにその影響を色濃く残している中国・韓国に比べれば、家族関係が、日本では、より「希薄になっている」ことも、儒教の衰退と多分、無関係ではないだろう。
ここで考えなければならないのは、日本における独自の神道の影響である。神道は、いうまでもなく、自然を媒介として神と人が結ばれた日本固有の民族宗教であり、穢れを忌み嫌い、清浄を尊ぶ伝統をもつ。その影響が日本人の美意識から人間関係にまで及んでいることを呉氏が触れているのは、一つの卓見である。この対談のなかで、呉氏がまず言う。「日本の場合は、人間関係も、美学でみればよくわかるんですね。美しいか、美しくないか。品があるか、ないかということが、ものすごく大事。朝鮮半島・中国では、美学よりも、いい人か悪い人かというのが対象になりますから・・・・・」 そして、呉氏はさらに、このように続けた。
「世界の中でも、人間関係のあり方は極めて独特です。とにかく日本は、あらゆるもの―芸術であっても、人間であっても美で生きるというのが日本人。それに結びつくのが、私は自然風土だと思うのですね。日本の自然というのは極めて美しいわけで、それを言いますと、どこの国だって、それなりの美しさがあるじゃないか、と言われてしまうのですが、自然のあり方が、人間関係のあり方、精神性に深く刷り込まれていて、それがあらゆるところにそのまま延長で現われていることが多いと思います」
この見解に対して、石氏は、「中国と韓国と、(日本が)どう違うかというと、やはり日本には神道があるということ。神道は人間関係の倫理をはじめ、あまり語らない。ただ、ひとつ、清らかさだけを語る。美しい、または潔い。この精神の根底、日本的な人間関係を、さかのぼっていけば神道にたどりつくのではないかと思うのです」と、応じている。対談もここまでくると、主題の「朋友」の受け止め方が、中国・韓国と日本では、「どう違うか」から、「なぜ違うのか」まで、両氏の国際的な視野と学識のもとに、かなり明確に浮き彫りにされてきたといえるであろう。
結局、日本でいう朋友とは、ベタベタとした濃厚な人間関係ではない。兄弟のように親しくなることはあっても、相手に負担をかけることを避けたいという斟酌から兄弟のようには頼ることはしない。お互いに多くを語らなくてもすむのが友人であって、友人としての付き合いにも、ある程度距離をおいた淡白な人間関係として、長続きさせようとする。無意識ではあっても以心伝心ははたらき、付き合いが深まっていっても節度があって、恥の文化の枠組みからもはみ出すことはない。そして、そのような日本人の人間関係をもたらせた背景には、美しい自然と、豊かな国土、そこから生み出された情緒的な安定感と美意識の伝統、多言を必要としない内輪の世界のぬくもりと、礼節、秩序を重んじる精神などが、あげられるであろう。
以上の比較文化の考察の最後に、付け加えておきたいことがひとつある。ここで取り上げてきたような「朋友」という言葉の微妙な捉え方の違いを含めても、日本文化そのものが、世界の中では極めて特異ということである。おそらく、比較対象になるヨーロッパ文化や中国、韓国文化など、相手側が日本文化とは違う、という言い方よりも、こちら側の日本文化そのものが世界の多くの文化からかけ離れている、というべきかもしれない。つまり、いい意味でも、悪い意味でも、相手が違うのではない。自分が違うのである。
かつて、和辻哲郎は、ヨーロッパでの研究生活から帰国した時、「この日本というものが、アラビアの砂漠にも劣らないほど珍しい、全く世界的にも珍しいものであることを痛切に感じざるをえなかった」と述べた。そのことばは、少しは色褪せても、いまも生きているといってよいであろう。
(2010.10.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神界から来た人
ー生活と文化をめぐる随想(73)ー
霊界というのは階層社会ですから、私たちは死後、自分の霊格に応じた階層へ還っていくことになります。霊格の高い人ほど、上層の光に近づき、低い人ほど、下層の闇に近づくと考えていいでしょう。そして、その最上層部には神界があります。これは光の世界で、そこに、釈迦やイエス・キリスト、孔子など、多くの覚者がいると一般にはいわれています。そのような覚者のなかには、私たちのような煩悩に苦しむ衆生を救うために、地上世界に降りてくることもあるようですが、もし、そうであれば、それは地上ではどのような人になるのでしょうか。
私は、15歳の頃、高熱を発して生死の間をさまよっていた時に、燦然と輝くお釈迦様のような存在から、じっと見守られていたことがあります。完全に意識を失ってしまうまで、私は継続的に、その燦然と輝く光とやさしい温もりの感じを受け留めていました。世間では、同様の体験について、それは、高熱によって意識が混濁した結果生じた幻覚だ、などというもっともらしいコメントをする人もいますが、私は、確かな根拠もあって、自分の体験を幻覚かもしれないと思ったことは一度もありません。いまでも、燦然と光り輝いている「お釈迦様のような存在」は、強く記憶に残っていますから、霊格の高い高位霊から発する光とはどういうものか、私には分かるつもりでいます。
でも、その光は、通常の状態の肉眼では見ることはできません。かりに神界の高位霊が、地上に降りてきて、例えば、この日本のどこかに住んでいるとしても、光は見えませんから、まわりの人々にはほとんど気付かれないのではないかと思われます。自分は神界から来たと広言して名声と蓄財に執着するような新興宗教の指導者などは論外で、本当の高位霊は、みずからを宣伝し金銭を集めるような下賤の言動からはほど遠い存在のはずです。ですから、一般の人々には、「神界の人」とか「光」などといわれても、遠い未知の存在ということになってしまいますが、それでも、それはどんな人か、知ろうと思って探していけば、見つからないわけではないようです。
その一つの例が、作家の佐藤愛子さんが『私の遺言』(2002年、新潮社) のなかでで触れられている相曽(あいそ)誠治氏です。佐藤愛子さんは、昭和50年、51歳の時に、北海道の浦河に別荘を建てますが、そのとき以来、屋根の上で人の歩く音がしたり、玄関に置いてあったダンボール箱がなくなったり、電気が急に消えたり、水道のないところでザアザア水音がしたり、などなど、異常現象が次々に起こり始めるようになりました。それを彼女は、『こんなふうに死にたい』(新潮文庫、1992年)に書いていますが、それを読んで、佐藤さんのところへやってきたのが名古屋の小児科医を名乗る鶴田光敏という医師でした。この鶴田医師を通じて知り合ったのが、「田舎の村長さん」といった趣の相曽誠治氏であったということです。
この鶴田光敏さんは、佐藤さんの家で霊能者の美輪明宏さんに会っています。人は会うべくして会うのだということを示す好例として、このときの美輪さんとの会合は興味深いのですが、その時に美輪さんは、佐藤さんと鶴田さんとの前世の出来事を次のように霊視しました。
見渡す限りの銀世界。川が流れている。そのそばを髪が乱れ戦いに敗れてボロボロになった武士がよろめきよろめきやって来る。川の左側に萱葺きの百姓家がポツンと建っている。家の中の土間の壁に鞘を被せた長柄の槍が五、六本懸っている。土間の上は板の間で、囲炉裡の前に居ずまい正しく、背筋がスッと伸びた老女が坐っている。
そこへよろめきつつさっきの落武者が入って来た。老女は囲炉裡に懸けた鍋の中のものを碗によそって落武者にさし出す。彼はそれを食べ終るとその家を出て、また川に沿って歩いて行く。暫く歩いて、川の畔に正坐して、割腹して果てた……。(『私の遺言』p.45)
そして、美輪さんは「その老女が前世の佐藤さん。落武者は鶴田さんよ。鶴田さんは前世で、佐藤さんに恩があるの……」と解説しました。鶴田さんの下腹には、いまでも、真横に一筋、20センチほどの切腹の痕みたいな傷痕が残っているそうです。それを二人の前で見せながら、「これは生れた時からあったんです。何だろうって皆でふしぎがったっておふくろがいってました」という鶴田さんのことばを、佐藤さんは伝えています。
こうして、佐藤さんは、北海道の浦河の別荘の超常現象を鎮めるために、はじめは美輪さんに頼っていたのですが、その後も江原啓之さんや、日本心霊科学霊協会の霊能者たちの助けを借りていきました。しかし、それでも超常現象は収まらず、東京の自宅でも起こるようになって、佐藤さんは体調まで崩してしまいます。鶴田さんの医師としての目にも、心身の衰弱がはっきり見て取れ、死を予感したとさえいいます。心配した鶴田さんは、ついに神道家の相曾氏を見つけました。「この人をおいて佐藤家の怨念を相談できる人はいません。最後の人です」と佐藤さんに知らせ、鶴田さんの尽力で、相曽誠治氏に北海道の浦河まで行ってもらうことになったようです。
相曾氏は、浦河での神事を終えたあと、「これでこの土地も少しずつ浄化されて行くでしょう。しかしこれだけの大きなカルマですから、いっぺんでサーッときれいになるというわけには行きません。神界から神のお使いが来られて、月に二体か三体くらいずつ霊界へ導かれて行くのですから、時間がかかります。けれども最終的にはすべて救われます」と笑顔をみせました。佐藤さんも本当に救われた思いがしたことでしょう。このあとの佐藤さんの文章には、穏やかな安堵の響きが感じられます。つぎのようにです。
遅い夕食の後、気がつくと丘の下で頻りに嘲る小鳥の声が聞えていた。何ともいえないきれいな、まろやかな声だ。小鳥はピイピイかチイチイ、チュンチュンと啼くものだが、この鳥はラリルレロの音でなめらかに啼いている。実に気持のいい囀りだ。こんなに夜が更けているのに囀るなんて不思議ですね、というと、いや、あの小鳥は今を昼間だと思っているのでしょう。おそらく小鳥の目にはこの丘は今、光に包まれているのだと思いますよ。今夜はここは神界の光をいただいているのですから。そういう相曽氏の声はいつものように静かなのだった。(前掲書pp.194-195)
ここにも「神界の光」がでてきますが、この相曽誠治氏とはいったいどういう人なのでしょうか。佐藤さんも考え込まずにはおれなかったようで、鶴田さんに聞くと、「私は今まであんなに無私の、清らかな魂を持った人に会ったことがありません。どんな人に対しても、どんな時でも同じ表情、変らない態度。あれは自然体というのでしょうか。しかしその自然体は我々俗人の自然体とは次元が違うように思われますねえ」と、彼は答えています。そしてある時、佐藤さんがたまたま名古屋駅のプラットフォームで相曾氏と一緒に電車が来るのを待っている間に、彼女はふと、ある衝動に駆られてこう訊ねました。「失礼ですが、先生は、神界からおいでになった方ではございませんか」。
そんな唐突な問いかけに、氏は驚きも笑いもせず、極めて平静に頷いて答えました。「私はことむけのみことと申します」。佐藤さんが訊かなければ、自分ではなにも言わなかったのかもしれませんが、彼女が訊きましたので、相曾氏は自分が「神界から来た人」であることを、「頷いて」はっきりと認めました。これは極めて重大な答えですが、その返事を聞いたときの感じを、佐藤さんは、その口調はまるで、お故郷はどちらですかと訊かれて「青森です」と答える人のような、まことに日常的な応答だった、と書いています。そして、次のように続けました。
「そうでしたか」と私はいった。やっぱり……と心に領いていた。「ことむけのみこと」とは多分「言向命」と書くのであろう。即ち力で従わせるのではなく、言葉をもって導くという意味であろう。私は素直にそう思った。(前掲書p.199)
いかにも温和で、「田舎の村長さん」という趣の、質素な背広に中肉中背の身を包んだ素朴な老人。自信、威厳というのは何もない。ただ感じるのは初対面であっても初対面の人のような気がせず、理由のわからない懐かしさのようなものがこみ上げてくる人。これが、「神界から来た人」相曾氏に抱いている佐藤さんの印象です。街のなかですれ違っても、誰も気がつかず、見向きもされないような一老人かもしれませんが、もし、霊能者で十分に力のある人が見たら、この相曾氏の姿は、おそらく、大きな、輝かしい光の輪に包まれているのでしょう。
相曾氏は、1910年生まれで、佐藤さんの浦河の別荘へ行った平成6年(1994年)には85歳に近くなっていたはずでした。その頃でも、相曾氏は毎年7月には、日帰りで富士山に登って神事をされていたといいます。80代半ばの高齢で富士山の登山下山が日帰りでできるというのは、ちょっと信じがたい話ですが、相曾氏にそのわけを尋ねたときの様子を、佐藤さんはこう書いています。
「天狗さんが助けてくれますので」
冗談かとその顔を窺うが、極めて当り前のことを話しているように、
「登る時はみんなで後押しをしてくれますのであっという間に山頂に行き着きます。でもその姿は人の目には見えません」
と涼しげである。山頂には既に汚れていない場所が用意されているので、すぐに神事を始めることが出来ます。お供えのお塩、お洗米、お神酒、お水、海の幸、山の幸など、あっという間に整います。そこで秘事を唱え、祝詞を奏上し、日本及び世界の平和を祈願して下山します……。
天狗というと、手に団扇を持ち、鼻高く顔赫く眼はいかっていて、鞍馬山で牛若丸を鍛えたあの天狗を私は思う。だがそれを訊こうとしても、氏のあまりに泰然とした様子に気圧されて、何もいえずに傾聴の姿勢になってしまうのである。(前掲書pp.195-196)
私たちも、「天狗に後押しされて登山する」といわれますと、さすがに、う~んと考え込んでしまいそうになりますが、ここでは、佐藤さんのお人柄を信じ、作家としての彼女のペンの力に頼って、その「事実」に、ひたすら無心についていくほかはありません。この「無私で清らかな魂」の相曾氏が、私たちの間ではよく見られるような、虚栄のために事実を曲げたり、自分の業績を誇示したりするようなことは、おそらく考えられないでしょう。不思議な話がいろいろと明らかにされる中で、相曾氏が、さらに、神界について次のようにも述べました。このなかの五次元というのが霊界のことで、人が死んで最初にいく幽界は四次元と考えてよいようです。
「五次元の上の方にはキリストや釈迦、孔子などがおられて、神界を目ざして修行しておられます」
と相曽氏はいう。
「お釈迦さんは立派な方ではありますが、今のところ六次元止で、七次元にはまだ到達していません。釈迦といえども神界に行かれてはいないのです。苦心惨憺して、あれほど厳しい修行を積んでもなかなか神界には入れません。仏教には神界に入れない因縁があります。研鑽を積んだ釈迦といえども、ぎりぎり最後のところでは神理に到達していませんでした。あの方は真面目な方ではありますが、少し性格が暗いですね」
町内会長のことでもいうようにお釈迦さんのことをいわれると、
「は~ァ……」
としか私はいえない。「キリストさんはちょっと泣き虫ですね」といわれても、疑問も質問も言葉にならない。氏の言葉を私は荒唐無稽だと思ったり、また納得させられて心正して聞くべき正論だと思ったり、常に揺れ動いた。鶴田医師も私と同様の気持だったにちがいない。だが氏と直に会って柔和な目差し、礼儀正しい物腰、穏やかな声音に触れると、品性の高さを感じて疑問が消えてしまう。(前掲書pp.197-198)
相曾氏は、「仏教には神界に入れない因縁がある」などと言われていますが、これは、氏が神道系であることと関わりがあるのでしょうか。また、お釈迦様やイエス・キリストについての、ごく身近にいる親しい人からのような評価には、いささかの戸惑いを抑えきれませんが、ただ圧倒される思いです。やはり私たちには、うかがい知ることのできない別世界としか、言いようがありません。しかし、私たちにも分かりやすい具体的な例もあります。佐藤さんは、こんなことも書いています。
平成七年一月十日、私のところへ相曽氏から電話があった。
「近々、地震が来ます。ご用心なさって下さい」
いつもの穏やかな口調だった。それはどこですか? 東京ですか? と訊くと、
「場所は申せません。しかし必ず来ます」
とだけいわれた。
神戸に大地震が起きたのはそれから七日後である。その報道を見て私は、地震の警告を半信半疑のまま聞き流していたことに気がついた。(前掲書、p.199)
この相曽氏は、1999年12月31日午後11時に89歳で亡くなりました。ご家族で揃って年越しそばを食べ、かねてから老衰で体が弱っていた夫人が厠に立ったのを気遣い、様子を見ようとして廊下へ出たあとに、途中で崩れ落ちて息絶えたということです。
人のために尽くし、「この国を本来あるべき姿に正そうという」使命に生きていた氏は、晩年になって、体力が衰え足腰が弱ってからも、神事などの頼みごとを受けると決して断らずに、どこへでも出かけられたということです。しかも、謝礼のようなものは、一切受け取られませんでした。佐藤さんのためにわざわざ北海道の浦河へ行かれたときも、飛行機代などはすべて自分で負担していたようです。
霊界の神界から高級霊が降りてくることがもしあるとすれば、それは地上ではどういう人になるか。その問いに対して、「神界から来た人」はこういうふうに生きて、こういうふうに死んでいくものだという一つの例を、私たちは、佐藤さんの本によって垣間見ることができます。あと一時間で2000年を迎えるというあの最後の瞬間の相曽誠治氏の姿は、普通にみれば一老人の衰弱死と変わらないでしょう。しかし、見る人が見れば、相曽氏は、私の子どもの時の頭に焼き付けられた、あの燦然と輝く光に包まれながら、地上での使命に一区切りをつけた穏やかな心境で、神界へ還って行かれたのかもしれません。
(2010.08.01)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人の罪の償いと赦しをどう考えるか
ー生活と文化をめぐる随想(72)ー (2010.06.01)
いま、日本の社会でも、国民の参加による裁判員制度が始まったばかりで、人を裁くことの意味が、改めて、問い直されようとしています。親殺し子殺しなどを含めて、残忍残酷な殺人事件、凶悪犯罪が後を絶たず、これらに対しては、厳罰と極刑で臨むほかはないのではないかという声も目立ってきました。私たちは、これにどう対応していけばよいのでしょうか。
この間、宗教思想家といわれる山折哲雄氏が、「読売新聞」の朝刊(2010.4.25)に「償いと赦し・菊池寛の洞察」という一文を載せていました。ここでは、菊池寛の小説、『恩讐の彼方に』と『ある抗議書』が取り上げられ、赦しについての対照的な二つの姿勢が紹介されています。
『恩讐の彼方に』はよく知られているように、大分県中津市の名所『青の洞門』を題材にした作品で、徳川吉宗のころ、旗本の主人を殺して逃亡した市九郎の贖罪の話です。市九郎は流浪の果てに、僧侶の導きで仏門に帰依しますが、後に、九州の耶馬溪に至り、人を寄せ付けない大岩壁に立ち向かって、自分ひとりの力で人道をくり抜こうと決意します。主人を殺した懺悔の気持ちからでした。
20年も鑿を振るい続けて、開通もまじかになった頃、殺された旗本の息子が現われて、仇討ちの名乗りをあげます。運命の対決になりましたが、市九郎の鑿が最後の壁を打ち砕き、人道が貫通して光が差し込んできたとき、旗本の息子の心には一切の怨みが消えていました。相手が父親殺しの犯人であっても、20年もの間、懺悔の鑿を振るい続けてきた孤高の姿に仏の光を見たからかもしれません。
これは、ある意味では、わかりやすい赦しの姿だと思います。「加害者」の20年におよぶ筆舌に尽くしがたい過酷な懺悔の歳月は、親を殺されたという怨みをも、時には消し去り、罪を償うものとして「被害者」を納得させることもできるということでしょうか。
もう一つの『ある抗議書』は、大正3年(1914年)に発生した実際の殺人事件を題材にしたもののようです。『恩讐の彼方に』とほぼ同時期に書かれていますが、これは、山折氏もいっているように、氏をも含めて、いまの私たちにはあまり知られていません。この作品では、年配の夫婦が殺されて、犯人が捕らえられ、死刑の判決が下されます。獄中の犯人は、刑務所の教戒師のことばで改心し、キリスト教徒になりました。そして、処刑のときには、神に感謝しながら死んでいくのです。
事件の筋書きはこれだけですが、問題は、その加害者の最後の姿を聞いた被害者の遺族です。殺された人間が地獄におちる苦しみのなかで死んでいったのに、なぜ殺した者は天国にのぼる心境で安らかにこの世を去っていったのか。「不公平ではないか」と悲痛な抗議の声をあげるのです。著者の菊池寛は、この遺族の気持ちに同情し、「司法大臣閣下」にぶつける抗議書の形式でこの作品は書かれたのだと、山折氏は述べています。
このような被害者の心情に関して、氏は、最近見たという韓国映画『シークレット・サンシャイン(蜜陽)』についても触れています。
この映画では、夫を事故で亡くしたピアノ教師の若い女性が、幼い息子を連れてソウルから小さな地方都市の蜜陽へやってきます。ここで突然、息子が誘拐され、やがて遺体で発見されるという事件が起こってしまいました。犯人は挙げられましたが、ひとり取り残された女性はどんなに悲しく辛かったことでしょう。絶望の淵のなかで藁にも縋る思いで教会の集まりに出るようになります。やがて、信者たちの神への祈りに励まされ、こころの安らぎを得て、犯人を赦す心境にまでなりました。ついに刑務所へ出かけて犯人に会い、許しの気持ちを伝えようとするのです。ところが犯人は、こう言いました。「自分はすでに神の赦しをえて神の愛に包まれ、感謝の毎日を過ごしている」と。山折氏は、その場面を、「その犯人の言葉に驚愕した女の表情がみるみる暗転し、痴呆のように放心した姿がクローズアップされていく。何という理不尽な神の摂理・・・・・」と書いています。
私は、『恩讐の彼方に』の場合の赦しを、「わかりやすい赦しの姿」と書きましたが、『ある抗議書』の場合には、もちろん、赦しの姿はありません。そして、『シークレット・サンシャイン』の場合も、赦す気持ちを持ち始めていたとはいえ、本当の赦しの姿からはまだ遠いといえるでしょう。この両者とも、極悪の罪が許されるのは、「無限の贖罪行為が積み重ねられた果てにおいてのみ初めて可能になるのだ」という被害者側の執念が色濃く反映されているようです。
山折氏は、近頃の凶悪犯罪が続出する傾向のなかで、厳罰主義が広がりをみせている底流には、このような、いわば、「いとも簡単な」改悛と懺悔では赦されないという考え方がある、としていますが、それについての氏の見解は示されていません。凶悪な犯罪を犯した人間は、たとえ改悛したとしても、少なくとも『恩讐の彼方に』の市九郎のような長年月の懺悔の行為がなければならないと、私たちもまた「厳罰主義」に与するべきなのでしょうか。
少し突飛にみられるかもしれませんが、このような問題を考える場合には、どうしても、人のいのちと神についての深い洞察がまずなければならないと思われます。人はすべて、加害者も被害者をも含めて、輪廻転生を繰り返しながら永遠の命を生きている霊的存在で、一分一厘の狂いもなく働いている宇宙の法則のなかで生かされています。その観点からみると、この問題に対する答えは自ずから明らかで、「理不尽な神の摂理」というのはありません。「不公平」も全くありません。そして、人の罪は赦すべきなのです。懺悔の行為の有無にかかわらず、或いは、厳罰主義の声がいかに高まっても、赦す以外に正しい道はないでしょう。
人の罪を赦すというのは決して容易な行為ではなく、私自身も、かつて被害者の遺族の立場で、長い年月、赦すことができずに苦しんだことがありました。しかし、「目には目を、歯には歯を」的な憎しみや報復は、また新たに憎しみと報復を生み出すだけで、決して問題の解決にはなりません。それによって、こころの安らぎが得られることもなく、社会の安寧や世界の平和を願うこともできないでしょう。これは山折氏も知っているはずですが、仏教、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教をはじめ、世界の主な宗教は、すべて例外なく、人が人を赦すことの大切さを教えています。そのことの意味を、私たちは、むしろこういう時代だからこそ、よくよく考えてみたいものだと思うのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
人間のもつ驚異的な能力
ー生活と文化をめぐる随想(71)ー (2010.04.01)
もう10年以上も前になりますが、私は、西野塾というところで呼吸法を学んでいる友人に誘われて、渋谷の道場へ行ったみたことがあります。そこでは、精神を集中して気を送れば、目の前の相手に触れることなく、吹き飛ばせるということでした。私は、まず、そのデモンストレーションに参加してみることにしました。
塾長の西野皓三氏の前に2メートルくらい離れて、屈強な若者が3人縦に並んで立っています。その3人に向かって、西野氏が手を差し伸べ気を送りますと、前の3人は、何か大きなエネルギーの流れに耐えるように踏ん張っていましたが、やがて、後ろのほうから一人ずつ、空中を飛ばされていきます。友人の言っていたことは本当でした。この空中を飛ばされている写真は朝日新聞にも大きく載せられたことがありますから、ご覧になった方もおられることでしょう。
私が、一週間に一度だけでも、半年間、その塾に通うようになったのは、誰でも、練習さえ積めば、西野氏のように、相手を飛ばせることができると聞いたからでした。なるほど、ふだんは、何人もの若い西野氏のお弟子さんたちが、気を送って、塾生たちを次々に飛ばしています。しかし、私はどういうものか、気を受けても飛ばされることはありませんでした。真実を受け入れる素直な気持ちが欠けていたからでしょうか。それでも、修行さえ続ければ、人間には、気を送っただけで相手を飛ばすことができるということを、目の前で見て知ることができたのは、私なりの収穫でした。
それから、何年か経って、北京のある病院を訪れた時、そこの女医さんが気功の達人であると紹介されました。ぺらぺらの中国人民元の紙幣で、太い箸を切ることもできるといいます。私が、日本の古い千円札を差し出して、これで切ってみてほしいと頼みますと、彼女はその千円札の皴を伸ばして、私が両手でしっかり握っている中国の太い骨の箸にさっと振り下ろしたのです。箸は見事に切断されました。私は、ちょっと驚いて、「どうしてこんなことができるのですか」と聞きますと、女医さんは、「練習すれば誰にでもできますよ」と微笑んで答えました。この体験で、私は、千円札でも太い骨の箸が切れることを知っています。
しかし、世の中には、こんなことよりはるかに「特異な」能力をもつ人がいます。たとえば、森田健さんは『ハンドルを手放せ』(講談社α文庫)のなかで、中国の超能力者が、ゆで卵を元の生卵に戻す、煮た豆から芽を出させる、茹でられて死んだはずのエビを生き返らせる、というのを目撃した話が書いてあります。船井総研の船井幸夫氏が「信じられない」というので、森田さんは、中国へまた出かけて、その超能力者を来日させ、船井氏の目の前で、事実であることを証明させたのだそうです。私はそれを見ていないので、それが事実であることは知りません。しかし、そのような事実があり得ることを信じることはできます。ただ、超能力もここまでくると、誰でも修行を積めばできるというものではないのかもしれません。
超能力というと、なにか不可解な神がかりのイメージもありますが、いわば、記憶の超能力というのもあります。昨年(2009年)11月に、イギリスのロンドンで、世界記憶力選手権大会が行なわれて、その模様が去る3月7日のNHKハイビジョンで紹介されていました。(特集「記憶―脳と人間の物語」)
競技は10種目に及びますが、そのなかには、たとえば、「スピードカード」というのがあります。トランプのカード52枚をばらばらにしたものを束ねて、その順序の通り、すべてのカードを覚える早さを競うのですが、世界記録保持者は、イギリス・バッティンガムの会社員ベン・プリットマンさんで、24.97秒だと伝えられていました。
「顔と名前」というのもあります。それぞれに名前がつけてある写真を与えられて、15分の制限時間内に顔と名前を何人覚えられるかを競うのです。この世界記録保持者はドイツ・ドルトムントの脳科学専攻の学生ボリス・コンラッドさんで、117名でした。
コンラッドさんは、名前から何が連想できるかを考え、それを顔に結び付けて覚えるのだそうですが、それを瞬間的にやってのける能力は、神業としか思えません。しかし、そのコンラッドさんは、「子どもならもっと簡単にできるでしょう。大人は、想像の世界から離れてしまっているだけです。練習を続けていけば誰にでもできますよ」と語っていました。
「一時間ナンバー」というのもあって、これは、ばらばらに並べられた数字を一時間かけて覚えるというものです。厖大な数の数字の羅列に一時間目を通し、そのあと、2時間かけて、覚えた数字を紙に書いていきます。数字を一つ間違えても失格ですからたいへんな作業ですが、ここでは、中国四川省の会社員スー・リー・チャオさんが実に2080個の数字を順序どおり正確に書き上げて世界記録を樹立しました。やはりこれも、練習に練習を重ねた成果なのだそうです。
これらも超能力に違いありませんが、世界に広く公開された場で示された能力は、もはや、そのような能力を信じるか信じないかの問題ではなくて、知っているか、知らないかの問題だといえそうです。オリンピックのフィギュアスケートで浅田真央選手が3回転ジャンプを2回続けたのを「信じるか」、とは言わずに、「知っているか」と言うのと同じようなものです。
超能力は超脳力といってもいいでしょう。普通、私たちは自分たちのもっている脳の3パーセントも使っていない、というようなことがよくいわれますが、いろいろな超能力を知るようになりますと、改めて人間には、誰にでも、ほとんど無限の能力が秘められていることを、深く考えさせられてなりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
偏見と差別について考える
ー生活と文化をめぐる随想(70)ー (2010.02.01)
「朝日新聞」の夕刊では、最近、10回にわたって被差別部落問題をとりあげ、「差別を越えて」と題する特集記事を連載していました。(2010.1.19~1.29) そのうちの第4回は、「屠場、いつかマイスター」というのが見出しです。部落差別、屠場差別がなくしていくためには、屠場の仕事は、「社会に必要な専門職だという評価がほしい。マイスターとして、堂々と名前を出せるようになれば、部落差別、屠場差別の払拭にもつながると思う」と述べた、ある部落出身者のことばをタイトルにしたものです。
島崎藤村の『破戒』を持ち出すまでもなく、日本の社会には、古くから、家畜処理業者に対する陰湿で根強い偏見と差別が深く浸透していました。そして、その偏見と差別は、いまもなお、決してなくなっているわけではないことを、この10回の連載記事が如実に示しています。この第4回の記事の中でも、東京の芝浦屠場で働くTさんが、次のように語っているところがあります。
「ぼくは被差別部落の出身ではないけど、部落出身と見られているでしょうね。屠場で働けば、部落出身者であろうとなかろうと、部落出身者と見られ、差別を受ける。屠場への差別の表れ方は職業差別だが、根っこにはケガレ観と部落差別があると思うんです」。
そして、このケガレ観については、「動物を殺したり処理したりすることに対し、身分制の歴史の中で、ケガレ観が人々に刷り込まれた。それが部落差別につながる。このケガレ観の刷り込みを壊したい」と、Tさんは述べています。
この偏見と差別の背景にあるのは、日本の稲作文化の土壌だと思われますが、これとは対照的なヨーロッパの肉食文化では、家畜処理や、業者に対する見方は、日本とは全く逆になります。
たとえば、イギリスのイングランド北東部の古都ヨークは、英語と英語文化発祥の地で、そこには、カンタベリー大聖堂と並ぶ英国国教会の聖地であるヨーク大聖堂があります。聖地である以上、ケガレなどが入り込む余地はありませんが、実は、その大聖堂の前の一等地で、Shamblesという名前のついた通りが家畜処理業者の店が並んでいるところなのです。Shambles
というのは、屠場の意味で、この通りの店先には、いまも軒下に、処理した家畜を吊るすために道路にせり出した鉤が多く残されています。
ヨーロッパでは、植物を育てるための熱にも水にも土にも恵まれていませんから、農業生産性はきわめて低く、生きていくためには仕方なく肉食に頼らざるを得なかった歴史があります。ですから、大聖堂前の一等地に家畜処理業者の店があるというのは、日本でいえば、大寺院の門前町に米屋さんが店を構えているのと同じようなものといえるでしょう。つまり、イギリスのみならず、ヨーロッパ各国では、家畜の解体業者というのは、むかしから、「堂々と名前を出す」だけではなく、しばしば、社会的な名誉と地位と富をも手に入れた専門職マイスターであったのです。
その肉食文化のヨーロッパのなかでも、特にイギリスでは、動物愛護の精神が強いといわれますが、それについては、「血のしたたるようなビフテキを食べているのに動物愛護を説く」と揶揄されることがあります。これも実は、「食べているのに」ではなくて、「血のしたたるようなビフテキを食べているから」動物を愛護するのだと捉えるべきでしょう。日本人が、お米を大切に育て、収穫したら神棚に供えたりして、そして、食べてしまうのと同じことなのかもしれません。
それにしても、この「差別を越えて」という連載記事を読んでいますと、あらためて、日本人の差別意識の強さを考えさせられます。部落民差別は無論、その他もろもろの人種差別とも無縁ではありません。日本人は決して単一民族ではありませんが、極東の島国で長い鎖国を通じて培われてきた単一民族的な感覚と、強固な身分制度のしがらみが、社会の底辺に押しやられた人びとや「異人種」に対する陰湿な差別感覚を助長する要因になってきたのでしょうか。
私はむかし、アメリカに留学していた時に、アメリカでの黒人差別を容認するアメリカ人の学友と差別のことで議論になったことがありました。私が、アメリカが信奉する民主主義と黒人差別は矛盾するではないかといいますと、彼は、確かにアメリカでは白は黒を差別するが、日本では、黄色が同じ黄色を差別しているではないかと、言い返されたことがありました。
他人の欠点は目についても、自分の欠点のことにはなかなか気がつきにくいのが人間で、そのことをふまえたうえで、要するに、偏見と差別は無知と同義であることを、私たちは、しっかり理解していかなければならないようです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
劇的なパウロの回心
ー生活と文化をめぐる随想(69)ー (2009.12.01)
キリスト教をローマ帝国に普及するのに最も功績が大きかったといわれるパウロは、西暦3年ごろ、シリアのタルソ(現トルコのタルスス)で、富裕なユダヤ人の家庭に生まれました。ユダヤの律法に従って、生後8日目に割礼を受け、子供の時からすべての面で厳格な律法の解釈にしたがって育てられたようです。「ピリピ人への手紙」のなかには、有名なパウロの自己紹介がありますが、そこでは「律法の上ではパリサイ人、熱心の点では教会の迫害者、律法の義については落ち度のない者」と述べているくらいですから、回心前のパウロは、律法を無視し、イエスを「神の子」と称するキリスト教徒に対しては「迫害者」にならざるをえなかったのでしょう。
その彼が、迫害の先頭に立ち、キリスト教徒を追ってダマスコへ至ったときに天からの光に打たれ、イエスの声を聞きます。そして、それを契機にパウロは、迫害者の立場から180度転換して、熱心なキリスト教徒に変わってしまいました。それからのパウロは、3回にわたって2万キロに及ぶキリスト教の大伝道旅行を行い、キプロス島、小アジア、マケドニア、ギリシアに布教して、最後には、62年頃にローマで殉教したとされています。彼は、その伝道の苦労を、「コリント人への第二の手紙」のなかで、次のように述懐していますが、これは、決して誇張したものではなかったのでしょう。
《・・・・・苦労したことはもっと多く、投獄されたことももっと多く、むち打たれたことは、はるかにおびただしく、死に面したこともしばしばあった。ユダヤ人から四〇に一つ足りないないむちを受けたことが五度、ローマ人にむちで打たれたことが三度、石で打たれたことが一度、難船したことが三度、そして、一昼夜、海の上を漂ったこともある。幾たびも旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、海上の難、にせ兄弟の難に会い、労し苦しみ、たびたび眠れぬ夜を過ごし、飢えかわき、しばしば食物がなく、寒さに凍え、裸でいたこともあった。》 (11:23-27)
前述のように、パウロはダマスコで、ゴルゴダの丘で刑死したはずのイエスから、じかに自分の名を呼ばれて、「わたしはあなたが迫害しているイエスである。なぜわたしを迫害するのか」とイエスの声を聞いていました。その疑いえない自己の体験から、このようにキリスト教の迫害者から熱心な伝道者へと大変身を遂げたわけですが、このイエスのよみがえりの事実は、当時でも、キリスト教徒のなかでさえ素直には受け止められていなかったようです。
実際、イエスの弟子たちも、イエスが十字架に架けられたときには、彼らのほとんどは、師のイエスを見捨てて逃げ隠れていました。彼らは、その時はまだユダヤ人たちが逮捕に来ることを恐れて、隠れ家の戸を固く閉ざし、不安の中で息をひそめていたのです。
よみがえったイエスは、その弟子たちの隠れ家に現れました。十字架に釘打たれた手と槍で突かれたわきの傷跡を弟子たちに示して、「安かれ、父がわたしをおつかわしになったように、わたしもまたあなたがたをつかわす」と、彼らに語りかけます。イエスの弟子たちはみんな、そのイエスの復活した姿を目の前に見て、驚き感動し、そして畏れおののいたことでしょう。
ところが、十二弟子のひとりのトマスは、たまたまそのとき、彼らと一緒にはいませんでした。ほかの弟子たちから、イエスが現われたことを聞いても、トマスは、「わたしは、その手に釘あとを見、わたしの指をその釘あとにさし入れ、また、わたしの手をそのわきにさし入れてみなければ,決して信じない」と言ったのです。(ヨハネ20:25)
しかし、その8日後、イエスはまた、隠れ家に潜んでいる弟子たちの前に姿を現わします。今度はトマスもいました。イエスはトマスに向かって、「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手をのばしてわたしのわきにさし入れてみなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい」と言います。トマスはことばも出ませんでした。「わが主よ、わが神よ」というのが精一杯であったと伝えられています。(20:27-29)
死んだ人間がよみがえるというのを信じるのは確かにむつかしいことです。敬愛する師のイエスから、何度も復活の予言を聞かされていた弟子たちでさえこのように、目の前にイエスが現われるまでは、信じようとはしませんでした。それだけに、パウロの伝導のなかでも、このイエスのよみがえりをキリスト教徒に信じさせることは、大きな課題になっていたようです。たとえば、パウロは54年ごろに書いた「コリント人への手紙」のなかで、こう書いています。
《さて、キリストは死人の中からよみがえったのだと宣べ伝えられているのに、あなたがたの中のある者が、死人の復活などはないと言っているのは、どうしたことか。もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、わたしたちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もまたむなしい。すると,わたしたちは神にそむく偽証人にさえなるわけだ。なぜなら、万一死人がよみがえらないとしたら、わたしたちは神が実際よみがえらせなかったはずのキリストを、よみがえらせたと言って、神に反するあかしを立てたことになるからである。》 (15:12-15)
パウロがこうして、切々と訴えているように、イエスは間違いなく復活しました。パウロはその生き証人の一人でした。そして、この復活の事実を目の前に見て自ら体験したからこそ、パウロだけではなく、あの弱かったイエスの弟子たちも、はじめて深い信仰に目覚め、捕らえられても、投獄され鞭打たれても、そしてやがて殉教の死を遂げるようになっても、決してイエスを信じることをやめようとはしなかったのでしょう。
イエスが処刑されたのが紀元30年で、パウロや弟子たちはそのイエスの復活を契機にして、文字通り身命を賭してイエスの教えを広めはじめました。そして、そのあと紀元64年にはもう、あの歴史に残る皇帝ネロのキリスト教徒迫害が起こっています。イエスの死後わずか34年で、イエスの教えは、遠く離れた帝国の首都ロ-マにまでひろがり、皇帝ネロの弾圧の対象となる程までに影響力のある宗教になっていたのです。これは、イエスの復活の事実がもたらした、驚くべき一大社会現象と言ってもいいかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神を知るために生まれる
ー生活と文化をめぐる随想(68)ー (2009.10.01)
講談社から1994年に刊行された、中村天風『運命を拓く』という本があります。この著者は、昭和43年に92歳で永眠していますが、30歳で肺結核を患っていた頃、エジプトのカイロで偶然出会ったヨガの大聖人に教えを受け、「悟入転生の新天地を拓いた」といわれる人です。大正8年、43歳の時に一切の社会的地位、財産を放棄して、現在の「天風会」を創始しました。皇族、大臣、事業家をはじめ、直接薫陶を受けた人は10万人を数える、とこの本では紹介されています。
中村天風氏は、この本のなかで、「神とか仏というのは、人間が便宜上付けた名前だから、このようなものに捉われてはいけない」と言って、次のように続けています。
《あなたがたは、抽象的で、あまりにも漠然としたものを、やれ、神だ、仏だ、と思っているが、では「神とはどんなものか」と聞かれたら、何と説明するか。「仏とはいかなるものか」と聞かれたら、どう説明するか。見たことも聞いたこともないものに、説明の与えられるはずはない。そう思うと、何となく安心が出来るといったような、同時に、自分が一種の信仰というようなものを、何となく気高いと感じる、という感じで考えられるだけではないだろうか。だから、私からいわせれば、やれ神だ仏だ、といっている者は、安直な気休めを人生に求めている哀れな人だといわざるをえないのだ。》 (p.30)
これは、ちょっと思い切った言い方のようにも思えますが、中村氏は、もちろん、「無神論者」なのではありません。神の捉え方を間違えてはいけないと戒めているのです。そして氏は、神に自分の生命や運命の安全ばかりを願うのは、自己本位な「第二義的信仰」であって、「そのような信仰を持っている人間は、何となく神があり、仏があるように思い、その神や仏がこの宇宙を創っているように思っているが、それは違う」(p.32)とも述べています。
それでは、神とはどういう存在で、宇宙は誰が創ったといっているのでしょうか。氏は、神とは実は「宇宙霊」ともいうべきもので、その宇宙霊が宇宙を創ったのだというのです。そして、この宇宙霊を指していうのなら、「神でも仏でもいい。が、しかし、あなた方が今まで、神や仏と呼んでいた同じ気分で、この宇宙本源を考えては駄目である」(p.34)と、氏は繰り返して嗜めています。
人間の本性も霊であって、その霊は、宇宙霊と繋がっている。だから、その宇宙を創り出した宇宙霊のエネルギーが人間の思考にも内包されていて、「人間の心で行なう思考が、人生の一切を創る」というのが、氏が数十年かかって悟り出した天風哲学の基本的法則になっているようです。そして氏は、「この法則を厳として自覚し、常に、この法則を乱さないように活きるならば、人生は、期せずして、大きな調和のもとに満たされる。そして、無限の強さと、生命の無限の自由というものが、自然的に出てくる。これが、仏教でいう“無碍自在”である」(p.39)と教えているのです。
しかし、「宇宙霊」が神だといわれても、やはり、限りある小さな存在である私たちには理解するのが容易ではありません。シルバー・バーチも、「神とは宇宙の法則です。物的世界と霊的世界との区別なく、全生命の背後に存在する創造的エネルギーです。完全なる愛であり完全なる叡智です」(『霊訓 12』 p.108)というような言い方を何度も繰り返していますが、同時に、「神の概念を完全にお伝えすることは不可能です。神は無限です。一方、言語や概念、心象といったものはどうしても限界があります。小なるものが大なるものを包み込むことはできません」(『霊訓 9』 p.129)とも述べてきました。これは、ある日の交霊会で、「神とは何でしょうか」という質問に答えたシルバー・バーチのことばの一部ですが、その時には、さらに続けて、「しかし、宇宙をご覧になれば、ある程度まで神についての概念をつかむことができます」とつけ加えています。
地球上の生命は、太古の昔、海から生まれましたが、その海の母体である地球は、宇宙から生まれました。だから、私たちは「海の子」であり、「星の子」でもあります。私たちは、その海と星の痕跡を、現に、自分の体の成分として持ち続けています。大海原を眺めるとこころが安らぐのも、天に輝く星を見れば、懐かしさのようなものを感じさせられるのも、海や宇宙の星が、かつての自分のふるさとであったことを、奥深いところで私たちの魂が記憶しているからではないでしょうか。そして、シルバー・バーチは、ここでは、その「星の子」が、実は、宇宙創造の巨大エネルギーをもつ神の子であることにも気がつくことを、私たちに促しているのかもしれません。そのシルバー・バーチは、別のところでは、こうも言っています。
《イエスは「神の御国はあなた方の中にある」(ルカ17:21)と言いました。実に偉大なる真実です。神はどこか遠く離れた近づき難いところにおられるのではありません。実にあなた方一人ひとりの中にあり、同時にあなた方は神の中に居るのです。ということは自分の霊的成長と発達にとって必要な手段は全て自分の中に宿しているということです。それを引き出して使用することが、この世に生まれてきたそもそもの目的なのです。》 (『霊訓 1』 p.191)
先に挙げた中村天風氏の「人間の心で行なう思考が、人生の一切を創る」というのも、思考のエネルギーが巨大な宇宙霊のエネルギーにつながっているためで、このシルバー・バーチのことばと軌を一にするものといえるでしょう。こういうふうにみてきますと、人間として生きていくうえで、自分を知り、神を知ることがいかに大切であるかが、少しはわかってくるような気がします。
むかし、文部大臣賞の『カキツバタ群落』など多くのすぐれた作品を書いた作家の田中澄江さんが、「神を知るために」と題する文のなかで、次のように書いていました。
《自分は、どこから来て、どこへゆくのか。自分は何をしに、この世に生まれて来たのか。物ごころついて以来、心に持ったはずの問いかけを、まだ、私は持ちつづけ、まだ、問いつづけている・・・・・
二十三歳のとき、芝白金三光町の聖心女子学院の教師となり、マザー・ラムという英国人から公教要理の講義を受けた。開口一番、ひとは何のために生まれましたか。神を知るためですねと言われたとき、大粒の涙が机の上にぼたぼた落ちて、そうだ、本当にそうだ、神を知るために生まれたのだと、全身で叫びたい思いになった。以来半世紀を経て、いまだにその感激が胸の底に燃えているような気がする。》 (「朝日新聞」1991.3.11)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
親鸞の「生まれ変わり」と「極楽浄土」
ー生活と文化をめぐる随想(67)ー (2009.08.01)
ご存知の方も多いことと思いますが、『歎異抄』の第5条に次のようなことばがあります。
「親鸞は、父母の孝養のためとて、一返にても念仏まふしたることいまださふらはず。そのゆえは、一切の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり。いづれもいづれもこの順次生に仏になりてたすけさふらうべきなり。」
親鸞は、亡くなった父母の供養のためには一度も念仏をとなえたことはない、と言っているわけですから、はじめてこれを読んだときには、このことばは、私の胸に実に新鮮に響きました。そして、親鸞は、そのわけは、長い前世においては、すべての生きとし生けるものは、いつかの生においては自分の父母であり兄弟であった。だから、私たちが死んで極楽浄土へ行ったときには、仏になって、今生の自分の父母や兄弟ばかりではなく、すべての生きとし生けるものを助けなければならないのだ、と述べています。
人間は永遠に、輪廻転生を繰り返していきますから、そのことを前提とすれば、どうしても、「一切の有情はみなもて世々生々の父母兄弟なり」ということになります。親鸞の著作には、このほかにも、聖徳太子をはじめ、いろいろな高僧、聖賢の生まれ変わりについて少なからず触れているところがあります。それだけ親鸞は、生まれ変わりの真理を深く洞察していたのでしょう。
釈迦の教えである仏教では、すべての生きものは、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間、天の六つの世界に生まれ変わり死に変わりして流転を続けることになっています。しかし、この永劫の流転は、一般に、ネガティヴな面で受け留められているのではないでしょうか。むしろこの六つの世界、すなわち六道の永劫の輪廻から抜け出て、輪廻の外に出ることが悟りの道であり、涅槃の境地であると教えているのが仏教です。親鸞の場合は、これとは少し違って、生まれ変わりを、いわばポジティヴに理解し、その意味を深く追求していったといえるかもしれません。それが、「いづれもいづれもこの順次生に仏になりてたすけさふらうべきなり」ということばに繋がっていくのです。
この「仏になりて」というのは、親鸞の場合、「他力によって」と言い換えられるように思われます。「他力」と「自力」の違いは、親鸞の思想の根幹の一つですが、「自力」によっては、人を救うことはできないと言っているのでしょう。たとえば、いまわが子が目の前の池に落ちて溺れようとしているとします。母親は、必死になって溺れている子を救おうとしますが、悲しいかな、母親には両腕がありません。両腕がないから手を差し伸べてわが子を救うことができないのです。この両腕のない母親の「救い」が自力です。だから、「他力によって」つまり、仏になって、人を救うことができるのだ、と親鸞は教えているのではないでしょうか。
この『歎異抄』第5条の後半は、次のように続きます。
「わがちからにてはげむ善にてもさふらはばこそ、念仏を廻向して父母をもたすけさふらはめ。ただ自力をすてて、いそぎさとりをひらきなば、六道・四生のあいだ、いづれの業苦にしづめりとも、神通方便をもて、まづ有縁を度すべきなりと云々。」
念仏が一生懸命自分が努力して積み上げる善行であるのなら、その念仏の功徳で父母を助けることもできるでしょう。しかし、念仏はそのような自力の行ではないので、それでは、本当に救うことはできない、と親鸞は述べています。だから親鸞は、自力を捨てて急いで極楽浄土へ行き、悟りを開いた仏になりたい。そうすれば、「他力」によって、つまり仏の力で、父母や兄弟たちが、前世からの因縁でどのような苦しみに沈んでいても、父母兄弟など、まず自分にもっとも縁の深い人々から救い出すことができるのだと、言っているのです。
一般には、私たちが父母のために念仏を唱えるというのは、いま生きている私たちが、あの世にいる父母の幸せを願っての善行ですが、親鸞が、一度も唱えたことはないといっているのは、そういう意味での念仏ということになります。そしてさらに、仏になって「神通方便をもつ」極楽浄土の意味にも、親鸞は、師の法然の教えを超えた独自の深い思いを込めていました。
親鸞においては、他力と自力との相違が、極楽浄土にも一種の格差をもたらしているのです。親鸞は、ひたすらに他力を信じて念仏の行に励む人はいわば真の浄土である「真仏浄土」へ極楽往生できるとする一方で、自力信仰、あるいは、他力信仰に自力信仰を交える人はいわば仮の浄土「化身浄土」へ往生すると説きました。そして、化身浄土から真仏浄土へ移行するには通常、500年の歳月が必要だともいっています。この『歎異抄』第5条で、親鸞が、父母を救い、衆生を救うために極楽浄土で仏にならなければならないといっているその極楽浄土も、ほかならぬ、この真仏浄土を意味していることも私たちは理解しておく必要があるようです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
イギリスのカンタベリー大聖堂
ー生活と文化をめぐる随想(66)ー (2009.06.01)
1.jpg)
カンタベリー大聖堂からハイ・ストリートへ出て
ウエストゲイとへ向かう途中の小川の風景
(筆者撮影)
昔のイングランドがキリスト教に初めて接したのは、597年になってからのことである。その起点がカンタベリーであった。それまでのイングランドは、当時のローマからみると文化果つる北辺の野蛮国であったから、その野蛮国の蛮人たちに神の教えを説くということは、命がけの冒険と考えられていた。その布教のきっかけを作ったのは、当時のローマ教皇GregoriusⅠ(グレゴリウス一世)である。
六世紀の初め、まだ教皇になる前のグレゴリウスが、ローマ市内のとある市場を通りかかった時、金髪の美しい少年たちが奴隷として売られているのを目にした。Britain(ブリティン)という島から連れて来られた異教徒であると聞かされた彼は、「こんなに美しい顔つきをしているのに野蛮人であるとは、哀れである」と嘆いたと伝えられている。
いかに金髪で美しい少年たちであっても、キリスト教徒でなければ野蛮人であり、奴隷にされても仕方がないというのが、ローマ人の考え方であった。この考え方は、のちに広くヨーロッパ全域にキリスト教が浸透するようになってからも受けつがれた。かつての「野蛮人」であったヨーロッパ人がキリスト教化すると、今度は、自分たち以外の異教徒に対してこの考え方を持ち続けたのである。
イスラム教徒に対して繰り返された十字軍の、想像を絶する殺戮残虐行為や、1492年以来40年間だけでも、1,500万人以上の南米原住民を殺害したといわれるコロンブスやマゼランとその一味・後継者たちの非道もまた、異教徒は野蛮人で、家畜に等しいものと割り切っていたキリスト教徒たちの仕業であった。
もちろんこれらは、イエス・キリストの真の教えを理解しない誤まった一部の「キリスト教徒」の所業であるには違いないのだが、このような考え方の痕跡や傾向は、いまもおそらく、欧米人の中には根強く残されているといってよいであろう。それだけに私は、イギリスやアメリカなどで「あなたの宗教はなにか」と聞かれて、「無宗教である」と無邪気に答えることの多い日本人には、内心、はらはらさせられることがしばしばである。
話をまた、六世紀初めのローマに戻そう。
グレゴリウスは、それらの野蛮人の美しい少年たちは「どこの国の者か」とさらに尋ねた。すると「あの少年たちはAngles(アングル人)と呼ばれています」という答えが返ってきた。「よろしい、それなら彼ら“angle”を
“engla”に変えよう」とグレゴリウスは言った。“engla”は英語ではangelで、天使である。つまりキリスト教徒にするというわけである。そこでいよいよ、イングランドへの布教が始まることになった。
グレゴリウス一世は自分で布教団を率いてイングランドへ乗り込むつもりであったらしいが、それは果たせなかった。なにしろ、当時のイギリスというのは、地の果ての蛮地であった。「獰猛な野蛮人」を教化するなどということは文字通り命がけだと考えられていたから、周囲の反対が強かったのかもしれない。結局、彼の下にいたAugustinus(アウグスティヌス)が
50人の修道僧を率いてイングランドへ向かった。そしてたどり着いたのが、ケント王国のカンタベリーなのである。
着いてみると予想に反して、ケント国王Aethelbert(エセルバート)は、この布教団に非常に友好的であった。国王は、真剣に教えを説くアウグスティヌスに対して、国民とともに奉じてきたそれまでの信仰をキリスト教に変えるつもりはないが、キリスト教の布教には反対しない、と告げたのである。そればかりではない。彼はアウグスティヌスのために、カンタベリーの屋敷まで与えた。これがSt.
Augustine’s Abbey(聖アウグスティヌス修道院)の始まりとなった。やがて、アウグスティヌスは、ケント国王をもキリスト教に改宗させることに成功し、それによって、寺院が建てられた。これがCanterbury
Cathedral(カンタベリー大聖堂) の始まりである。
現在では、この修道院のほうはなかば廃墟と化しているが、大聖堂はカンタベリーの重要な観光名所となっている。大聖堂への正面の入口、Christ
Church Gate(クライスト・チャーチ門)から東に向かって数分歩くと、やがてカンタベリーを囲む城壁が見えてくる。その城壁を通って、さらに少し歩き続けると、修道院の大きな門がある。その中が修道院の跡である。
アウグスティヌスの布教以来、キリスト教は徐々に、しかし確実に浸透してゆき、英語の発展に大きな影響を与えたのみならず、高度の文化をもたらす結果になった。こうして八世紀の終わり頃には、かつての「野蛮国」は、ヨーロッパでももっとも進んだ文化国家へと変貌を遂げていったのである。そして、常にその中心にあったのが、カンタベリー大聖堂であり、それは六〇一年にアウグスティヌスを初代大司教として迎えて以来、イギリスにおけるキリスト教の総本山であり続けた。1529年から36年にかけてのChurch
of England(英国国教会)成立後から現在に至るまでも、その状況は変わってはいない。
カンタベリー寺院の創建時の建物は、二度にわたる火災にあって、消滅してしまった。現在の壮大なゴシック調の大聖堂は、1070年に着工されたが、途中200年間中断して、1503年に完成したものである。
中に入ると、カンタベリー大司教であったSaint Thomas Becket(聖トーマス・ベケット)が1170年に暗殺された場所、というのが残されている。カンタベリーの強大な権力と影響力を恐れたヘンリー二世は、大司教トーマス・ベケットの力に制約を加えようとして彼と対立していた。そのヘンリー二世のふとした軽率な発言で、はやまった四人の騎士が、寺院に押し入って大司教を暗殺してしまったのである。世論は沸騰してヘンリー二世の非を咎めた。
その世論を鎮めるために、ヘンリー二世は仕方なくベケットの墓へ謝りに行ったのだが、そのために、いっそう、カンタベリー寺院の権威が高まってしまった。カンタベリーを訪れる巡礼者の数も一挙に増えたという。チョーサーの『カンタベリー物語』は、そのようなカンタベリー寺院への巡礼者たちが語る諸国物語である。
大聖堂への入口になっているクライスト・チャーチ門も、中世の歴史の重みを感じさせる壮麗な門であるが、そこから中心街のハイ・ストリートへ出て、もうひとつの、イギリスではもっとも立派な門といわれるWest
Gate(ウエスト・ゲイト)までの間が、観光客でいつも賑わう繁華街である。途中に小さな川があって石の橋がかかっている。私はここまで来ると、決まってしばらくは立ち止まった。ここから眺める川の水面は、周囲の中世そのままの家々の佇まいを映しながら静かに流れて、異邦人にとっても忘れ難い風情である。
武本昌三『イギリス比較文化の旅』(鷹書房弓プレス、1998)pp.63-67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メーテルリンクの『青い鳥』
ー生活と文化をめぐる随想(65)ー (2009.04.01)
メーテルリンクの『青い鳥』は、貧しい木こりの子どものチルチルとミチルが、幸福の象徴である「青い鳥」を求めて冒険の旅に出る物語です。「思い出の国」では、すでに亡くなっている祖父母と再会し、「未来の国」では、これから地球に生まれてくる弟とも出会います。作者のメーテルリンクはベルギー生まれで、法律を学んだ後、文学を志した詩人・劇作家ですが、クリスマスのための童話を頼まれて、1906年にこの戯曲を書きました。1910年には、ノーベル文学賞も受賞しています。
このメーテルリンクの『青い鳥』が、私のホームページ「学びの栞」(B)36-fで取り上げているコナン・ドイルの『人類へのスーパーメッセージ』(講談社、1994年)にも出てきます。この「スーパーメッセージ」は、コナン・ドイルが自分の死後、霊界から送ってきた通信の一部を紹介したものですが、そのなかで、『青い鳥』について、次のように触れているところがあります。
《こちらの世界から、著名な作家のインスピレーションがどこから来ているのかを見ていると、じつに興味深いものがあります。メーテルリンクの『青い鳥』を思い出します。その本の中に、子供たちが地球に戻るべく名前を呼ばれるのを待ちながら、みんなが集まっている場面があります。
それぞれの子供は袋を持っていて、その袋には、地球に持ってかえる贈物や知識だけでなく、自分が患うことになる百日咳や狸紅熱といった病気も、きちんと包まれて入っています。子供たちは、星の海を
“父なる時”の船に乗って渡り、地球で待っている母親のところに帰ろうとしているのです。》
(pp.264-265)
これは、いうまでもなく、人間がこの世に誕生するのは、時を選び、親を選んで、地上で体験すべきこともすべて了解し納得したうえであることを示しています。しかし、通常はこういう霊的真理は容易には理解されることがありません。そのことをよく知っているコナン・ドイルは、ですから、このような話を、「ただのおとぎ話だと言う人もいるでしょう。しかし、ここには、大変な真実が述べられているのです。それはおそらく、宇宙存在から降りてきたか、作者の自我の前意識のレベルから出てきたものでありましょう」と、つけ加えているのです。この地上で、人間があらわす偉大な業績は、しばしば、霊界からの導きによるものであることがシルバー・バーチの霊訓などによっても示唆されていますが、メーテルリンクが、このような作品を書くことができたのも、決して例外ではないことを、コナン・ドイルも伝えたかったのでしょう。
コナン・ドイルが例にあげているこの場面は、『青い鳥』の第5幕第10場「未来の国」にあります。改めてここで検証するために、その該当部分を岩波少年文庫『青い鳥』(末松氷海子訳、2004年)から再現してみましょう。未来の国へ行ったチルチルとミチルが、その翌年、チルチルとミチルの弟として生まれてくることになっている「一人の子」に会う場面から、ト書きを省略して、会話の部分だけを引用してみます。未来の国のその子は、広間の奥から走ってきて、まわりに沢山いる子どもたちを掻き分け、チルチルの前に出て、挨拶をするのです。
一人の子 チルチル、こんにちは!
チルチル あれっ! どうしてぼくの名前、知ってるの?
その子 こんにちは! 元気かい? ねえ、ぼくにキスして! ミチルもね。ぼくがきみたちの名前を知ってたってふしぎじゃないよ。だって、ぼく、きみたちの弟になるんだもん。たったいま、きみたちが来てるって聞いたから・・・・・ぼく、広間のずっと奥にいて、夢中になって考えてるところだった。ぼくはもう準備ができてるって、母さんに言ってね。
チルチル なんだって? ぼくたちのところへくるつもりかい?
その子 そうだよ。来年の復活祭直前の日曜日にね。ぼくが小さいうちは、あんまりいじめないでね。今から二人にキスできて、とってもうれしいよ。父さんに、こわれたゆりかご直しておいて、って言ってよ。ぼくたちのうちっていいとこ?
チルチル まあ、悪くはないな。母さんはとってもいい人だし・・・・・
その子 どんなもの食べるの?
チルチル その日によってちがうよ。お菓子を食べる日もあるんだ。そうだよね、ミチル?
ミチル お正月と、それから七月十四日の革命記念日ね。母さんが作ってくれるの。
チルチル その袋の中になにが入ってるの? ぼくたちに、なんか持ってきてくれるの?
その子 三つの病気を持っていくんだ。しようこう熱と、百目ぜきと、はしかと・・・・・
チルチル えーっ! 三つも! じゃ、そのあとはなにするの?
その子 そのあと? 死んでしまうのさ。
チルチル それじゃ、生まれたって、なんにもならないじゃないか。
その子 そう決まってるんだもの。しかたないよ。
この最後の部分の会話には考え込まされてしまいます。「その子」は、チルチルとミチルの弟として生まれ、猩紅熱、百日咳、はしかを病んで、そして死んでいくことをも「選んで」、地上に生まれてくるわけです。地上では、これは大変不幸な生涯ということになりますが、霊界では、永遠の生命は自明ですから、当然のことながら、その「不幸」の捉え方も同じではないはずです。幼くしてこの世を去っても、それは、霊性の向上のために必要な体験で、学ぶべき課題がそれぞれに与えられている、という大切な意味をもつことになるのでしょう。そしてそれが、決して、単なるおとぎ話ではなくて、「大変な真実」であることを、霊界に行ったコナン・ドイルが再確認してくれている、といってもいいのかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日本人の宗教感情と葬式について
ー生活と文化をめぐる随想(64)ー (2009.02.01)
日本には、正月に初詣をしてその年の幸せを祈るという慣習があります。神社やお寺にお参りすると、誰でも、なんとなく心が清められ、落ち着くような気持ちになるようです。東京の明治神宮などでは初詣の参詣者は今年も300万人を超えましたし、成田の新勝寺、浅草の浅草寺などへも、毎年正月には二百数十万人が訪れていることがよく知られています。これは、日本人が古来持ち続けてきた宗教心とおそらく無関係ではないでしょう。
日本人は一般に無宗教ではないかと思われることも多いのですが、実は、宗教感情は非常に強いという、調査結果が発表されたことがありました(『日本人の心をはかる』 朝日新聞社、1988年)。この調査では、たとえば、「宗教を信じますか」との問いに「はい」と答えたのは、30パーセント前後でしたが、これに、「宗教的な心は大切ですか」と聞かれて「はい」と答えた人を加えますと、その割合は全体の80パーセントにもなったといいます。
これは、少し古い調査ですが、この宗教的感情は、日本人が日本に生まれ、日本文化の雰囲気のなかで育っていくうちに、いつの間にか身についていったものでしょう。21世紀に入った現在でも、このような神社、仏閣への初詣が廃ることなく続いているのを見ていますと、宗教感情の強さは、昔も今も、少しも変わってはいないのかもしれません。
ところで、いまではあまり使われることはありませんが、村八分(むらはちぶ)ということばがあります。江戸時代から、日本の村落のなかで、村の掟や秩序を破った者に対する制裁行為を示したことばで、村八分にされたら、村の生活における十の共同作業のうち、葬式と火事の場合の二分を除いては、人びとから絶交されることを意味していました。他の八分とは、成人式、結婚式、出産、病気、家の新改築、水害、法要、旅行で、これらのことには、村人からの助力や付き合いは、一切断られることになります。
入会地などの共同所有地も使えないことになっていましたから、村八分にあえば、事実上、その村で生活していくことはできなくなってしまいますが、それでも、葬式と火事の二つの場合だけは、助け合うというのは、日本人の憎しみに徹することのない心情を表したものとして興味深く感じられます。火事は当然のこととして、葬式は、「死ねば仏」で、恩讐を超えて、すべての人びとが参列しなければならないと考えていたのでしょう。「冠婚葬祭」といわれるなかでも、葬式は特別の意味を持っていたようです。
一般的にも、葬式というのは社会通念としても、なによりも厳粛に受け留められてきた大切な慣習で、「義理を欠く」ことのないように、たとえ忙しい日程をやりくりしても、葬式には出席するものだ、とひろく社会的に考えられてきたように思われます。これも、日本人の「強い宗教的感情」の一つのあらわれといえるのかもしれません。
しかし、このような「強い宗教的感情」があるにもかかわらず、近頃では、金銭主義がはびこっているからでしょうか、葬式については、「お金のかかる事はしません。全て節約です。私も葬式はして欲しくない派です。父も必要無いと言っているので火葬のみで戒名もいりません」というような人も出てくるようになりました。
これは、インターネットに載った葬式に関する問答の一部ですが、このような葬式無用論に対して、「葬式は、残った家族の気持ちの問題でしょう。葬儀をせず、お経を唱えていただかないで、気持ちとして良いのかを聞きたいですね。お金の問題でなく、しないのであれば、まわりからみれば、少し変わった冷たい家族だという見方は避けられないでしょう」という、葬儀賛成派の反対意見なども載せられています。
おそらく、この場合、大切なことは、葬儀をするほうの視点だけではなくて、葬儀をされる側からの視点でも考えてみることでしょう。世の中には、人は死ねば灰になって、無に帰するだけだと思っている人も少なくはないようです。確かに「死んだ人」は肉体からは離れますが、しかし、実は、人間は死んでも霊体として生き続けていることを知らねばなりません。葬儀の様子は、すべて、「死んだ人」にもつぶさに見られている、のです。
そのことについて、私には思い出される一つのエピソードがあります。私の知人で、映画会社のディレクターをしているTさんから直接聞いた話です。
Tさんは、すぐれた霊能者で、死がどういうことかよく知っていましたから、お母さんが病気で亡くなったときも、特に悲しい思いはしなかった、と言っていました。葬儀の式場では、Tさんは、お母さんの霊体の姿を見ることもできました。長い病気の苦しみから解放されて晴れ晴れした美しい顔つきだったそうです。Tさんが、「お母さん、綺麗だね」と語りかけると、「まあ、そんなことを言って」と、お母さんは照れたように微笑んでいたそうです。
Tさんのお母さんは、自分の葬式に集まってくれた家族や大勢の参列者を見ながら、おそらく、顔見知りの一人ひとりに感謝していたことでしょう。Tさんとも会話できたことで、こころから満足し、幸せを感じていたかもしれません。
これは一例に過ぎませんが、Tさんのお母さんだけではなく、人は誰でも、死んでも生き続けていて、いのちは永遠です。本来、人間とは、霊を伴った肉体ではなく、肉体を伴った霊である。遠い昔から、日本人に宗教的感情が強く受け継がれてきたのも、実は、この霊的真理がこころの奥深くに潜在意識として残っているからではないでしょうか。それが理解できれば、或いは、葬式に対する考え方や心構えも、金銭主義に流されることなく、おのずから正されていくのではないかと思えてなりません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バブル期のアメリカ 三つの断章
ー生活と文化をめぐる随想(63)ー (2008.12.01)
・・・・・この家は、五年前に新築されたとき、十九万ドルで買ったのだそうである。しかし、いまでは少なくとも四割くらいは値上がりしているとミチヨさんは言う。私は、アメリカの物価の動向には関心を持ち続けていたので、このような不動産の値動きも興味深かった。
たとえば、ニューヨークでもマンションの平均価格は過去一年間だけでも二割ほど値上がりし、地方のデンバーなどでも、五年前に二十一万ドル(約二千三百万円)だった住宅が今では三十六万ドル(約四千万円)にもなっているそうである。日本もバブルがはじけるまでは、土地も家も毎年のように値上がりしていたが、いまアメリカは、ちょうどそのバブル経済の絶頂期にある。
ごく大まかにいって、日本ではバブルがはじけて以来、株価は半分に下がったが、アメリカはその間に逆に三倍以上に上がった。一九九一年頃、平均株価が三千ドル台であったのが、九五年には五千ドル台になり、それからも上昇を続けて今年はついに一万ドルを突破し、なおも値上がりを続けている。アメリカはいま空前の株式ブームで、この株価上昇分が消費を押し上げ、大邸宅、高級ヨット、宝石類が高所得者層の間で人気を集めているらしい。
自動車の売上も過去最高の勢いで伸びて、年間千六百万台を軽く越える勢いである。日本の場合は、一九八九年以降、ほぼ五百万台で推移していた販売台数は昨年当たりから急に落ち込むようになり、今年は四百万台を下回りそうになっているのとは対照的である。
私がミチヨさんの家を訪れた日、ミチヨさん夫妻は、中田さんと私をダナポイントという太平洋岸の小さな港町へ連れて行ってくれた。南西へサンクレメンテ寄りに車で三十分ほどの美しい保養地である。一緒に食事をし、海岸を散歩したり高台から港の景色を一望したりして楽しいひとときであった。
高台から見ると、ここでもヨット・ハーバーには移しい数のヨットが係留されているのがよくわかる。数人乗りのものから、外洋航海用の大型ヨットに至るまで、大きさも形も様々で、それぞれに美しく華やかである。太平洋岸を走っていて、あちらこちらの港町で目に付くこのような夥しいヨットの群は、否応なしにいまのアメリカの好景気を感じさせる。しかし、この史上空前といわれる好景気は、受益者がきわめて偏っているという意味で、いわば、富裕層だけの歪んだ好景気であるといえなくもない。
たとえば、この好況でアメリカのトップ経営者の平均年収は、九〇年の約百八十万ドル(約二億円)から九八年の約千六十万ドル(約十一億八千萬円)にまでなったそうである。一方、製造業の従業員の年収は、この間、約二万三千ドル(約二百五十万円)から約二万九千ドル(約三百二十五万円)へ二十八パーセントしか増えなかった。トップと従業員の収入格差は九〇年の七十八倍が、いまでは三百六十二倍にまで広がっているのである。もともと大きな貧富の格差を、さらに一層大きく広げたのが、いまのアメリカのバブルの特徴であるといえよう。(「朝日」’99・9・1)
バブルは、しかし、必ず崩壊する。日本人の多くはそれを経験したことで実感しているが、いまのアメリカ人にはまだ、その実感がない。いままで株高が予想外に長く続いたことで、多くの人々が、繁栄やブームがこれからもまだ続きそうな幻想を抱いているが、ブームのあとには破綻が来るのが資本主義の宿命なのである。アメリカのバブルが例外であるはずはない。
いまでこそ、アメリカの消費者は財布のひもを緩めて過剰なほどお金を使っているが、一旦バブルがはじければ、浮かれた気分は一気に沈み込み、浪費癖を直してもとの堅実な消費生活に戻らざるを得なくなる。しかし、それが、本来のアメリカなのである。
武本昌三『アメリカ 光と影の旅』(文芸社、2001年)pp.281-283
*****
・・・・・サンディエゴに着いたのは昼過ぎである。サンディエゴは、今では人口百二十万を超えて、カリフォルニアではロサンゼルスに次ぐ第二の大都会である。メキシコまでわずか二十五キロメートルという地理的条件や、スペイン統治時代の歴史的背景もあって、南カリフォルニアの中でも独特のエキゾチックな雰囲気を漂わせている。ダウンタウンから西北へ五キロメートルほど離れたOld
Townには、一七六九年にスペイン人によって建てられた最初の教会がいまも残っている。これがいわば、サンディエゴ発祥の地である。
産業としては、観光のほか、航空工学、電気、造船、漁業などがあり、最近ではハイテク企業の進出も盛んなようである。しかし、もともとサンディエゴの発展を支えてきたのは、アメリカ太平洋艦隊の主要基地としての役割であった。サンディエゴ港の南のコロナード半島沿いに走っていると、バスの窓からもこの海軍基地にさまざまな艦船が停泊しており、あの一九九一年一月から二月にかけての湾岸戦争にも出動したという航空母艦などの姿も見ることができる。コロナ橋からの展望では、広大なノース・アイランド海軍飛行場を背景に、これらの艦船群は一大スペクタクルといえないこともない。米ソの冷戦構造が崩れてきた現在でも、これらの数多くの艦船群は、この巨大な海軍基地の中で、米軍の威信をかけてその存在価値を誇示しているように見える。
いままでアメリカは、世界を睥睨しながら、ことあるごとに星条旗をなびかせて、遠く外国にまで武力行使をほしいままにしてきた。しかし、このようなアメリカ政府や軍部のあり方は、もう、アメリカ以外の国々では受け容れられなくなってきているのではないか。肝心のアメリカ国内でも、「アメリカは世界の警察官ではない」という考え方がだんだん強くなってきている。政府が、世界の平和維持のためにという大義名分を強調しても、アメリカの世論は、特にベトナム戦争での敗北以来、海外での武力行使に強くブレーキをかけはじめるようになってきた。しかし、そのアメリカの危険な側面の一つは、軍と軍事産業との複合体が、国民の見えにくいところで、いまなお強大な影響力を温存しているということである。
かつてアイゼンハウアーは、一九六一年に大統領としての職を去るとき、「大規模な軍事組織と巨大な軍需産業との結合」の肥大化に対して、異例の警告を発していた。一九四〇年代の核兵器、五〇年代の大陸間弾道弾(ICBM)、六〇年代の月着陸、八〇年代の戦略ミサイル防衛(SDI)などで、「軍産複合体」は確実に勢力をのばしてきたのである。その「軍産複合体」は、ここへきて、冷戦の終結とともに大規模な国家プロジェクトの先細りに直面することになった。いま、その彼らが必死にしがみつこうとしているのが、米本土ミサイル防衛(NMD)や戦域ミサイル防衛(TMD)などのミサイル防衛計画である。
この時代錯誤的なアメリカの防衛計画に対しては、彼らの言う「ならず者」国家からのミサイルを空中で撃ち落とすという武器が本当に必要なのか、むしろ、ロシアや中国などとの軍拡競争をあおり、冷戦時代に逆戻りするのではないか、と危倶する声も内外であがりはじめている。
多分こう言っても的外れではないと思うが、「軍産複合体」という巨大勢力は、「唯我独尊」的に、常に自らの利益のためだけに動く存在である。彼らがいかにアメリカの正義や世界の秩序を声高に叫んでも、アメリカ庶民の願いとは裏腹に、内心ではおそらく、戦争や紛争のない平和な世界は望まない。真に平和な世界とは、彼らの巨利を貪る既得権を侵し、彼ら自らの存在基盤を危うくするものにほかならないからである。
そのような目でみていると、この巨大なサンディエゴの海軍基地も、なにやら、疎ましいものに思われてくる。本来、無用の長物であるはずのものがこのように幅を利かせている社会というのは、これも健全とはいえないのかもしれない。
武本昌三、前掲書、pp.300-302
*****
・・・・・一九五七年の夏、カリフォルニア大学バークレイ本校のインターナショナル・ハウスにいた私は、首都サクラメントで開かれたState
Fair(州博覧会)を見に行ったことがある。大学が世界各国から来ている留学生のためにバスを仕立てて招待してくれたのである。その時にバスの中で、一人一人に”sack
lunch” なるものが渡された。紙袋に入れられた昼食の弁当である。
プラスチックのケースに入ったサンドイッチに、紙容器の牛乳、オレンジ・ジュース、ヨーグルト、それにリンゴなどの果物が入れてあり、プラスチックのナイフとフォークまで添えられている。食べてしまえば、洗うことも必要ではなく、全部紙袋のまま捨ててしまえばよい。サクラメントの広大な博覧会場のあちらこちらのレストランでの食事も、ほとんどが紙皿、紙ナプキンを含めて使い捨て方式で、効率はよく人件費もかからない。私はその時、いま思えば浅はかであったが、さすがアメリカだ、なんと便利なことかと、感心したことを覚えている。
貧しい当時の日本では、紙容器に入った牛乳やジュースなどというものは、まだなかった。駅弁の折箱や割り箸を捨てることはあったが、まだ使い捨て文化が浸透していたわけではない。いまでこそ日本も、アメリカ並みに、あるいはそれ以上に、使い捨てが当たり前のようになってしまったが、考えてみるとこれは罪深い行為である。
人間というのは、豊かになるとどうしても自己中心的で奢りがちになるようである。弱い者に対する思いやりのこころを失ない、カネさえ出せばすべてが解決できると考えて、地球の資源を収奪していることにまでは思いが及ばない。「私たちの地球を救いましょう!」のステッカーが必要なのは、いまではアメリカだけではないであろう。
むしろアメリカは、エネルギーの大量消費と使い捨て経済路線の先頭を突っ走ってきただけに、その及ぼす環境破壊の影響の深刻さにいち早く直面させられることになった。今はアメリカ中の広範囲の人たちが、従来とは違った価値観で新しい生き方を模索するようになってきているといえる。それを促したのが、たとえば、第五章でも触れたレーチェル・カーソンの『沈黙の春』であった。
最近では、シーア・コルボーン博士が『奪われし未来』で、環境の中にある化学物質、いわゆる環境ホルモンが内分泌を乱し、人間の成長や生殖にも異常をもたらすという警鐘を鳴らし続けている。この本は、三十六のアメリカの大学で教科書に使われ、世界の十八もの言語に翻訳されてきた。
博士によれば、商業目的で作られた化学物質は八万七千種類もあるそうである。そのうちよく使われているのが一万五千種類で、人体には五百種類が蓄積されているという。これらのいずれもが、二十世紀の初めには人間の体内にはなかった。人類はいま、かつてない化学物質の汚染の脅威にさらされているのである。私たちはいったいどうすればよいのだろうか。博士は、一人一人の市民のできることとして、「大量消費をやめ、本当に必要なものだけを買う。殺虫剤は使わずに、農作物も有機栽培のものだけを買うようにしよう」と社会にひろくよびかけているらしい。(「朝日」’00・8・4)
それも、もちろんいいことである。特に、使い捨てをやめ大量消費を抑えるということは、地球の上で生かせてもらっている人間が等しく守るべき義務であるといってよいだろう。アメリカ人も、いまはそのことに気づきはじめているのである。しかし問題は、いまのアメリカ経済の継続的繁栄が、ほかならぬこの大量消費によって支えられてきたということである。資本主義市場経済の発展と大量消費の抑制とは、もともと二律背反的で相容れない。アメリカ人の一人一人が、真剣に「大量消費をやめ、必要なものだけを買う」生活を実行しはじめたら、それだけでも、いまのバブルは、忽ちにして崩壊する。
武本昌三、前掲書、pp. 304-307
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
乙女たちの殉職と引揚げ船の遭難
ー生活と文化をめぐる随想(62)ー (2008.10.01)

留萌市の近く小平町鬼鹿海岸に建てられた
「三船遭難慰霊之碑」(2008.08.30 筆者撮影)
去る8月25日に、日本テレビが、「樺太・真岡郵便局に散った九人の乙女たち」というタイトルのドラマを放映しました。これは、1945年8月20日、当時はまだ、日本領であった樺太南西部の真岡(現在のホルムスク)に、ソ連軍が艦砲射撃を加えて侵攻してきた際、真岡郵便局の電話交換手12名のうち、9名が自決した事件を扱ったドラマです。北海道・稚内市の稚内公園のなかには、「九人の乙女の碑」が建てられていて、「皆さん、これが最後です。さようなら、さようなら」という、交換手たちが自決の前に残した最後のことばが表面に大きく刻み込まれています。
その裏面には碑文があって、そこには、「・・・・その中で交換台に向かった九人の乙女らは、死を以って己の職場を守った。・・・・・静かに青酸カリをのみ、夢多き若き尊き花の命を絶ち職に殉じた・・・・・」と、その最後の様子が記されていました。しかし、『昭和史の天皇』(読売新聞社、1980年、363頁)によれば、これは、書き換えられたもので、もとの碑文では、自殺は日本軍の命令であることになっていたようです。つぎのようにです。
《昭和二十年八月二十日、日本軍の厳命を受けた真岡郵便局に勤務する九人の乙女は、青酸カリを渡され最後の交換台に向かった。ソ連軍上陸と同時に、日本軍の命ずるまま青酸カリをのみ、・・・・・》
私も、何度か稚内で、この「九人の乙女の碑」の前に佇んだことがありましたが、それが、このように書き換えられたものとは知りませんでした。真偽のほどはわかりません。しかし、昭和一桁生まれで、戦争中の軍国主義一色に染められた雰囲気をよく知っている私たちからすれば、「軍の命令」であっても、少しも不思議ではないようにも思えます。
当時は、アメリカもイギリスも「鬼畜米英」でした。もし日本本土に敵が攻め込んでくるようになったら、男は奴隷にされ、婦女子は陵辱される、というのは、日本では普通に信じ込まされていたことです。日ソ中立条約を破ったうえ、八月十五日以降にも侵攻を続けたソ連軍も、当時、樺太にいた日本人にとっては、「鬼畜」そのものであったことでしょう。仮に「軍の命令」がなかったとしても、「九人の乙女」のような自決は十分に起こりえたのかもしれません。ドラマでは、自決し損なった電話交換手の一人が、ソ連兵に陵辱され、それを知って食って掛かった彼女の義父は、その場で射殺されてしまっています。
戦争は人間を狂気に駆りたて、理性を失ったケダモノにしてしまいますが、敗戦後の樺太にまつわるもう一つの大きな悲劇を、私たちは忘れることができません。それは、この乙女たちの自決から二日後に起こった樺太引き揚げ船3隻の遭難事件です。
1945年8月22日早朝、樺太の大泊(現在のコルサコフ)から引揚者を満載して、それぞれ、北海道の留萌と小樽に向かっていた小笠原丸、泰東丸、第二新興丸の3隻が、留萌付近の小平(こびら)、増毛の海岸数キロにまで来たところで、ソ連潜水艦の魚雷攻撃を受けました。小笠原丸と泰東丸は瞬時にして沈没し、第二新興丸だけは大破しましたが、辛うじて留萌にたどりつきます。死者、不明者は3隻で計1708人に上りました。
この攻撃は、日本がポッダム宣言を受諾し敗戦したあとであったのに、ソ連は、北海道の北半分を占領しようとして、そのためにとった一部の作戦行動であったと考えられています。しかし、公式には確認されていません。
当時のソ連は、引き揚げ船に攻撃を加えたことも認めていなかったため、長い間、潜水艦は、「国籍不明」とされていました。ソ連崩壊後の1990年代の初めに、ソ連潜水艦の攻撃であることを裏付ける資料が明るみに出た後も、ロシア側はまだ、「ソ連潜水艦」であったことを認めていないようです。
3隻の引き揚げ船のうち、大破しながらも沈没を免れた第二新興丸では、それでも死者、行方不明者が、400人を数えました。そして、この悲劇のなかにはもう一つの悲劇が隠されていました。沈没寸前の混乱状態のなかで理性を失った一人の軍人の、つぎのような狂気の行動が語り継がれています。
魚雷攻撃を受けて傾いていく第二新興丸からは、大勢の人びとが海上に投げ出されたり、残った人々も、救命ボートに殺到したりしていました。そのうちの上甲板にある救命ボートには、百人くらいの人びとが乗り込んだのですが、誰もボートの降ろし方がわかりません。そのときに、若い士官が近づいてきて、「お前たちだけ逃げるのか!」と、軍刀を抜くや、いきなりボート前方の綱を切断してしまったというのです。ボートは空中に直立して、乗っていた人びとは全員、悲鳴をあげながら海へ落ちていきました。(「戦後60年戦禍の記憶」『北海道新聞』 2005.08.06)
留萌の近くの小平町鬼鹿海岸には、1975年8月22日に建てられた「三船遭難慰霊の碑」があります。今年の8月末に私が訪れた時は、慰霊碑の背景には明るい太陽の下に青い穏やかな海が美しく広がっていて、遭難の碑文がことさらに哀しく思えました。その碑文は、こうです。(句読点、筆者)
・・・・・昭和20年8月22日、早暁の海は波穏やかにして微風甲板を渡る。
この日、泰東丸、第二新興丸、小笠原丸の三船は、戦乱の樺太より緊急引揚の老若婦女子、乗組員、5,082名を乗せ、鬼鹿沖にかかりしが、突如、旧ソ連の潜水艦による雷砲撃に遭い、瞬時にして沈没、或は大破し、1,708名の尊き生命を奪わる。
留別の地・樺太を脱し、数刻夢に描きし故山を目睫にして、この惨禍に遭う、悲惨の極みなり。
星霜ここに30年、我等同胞、慟哭の海に向かい、霊鎮まらんことを祈りつつ、この碑を建つ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
私というのはいったい何か
ー生活と文化をめぐる随想 (61)ー (2008.08.01)
作家の石上玄一郎は、1910年に札幌で生まれ、旧制の弘前高等学校では太宰治と同窓でした。『石上玄一郎作品集』(全3巻、冬樹社)のほか、多くの著作の中には、『太宰治と私』(集英社)などもあります。
彼は、3歳で母を、5歳で父を失ってからは、妹と共に、父の郷里の盛岡市へ移り、祖母に育てられました。岩手県立盛岡中学校(現在の岩手県立盛岡第一高等学校)から4年修了で弘前高等学校へ入学していますが、その当時から持ち前の文才を発揮し、「校友会雑誌」に『予言者』を発表したときには、当時の津島修治(後の太宰治)に大きな衝撃を与えたといわれています。
しかし、1930年には、公金私費スキャンダルに絡む校長排斥運動に関係し、その弘前高等学校からは放校処分を受けてしまいました。その後は、非合法左翼運動の闘士として活躍していましたが、23歳の時に祖母が亡くなってからは、政治からは遠ざかり、文学に打ち込んでいきます。そして、後年には、仏教への傾斜を強めていくことになりました。
その石上玄一郎の書いた本に、『輪廻と転生 ―死後の世界の探求― 』(1981年、第三文明社)があります。「死後われわれはどこへ行くのか?輪廻転生を巡り生命の本質に迫る」と、表紙の帯には書かれています。
本の内容は確かにその帯書きのとおりで、先史時代の風葬、葬法の意味から始まって、エジプトの不死の観念、ギリシア諸家の輪廻感、インダス人の来世観を説き明かし、仏教における輪廻思想にまで論考を展開する達意の叙述は、すぐれた学術論文に接しているような一種の高揚感と感銘を与えてくれます。著者が「本格的に取り組んだ」第一級の学術研究書といってもいいのでしょう。
しかし、学術論文がすぐれて「科学的」でなければならないとされているように、やはりこの本は、内外の広範囲な哲学、宗教、思想関係資料をしっかりと基盤に据えながらも、あくまでもこの世界の3次元の枠組みのなかからのみ「生命の本質に迫る」だけで、そこからは一歩も抜け出せていないもどかしさが、どうしても残るように思われるのです。
この本の序章のなかで、著者は、弘前高等学校時代、同期であったある大会社社長の死に際会したことについて述べています。家庭的にも社会的にも恵まれ、大会社の社長として「顕官名士との交友に明け暮れ」していたその友人が、突然、命取りの悪性腫瘍に冒され、病苦を押して、つぎのような手紙を書いてきたというのです。
《私はこれまで世事に追われ、慌しく毎日を送ってきた。自分の責務をはたすことに手いっぱいで、自らを顧みる心のゆとりを持てなかった。幸運にも、事業は順調に行き、経営の基礎もかたまったので、会社は私がいま引退してもさしあたって支障はない。また家の方は息子達もどうにか一人前になっているので、まさかの場合にも、別に後顧の憂いはない。
だが、こうしてひとり病床に臥していると、何とも言えず空しく、しきりに心の飢えをおぼえる。これまでの自分の生涯ははたして何であったか、この自分はいったい何者なのかという、ふかい懐疑に捉えられずにはいられない。君よ、教えてくれ、今、ここにこうしているこの私はそもそもいったい何なのだ……》
この友人は、間もなく亡くなったのですが、著者は、その少し前に、高級ホテルとまがうばかりに設備の整った病院を訪れ、完全看護を受けている友人を見舞っています。そしてそこでも、同じように、「君、教えてくれないか、こうしている俺はそも何者なのだ」と聞かれたのです。彼は、辛うじて、こう答えました。
《それはわれわれ人間にとっての永遠の課題だよ、古来、世の哲学者や宗教家は、この疑問をとくために苦しんできた。だがおそらくそれを明らかにした人はいないのではないか。この私自身それが分らぬし、答えるすべを知らない。またたとえ誰かそれに応えたにしろ、それはその人のものであって、君のものではない筈だ。》
著者は、この見舞いの折のことばを回想して、「冷淡ともいえる私の言葉におそらく彼は失望したに達いないが、それでも黙ってうなずいてくれた」と書いています。しかし、彼自身も、その返事には満ち足りぬものがあったのでしょう。「その時から、彼の問いは今度は私自身の虚空の声ともなって、あたかも幻聴の如く、鳴り響いてやまぬのである」と、つけ加えています。あるいは、このような友人との苦い死別の経験も、著者がこの本を書くことになった一つの要因になったのかもしれません。
それでは、その後の石上玄一郎は、宗教の研究に打ち込み、この本を書くことによって、この「虚空の声」に自分なりの答えを見出すことができたのでしょうか。どうも、そうはならなかったようです。この本の終章にあたる「輪廻思想の虚妄と真実」まで書き進めてきて、彼は、こう続けています。
《これまで東西の輪廻思想に就いて、私は私なりにあたう限りの模索を続けてきたが、どうやらこのあたりで、私自身の輪廻観を問われねばならぬときに立ちいたったかのようである。私は、あらためて、もの心づいてからこの方の、自分の前半生を振返ってみる・・・・・》
そう述べて、4歳のときに母親と死別した時以来の思い出に触れていくのですが、その後に続く、つぎの述懐には、彼自身の「虚空の声」に応えられない無力感と哀しみがまだ深く後を引いているように思えてなりません。読む者のこころには、その哀しみの余韻が、訴えられるかのように強く響いてくるのです。
《両親に死に別れたあと、東北の城下町で祖母に育てられた少年時代、それは貧困と寂蓼の中で、傷つきやすい心に夢想癖だけが昂じた一時期だった。やがて訪れたあの重苦しい軍国主義の時代、私はただ激流にもまれる木の葉のように生きていた。無力な抵抗と挫折、青春はむなしく屈辱と痛恨の中に過ぎていった。
だが齢、不惑を過ぎてなお疑惑はいよいよつのり、煩悩はたちがたく、妄執は去りがたい。恩愛に溺れ、名利に誘われ、彷徨、流転するだけだった。そしていまや人生の黄昏を前にしつつも、迷いの雲のついにはれるときなく、真如の月はとうてい望むべくもない今日この頃である。
そして、わたくしはまもなく死ぬのだろう。
けれどもわたしというのはいったい何だ。
何べん考えなおし読みあさり
そうともきき、こうも教えられても
結局まだはっきりしていない
わたくしというのは・・・・・・・・
郷土の先輩、宮沢賢治が、死を前にして述べた言葉、またかの旧友が、死の床から私に問いかけたと同じ言葉で、私はいま自分自身に問わねばならなくなった。だがその問いは恰も幻聴の如く、わが耳に鳴り響くだけで、それに対するいかなる応答も私は未だに見出せないのだ。》
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不思議現象を探索する
ー生活と文化をめぐる随想(60)ー (2008.06.01)
2001年の春、中国の西安を訪れた時、どういう経緯であったか記憶は曖昧ですが、西安市西影路にある中国人民解放軍医療センターに立ち寄ったことがあります。そこで漢方医学による治療を担当しているという中年の女医から伝統的な漢方薬の話をいろいろ聞かされたのですが、そのときにちょっと面白い体験をしました。
人間の「気」の力に話が及んで、「気」を使えば、例えば、人民元の紙幣で箸を切ることもできると彼女が言ったのです。日本でも、名刺で割り箸を切るというのは、マジックショーか何かで私も見たことがありましたが、名刺よりはるかに薄いぺらぺらの紙幣で、中国の骨で出来ているような太い箸を切るというのは、ちょっと信じられないような気持ちでした。
そこで私が、日本の千円札を一枚取り出して、これで切れるかと、聞きなおしたのです。彼女は切れると言いました。そこで、私は、持ってきてもらった中国の箸の両端を両手で握って、彼女の前に差し出しました。彼女は、千円札の皴を伸ばすように撫でて、右手の親指と人差し指の間に挟み、ちょっと呼吸を整えてから、さっと振り下ろしました。太い箸は見事に切れました。その切られた箸は、いまも私の手許にあります。
しかし、この程度のことは、超能力に詳しい人から見れば、不思議でもなんでもなく、超能力の名にさえ値しないのかもしれません。そんなことを考えさせられるのが、例えば、森田健さんがいろいろと公表されている不思議な体験談です。ゆで卵を元の生卵に戻す、煮た豆から芽を出させる、茹でられて死んだはずのエビが生き返って動き出したりする、というのですから、さすがに、「本当ですか」と疑いたくもなります。でも彼は、中国へ何度も出かけて、何人もの超能力者に逢い、それらを目の前で目撃しているのです。その「科学的に検証」された結果は、写真入で、『「私は結果」原因の世界への旅』、『自分ひとりでは変われないあなたへ』、『ハンドルを手放せ』(いづれも講談社α文庫)などのページを開きさえすれば、誰でも見ることが出来ます。
このうちの『ハンドルを手放せ』には、森田健さんの「科学的検証」に共鳴している船井幸雄氏が、解説を付け加えていますが、そのなかで、氏は次のように述べています。
《実は森田さんが1998年の夏前頃から次のようなことを言い出したのです。
「死んだものが生き返ると思いますか」
「そんなもの生き返るはずがないでしょう」
「しかし煮た豆から芽が出たんです」
それで、
「バカなこと言いなさんな」
と言ったのです・・・・・・(中略)
それからまた中国に行ってきた彼は、二カ月ほどたって帰ってきてすぐに、「三回ほど私の目の前で、煎ったピーナッツや炊いた豆から芽が出ました。それだけでなく、頭と胴の離された死んでいたエビが、もとの通りくっついて生き返ったのです」
と私に報告しました。
「嘘だろう」
と言うと、
「私は嘘はつかないですよ」
確かに彼は嘘をつくような人じゃありません。
「しかし常識的には信用できないね」
「じゃあ北京まで行きましょう」
「そんな暇がない」
と言ったら、
「では、その生き返らせた人を日本に連れてきましょう」
ということになったのです。
その人は孫儲琳さんといって中国地質大学の研究員の人ですよと、写真などを見せながら詳しく説明してくれました。
その結果、まず1999年2月に孫さんが日本に来ました。そして私たち何人かの面前で煎ったピーナッツから芽を出してくれました。そのピーナッツは、私の会社の社員が社内で育てて大きくして、何個か実がなり、いまではそのなった実からまたピーナッツが発芽して大きくなっています・・・・・・》
船井氏は、この解説に「煎ったピーナッツから芽が出るのを確認」とタイトルを付けています。事実は事実として、認めざるをえなかったのです。氏は、人間として幸せになるためには、「素直」で「勉強好き」で「プラス思考」するという三条件が必要だというのを持論にしています。それが考え方の基本だというのです。そして、知らないことや確認できないことを否定しないというのが「素直」ということだと常々言っているそうです。私たちも、森田健さんが熱心に、そして楽しみながら、いろいろと提示してくれているこれらの「科学的検証」には、狭い常識や既成概念に捉われることなく、「素直」に向き合うべきなのかもしれません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
霊や霊能力は存在するか
ー生活と文化をめぐる随想(59)ー (2008.04.01)
去る、3月5日の「朝日新聞」『声』欄に、読者からのつぎのような投書が載っていました。書いたのは、43歳のMさんという熊本県在住の高校教員です。
《放送倫理・番組向上機構(BPO)が、「スピリチュアルカウンセラー」を名乗る人物の番組内の言動について「出演者への配慮が欠けている」としてテレビ局に自制を求めました。当然です。
私自身、霊能力者や占師などが出演する番組はあまり見ませんが、新聞のテレビ欄を見ると、霊感的なものがブームになっていることは分かります。
その番組以外でも、霊能力者や占師がメディアで色んなことを述べているようです。しかし、当たり前のことながら、それらの人たちの「能力」には科学的根拠はありません。
私は、ブームに乗ってこのような番組を作り、流し続けることに強い危機感を覚えます。判断力の育っていない子どもが、霊の存在や霊能力を事実のように取り上げる番組を見続ければ、死生観は混乱するでしょう。
そういう私も先祖の墓参りくらいは行きますが、このような風潮は案じられてなりません。》
この文中の、「出演者への配慮が欠けている」とされている「スピリチュアルカウンセラーを名乗る人物の番組内の言動」というのは、それがどういうものであったか、私はテレビを見ていないのでわかりません。しかし、「霊の存在や霊能力を事実のように取り上げる番組」には「強い危機感を覚えます」といわれているのには、ちょっと考えさせられました。科学的根拠のない霊の存在や霊能力を、当然のように、「事実ではない」と言い切っておられることになりますが、果たしてそうなのでしょうか。「科学的」でないものは、この世の中には存在しないのでしょうか。
臨死体験を超えるといわれる『死後体験Ⅱ』(2004、ハート出版)の著者・坂本政道さんは、東京大学理学部卒業後、カナダのトロント大学大学院で電子工学を専攻した科学者ですが、坂本さんは、この本の中で、つぎのように書いています。(12-13頁)
《世の中には、科学的に存在が証明されたことしか信じない人たちがいる。証明されてない事柄はすべてウソだ、幻覚だとして受け入れない人たちである。たとえば、霊や死後の世界の存在について、科学的に証明されていないからそういうものは存在しないと言う・・・・・。
そういう人たちは、今の科学はこれ以上進歩発展しないと考えているのだろうか。なぜなら、今までに存在が証明されたことしか存在しないのなら、これから発見される事柄は存在しないことになるからである。
彼らの論理に従えば、物理学の最先端で議論されている海のものとも山のものともはっきりしないような新しいアイデアや新しい素粒子はすべてウソということになる。
たとえば「11次元の超ひも」や「M理論」などである。あるいは、宇宙物理学で登場するダークマターやダークエネルギーである。これらの存在はまだ科学的に証明されていない。彼らの論理に従えば、こういうものは存在せず、これらはウソであり幻覚ということになる。
このように、科学的に存在が証明されたことしか信じないと言う人たちは、科学的ではない。むしろ彼らは既存の出来上がった科学を信奉する宗教家である。科学信奉という新宗教の信者である。》
私たちはこの「青く美しい」といわれる地球に住んでいますが、この地球は、広大な宇宙のなかでは小さなゴマ粒のひとつにもならないくらいのちっぽけな存在です。そのちっぽけな地球のうえで、これも宇宙の視野からみれば一瞬の、たかだか100年単位の短い歴史しか持たない近代科学を金科玉条にして、そのモノサシで測れないものは、真実ではなく迷信であると断定するのは、やはり人間の傲慢であり、無知というものでしょう。まして、霊とか霊能力というのは、地球的尺度の次元をはるかに超えて、宇宙的視野のなかでなければ捉えられない実在だと思えるからです。
しかし、冒頭の投稿者Mさんのような人は、決して珍しい存在ではなく、むしろ、多数派です。いわゆる知識人、学識経験者などと呼ばれるような高学歴の人びとには特に多く見られるといってもいいでしょう。私自身も、かつては、そうでした。だいたい大学教授などが霊とか霊能力を口にしたりすれば、もうそれだけで「真理探究の殿堂」にはふさわしくないという批判や軽蔑をうけるような風潮は、いまでも決してなくなってはいないのです。一部には霊能を売り物にした「宗教」団体や「霊能力者」たちの金銭目当ての詐欺行為が後を絶たないことも事実ですから、それがこのような風潮を助長している面もあるかもしれません。
確かに難しい問題ですが、霊や霊能力はあるのでしょうか。それに、死後の世界は本当に存在するのでしょうか。その真実を知るためには、私たちは古からの求道者のように、難行苦行を重ねて悟りを開かねばならないのでしょうか。そういうことはありません。実は、偏見に捉われずに理性を働かせて真摯にその答えを求めていけば、いまは誰でも身近に、その答えを受け取ることができるのです。宇宙的視野でその真理を伝えてくれているシルバー・バーチの教えもそのひとつでしょう。無数に散りばめられたその珠玉のことばのなかには、たとえば、次のような証言もあります。
《すでに地上にもたらされている証拠を理性的に判断なされば、生命は本質が霊的なものであるが故に、肉体に死が訪れても決して滅びることはありえないことを得心なさるはずです。物質はただの殻に過ぎません。霊こそ実在です。物質は霊が活力を与えているから存在しているに過ぎません。その生命源である霊が引っ込めば、物質は瓦解してチリに戻ります。が、真の自我である霊は滅びません。霊は永遠です。死ぬということはありえないのです。》 (サイキック・プレス編『シルバーバーチは語る』13頁)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
コナン・ドイルに導かれて
ー生活と文化をめぐる随想(58)ー (2008.02.01)
ロンドンの大英博物館の前の通りをちょっと曲がると、ミユージアム・ストリートがあって、その並びに、「アトランティス」という名の小さな古本屋があります。もう15年以上も前のむかし、私が客員教授として在籍していたロンドン大学は、大英博物館の隣にありますから、大英博物館を訪れたような時には、時折、この小さな古本屋にも立ち寄っていました。そこで買い集めた本のなかに、コナン・ドイルのThe
New Revelation(『新しき啓示』)とThe Vital Message(『重大なメッセージ』)があります。
コナン・ドイルというのは、もちろん、あの名探偵シャーロック・ホームズの長短六十編におよぶシリーズの原作者ですが、その彼が、エジンバラ大学医学部出身の眼科医であったことはあまりよく知られていません。医者としての仕事の暇つぶしに書いた『緋色の研究』が思わぬ好評を博したので、それをきっかけに、次から次へと書き続けるはめになってしまったのがどうも真相のようで、コナン・ドイル自身は、このシリーズを書き続けるのにあまり乗り気ではなかったといわれています。
その理由は、多分、コナン・ドイルには、世間一般にはもっと知られていない、もうひとつの顔があったからだと思われます。それは、「地球浄化の原理」といわれるスピリチュアリズムの研究者としての使命感に燃えていた顔でした。前述の二書を書いたのは、1918年と1919年ですが、その後も彼は、熱心に研究を続けて、1926年には大著『スピリチュアリズムの歴史』
I、Ⅱを刊行しています。
このコナン・ドイルの『新しき啓示』と『重大なメッセージ』は、私の「目覚め」のための貴重な道しるべになりました。私は、自分自身のためにも、時間をかけてこれらの本の翻訳に取り組みながら、当時、まだ足を踏み入れたばかりであったスピリチュアリズムの理解を深めていきたいと考えるようになっていました。ところが、その後間もなく、シルバー・バーチ霊訓集の名訳で知られる近藤千雄さんがこの本も翻訳されていることを知ったのです。それが「コナン・ドイルの心霊学』(新潮社、1992年)で、出版されたばかりのその一冊は、近藤さんからわざわざ私のところへも送られてきました。
この本にも書かれていますが、コナン・ドイルは自分に与えられた人類に対する使命を自覚して、自分の得た金銭的な富、豊かな生活、世間の承認と名声をもすべて投げ打ち、その生涯をスピリチュアリズムの普及に捧げ尽くしたのです。
彼が「死んだ」とき、イギリスのサセックス州、クロウボローに近い自宅には、世界中の彼の作品愛読者、友人、知人等からの夥しい量の花束が、特別仕立ての列車で運ばれてきました。それらの花々はひろい庭をいっぱいに覆い尽くし、コナン・ドイルの葬儀は、湿った雰囲気とは無縁の、明るく静かな大規模のガーデン・パーティであったといわれています。数多くの参列者は、ほとんど喪服も着てはいませんでした。
彼のよき理解者であったジョン・ディクソン・カー氏は自分の著書『サー・アーサー・コナン・ドイルの生涯』を、「彼の墓碑銘を書くなかれ。彼は死んではいない」ということばでむすんでいます。
このことばのように、「死んではいない」コナン・ドイルは、霊界へ行ってからも、霊界の真相を伝えるための通信を送り続けてきました。この通信を仲介したのが、アメリカの女流作家で「ミネスタ」と呼ばれる著名な心霊主義者です。彼女は生まれながらの超能力者で、透視や、未来を予見する能力のほか、病気を診断し癒す才能なども身につけていました。
しかし、ミネスタは生前のコナン・ドイルには会ってはいませんでした。1930年の夏、しきりにミネスタに会いたがっていたコナン・ドイルは彼女を自宅に招待していたのですが、その面会が実現する直前、1930年7月7日に、彼女はコナン・ドイルの訃報を受け取ってしまったのです。これは二人にとっても心残りであったに違いありません。コナン・ドイルが、この世では会うことのできなかったミネスタを自分の霊界通信の仲介者として選んだのも、決して意味のないことではなかったのでしょう。英語の原文
(The Return of Arthur Conan Doyle) からも判断できるのですが、この通信の「純粋度」もそれだけに、極めて高いものと考えられるのです。
幸いなことに、このコナン・ドイルが2年間に亘って霊界から送り続けてきた数多くのメッセージは、いまでは、日本語にも翻訳されて、手軽に読めるようになりました。それが、大内博訳『コナン・ドイル―人類へのスーパーメッセージ』(講談社、1994年)です。このなかで、霊界のコナン・ドイルは、ある時の交霊会で、地上の人間の退廃ぶりを嘆きながらも、つぎのように語っています。
私は今、地上にいたときには想像したこともないような素晴らしい生活、より高貴な道を示すべく戻ってきました。すべてをあるべき姿にしなければなりません。人類は死後の生活について知る必要があります。私はそれを皆さんに教えます。皆さんはそれを世界中の人々に知らせてください。私を本当に知っている人、私の考えや書いたものを理解できる人は、私の言葉を疑うことはけっしてないでしょう。彼らは私の言葉の中に、私を認めるはずです。彼らは私が話そうとしていることを理解するでしょうし、理解しなければなりません。(139頁)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No,1~No,10へ
No,11~No,20へ
No,21~No,30へ
No,31~No,40へ
No,41~No,50へ
No,51~No,57へ
|