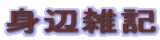
私が体験してきた不思議なこと(1) (身辺雑記 No.110)
私はいままで八十数年を生きてきて、これまで、いくつかの不思議なことを経験してきた。そのなかには神秘体験といってもいいようなものも含まれている。通常はありえない事態に遇ったこともある。きわどいところで命びろいをしたことも一度や二度ではなかった。それらの主なものをここで取り上げておきたい。世の中には偶然はないというが、それを改めて考え直すよすがにもなるかもしれない。私が体験してきたこれらのことがすべて必然としたら、個々の出来事に対しても、新たな視点が加わることになる。そして、それは、何よりも、私は生かされて生きてきたという認識につながっていく。確かに私は、生かされて生きてきた。そのことをかみしめながら、個々の体験を改めて振り返ってみたい。
1.尻無川のほとりで
昭和10年(1935年)、5歳の私は大阪市大正区の尻無川のほとりに住んでいた。まだ30代の若かった父が勤めていた鉄鋼会社からあまり遠くない小さな借家であった。近くに尻無川の対岸との間を往復する渡し船の発着場「甚兵衛渡し」があり、その斜め前には、道路を挟んで家主の伊藤さんの大きな二階家があった。その伊藤さんの家には、私より2歳年長の男の子で「カズちゃん」がいた。
その年のお盆が過ぎた頃だから、8月の下旬であったかもしれない。カズちゃんと私は、連れ立って、家の前の尻無川へでかけた。お盆の終わりには、木の舟に果物や菓子をのせて川へ流すみ霊送りの風習がある。この木の舟は、30センチくらいの小さなものから1メートルにもなるような大きなものまで様々で、それらが尻無川から一旦海まで流されたあと、波にもまれ風に吹かれて、たまに、川岸へ帰ってくることがある。そのような舟を見つけて持ち帰ろうというのである。うまくいけば大変な「収穫」になるはずであった。
川岸の一部には、多くの原木が筏に組まれて繋ぎ止めてある。その筏の上に乗って一番端まで来たところでカズちゃんと私は、根気よく空っぽになった舟が流れ着くのを待っていた。いまなら、大人の監視の目がうるさく、とてもそんなまねは出来ないに違いない。しかしその頃は、周りに人々がいることもあまりなく、親たちも、子どもたちの遊びにはほとんど干渉しないのが当たり前であった。その日は、晴天で暑かった。それでも1時間ほどは待ち続けたであろうか。やっと、遠くからかなり大きな木の舟が近づいてきた。すぐ目の前に来てからは、カズちゃんと私は、棒切れで水を叩きながら、なんとかその舟を引き寄せようと必死になった。私は小さな手を力いっぱいに伸ばした。それでも届かないので、もっと手を伸ばそうと身を乗り出し、そして、水に落ちた。
5歳の私は泳ぎはまだできない。私は水の中で泣き叫びながら沈んでいった。口からも鼻からも水が入ってきて苦しい。息ができずにばたばた手足を動かしているうちに、一度、上へ上がってきた。しかし、振り回している私の手は何にも触れることなく、また小さい体はぶくぶくと沈んでいった。筏の上で、私が落ちたのを見た7歳のカズちゃんも、ことの重大さはわかったであろう。手で水をかきまわしながら、懸命に私を掴まえようとしていた。そのカズちゃんの手に、もがきながら2度目に上がってきた私の手がちょっと触れた。しかし、二つの手は結ばれることなく、するりと抜けて、私はまた、ぶくぶくと水の中を沈んでいった。青白い水のなかで私はばたばた手足を動かしながら泣き叫んでいる。かなりの水を飲んで、苦しい。もうあれが限度であったろう。死が迫っていた。そして3度目、ぶくぶくとまた上へ上がっていった時に、私の小さな手ははじめてカズちゃんの手をしっかりと捉えたのである。
もうあれから80年以上経っているが、いまではこのあたりの川岸にも高いコンクリートの護岸壁が連なり、渡し場へ通ずる広い道路には高層アパートが建っていたりして、昔の面影はほとんどない。しかし、尻無川自体は、同じ場所を昔も今も同じように流れているはずだから、甚兵衛渡しからは、かつて私が溺れかかった場所は、ほぼ正確に特定できる。私は、後年、東京や札幌に住むようになってからも、大阪へ出かけてその場所に何度か行ってみたことがあった。かつては、私は、この場所で溺れかかっても救われたことを九死に一生を得た偶然の幸運のように考えていた。しかし、おそらくそれはそうではないであろう。もともと偶然というのはないのである。あの時、私の手を捉えた7歳のカズちゃんの手は、まぎれもなくそれは、神の手であった。
2.奇跡的な飛び方をしたグライダー
昭和15年(1940年)の3月、父は長年勤めていた大阪市大正区の伸鉄会社を退社し、生野区の田島に自分の小さな鉄工場をもつことになった。家も広々とした新築の二階家へ引っ越した。学校は、それまで通っていた新千歳尋常小学校は3年生までで、4月からは、生野尋常小学校へ転校して4年生になった。父は、春に創業したばかりの鉄工場の経営で忙しくしていたが、秋頃から、度々、当時の関釜連絡船で玄界灘を渡って、朝鮮の仁川へ出張するようになっていた。大阪の大手の鉄工会社が仁川の郊外に1万坪の大きな工場を建設することになり、父がその工場の主力部門になる圧延工場の設計と建造を任されたのである。
父は、家にいるときには夜遅くまで、大きな図面を広げて、機械や工場の設計に取り組んでいた。はじめのうちは、自分の鉄工場の経営もあって、大変であったようである。しかし、やがてその父自身の鉄工場の経営も、一年で終わることになった。自分が設計した仁川の工場の建設が完成すれば、父がその工場長となって赴任することが決まったからである。翌年、昭和16年(1941年)の3月末に、私たち家族は当時の関釜連絡船、金剛丸で玄界灘を渡って、朝鮮の仁川に住むことになった。
仁川では旭国民学校(当時、小学校は国民学校といわれるようになった)5年生になった。「外地」の学校は概して立派で、旭国民学校も校舎は堂々とした4階建てであった。よく整備されたグラウンドも、それまでいた大阪の生野小学校に比べると4倍近くも広いように見えた。
戦時色がだんだん色濃くなっていくなかで、私はその前年の生野小学校の時以来、模型飛行機作りに熱中していた。私は学校では成績はよかったが、国語や算数などよりも一番好きで得意なのは工作であった。旭国民学校でも、工作の先生から、私は模型飛行機の作り方で助言を求められたりして、工作の才能を認められていたかもしれない。たまたま、その年の夏休みには工作の宿題で、5年生のクラス全員が模型グライダーを作ることになった。
夏休み明けのある日、工作の時間に、自分たちが作った模型グライダーの飛行テストが行なわれることになった。クラスの40人くらいが、それぞれ自分の模型グライダーをもって、屋上に上がった。屋上から、下のグラウンドへ向けてグライダーを飛ばすことになったのである。下のグラウンドには看視役がいて、飛ばした人が降りて取りに行く。グラウンドは広いので、真ん中より遠くまで飛ぶことはあまりない。中には、それよりも遠く、グラウンドの端近くまで飛ぶのもあったがそれは稀であった。20人くらい飛ばしたところで、私の番になった。
私も、グライダーを手にもって、やや下向きにグラウンドへ向けて手放したのだが、私のグライダーは、どんどん降下していくことはなかった。少し飛んだところで、逆に高度をぐんぐん上げ、高い高度を保ったまま、まっしぐらにグラウンドの端を軽く越えて、500メートルほど離れた仁川神社のほうへ向かって飛び続けた。採点をしていた工作の先生もまわりの子供たちも、みんなが声もなく呆然とした。もう、そのグライダーを取りにいける距離ではなかった。
ところが、仁川神社の近くまで飛んで、ほとんど小さく見えなくなっていたそのグライダーは、急に大きく弧を描いて、今度は、一直線に旭国民学校へ向かってきたのである。機影はぐんぐん大きくなってきた。私は、何とか無事に、学校のグラウンドに落ちることを祈った。しかし、私のグライダーは、グラウンドへは落ちなかった。
グラウンドよりははるかに高い上空を戻ってきたグライダーは、先生や私たちが呆然と見つめている屋上の上を飛び越え、今度は、反対側の深い木立ちの奥のギリシア正教の大伽藍のほうへ向かった。またグライダーの影は小さくなって、ほとんど見えなくなってしまった。
折角Uターンして帰ってきてくれたのに、と私は悲しかった。もうグライダーを取り戻すことは不可能に思われた。裏の深い木立ちの奥では、落ちたグライダーを探し出すすべもない。と、その時、なんと私のグライダーは、再び上空でUターンしたらしく、小さな機影を見せ始めたのである。みんなが一斉にどよめいた。
小さな機影は、だんだんと姿を大きくしながら、真っ直ぐに、旭国民学校の屋上へ向かってきた。飛びながら高度を徐々に下げて、屋上の高さに近づいてきた。屋上の反対側の端の低いフェンスをすれすれに飛び越えて、私が立っている足元に、私の靴とほとんど接触する間際の位置で、ぴたりと着地した。まわりはシーンと静まりかえった。
あり得ないと思われることが現実に目の前で起こったのである。私は涙が出そうになるのをこらえながら、そっと、そのグライダーを拾い上げた。普通なら、飛ばしたあと、せいぜい数十メートルで着地するところを、数百メートルどころか、一キロ以上も飛び続けて、私のもとへ帰ってきたそのグライダーが無性に愛しかった。
たまたま、その時に発生した上昇気流に乗ったまでだと、考えられないことはない。確かにそういうことはあるだろう。しかし、Uターンを2度も繰り返して、そのグライダーを飛ばした屋上の上の私の足もとに着地する確率は、何分の一になるのであろうか。その分母は、天文学的数字になるに違いない。
私は宝くじのようなものは買ったことはないが、もしかしたら、毎年連続して宝くじの特賞に当選し続けるような確率なのかもしれない。私は長い間、あれはいったい何であったのだろうと考え続けてきた。奇跡といえば奇跡だが、私の見えないところで、誰かの何らかの作為があったに違いない。私はいまでは、あれは、私を見守ってくれている守護神の軽い戯れではなかったかと思ったりしている。
3.燦然と光り輝くみ仏の姿
昭和19年(1944年)の秋、当時の旧制仁川中学の1年生であった私は、戦局が日増しに緊迫の度合いを深めていく中で、10人ほどの級友たちといっしょに、当時の京城(現在のソウル)へ出かけて、陸軍幼年学校の入学試験を受けていた。卒業までにはどこか軍の学校へ受験するようにという学校の指導もあって、上級生は陸軍士官学校や海軍兵学校などを受験していたが、当時の中学1,
2年生にとってのエリートコースが、陸軍幼年学校であった。
翌年の2月、合格内定の通知が届いて、私の名前が他の3名の内定者の名前と共に、仁川中学の講堂入口の掲示板に大きく貼りだされた。憧れの「陸幼」に入れそうになって、私はうれしかった。しかし、その直後に私は生まれてはじめて病気になった。ある朝、急に40度を超える熱を出し、急速に、急性肺炎から肋膜炎に進んでしまったのである。
病院に運ばれるまでには、家の近くの医者の往診を受けて、2日か3日くらいは家で寝ていた。その間、高熱にうなされながら、家が台風で流されたり、空襲で家が燃えたり、陸軍幼年学校からの出頭命令を受けて出頭できずに苦しむなどの幻覚に襲われ続けた。その時に不思議な体験をする。私の寝ている足下の右上の方にみ仏の柔和な姿があり、じっと私を見下ろしている。そしてそのみ仏の姿からは、燦然と、目もくらむばかりにまばゆい金色の光が射し込んでくるのである。
み仏の姿はいつまでも消えなかった。嵐、濁流、家が流れる、空襲、破壊・・・・・もろもろの幻覚に襲われながら、それでもいつでも右上には、柔和に私を見下ろしているみ仏の姿があった。燦然とあたたかい感じがする光を放ち続けていた。私は何度も何度も見直していた。間違いなくそれはみ仏の実像であった。
高熱にうなされながらも、少しは正気に返る時があるものであろうか。工場長をしていた鉄鋼会社も休み、片時も私のそばを離れようとはしなかった父に、私は確かに言ったはずである。「お父さん、もし、僕のこの病気が治ったら、あそこのところ、あの壁の上の方へ神棚を祭ってよ」と。
み仏なのになぜ神棚と言ったのかわからない。神棚は奥の部屋にあったがそれを忘れていたわけでもなかった。いま思うと、神の姿を知らず、見慣れた仏像からの連想でみ仏と思ったのかもしれないが、それでも私は、何度見直しても、み仏の姿がその場所にはっきり見えたので、その場所を指差しながら、傍らにいた父にそう言ったのである。
父は慌てて、私の額に手を当てた。高熱で頭を侵されたのかと、心配したのかもしれない。それを見て私は、「ああ、こういうことを言えば心配をかけるだけだ、言ってはだめだ」と、その時たしかに思った。そして言うのをやめた。み仏の姿は、それからも相変わらず、燦然と輝き続けた・・・・・・・。
これは私の初めての神秘体験であったかもしれない。おそらく、人に話しても、それは高熱の時に見た幻影に違いないといわれるだけだと思っていたから、私は長い間、誰にも話そうとはしなかった。しかし、その燦然と光り輝く柔和なみ仏の姿は、いまも確かに私の心の中にある。
4.奇跡の解熱剤「トリアノン」
昭和20年(1945年)の2月、その時に入院したのはかなり大きな仁川総合病院であったが、入院したからといって、いい薬があるわけではなかった。ペニシリンなどもまだなかった。戦争末期で輸入の薬剤も途絶え、軍関係の病院でも、ぶどう糖の注射液さえ手持ちはなかったそうである。
私は病院でも高熱を出し続けたまま、ほとんど意識を失っていた。だから、自動車が手配できず、担架でゆらゆらゆられて病院へ運ばれていったのはかすかな記憶があるが、その後はまったくの空白である。その空白を埋めるのは、父と母の話だけしかない。
温顔で人望の厚かった病院長は、このままでは、希望は持てないと言ったそうである。「アジプロン」とか「トリアノン」という解熱の特効薬があったが、ドイツからの輸入品で、戦争以来、輸入は止まり、ストックも底をついて久しい。だから打つ手がない、というようなことであったらしい。しかし、父と母は、この幻の「アジプロン」と「トリアノン」を諦めなかった。なんとか手に入れる方法はないのかと、必死に院長にすがりついた。
院長も困り果てたすえ、可能性はないと思うが、と前置きして次のように言った。「どこかの薬局で、販売用としてではなく――それはとっくの昔になくなっているはずだから――万一の場合に備えて自分の家族のために、一箱でも注射薬を残しているところがあればいいのですが・・・・・・」そのことを聞いた瞬間から、母を私のそばに残して父の薬局まわりがはじまった。
その当時の仁川市は人口30万くらいであったろうか。薬局も全市で十数店はあったかもしれない。広い市内を、端から端まで、父は一軒一軒歩いてまわった。しかし、答はもちろん決まっていた。どこへ行っても、「いまどき、そんな薬はありませんよ」で、とりつくしまもなかった。
そのまま病院へ帰るわけにもいかない。帰っても、ただ私の死を待つだけである。父はまれにみる強靭な意志力と、人並みはずれた忍耐力の持ち主であった。その父が、二日、三日と街中を歩きまわり、疲労困憊して倒れそうになりながら、旭国民学校の正門あたりにさしかかった時、まったくの偶然で、20年ぶりの大阪の友人に呼び止められた。父は、名前を呼ばれても気がつかず、そのままふらふら歩き続けようとしていたらしい。
父はその旧友に私のことを話した。その旧友も同情してはくれたが、どうすることもできない。「ただ・・・・・」と、その人は言った。「私の知り合いの中にも、薬局を営んでいた人がいたのですが、いまはもうやめてしまって、郊外に引っ越してしまっています。お力になれなくてすみません」
しかし父は、そのことばにもすがりつこうとした。数キロ離れたその郊外の住所を聞いて、尋ね尋ね歩いて行った。やっとその家を探し当てた時は、もう夜もかなり更けていたらしい。綿々と事情を訴えるのを聞いたその家のご主人は、それでも、気の毒そうな顔で、「そういう薬はもうありませんねえ」と答えた。それで最後の望みは絶たれた。どうすることもできないまま、よろよろと父はその家を離れた。
2月下句の深夜である。その頃はまだ仁川は厳寒であった。父はその冷たい夜空のもと、凍てついた田舎道をどんな思いで足を運んでいたのであろうか。茫然として涙を流しながら、数分歩いていたのだという。
突然、父の頭にひらめくものがあった。仁川中の薬局という薬局をすべてまわりつくして、どこでも聞かされたのは、そういう薬はもうない、というきっぱりとした否定である。その時の雰囲気がどうであれ、言い方がどうであれ、その答え自体には真実であることを疑わせる響きは少しもなかった。しかし、最後のご主人のことばの中には、かすかにではあるが、ためらいがある。迷いのようなものがあったのではないか。もしかしたら・・・・・。
父は、取って返した。深夜のドアを叩いて、何事かと顔を出したご主人の前に、父は黙って用意していた分厚い札束を置いた。そして父はひざまずいた。ひとこと、「助けてください」とだけ言った。しばらくは沈黙が続いたそうである。やがて、ご主人は静かに口を開いた。「わかりました。実はトリアノンが一箱だけあります。これは私が家族のために残してあるものですが、それを差し上げましょう」
私のいのちはこれで救われた。「トリアノン」を打ったあと、高熱ははじめて急速に下がりはじめ、私は回復へ向かった。命の瀬戸際に立ったのは、5歳の時に大阪の尻無川で溺れかかって以来、これが2度目であったが、私は、ここでも死ななかった。生きるべくして生きた。昔は、あの最後の瞬間に父の脳裏にひらめかせたものは何であったのか、とよく考えたりもしたが、いまでは、この点でも疑問に思うことはない。
5. 間違いではなかった予言
後年、私はアメリカ留学を終えて、昭和34年(1959年)の春、太平洋を2週間かけて船で帰国した。帰国して数日後、東京外国語大学ロシア語科主任教授の佐藤勇先生のお宅へ帰国の挨拶に訪れた時、着いてみたら、東京外大で1学年下の女子学生であったTさんが、先に来ていた。私は学生時代はアルバイトに明け暮れていて、ほとんど大学には出席していなかったから、彼女と話し合ったことはなかったが、彼女がクラスではロシア語を誰よりも流暢に話せることを友人たちから聞いて知っていた。
佐藤先生は露和辞典の編集などもしておられたから、優秀な彼女は、そのお手伝いか何かの打ち合わせに来ていたのだろうと推測した私は、佐藤先生へのご挨拶もそこそこに、引き揚げることにした。理知的な顔つきで落ち着いた雰囲気の彼女とも、ほんの少しことばを交わしただけで、佐藤先生から昼食を一緒にと勧められたのを辞退して、お別れした。この時のTさんとの邂逅は、実は、大きな意味があったことを、その時の私は知る由もなかった。
その後、私は名古屋の中京大学へ赴任したのだが、6月の下旬、東京の佐藤勇先生から大学へ電話での伝言があった。6月20日、土曜日の午後5時半から、栄町の中華料理店平和園で、東京外国語大学の名古屋支部同窓会が開かれるからそこで会いたいとのことであった。行ってみると、学長の岩崎民平先生のほか、英語の小川芳男先生、ロシア語の石山正三先生も来ておられた。私の中京大学就任でお世話になった南山大学の直井英文学部長とも、その席でお会いした。
支部同窓会は、60人ほどの出席者で、盛会であった。2時間ほど、賑やかに懇談が続いて閉会になったあと、佐藤先生に誘われて、二人で近くの喫茶店へ移った。そこで、思いがけなく、佐藤先生から、この間、佐藤先生のお宅へ帰国のご挨拶に伺った時にたまたま逢ったTさんの写真と履歴書を渡されたのである。先生に、Tさんからの「結婚のプロポ―ズを頼まれた」と言われて、私はちょっと驚いた。Tさんのお姉さん二人も、大学教授のところへ嫁いでいる、というようなことも言われた。
佐藤先生も、この「プロポーズ」には、賛成であったのであろう。もしかしたら、帰国のご挨拶に先生のお宅へお邪魔した際、たまたまTさんが来ていたのは、見合いのような意味があったのかもしれない。私に対する先生のご厚意は有り難かった。しかし、このようなプロポーズの仕方を急に目の前にして、私は戸惑っていた。アメリカから帰ったばかりで、交際を始めるというならともかく、私はまだ結婚を考えるような気持ちの余裕はなかった。私はTさんには鄭重に手紙を書いて「辞退」した。
名古屋では中京大学の本部の前にある中京荘というアパートに住んでいた。教員では私のほかに、社会学担当の南谷教授が住んでいた。もう高校生のお子さんが二人もいるが、実家は三重のどこかで、中京大学へは単身赴任していた。円満な人柄で、私は時々、夕食時には南谷さんの部屋へお邪魔して、一緒に日本酒やビールを飲むのを楽しみにしていた。たまには、近くに住んでいる法学担当の沢登助教授もやってきて、3人で飲みながら大いに歓談することもある。
沢登さんは、私より3歳上で、京都大学法学部の出身であった。優秀な法学者で、後年、新潟大学の教授になって法学関係の多くの著作を出版している。晩年には自らの哲学的研究の成果をまとめた『宇宙超出論』なども刊行した。
その沢登さんは、あるいは霊感が人一倍発達した霊能者であったのかもしれない。当時、手相占いの名手として、知る人ぞ知る存在でもあった。沢登さんから手相を見てもらった女子学生が、決して他人が知っているはずのない内面の悩みや苦しみを正確に言い当てられて、わっと泣き出したという話を、誰かから聞いたこともある。
11月の初めであったか、ある日の夕、南谷さんの部屋でいつものように3人で鍋を囲みながら酒を飲んでいた時、沢登さんは、急に私の手相を見てやろう、と言い出した。私は手相占いのようなものには関心もなく、信用もしていなかったので断ったのだが、沢登さんは、「まあまあそう言わないで見せてください」と言って、私の手相をしげしげと見つめ始めた。
その時いろいろと言われたことは記憶にない。しかし、ただ一つ、今でも鮮明に記憶していることがある。沢登さんが、「あなたは近いうちに結婚しますね。数か月以内には、必ず結婚します」と言ったのである。私は笑い出した。それなら私にはすでに結婚話が進行していなければならない。「それは間違いです。絶対にそれはあり得ません」と私は答えた。それでも沢登さんは、「結婚する」と言い、私は「しない、あり得ない」と言い張って、それを聞いていた南谷さんも笑い出し、その話はそれで終わった。
私はその時、酔った頭で、T さんのプロポーズを断ったことを思い出し、その余波のようなものが私のどこかに残っていたから、それを沢登さんが勘違いして感知したのではないか、と考えたりした。しかし、沢登さんのこの予言は、重大な意味を持っていたことを、後に、私は知るようになる。
中京大学の英語担当の教授に旧制東京外語出身の室橋教授がいた。家も中京荘から近く、私は後輩ということで、一緒に長野へ旅行したりして親しくしていた。12月に入ったある日、私は、室橋さんの自宅の夕食に招待された。室橋さんにはお子さんはなく、奥さんと二人で住んでいる。日本酒を飲みすき焼きをご馳走になって、食後のよもやま話のあと、室橋さんは、ふと思い出したように奥の部屋から写真と履歴書を持ち出してきて、テーブルの上に置いた。こういう縁談があるのだが、と室橋さんは切り出した。私に勧めているようであった。
相手は、名古屋の製菓会社の社長の娘で、県立女子大国文科出身の24歳だという。私はアメリカから帰国して半年経っていたが、渡米した時とは逆のカルチャーショックがまだ消えずにいた。結婚話についても、どういうものか、その頃はまだ考える気にはなれなかった。その何週間か前に、法学の沢登さんに、近いうちに必ず結婚すると予言されたときにも、本気で、そういうことはあり得ないと思い込んでいた。
室橋さんは先輩だが、同僚の気安さもあって、その時も、笑い話に紛れさせて、写真と履歴書も手に取って見ようともしなかった。一度見たうえでそのまま返したら、失礼だと思ったわけでもない。私はそのあとちょっとまた歓談を続けて、写真と履歴書はテーブルの上に残したまま、室橋さんの家を辞している。
その後2週間ほどで、昭和34年(1959年)のクリスマスであった。冬休みに入る二日前の午後、大人数の学生相手にマイクで「英文学」の授業を行っていた時、教室のドアが開いて、教務課の職員が入ってきた。私に一礼して一通の至急電報を差し出した。その時の授業は、もう少しで終わるところであったが、至急電報だから、授業中でも届けてくれたのであろう。電報は苫小牧の弟からであった。当時、父は北海道へ進出して苫小牧でアルミニウム関連の会社を経営していた。その父が市立病院で手術を受けた結果、重度の肝臓がんであったことが判明したというのである。目の前がすっと暗くなった。
私はやっとの思いで、その授業をなんとか切り上げ、翌日、冬休み前に残っていた一つの授業を休講にしてもらって、慌ただしく身の回りの荷物をまとめて、東京へ向かった。夜遅く、荻窪の自宅に着いたが、私は母には平静を装って、父の肝臓がんのことは何も知らせなかった。翌日の朝、私は悲しみを母に覚られまいとして無理に笑顔を見せたりしながら家を出て、上野駅から苫小牧へ向かった。
私は、その3か月前、夏休みも苫小牧で父と過ごしている。腹具合がよくないというので、父を説き伏せて市立病院に入院してもらったのだが、その時は2週間ほどでよくなったというので退院した。12月中旬には、また腹部の痛みが出てきたというので入院するという連絡は受けていたが、私は今度もしばらくすれば退院できるのであろうと軽く考えていた。冬休みに入れば苫小牧へ行くつもりで、その時には元気な父に会えることにいささかの疑いも抱いていなかった。それが、重度の肝臓がんとは一体どういうことなのか、と私は納得できなかった。
苫小牧に着いてからは、父に覚られまいとして無理に笑顔を見せたりしながら、担当の医師に会い、院長に会い、当時がんの権威といわれていた札幌医大学長の中川先生にも頼み込んで往診をお願いした。肝臓がんの末期で余命は長くてもあと半年と聞かされて、すべての回復の望みは断たれた。3か月前の入院の時に退院させたのは明らかに担当医師の誤診であったが、いまさらそれをどうすることもできなかった。
父はほとんど命がけで私を愛し育ててくれた。その父は、私にとって絶対的な存在であった。子どもの頃から、父が死ねば私も生きておれないなどと考えていた。絶望感に打ちのめされながら、父の最後の時間を少しでも一緒に過ごせるように私は苫小牧付近の大学へ転勤することを考えた。そして、相手がいたわけではなかったが、父の楽しみであったはずの私の結婚を、できれば父の生きているうちに実行して、新婚の二人で看病したいと思った。父の死後、父の知らない人と結婚するということには耐えられない気がしていた。
私は、中京大学の学長へ手紙を書き、父のことを知らせて、辞職したい旨を伝えた。それから横浜の父の親しい実業家のS氏にも手紙を書いた。S氏は、父に頼まれて、かねてから私の結婚についても考えてくれていることを私は知っていた。
年が明けて、昭和35年(1960年)の1月、私は名古屋で中京大学の学長に会って、突然の辞任申し出を詫びた。学長は状況を理解してくれたようであった。「私の娘と結婚してもらって大学を継いでもらいたいと思っていたのに残念です」と学長は言った。横浜の実業家S氏にも会った。S氏は鎌倉にいる自分の姪を私の候補として考えていたようで、早速鎌倉へ出かけて本人に会ったら、すでに婚約したい人がいると打ち明けられたと言った。しかし、その後もS氏は熱心に動いてくれて、やがて二人の候補者が浮かび上がってきた。S氏は、「二人とも甲乙をつけ難い」と伝えてきた。私も二人に会い、そのうちの一人とは、文通を始めるようになった。
東京では、もう一つしなければならないことがあった。父の転院先を見つけることであった。父はできれば東京の大病院へ転院したいという希望があった。肝臓がんであることは伏せていたが、担当医師の病状説明に納得できなかったのであろう。しかし、私から肝臓がんの末期であるとは言えなかった。私は悩み苦しんだが、少しでも父に希望をもたせることができるのであればと、小型飛行機をチャーターして父を東京へ移すことを考えた。
3月の中旬、文通していたYさんと婚約することになり、佐藤勇先生がYさんの家へ行ってくださった。先生は、前年の春にTさんのことがあったにもかかわらず、心から私の立場に同情してくださっていた。Yさんのご両親に会っていただき、婚約は成立した。それが妻となった富子である。私は婚約の翌日、3月10日、富子をつれて羽田から当時のプロペラ機で3時間半かかつて千歳へ飛んだ。苫小牧市立病院へ直行して病床の父に富子を紹介すると父は本当にうれしそうであった。
その頃には、これは思いがけないことであったが、私の室蘭工業大学への就任も確定していた。父には、二人で苫小牧に住みながら、室蘭工業大学へ通勤することも伝えた。一泊して翌日、富子は再び父を見舞い、しばらく談笑して、部屋を出てエレベーターで降りていったとき、歩けなかったはずの父が立ち上がって部屋から歩いて出てきた。帰京する富子を見送りたかったのだという。その後、これも佐藤勇先生の奥様のお世話で父の東大病院への転院が3月17日に決まった。
3月14日、昼頃まで病室で父に付き添った後、午後の飛行機で東京へ向かった。翌日の3月15日、午前中に東大病院へ行って父の入院の打ち合わせをした後、午後、池袋の三越のグリルで、私と富子は結婚式をあげた。横浜のSさんは、たまたま腎臓疾患で入院中で欠席したが、佐藤勇先生ご夫妻と富子の両親、私と富子の友人たち少人数の式であった。翌朝、私は飛行機で苫小牧へ引き返した。父は、医師の話では、もうしばらく持ちこたえるはずであったが、痛み止めのモルヒネの影響であろうか、すでに意識を失っていた。チャーターしていた東京行きの小型機の予約はキャンセルした。父は、家族全員が見守る中で、3月17日午後11時16分、大きく一つ最後の息をして、59歳の生涯を閉じた・・・・・。
前年の11月に、中京荘で沢登さんが「数か月以内には、必ず結婚します」と言ったのは事実になった。私はあれから4か月後に確かに結婚した。しかし、その結婚には、こういう父と私の重大な運命の変転がからみあっていくことを、あの時の沢登りさんには見えていたのだろうかと、いまもふと思うことがある。
(2017.02.01)
私が体験してきた不思議なこと(2) (身辺雑記 No.111)
6.長男が思い定めていた他界の時期
むかし、ロンドンの大英心霊協会で知り合った霊能者アン・ターナーを通じて、2000年6月5日付で、長男・潔典(きよのり)からの手紙を受け取ったことがあった。その手紙には、「ぼくたちは、生まれるときには、好きな家族を自分の責任で、自分で選んで生まれてくるのですね。友だちなどもやはり、生まれるときに、自分の責任と好みで選んでいるのです。こういう特別の愛があることも、いまのぼくにはわかってきました」という一節があった。そして、「ぼくがお父さんと、この世で最後の会話をしたときからも、長い年月が流れました。どうか、あのときの不安がっていたぼくの態度を許してください。少し甘えながらあらためてお詫びします」という一節もある。
1983年の夏、アメリカのノース・カロライナ州立大学の客員教授をしていた私のところへ、母親と二人でやってきて夏休みを一緒に過ごした潔典は、1983年8月30日の午後、ノース・カロライナ州ローリー・ダーラム空港から、母親と二人で帰国の途についた。フィラデルフィア経由のユナイテッド航空機でニューヨークのケネディ空港には、午後6時過ぎに到着している。それから国際線にまわって、午後11時50分発のソウル経由成田行きの大韓航空機007便に乗ったのである。
潔典からは、ケネディ空港から、2度電話がかかってきた。無事に着いたというのが午後7時過ぎ、それから、もうチェック・インもすんで、座席も窓際が取れ、あとは乗るだけ、というのが午後9時過ぎであった。上述の手紙で「あのときの不安がっていたぼくの態度を許してください」と潔典が言っているのは、この最後の電話での会話のことである。
いつも明るい潔典の声が、その時だけは、しどろもどろで、飛行機に乗り込む前の状況を急いで説明したあとは、慌てたように「ママと代わるから、代わるから」と言って、母親に電話が代わってしまった。妻の富子とは、普通にしばらくおしゃべりして電話が切れたのだが、私は、電話が終わった後しばらくは、何か、暗い胸騒ぎを抑えきれなかった。子供のときから素直で天真爛漫な潔典を、私はほとんど叱った記憶はない。しかし、あの時だけは、東京に着いたらかかってくるであろう電話で、「潔典、あんな電話のかけ方をしたらお父さんは心配するではないか」と、強く注意しておこうと思ったくらいである。
実は、この電話の前にも、いくつもの潔典の不安を示す態度やことばがあった。『疑惑の航跡』(潮出版社)のなかにも書いたが、帰国前のバーベキューで、その材料を仕入れにスーパーマーケットへ行ったとき、巨大な1キロ半はありそうなステーキの塊を指差して、潔典がにこにこしながら、「死ぬ前にこんなビフテキを一度食べてみたいな」と言ったことがあった。そのようなことなどを含めて、潔典の態度やことばは、今にして思えば、私に対してそれとなく別れを告げていたのかもしれない。しかし、鈍感な当時の私は、それらからほとんど何も察知することは出来なかった。事件が起こってから初めて、愕然として、それらのすべてをまざまざと思い出したのである。
いまの私にはわかるが、潔典は、あの時、自分がこれから死出の旅路に出ることを魂の奥深くでは知っていて、そのことを、それとなく意識し始めていたのだと思える。シルバー・バーチは、死ぬ時期というのは、本人には分かっていることで、ただ、「それが脳を焦点とする意識を通して表面に出て来ないのです・・・・ 魂の奥でいかなる自覚がなされていても、それが表面に出るにはそれ相当の準備がいります」と述べているが(栞A57-e)、潔典がケネディ空港でしどろもどろの電話をしたというのも、「それ相当の準備」がまだ終わっていない段階だったからなのかもしれない。
その後、2005年8月31日には、東京でA師を通じての、新しいメッセージを受け取った。そのなかでは、潔典は私に対して、「有難うございます。よく耐えてくださいました。もうじきお会いしましょう。こちらで待っています。他界する時期は自分でもわかるでしょう。僕も分かっていました」と語っている。この「よく耐えて」というのは、私が妻の富子と潔典が霊界で生き続けていることを理解するようになるまでの長い悲嘆の道のりを言っているのであろう。そして、「僕も分かっていました」というのは、もちろん、潔典の他界した時期のことで、1983年9月1日〔日本時間〕を意味している。潔典は、生まれ故郷の北海道を目前にしたサハリン沖の海上で、この日の未明、母親と共に散っていった。
7. ノース・カロライナへの道
1982年(昭和57年)2月8日(月)の早朝に発生した東京・千代田区赤坂見附のホテル・ニュージャパンの火災は、死者33名、負傷者34名を出す大惨事となった。当時、小樽商科大学に在職して札幌に住んでいた私は、この日の夕方、空路で羽田に着いて東京に滞在していた。その翌日、フルブライト上級研究員の最終口頭試験に臨むためであった。この「フルブライト上級研究員」は、いま振り返ってみると、始めから終わりまで、異常な、不思議な陰影がつきまとっていた。最後には、慟哭の悲劇で幕を閉じた。
フルブライト試験会場の山王ビルは、その火災を起こしたホテル・ニュージャパンに隣接していた。私がかつて通っていた高校は、その裏側の丘の上にあったので、この辺の地理には私は詳しかった。久しぶりに現地を訪れた時、ホテル・ニュージャパンは前日の火災の惨状をまだそのまま残していた。黒こげになったホテルの窓のいくつかからは、宿泊客が脱出を試みたと思われるシーツを繫ぎ合わせてロープ状にしたものが何本も汚れた壁に垂れ下がったままになっていた。私は不吉な影を追い払うようにして、フルブライトの試験場に入った。
フルブライトの書類審査は前年の秋から始まっていた。その時の口頭試験は予備審査を通過したあとの最終段階であったので、その合否については、まもなく通知がくると思われた。通常は最終段階の口頭試験から一か月もかからないことを私は聞いていた。しかしその年に限って、合否の通知は、1か月過ぎても、2カ月経っても来なかった。
大学で教えている場合、一年も海外へ出かけるような長期出張には、当然ながら留守中の授業担当者を非常勤で手当てするなどの措置が必要になるから、少なくとも半年以上の余裕をもって申請しなければならない。5月に入って、もうこれ以上は待てないから、大学に迷惑をかけないためにも、フルブライトへは辞退の連絡をしなければならないのではないかと考え始めたころ、やっと、「上級研究員」決定の通知が届いた。後でわかったことだが、アメリカの不景気による政府の財政難で、その年に限って、予算決定が大幅に遅れたからであったらしい。
私は9月中旬に、1983年9月14日までの一年間の予定でアメリカのアリゾナ大学へ向かうことになった。妻とアリゾナ大学への編入が決まった長女が同行し、東京外国語大学在学中の長男は東京に残る予定であった。ところがその後、当時、東京・荻窪の実家に住んでいた妻の母親が胃がんに冒されていることがわかって、妻は急遽、渡米を取りやめ、看病のために東京に残ることになった。私と長女だけが渡米して、アリゾナのツーソンに住み始めた。妻の母親、山本雪香はその年は持ち越したが、翌年、1983年の2月に亡くなった。母親に付き添って看病に明け暮れていた妻は、悲しみと過労で、葬儀のあと寝込んでしまった。
長男の潔典は、はじめの予定では、1982年9月に私と妻が長女と渡米した後は、翌年3月からの春休みに、アリゾナへ来て家族と合流することにしていた。それが私たち家族にとっては2度目のアメリカ生活になるはずであった。1973年の暮れから1975年の初めにかけて私は文部省在外研究員としてアメリカのオレゴン州に滞在したが、その時は家族4人が一緒であった。1983年の春休みに長男が来れば、またアリゾナのツーソンで家族水入らずのアメリカ生活ができることになる。
私はその時も子供たちに貴重な教育の機会を与えることに執着していた。しかしそれも、妻の母親の葬儀と、その後の妻の体調不良で、妻と長男の渡米は諦めなければならなかった。次のチャンスは、夏休みしかない。しかし、夏休みをアメリカで過ごすためには、私のフルブライト上級研究員の滞在期間を少なくともあと半年は延長する必要があった。
フルブライトの上級研究員の場合、通常であれば、滞在期間を延長するのはあまり困難ではない。一年後の9月以降、どこかの大学で研究を続けるか教えるかして、給与を受け取る形を整えればよいことになっていた。私は妻と長男の春休みの渡米が困難になった時点で、私の研究分野に沿うような教育・研究担当者の公募があれば応募することを考えるようになった。アメリカは大学の数も多いし、「フルブライト」にはそれなりの権威が認められていたから、私は何とかなるのではないかと思っていた。
しかし、現実は予想外に厳しかった。その年に限って、アメリカの大学は、私の居たアリゾナ大学を含めて、軒並みにあまり前例のない大幅な予算削減に苦しんでいたからである。アリゾナ大学卒業生の就職も「最悪の状況」といわれていた。
そんな折に、12月中旬、カリフォルニア州モントレーのアメリカ海軍語学校から、私が所属していたアリゾナ大学言語学部に、日本語講師公募の書類が送られてきた。私はここの外国語教育には関心があった。効率の高いことで知られているこの学校独特の外国語教授法の実態を知りたいと思ってきた。私はアメリカ海軍語学校の教員公募に応募することにした。これが無事に通って、翌年9月からカリフォルニアへ移ることになれば、家族との再会もカリフォルニアにすればよい。それは望ましいことでもあった。
私は、履歴書、研究業績一覧表などと共に、要求された英文のエッセイと日本語のエッセイを新しく書いた。与えられたテーマについて、英語と日本語でそれぞれに口頭で録音テープに吹き込むという作業も済ませた。12月29日に応募書類とテープをアメリカ海軍語学校へ送った。念のために、アリゾナ大学言語学部の掲示板に貼り出されていた公募書類のうち、マサチューセッツ大学、プリンストン大学、ノースカロライナ州立大学にも、同様の応募書類を発送した。応募書類の作成で明け暮れしているうちに、何時の間にか、アリゾナの砂漠の町での1982年は過ぎていった。
翌年の1983年3月25日から3日間、サンフランシスコのヒルトンホテルで言語学会が開かれた。言語学、外国語教育の研究者が全米から集まることになっていて、アリゾナ大学からも十数人の教授、助教授、大学院学生と共に私も参加した。アリゾナのツーソン空港からロサンゼルスを経由して約1,300キロを飛んで10時過ぎにサンフランシスコに着き、学会会場のヒルトンホテルへ向かった。
アメリカでは、学会は求人の場合の候補者選考の場にもなっていた。研究発表のプログラムが終わると、別室に設けられたPlacement Service(就職斡旋)の部屋で、教員を公募している幾つかの大学が机を並べて、求職中の教員、大学院学生たちと面談することになっていた。学会二日目の午後、私はここでノースカロライナ州立大学のK教授に会った。K教授は私の採用に強い意欲を示していた。この時の面談でも、4月中旬には正式に決定できるだろうと言った。
アメリカ海軍語学校からもポジティブな反応が続いていた。1月下旬以降、私のパスポートとビザの写しを求めてきたり、私の1974年からのオレゴン大学客員教授時代の勤務内容についての照会があったりした。4月1日には、Notice of Rating (資格査定通知)が届いた。アメリカ海軍語学校独特の査定で、総合点数99点、1級インストラクター(GS-7)という書類が届き、「GS-7」に対応する俸給表なども同封されていた。
しかし、任用予定については何も触れていなかった。電話でそのことを問い合わせると、予算の決定があり次第、任用については追って知らせるというような返事であった。ここでもまた予算であった。私は滞在期間延長を在籍中の小樽商科大学へ申請するかしないかの決断を迫られていたので、少し考えて、5月末までにアメリカ海軍語学校の任用が決定されなければ、赴任することはできない、と手紙を出した。
それまでに、応募書類を出していたマサチューセッツ大学からは、1年間だけの短期任用は受け入れられないという返事があり、プリンストン大学からは、求人の対象は教授クラスではなく若手の大学講師クラスに絞っているという返事を受けていた。4月初めの時点で、滞在期間延長のための就職可能性が残されていたのは、アメリカ海軍語学校とノースカロライナ州立大学の二つだけになった。
ところが、そのノースカロライナ州立大学のK教授から4月中旬に手紙がきて、任用決定が少し遅れるかもしれないといってきた。さらにその後電話がきて、遠慮がちに、フルタイムで駄目の場合、パートタイムでも教えてもらえるかと聞いてきた。やはり予算削減で苦しんでいるようであった。パートタイムで週6時間教えて、給料はフルタイムの半分になるのだという。私はパートタイムでもいいから任用を決定してくれればそれに従うと答えた。給料の多寡よりも、滞在延長手続きのためには、任命決定書を早く小樽商科大学の人事委員会に提出する必要があった。
その年のアリゾナ大学の講義は、5月初めにすべて終わって、5月6日からは期末試験であった。娘の場合は、5月12日の人類学の試験が最後で、翌日からは夏休みに入る。5月30日からは、フルブライトの年次集会が予定されていた。アメリカ全土に散らばっているフルブライト研究員たちが呼び集められ、一堂に会して総会と研究分野別の研究会に出席するのである。
たまたま会場は、ノースカロライナ大学(University of North Carolina)の所在地チャペルヒルであった。通常、各州には二つの代表的な州立大学があって、ノースカロライナ州立大学(North
Carolina State University)のほうは首都のローリーにある。私はこの年次集会に出席している間に、ローリーへ行って、ノースカロライナ州立大学のK教授にも会うことになっていた。
そのノースカロライナ州立大学の任用は5月の20日を過ぎても、まだ決定の連絡はなかった。アメリカ海軍語学校のほうも、任用通知はまだ届いていなかった。私は悩みながら、滞在延長は取りやめて帰国することも考えるようになっていた。いずれにせよ、私のアリゾナでの生活はまもなく終わろうとしていた。
その頃、アリゾナ大学で私の世話役になっていたベイリー教授から、砂漠の中での朝食会に招待された。私の親しい友人で牧師のウエンガーさんが日本文化研究で博士号をとって、カリフォルニアの大学への就職が決まっていた。そのウエンガーさんや私に対する送別会のつもりであったようである。
5月28日の土曜日、午前6時半に、私と娘はベイリー教授の家に着いた。ベイリー教授一家4人、ウエンガーさんの家族4人、それにアリゾナ大学で博士課程にいる日本人留学生3名を含めて、総勢13名が3台の車に分乗して砂漠へむかった。町の中心部から東へ約40分、ツーソンでは一番高いレモン山へ行く途中に、ベイリー教授の目指す場所があった。灌木の中の空き地にテーブルを組み立て、持参のコーヒー、サンドイッチ、果物などで朝食をとりながら、とりとめのないおしゃべりを楽しんだ。
朝早いうちは何とかしのげるが、日中の気温は摂氏で40度近くに上がるので、長くは居れない。一時間ほど過ぎて、そろそろ引きあげようとしていた時、近くの灌木の陰でドーンという車がぶつかったような音がした。皆でかけつけてみると、なんとそこには、朝食後その辺で遊んでいたベイリー教授の長男で15歳のショーンが、小型トラックにはねられて倒れていたのである。騒然となった。救急車を呼んでショーンを病院へ運んだが、ショーンは死んだ。
私は大きなショックを受けた。フルブライトの年次集会に出なければならなかったが、旅行どころではないような気がしていた。私は鉛を飲み込んだような重い体と気持ちを引きずったまま、次の日の夜、深夜便でツーソンからフェニックスを経由してノースカロライナのローリー・ダーラム空港へ向かった。3,200キロの空の旅を私はぐったりして殆ど眠ったまま過ごした。
チャペルヒルでは会場の「ホテル・ヨーロッパ」で、5月31日の晩さん会から年次大会は始まった。世界各国から選ばれて集まっている百数十人の研究員たちは、ホテルの部屋を割り当てられ、翌日から、午前、午後、夜間の三回に分けて、いくつかの研究発表や分科会が開かれた。世界の人種問題、教育問題、経済問題、文化の違いと国際交流、世界情勢のなかのアメリカの役割、研究者、ジャーナリストの使命等々熱心な発表と討論が続いたが、私はまだ、ショーンの突然の死の後遺症が強く残っていて、会場の雰囲気になじめず上の空であった。発言するのも苦しかった。
2日目は、午前中にチャペルヒルの街とノースカロライナ大学を見学して、午後は研究会と討論、3日目も午前中はディユーク大学を見学して、午後の総会で年次大会は終わった。私はノースカロライナ州立大学のK教授に迎えられて、40キロ離れたローリーに移り、その夜はK教授の自宅で、日本食の夕食をご馳走になった。
私の任命については、学内の処理はすべて終わっていて、大学財務部の予算決定を待っている段階だという。K教授は、フルブライト教授をパートタイムで来てもらうのは申し訳ないといいながら、手続きが遅れてしまっていることを何度も私に詫びた。来週にも決定は降りるはずだから、私たちのアパート探しも心がけておくとも言った。
次の日の午後、私は泊まっていたローリーのヒルトンホテルで、フルブライト年次大会に出席していた東北学院大学教授の鈴木氏とたまたま出会った。鈴木氏は図書館学の専門家でノースカロライナ州立大学図書館を午前中訪れていたという。私は鈴木さんに誘われて、午後の時間を一緒にすごした。Roleigh
Little Theaterへ行き、ミュージカル「Southern Pacific」を観た。しかし、やはりミュージカルを楽しめる気分にはなれなかった。劇場を出てからは、ダウンタウンで日本風居酒屋の店を見つけて夕食をとり、その後はヒルトンホテルへ帰って、鈴木さんの部屋で深夜の12時近くまで缶ビールを何本も飲みながら話し込んだ。
少し酔いがまわってきたせいもあったかもしれない。私は苦しい胸の内を曝け出して、鈴木さんにツーソンでのショーンの死の話をした。いま滞在延長の予定が思い通りに進んでいないこともあって、延長はしないで帰国するかどうか迷っているところだと言った。その時、鈴木さんは、「実は」と、自分の息子さんの話をした。前年の春、そのショーンと同じ15歳の長男が、小児がんで亡くなったのだという。
亡くなる1週間前には病院から仙台の自宅へ移っていたが、夜中に長男が声を殺して泣いている様子が病室の外へ伝わってきて悲しかったと鈴木さんは打ち明けた。9月に日本へ帰っても、位牌の前に座るのが辛いとも言った。私はここでも、彼の息子さんの死が他人事ではないような気がして、暗く沈みこんだ。ふらふらと深夜の自室に戻り、ベッドの上に倒れるようにして眠った。
ローリーからツーソンに帰ってから一週間が過ぎても、ノースカロライナ州立大学の任用通知書は届かなかった。私はやっと決心して、滞在延長は取りやめることにした。私のフルブライトの滞在期限は9月14日となっていたが、それまでに帰国することをフルブライト委員会に伝える手紙を書いた。規定による帰国旅費の支給申請書も作り、6月15日の朝、近くのポストに投函した。辛い気持ちで何もする気がおこらず、その時はそのままアパートへ引き返した。その、ほんの20分ほどの留守の間に、ノースカロライナ州立大学からの速達便が届いていた。任用通知書であった。私は呆然となった。
しばらく苦しみながら考えた後、私はノースカロライナへ赴任することにした。先ほどフルブライトへの書類を投函したばかりのポストの前で一時間以上も待って、やがて現れた郵便物集配人に事情を話し、私の手紙を取り戻したいと言った。集配人は、規則でここでは返却できないので、郵便局本局へ身分証明書を持参して受け取りに行くように、と答えた。
翌日、私は言われたように郵便局の本局へ行って、フルブライト宛の書類を取り戻した。そしてアパートへ帰ってみると、今度は、アメリカ海軍語学校からの手紙が届いていた。予算措置ができて、これから任用手続きを始めるからもう少し待ってもらいたい、というのである。手続きを始めるのはいいが、それでまた少し待てといわれても、私にはもう待つ余裕はない。私は、アメリカ海軍語学校のほうは無視することにした。
7月1日、車に荷物をいっぱい積みこんで、私と娘はツーソンを後にした。アリゾナのツーソンからノースカロライナのローリーまで、直線距離は3,000キロだが、その間に、車では、ニューメキシコ、テキサス、アーカンソー、テネシー州などを通過して行かねばならない。途中、名所旧跡などに立ち寄りながら、私たちの車は3,400キロを走って、10日目の7月10日、ローリーの近くまでたどり着いた。
翌日には、大学から北へ30キロほどの2LDKで90平方メートルくらいのアパートを契約した。7月12日に引っ越しをして、14日に電話がついたので、東京の留守宅へ電話した。妻の富子に、これからでもこちらへ来れるようであれば来てはどうか、と言った。
私からの電話を受けて、東京では、ニューヨーク行きの航空券を手に入れるために八方手を尽くしたらしい。しかし急のことで、どこの航空会社の予約も取れなかった。キャンセル待ちの大韓航空の航空券でそれもソウル経由のものが8月3日になってやっと取れ、妻の富子と長男の潔典は、その二日後に慌ただしくニューヨークへ飛んできた。私と娘は、その前日にローリーを車で出発して、アメリカ時間の8月5日午後9時過ぎ、ケネディ国際空港で富子と潔典との一年ぶりの再会を果たした。
それから25日間、私たちはまた家族4人になって、かつてオレゴンに住んでいた時にそうしたように、車で東部諸州やノースカロライナ州の周辺を旅してまわった。そして、8月30日の朝、思い出深いアメリカ2度目の滞在を終えて、富子と潔典は帰国の途についた。ローリー・ダーラム空港からフィラデルフィア経由でケネディ空港へ飛び、そこで大韓航空機に乗ったのである。しかし、その大韓航空007便は、遂に富子と潔典を無事に日本へ帰してはくれなかった。
事件のあと何年も経って、私は「溺れる者は藁をも掴む」心境で仏典や聖書を学び、霊界の本を読み、霊界からのメッセージを求めて次々と数十人の霊能者と接触したりもした。そして、少しずつ霊的真理に目覚めていった。やがて霊界の富子と潔典とも「文通」できるようになり長年の悲嘆と苦しみからも抜け出していった。
その過程で、私がなぜあのような国際的な大事件に遭遇して妻と長男を失わねばならなかったのかを理解するようにもなった。このことについては、いままでに数多くの霊界からのメッセージや「証言」が寄せられている。たとえば、その一つの例として、潔典は霊界からこう伝えてきたことがあった。「お父さんなら、頭も聡明で、苦しませるのは高い霊たちにとっても辛いことで、決断を要したということです。でも必ず目覚めて立ち直る人だということがわかり、一人の苦しみが何百、何千人、いや何万人の人たちの魂を目覚めさせ、同様の苦しみや悲しみのなかで沈んでいる同胞に慰みと魂の癒しをもたらすことを、その聡明さによって、やってくれるということが期待されたからです。」(1999. 6. 5)
同様の「証言」は霊能者のA師を通じても幾つかあった。つぎのように言われたこともある。「・・・・・あなたが霊的なことに目覚め、価値観を正し、本当に大切なもの、すなわち、神と愛と命と心に目覚めるために、このこと(大韓航空機事件で妻と長男が亡くなること)が必要だったのです。否が応でもあなたはその方へ駆り立てられていきました。あなたは、その一連のプロセスを経ていくことで浄化され、価値観が変わり、神を求める人に作り替えられました。また、それをもって、この世の認識の暗い人たちに、大事なメッセージを体を持ったまま伝える任務に就くようにされました。」(2004.06.05)
これらの霊界からの「証言」やメッセージについては、私は『天国からの手紙』(第6章以下)などにも書いてきた。「世の中が偶然によって動かされることはありません。原因と結果の法則が途切れることなく繰り返されている整然とした宇宙には、偶然の入る余地はありません」と、シルバー・バーチは言っている。事件によって私が悲嘆のどん底に突き落とされたとしても、それは私にとって必要なことが必然的にもたらされたということになるのであろう。いまになって事件に至るまでの過程を逆に振り返ってみると、思い当たるようなことがいくつも出てくる。
まず、私は、フルブライトを受験して合格しなければならなかった。その決定がその年に限って異常に遅れたにも拘わらず、私はフルブライトを諦めるのではなく、受け容れてアメリカへ向かわねばならなかった。アメリカではアリゾナに一年居て帰国するのではなく、家族を呼び寄せるためにも、滞在延長をしなければならなかった。それも給与の高いアメリカ海軍語学校のモントレーで教えることによってではなくて、ノースカロライナ州立大学での給与の低い教職でなければならなかった。そうでなければ、それらの選択肢のうちの一つにでも私が別の選び方をしていれば、私は事件に巻き込まれることはなくなっていたはずなのである。今にして思えば、私は抗うこともできずに、ただ与えられた道を歩んできたとしか考えられない。
シルバー・バーチはこうも言っている。「一人ひとりの人生にはあらかじめ定められた型があります。静かに振り返ってみれば、何ものかによって一つの道に導かれていることを知るはずです。あなた方には分からなくても、ちゃんと神の計画が出来ているのです。定められた仕事を成就すべく、そのパターンが絶え間なく進行しています。人生の真っただ中で時としてあなた方は、いったいなぜこうなるのか、といった疑問を抱くことがあることでしょう。無理もないことです。しかし、すべてはちゃんとした計画があってのことです。天体の一分一厘の狂いのない運行をみれば分かるように、宇宙には偶然の巡り合わせとか偶然の一致とか、ひょんな出来ごとといったものは決して起きません。」
―― いまの私には、こういうことばも私なりに理解できるような気がしている。確かに私は、「何ものかによって一つの道に導かれて」きた。その結果、私はあの年にあのような事件に遇った。それは私の宿命であった。そして、そのことをも含めて、私は今まで、大宇宙の大いなる力によって導かれ、生かされてきたのである。
8.潔典のおもちゃの時計のことなど
長男の潔典は、1981年4月に東京外国語大学英文科に入学してからは、札幌から上京して、多摩市永山のアパートに住んでいた。大韓航空機事件に巻き込まれた1983年の夏も、このアパートから母親と一緒に、当時アメリカにいた私のところへ出発して、ついにこのアパートには帰ることはなかった。
このアパートの潔典の勉強部屋に、潔典がなにかの付録か懸賞でもらったらしい子供っぽい時計が残されていた。五百円玉よりちょっと大きいくらいのゲーム・ウオッチで、値段にすれば、おそらく千円もしないかもしれない。茶目っ気のある潔典は、その時計を、自分の机の脇の電気スタンドにぶら下げていた。
私は、事件後しばらくは辛くて部屋にも入れなかったが、2年くらい経ってからであったろうか、ぼんやり潔典の机に座っていると、急に「タタタータタ、ターララ、ラーラ・・・・・」と、時計が鳴り出しのである。私はちょっと驚いて、初めてこの「ムッシーちゃん」と名付けられた小さなおもちゃの時計が鳴ることに気づいたのである。
12時15分に鳴り出して、15秒ほどで終わるこのメロディーは、その後何年間も鳴り続けた。鳴り続けるだけでなく、画面の人形が可愛らしく踊るのである。それだけ、電池の消耗も大きいはずだが、私は、いつまでも鳴り続け、踊り続けるこの時計の「異常」に気がついて、7、
8年目くらいからは、ときどきビデオで時計の時間を音と映像とともに記録するようになっていた。
事件後10年になる1993年の夏、ロンドンでアン・ターナーにこの時計のことを話すと、彼女は「あなたに霊界のことを理解させるために、この時計は10年間鳴り続けてきたが、いまあなたは理解し始めている。それで、まもなく動くのを止めるだろう。止まっても新しくバッテリーを入れ替える必要はない。そのままにしておけばよい」と言った。
このビデオの録画は、1994年1月6日までの記録が残っている。文字盤の人形が踊り、ちゃんとメロディーが鳴っている。普通は1年か2年で止まってしまうと思われるのに、このおもちゃの時計は、11年以上も毎日、画面の人形が踊って鳴り続けたことになる。
2003年9月1日は、事件後20周年で、私は、北海道・稚内での慰霊祭に参加し、札幌の自宅では、長年そのままになっていた妻や長男の遺品などの整理を始めていた。長男の潔典の部屋には、高校時代まで使っていた机が元のままの状態でおいてあった。その机の引き出しを、初めて開けてみたら、小さなトランジスタ・ラジオがひとつ出てきた。大学に入ってからは、性能のいい別のラジオを使っていたから、このトランジスタ・ラジオは、その時の時点で、おそらく22年以上もこの引き出しのなかで眠り続けたことになる。
私は、自分のラジオを5年くらい放置して、なかの電池が腐食で流れ出したことがあったのを思い出して、この潔典のラジオも電池だけは抜き出しておこうと思った。その時、なにげなくスイッチを入れてみたら、ラジオから大きな音響で音楽が流れ出して、驚ろかされた。このラジオは、電池は入れ替えていないのに、22年以上経ってからでも、普通に使用できたのである。
1982年に、フルブライト上級研究員として、アリゾナ大学へ行ったとき、私はコンパクトなコニカ製のカメラを持っていった。翌年の夏に、当時留学生としてアリゾナ大学に在学していた娘と二人でノース・カロライナ大学へ移ったとき、そこへ、東京からやってきた妻と長男が合流して、家族4人でいろいろなところを旅行したが、そのおりおりの写真を撮ったのもこのコニカのカメラである。大韓航空機に乗るためにニューヨークへ向かう妻と長男を見送って、ノース・カロライナのローリー・ダーラム空港で二人の最後の写真を撮ったあとは、このカメラは使ったことはなかった。
当時のカメラは、まだほとんど手動式であったが、日付を写し込む部分だけは、電池を使っていた。2004年になって、私はそのことを思い出して、しまいこんであったそのコニカのカメラを取り出してみたのである。1981年に買って、もう23年にもなるそのカメラの日付は、閏年の誤差も自動修正して正確に、正しい日付を示していた。念のために、その後何年かして購入したたペンタックスとミノルタの一眼レフカメラをみてみると、いずれも、10年もたっていないのに、日付機能は電池切れで、消えてしまっていた。
潔典のおもちゃの時計が11年以上も、画面の人形が踊り、鳴り続けたというのは、アン・ターナーに言われるまでもなく、とても偶然とは思えないが、潔典のラジオが22年以上たっても大きな音響を失わず、潔典たちの最後の写真を収めたカメラは、その日付が23年たっても正常に表示されていた、というのはちょっと不思議な気がする。これらもまた、単なる偶然ではないのかもしれない。
9.深夜のバルト海で見た赤く光る飛行物体
2003年9月28日の夕方、私は北欧スウェーデンのストックホルムから、フィンランドのヘルシンキへ向かう3万5千トンのフェリー・ガブリエラ号に乗っていた。6階の海側の個室の窓から見えていたバルト海は、曇天で6時頃には真っ暗になって、どこまでも深い闇がひろがっていた。
船内のレストランでヴァイキング料理の夕食をすませて、8時半頃部屋へ戻っていた私は、翌日の忙しい行程に備えて、10時すぎにはもうベッドに横になっていた。まだ時差ぼけから抜けていなかったからであろうか、夜中に私はふと目を覚まし、時計を見ると午前零時であった。3万5五千トンの巨体は船底の方で鈍いエンジン音を響かせているだけで、船はほとんど波で揺れることもなく、粛々と進んでいるようである。私はカーテンを開けて、夜のバルト海に目を向けてみた。
私は、船旅は好きなほうで、1957年にアメリカ留学で二週間をかけて太平洋を船で渡って以来、船室から夜の海を眺めるという経験は、海外でも日本でも少なくはない。船室の窓から、月夜の美しい海原を眺めたことは何度もあったし、曇り空で、真っ暗闇の海を航行しているときには、全く何も見えないこともよく知っている。しかし、その夜の場合は、様子が違っていた。
曇天の暗い海上の遠くの方で、赤い光が、すーと流れ星のように流れていくのが見えたのである。よく見ると、それは水平に、そして、左右に素早く動いていて、流れ星でないことはすぐわかった。しかも、それが、三本の線になったり、四本、五本の線に増えたりするのである。みんな、鮮明に赤く光っている。私はその不思議な光景に、眼を凝らして、何とかその正体を見極めようとした。
それらの赤い光は、それが素早く飛んでいるから赤い線に見えたのだが、船からは遠く、おそらく百メートルも二百メートルも離れていたように思える。ずっと見続けていると、たまに船のそばまで近づいてくる光があって、船の近くでは、船の灯りを受けたからなのであろうか、一瞬、白く見え、そして羽ばたいていたような気がした。それで、私は、遠くの赤く光る物体も、鳥ではないだろうかと推測したのある。
しかし、赤色に光って飛ぶ鳥などというものは、常識で考えても、とてもあり得るとは思えない。蛍や、洞窟の中でかすかに光る苔などは、私も見たことがあったが、鳥の類が光るはずがない、と何度も思った。
真夜中の真っ暗闇の海の上のこどだから、もし物体が光るとすれば、それは船からの光を反射している、と考えられないことはない。しかし、その可能性もなかったようである。「光の明るさは距離の二乗に反比例する」ことも私の頭の片隅にはあって、何度も暗い海を眺めまわしたのだが、真夜中の船から漏れている明かりは、船のすぐそばの波の動きをわずかに捉えているだけであった。50メートルや100メートルの、あるいは200メートルもあるような遠方の空中の物体に船体の光が届くはずがないこともすぐにわかった。
あまりに不思議なので、私は、幻覚でも見ているのではないかと何度も思ったりした。しかし、何度見直しても、やはり間違いではない。赤い光は、断続的に、しかし、何度も何度も暗い夜空に赤い線を引きながら、左右に速い速度で直線的に飛んでいた。
いつまでも見ているわけにもいかず、眠らないでいると、翌日からの予定にも差し支えてくる。私はいったんは寝ることにしたが、念のために目覚ましを3時にセットして、3時に起きあがり、もう一度、窓の外を眺めてみた。赤い光が間違いないか、再度、確認しておこうと思ったのである。外は相変わらず、漆黒の闇であった。そしてやはり、赤い光を発する物体が、左右に速い速度で飛んでいた。ちょうど流れ星が横に流れているような感じで、鮮明に目に映ったのである。それは決して、幻覚ではなかった。
翌日、私は現地の人に、「この海ではこういう光景が見られるのか」と訊いてみようと思ったが、どう考えても幻覚だと一笑に付されそうで、訊くのはやめた。帰国してから、山科鳥類研究所へ電話し、手紙も出して、その実体を知ろうとしたが、やはり、「鳥が赤い光を出して飛ぶことはあり得ない」ということで、その実体を探索する道は絶たれてしまった。
そのまま、わからないまま数年が経過して、私は、思い切って、霊能者のA師に、この問題を持ち出してみた。バルト海で私が見たあの物体は何か、なぜ飛んでいたのか、私にだけ見えた現象なのかを、霊視で見てもらおうと思ったのである。私は何とか知りたい一心でA師に縋りついたのだが、A師にとっては、別に難題でも不思議でもなかったようであった。A師は、よどみなく、つぎのように答えてくれた。
《他の人にも見えることがありますが、でも、全員が見えるということではありません。人の中の何割かが見えるという程度です。その実体は何かというと、生命体です。霊界のみ霊そのものではありませんが、生命の要素が光って飛んでいるものです。物理的なものでなく、生命の発光体です。北方の寒冷の地で、しかも大海原で、生命の気が、或いは要素が、海上に沢山うごめいています。生命の要素は赤く発光することがあります。その生命の要素は、たとえば魚の霊とか、魚だけでなく魚介類など、そういった生命の要素が発光体として光ります。
人間の亡くなったみ霊というより、大自然の、特に、陸地よりも海に関わる生命の要素が沢山、寒冷の地の澄んだ大気の中で、特に夜は、生命の要素が真っ暗がりで目立つので、ちょうどオーラのように光るのです。それと似たものとしては、日本の墓地などで、浮遊霊が火の玉のように飛んでいることに近いです。墓地に昔見えた火の玉は、主に遺体の骨の燐の部分が発光して光っているものでした。最近は火葬が徹底しているし、密閉するようになったのでほとんど見受けなくなりました。
あなたがバルト海で見たのは、人間の霊ではなく、生き物たち、特に海系の生き物たちの生命の気です。また、あなたの心が澄んでいて、生死を乗り越え、達観視してきていたのです。自分では無我夢中で現実に対応してきたのですが、何時しか自分が実感している以上に達観して澄んだ心境になったので、余計あなたには目立って見えたのです。地球は生命に満ちあふれていて、生命は光り輝いていることをあなたに見せたのです。あなたは生命について、今生で苦しい体験を以って会得しました。普通には得がたいことでした。それがあなたに今生で与えられた贈り物です。》
10.不思議な咲き方をしたサボテンの花
かつて私が住んでいたアパートのベランダのサボテンは、毎年一回、一つか二つの花を数時間だけ開かせてきたのだが、2012年に限って、私の大腸がんと腹部動脈瘤の二つの病気の検査、入院、手術にタイミングを合わせるように、七回もの開花を繰り返した。
2012年当時の、このサボテン開花の一回目は6月14日で、この翌日から大腸がんの検診を受けて、内視鏡検査でがんが発見された。2回目の開花が7月19日で、がんの切除手術を受けて退院してきた二日後のことであった。ところが、このサボテンは、その後も、三回目・8月13日、四回目・8月20日、五回目・8月24日、六回目・9月23日、そして、10月12日には七回目が開花したのである。それぞれに撮っておいた写真によって改めてその開花の日の前後を確かめてみると、退院後と入院前の一連の検査や診断で、重要な節目の日に当たっていることがわかる。
年に一回しか開花してこなかったこのサボテンが、なぜその年に限って七回も花開いたのか、そもそもサボテンに限らず花というのは、そんなに年に何回も開くものなのか、私にはよくわからなかった。思い返してみると、2回の大きな手術の前も後も、私がなんの不安も怖れもなく穏やかに過してこれたのも、この純白の美しい花によっても見守られていたからかもしれない。
このサボテンが、2012年に、七回もの開花を繰り返しことには何か意味があるのではないかと考えていた私は、その翌年にはこのサボテンがどういう咲き方をするのか、興味を持って見守ってきた。やはりその年、2013年も、最初の開花は異常であった。5月21日の夜、八つの蕾のうち四つが花を開かせた。夜に開いた花は、朝になって陽に当たると数時間でしぼんでしまう。この四つの花は、5月22日の昼ごろにはしぼんで、代わりに残りの四つの蕾が花を開かせた。つまり、その年は、5月21日の夜から22日の夕方までに、八つの花が一度に開いたことになる。
それまで、二つ以上の花が一度に開いたことはなかったので、その年には、なぜこのような開き方をしたのか、ちょっと不思議であった。しかも、この八つの花が開くというのは、その後、6月16日に1輪、6月19日に7輪と、もう一度繰り返されたのである。この開花はさらに続いて、6月30日にも二つの花が開き、一週間後には、新しく一つの花が開いた。その年には、合計で19の花が6回に分けて開いたことになる。
その開花の「異常」の意味が知りたくて、私は、2013年6月6日、その年の8つの蕾が確認できた時点で、霊能者として高名なA師に聞いてみた。A師はこう答えた。
《「7」は生命の進化の段階を表わしています。よりよい霊的な働きは「7」で表わされます。あなたがこの世で病気になったので、富子さんや潔典さんをはじめ、あなたと繋がりがある、あなたをこころから思う霊界の存在たちが、あの世から生命力を送ってきていたのです。そのため驚くほど沢山、たて続けに咲いていました。その生命力のお陰であなたは手術がうまくいき、恢復したのです。
そしてその霊界からの支援は、いまでも続いて今年も咲き始めています。あの世とこの世との緊密な関係が感じられます。あなた自身、霊界に大分近づきつつあります。これからますます、霊界の雰囲気や霊的存在たちの臨在感を感じられるようになることでしょう。霊界とより緊密になっていき、徐々にあの世へと移行していくことでしょう。この世の側の身辺の整理や処理なども、少しずつしていってください。》
A師からの答えがこのようなものになるであろうことはある程度は予想していたが、それでも、7回の「7」の数字の意味は、私にとっては初耳であり、新鮮であった。その次の「霊界からの支援」については、私には十分に納得できる気がする。常日頃から、私は、霊界から妻の富子や長男の潔典が見守ってくれていることは、かなり強く意識して過ごしてきた。A師が言われるように、彼らがあの世から「生命力」を送ってきて、そのお陰で手術もうまくいったというのも、おそらくそのとおりであろう。しかし、その彼らが送ってくれていた生命力が、あのようなサボテンの花の開花という現世的な形でも示されていたことには、思い及ばなかった。
(2017.04.01)
東京都小平霊園の先人たち (身辺雑記 No.112)
東京都小平霊園は、武蔵野台地のほぼ中央、小平市と東村山市、東久留米市にまたがって住宅地と農地が混在した地域にある。65万平方メートルもの広大な広さをもっているが、霊園として利用されているのは、ほぼ半分だけで、残り半分は、緑豊かな公園として都民の憩いの場となっている。園内は、きちんと整列されたケヤキ並木が美しく、ソメイヨシノなどの桜の名所としても有名であり、春には、毎年訪れてくる花見客も多い。
小平駅北口から表参道を北へ進むと、霊園の正門に至り、そこからは広い中央参道が道路中央の緑地帯を挟んで一直線に北へ伸びている。園内は広いので、参拝者は殆ど車で来ているようである。電車で来る人は、表参道に並ぶ石材店などから無料貸し出しの自転車を利用したりしている。正門から中央参道を1ブロック北へ進むと、最初のロータリーがあり、さらに2ブロック北に進むと、右側に13区の一劃がある。その入り口の角の、目印になるような位置にあるのが大山郁夫の墓(13区1側1番)である。上半身の青銅レリーフが壁面に埋め込まれた大きい墓である。
大山郁夫(1880-1955)は、早稲田大学政治経済学部を首席で卒業して、早稲田大学教授になったが、後に政治家へ転じて、左派無産政党である労働農民党の委員長になった。戦後は、1950年の参院選に日本社会党・日本共産党などで構成される全京都民主戦線統一会議(民統)の支援を得て立候補して当選している。1951年の12月には、スターリン国際平和賞を受賞したが、1955年に参院議員在職中、硬膜下血腫のため76歳で死去した。
この13区には、13区25側9番に文学・文芸評論家として1920年代前半のプロレタリア文学運動の指導的な立場に立った青野季吉(1890-1961)の墓があり、英文学者でユーモア小説の先駆者であった佐々木邦(1883-1964)の墓(13区23側7番)もある。佐々木邦は、国際マーク・トウェイン協会名誉会員となり、1961年に児童文芸功労賞、1962年に紫綬褒章を受章しているが、81歳の時に心筋梗塞のために死去した。ほかに、13区37側1番には作家では中間小説、時代小説で活躍した浜本浩(1891-1959)の墓がある。作品の「絶唱」が映画化されて有名になった大江賢次(1905-1987)の墓も同じ13区である(13区7側?番)。
小平霊園に入って、中央参道からこの13区の大山郁夫の墓のところを右折すると、その2ブロックの奥が36区で、その隣が37区である。そのなかに、少し広めの22平方メートルの墓地が並んでいる一角がある。そのうちの一つが武本家の墓(37区12側4番)である。墓の使用名義人は東京都の住民でなければならない規則で、私が札幌に住んでいた頃から、名義人は東京在住の下の妹の名前になっていた。その下の妹も一昨年に亡くなったので、いまは、甥の武本之近が名義人になっている。私はもう87歳にもなっているから、名義人にはならなかった。墓誌には、父母や妻の富子、長男の潔典等の名前が法名と共に刻み込まれているが、私もそう遠くない将来、それに加わることになる。私の法名は、これもすでにつけられているが、「慈光院釈昌叡」である。
この小平霊園には、いわゆる有名人の墓も少なくはない。生前、会ったことはなくても著作などで私が親しんできた人たちが何人もいる。「袖触れ合うも他生の縁」というが、袖触れ合うことがなかったとしても、墓地が同じであれば、「他生」ではなくとも「多少」の縁はあるかもしれない。いわば同郷の縁のようなものである。そのうちの何人かの「同郷」の人たちを、ここに書き並べてみることにしたい。
そのなかで、誰よりも私が縁のようなものを感じているのは伊藤整(1905-1969)である。小説家であり文芸評論家・翻訳家でもあった伊藤整は、北海道松前郡に生まれた。旧制小樽中学(現小樽潮陵高等学校)を経て小樽高等商業学校(現小樽商科大学)で学んでいる。小樽高商時代には、『蟹工船』などの著作で知られる小林多喜二(1903-1933)が上級生であった。伊藤整の『若い詩人の肖像』には、小樽高商の授業風景なども描かれている。彼よりも25年年下の私は、大学時代から、彼の作品に親しんでいたが、後に、伊藤整の母校、小樽商科大学で教えるようになった。1969年に伊藤
整は胃癌のため死去した。法名は海照院釋整願で、墓は4区9側36番にある。
明治生まれの作家では、小川未明(1882-1961)の墓が23区29側6番にある。「日本のアンデルセン」、「日本児童文学の父」と呼ばれた児童文学の大御所であった。本名は小川健作で、童話の代表作としては、『金の輪』『赤い蝋燭と人魚』『月夜と眼鏡』『野薔薇』などがよく知られている。筆名の「未明」は、正しくは「びめい」とよむらしい。
小川未明は、新潟県高田(現上越市)に生まれた。旧制高田中学(現新潟県立高田高等学校)から、早稲田大学へ進学して英文科を卒業した。在学中の明治37年(1904
)処女作『漂浪児』を雑誌に発表し、この時、坪内逍遙から「未明」の号を与えられたという。卒業直前には『霰に霙』を発表して、小説家として一定の地位を築いた。卒業後は、早稲田文学社に編集者として勤務しながら多くの作品を発表する。大正15年(1926)年、東京日日新聞に「今後を童話作家に」と題する所感を発表して、童話専従を宣言した。ロマンや詩情、ヒューマニズムなどを表現した作品が多く、子供だけでなく大人の鑑賞にも堪えうるといわれていた。
この小川未明と同じ年に生まれたのが詩人の野口雨情(1882-1945)である。墓は 32区1側8番にある。野口雨情は、童謡・民謡作詞家としても著名で、北原白秋や西條八十と並び、童謡界の三大詩人と謳われていた。多くの名作童謡の歌詞を作ったが、なかでも、「赤い靴」、「七つの子」、「シャボン玉」、「黄金虫」、「青い眼の人形」、「あの町この町」、「雨降りお月さん」、「証城寺の狸囃子」などがよく知られている。「波浮の港」、「船頭小唄」など、昭和歌謡史に残る流行歌も残した。
野口雨情の生家は、茨城県多賀郡磯原町(現・北茨城市)に現存している。廻船問屋を営む名家であった。野口雨情は、18歳で東京専門学校(現在の早稲田大学)に入学し、坪内逍遥の元で学んだが一年で中退。詩の世界に没頭していった。詩を雑誌に投稿しだしたのもこのころからである。22歳の時に父が他界したので、実家に戻り家督を継いだが、詩作は続けた。この頃から「雨情」の号を使い始めた。しかし、地元磯原の生活に嫌気がさし、樺太にわたって新規事業に取り組むも失敗。東京に戻ったもののしばらくして北海道に渡り、今度は、小樽日報の記者となる。このとき石川啄木と同僚となった。
小樽日報をやめたころに二番目の子供(娘)が生後一週間で亡くなり、この時つくられた歌が「シャボン玉」とも言われている。小樽日報もあわせ6カ所の新聞社に勤めたが、母の死去により実家に戻り先祖からの全資産を管理していくことになった。植林活動や漁業組合の理事なども務めて、詩作に没頭できずに悶々としていたという。2度の離婚と再婚をくり返したあと、36歳の時に、水戸で中里つると結婚する。この頃より詩作活動を本格化させていった。1925年、43歳のときに日本童謡集の選者となり、1935年53歳で日本民謡協会を再興して理事長に就任。日本各地を旅行しながら、その地の民謡を創作した。戦時中の1945年(昭和20年)、宇都宮市にて疎開中に永眠する。享年63歳であった。本名は野口英吉である。
明治生まれの作家では、自然主義文学の大家として知られる徳田秋声(1872-1943)の墓も23区27側29番にある。徳田秋声が生まれた1872年は明治4年で、現在の金沢市横山町に加賀藩家老横山氏の家臣徳田雲平の第6子(3男)として誕生した。明治維新後、没落士族の末子として「宿命的に影の薄い生をこの世に享け」た子供であり、4歳で生家を引き払って後は居を転々とし、また病弱であったため小学校へも学齢に1年遅れで入学しなければならなかった。その小学校(現在の金沢市立馬場小学校)の一学年下には泉鏡花がいた。1888年(明治21年)第四高等中学校に入学したが、その3年後、父が死去したため第四高等学校を中途退学している。このころから読書熱が高まり、小説家を志望するようになったという。
その後、郡役所の雇員、新聞記者、英語教師などをしながら半放浪的生活を送り、1895年(明治28年)、博文館の編集部に就職する。そこで、当時博文館に出入りしていた泉鏡花の勧めで紅葉の門下に入った。1896年(明治29年)、被差別部落出身の父娘に取材した『薮かうじ』を「文芸倶楽部」発表して「めざまし草」の月評欄に取り上げられ、これが実質的処女作となる。以来、泉鏡花、小栗風葉、柳川春葉とともに紅門の四天王と称され、1900年(明治33年)「讀賣新聞」に連載した『雲のゆくへ』が出世作となった。1906年(明治39年)4月末頃、秋声は本郷森川町の住居に転居して、ここが生涯の住処となった。この住居は、東京都史跡に指定されて現存している。
1910年(明治43年)には、『足迹(そくせき)』を「讀賣新聞」に連載し、1911年(明治44年)には、私小説『黴(かび)』を、夏目漱石の推挽により「東京朝日新聞」に連載する。この二作によって、秋声は初めてといっていいほどの文壇的成功をおさめ、島崎藤村、田山花袋らとともに、自然主義文学の担い手として確固たる地位を築いた。1937年には芸術院会員になる。1943年、戦時中の昭和18年、肋膜がんのために死亡した。戒名は、徳本院文章秋声居士である。
明治生まれの、作家というよりは美学者、宗教哲学者として著名な柳宗悦(1889-1961)の墓も27区13側2番にある。柳宗悦は、明治22年に、東京で海軍少将・柳楢悦の三男として生まれた。旧制学習院高等科を卒業する頃から同人雑誌『白樺』に参加する。東京帝國大学哲学科に進学した宗悦は、宗教哲学者として執筆していたが、西洋近代美術を紹介する記事も担当しており、やがて美術の世界へと関わっていく
。1913年(大正2年)、大学卒業してからは、ウォルト・ホイットマンの「直観」を重視する思想に影響を受け、これが芸術と宗教に立脚する独特な柳思想の基礎となったといわれる。
1914年(大正3年)、声楽家の中島兼子(柳兼子)と結婚し、志賀直哉、武者小路実篤ら白樺派のとも付き合うようになって、旺盛な創作活動を行った。当時、白樺派の中では、西洋美術を紹介する美術館を建設しようとする動きがあり、宗悦たちはそのための作品蒐集をしていた。彼らはフランスの彫刻家ロダンと文通して、日本の浮世絵と交換でロダンの彫刻を入手する。1916年(大正5年)以降は、たびたび朝鮮半島を訪ね、朝鮮の仏像や陶磁器などの工芸品に魅了された。1924年(大正13年)にはソウルに「朝鮮民族美術館」を設立、李朝時代の無名の職人によって作られた民衆の日用雑器を展示して、その中の美を評価した。1957年(昭和32年)には、文化功労者に選ばれた。晩年はリウマチや心臓発作との闘病を余儀なくされ、1961年(昭和36年)春、脳出血により日本民藝館で倒れて、数日後に逝去した。享年72歳であった。
作家、評論家として戦後の保守系マスメディアで活動した山本七平(1921-1991)の墓も1区8側21番にある。1970年に出版された『日本人とユダヤ人』は大ベストセラーになったが、山本七平は、そのほかにも、『「空気」の研究』、『日本人の人生観』、『「あたりまえ」の研究』、『日本型リーダーの条件』、『日本人とは何か』など、数多くの日本社会、日本文化、日本人についての論考を発表してきた。私も、比較文化論の考察を進めていくうえで、彼の著作からは、いろいろと影響を受けてきた。忘れられない作家の一人である。
山本七平は、現在の東京都世田谷区三軒茶屋で、クリスチャンの両親の間に長男として生まれて、1937年 には青山学院教会で洗礼を受けた。1942年9月、太平洋戦争中のため、青山学院専門部高等商業学部を21歳で繰り上げ卒業して、10月に陸軍近衛野砲兵連隊へ入隊した。その後、甲種幹部候補生に合格して、愛知県豊橋市の豊橋第一陸軍予備士官学校に入校する。1944年5月には、陸軍砲兵見習士官として門司を出航し、ルソン島における戦闘に参加したが、1945年8月15日、ルソン島北端のアパリで終戦を迎える。マニラでの捕虜収容所生活を経て、1947年に帰国した。その後、世田谷区の自宅で聖書学を専門とする出版社、山本書店を創業し、『日本人とユダヤ人』をはじめ、多くの日本人、日本文化の著作を発表したが、1991年(平成3年)、膵臓がんで死亡した。遺骨の一部はイスラエルで散骨されたという。
昭和期の女流作家・小説家・詩人の壺井 栄(1899-1967)の墓も小平霊園にある。10区1側4番である。彼女の代表作『二十四の瞳』は、昭和の第二次世界大戦前期の瀬戸内海の小島を舞台に、新任の若い女性教師と、小学校入学直後の12人の児童のふれあいを描いた作品である。木下恵介監督・高峰秀子主演で映画化され、香川県小豆島の名を全国に知らしめた。瀬戸内海を見渡す海岸沿い約1万平方mの敷地に『二十四の瞳
映画村』もあるらしい。敷地内の壺井栄文学館には代表作「二十四の瞳」の生原稿をはじめ、愛用品、初版本などの他、夫壺井繁治(1897-1975)の書簡なども展示されているようである。
壺井 栄は、この小豆島の出身である。26歳で詩人壺井繁治と結婚。昭和13年(1938)処女作である『大根の葉』を発表後数多くの作品を執筆。芸術選奨文部大臣賞を始め、新潮文芸賞、児童文学賞などを受賞。代表作『二十四の瞳』が発表されたのは、昭和27年(1952)であった。私の妻からの霊界メッセージを伝えて下さった大空澄人氏も、この小豆島の出身で、この『二十四の瞳
映画村』へは何度か行かれているようである。氏の「続 いのちの波動」(2017.02.24)には、氏がこの映画村を訪れた時にインスピレーションで受けた高峰さんと壷井さんからのメッセージを、つぎのように伝えている。
「栄さんは私の恩人、栄さんのお蔭で私は女優として成長することが出来ました。あの二十四の瞳の映画のお蔭です。私は栄さんに大変感謝しています」。(高峰秀子)
「私の書いた二十四の瞳は高峰秀子さんという優れた女優さんに巡り合えたことによって全国的に知られるようになりました。彼女は私の恩人、大切な人なのです」。(壺井栄)
女流作家では、宮本百合子(1905-1996)の墓が2区11側6番にある。宮本百合子は、東京の裕福な家庭に生まれ、日本女子大学英文科中退。大正5年(1916)、坪内逍遙の紹介で中条百合子(本名ユリ)の名前で『貧しき人々の群』を『中央公論』に発表した。大正7年父精一郎と渡米。翌年コロンビア大学聴講生となるが、ニューヨークで古代東洋語の研究者荒木茂と知りあい結婚して12月帰国。1924年離婚。以後ロシア文学者湯浅芳子と同居生活に入る。この間『伸子』執筆に専念した。
1927年12月には湯浅とともにソ連に外遊した。滞在中に西欧旅行など経たのち昭和5年11月帰国。その翌月には、日本プロレタリア作家同盟に加入している。昭和7年2月、宮本顕治と結婚した。翌年12月スパイ容疑により顕治検挙。昭和9年中条から宮本へ改姓する。敗戦までの厳しい期間のなか百合子も投獄・執筆禁止などを繰り返しながら作家活動に励んだ。昭和20年10月、顕治が獄中から釈放され、夫と交わした書簡はのちに『十二年の手紙』として刊行された。戦後も社会運動・執筆活動へ精力的に取り組み多くの作品を残している。
ほかに女流作家では、有吉 佐和子(1931-1984)がいる。墓は、25区12側15番である。古典芸能や花柳界、日本の歴史から現代の社会問題まで幅広いテーマでカバーする幅広い作品で読者を魅了したベストセラー作家として有名であった。代表作である『紀ノ川』のほか、『花岡青洲の妻』、『出雲の阿国』、『和宮様御留』、『私は忘れない』、『不信のとき』、『一の糸』、『恍惚の人』、『複合汚染』、『三婆』、『悪女について』、『海暗』、『香華』など、数多くの作品を残した。松本清張、山崎豊子と並ぶベストセラー作家として、映画、TVドラマ化された作品も多数である。
有吉佐和子は、和歌山県和歌山市出身である。東京府立第四高女(都立竹台高校)から疎開先の和歌山高女へ。その後、光塩高女、府立第五高女(都立富士高校)を経て東京女子大学短期大学部英語学科卒業。昭和27年(1952)『地唄』が芥川賞候補となり注目された。『複合汚染』は日本の公害について書き上げた代表作となった。1964年
『香華』で第10回小説新潮賞、 1967年 『華岡青洲の妻』で第6回女流文学賞、『出雲の阿国』で第20回芸術選奨文部大臣賞、昭和53年(1978)
『和宮様御留』で第20回毎日芸術賞を受賞している。1984年8月、急性心不全のため死去した。53歳の生涯であった。
女流作家では、もう一人、私にとっては忘れられない人がいる。ノンフィクション作家で歌人でもあった辺見じゅん(1939-2011)である。角川書店の創業者角川源義の長女で、角川春樹の姉にあたる。1961年に、早稲田大学第二文学部史学専修卒業。1964年、清水真弓の名で私小説『花冷え』を刊行したが、以降は辺見じゅんの筆名に変えた。1984年に『男たちの大和』で新田次郎文学賞、1988年に『闇の祝祭』で現代短歌女流賞、1989年に『収容所からきた遺書』で講談社ノンフィクション賞を受賞している。
私は高校時代、東京都立第一高校(現・日比谷高校)2年生の時、一年飛び級で都立豊多摩高校3年生に編入学して、その翌年、大学へ進学したのだが、辺見じゅんは、その豊多摩高校では私の後輩にあたる。私が1983年の事件後、潮出版社から『疑惑の航跡』を出版した時、「朝日新聞」の書評欄でこの本は大きく取り上げられた。その際、この本を読んだ彼女が、「心理状態の細かい部分までよく書けている」と褒めていたと潮出版社編集部の南普三氏が伝えてくれたことがある。悲歎のどん底に沈んでいた私は、作家から褒められたことが有難く、生きていくためのささやかなこころの支えになった。彼女は、2011年に、東京都武蔵野市の自宅で亡くなった。72歳であった。墓は16区1側3番にある。
映画俳優・監督としてよく知られた佐分利信(1909-1982)の墓も小平霊園にある。2区17側15番である。彼は、北海道歌志内市出身で、昭和6年(1931)に俳優デビューした。松竹時代は上原謙、佐野周二とともに“松竹三羽烏”と呼ばれ、渋い二枚目として活躍した。
『戸田家の兄妹』(1941)、『嫉妬』(1949)、『自由学校』(1951)、『お茶漬の味』(1952)、『彼岸花』(1958)、『華麗なる一族』(1974)、『砂の器』(1974)、獄門島(1977年)などに出演している。俳優としてだけでなく、映画監督としても『女性対男性
』、『慟哭』、『叛乱』などで高い評価を受けていた。本名は石崎由雄である。
そのほか、小平霊園には文芸評論家であった荒正人(1913-1979)の墓が16区2側7番にある。『漱石研究年表』で毎日芸術賞を受賞したが、法政大学文学部英文学科教授在任中に死去した。戒名は、芳文院紫陽正人居士である。香川県出身の文芸評論家・十返
肇(1914-1963)は、『文壇と文学』(東方社刊)刊行以来、文壇に関する著書を数多く発表したが、舌癌で死去した。墓は41区2側1番にある。歴史、民俗学の学者として、私もその著書で親しんでいた和歌森太郎(1915-1977)は、1976年から逝去するまで、都留文科大学学長であった。墓は12区20側32番である。政治学者でお茶の水女子大学長なども務めた蝋山政道(1895-1980)は、民主社会主義の提唱者であり、行政学研究の先駆的存在であったが、急性心不全で死去した。墓は16区20側21番にある。経済学者で東京大学名誉教授、法政大学総長であった有澤廣巳(1896-1988)の墓は、32区13側22番にある。統計学が専門で、1981年に文化功労者に選ばれた。
さらに、実業家で電源開発初代総裁であった高碕達之助(1885-1964)の墓は39区1側8番にある。通商産業大臣、初代経済企画庁長官などを歴任した。千葉県出身の政治家、社会運動家の河野密(1897-1981)の墓も、23区1側16にある。東京大学卒業後、日本労農党に参加。更に社会大衆党へ移って、1936年の第19回衆議院議員総選挙で初当選して以来、12回当選したが、1972年の第33回衆議院議員総選挙で落選してからは、そのまま政界を引退した。
以上、私にとっても親しい名前の人々の墓が、小平霊園にある。「千の風になって」に歌われているように、これらの人々は、私の家族をも含めて、小平霊園に眠っているわけではないであろう。遺骨がここに収められているだけである。しかし、遺族にとっては、ここが地上での霊界への大切な接点であり祈りの場である。墓前に額ずいて、故人を偲び、こころからの対話を試みる。私もいままでそうしてきた。そう遠くない将来、私もこの小平霊園の墓地に入ることになるが、霊界では、やがて、私の家族以外のこれらの人々とも、逢うことがあるかもしれない。私はその時、小平霊園という、いわば地上での「同村の誼」で、生前いろいろと間接的ではあっても導かれてきたことを改めて感謝し、懐かしみを込めて新参者の挨拶をすることになるであろうと考えている。
(2017.06.01)
イエスとキリスト教についての真実 (資料) (身辺雑記 No.113)
よく知られているように、ヨハネの福音書(5:24)には、「わたしの言葉を聞いて、わたしをつかわされたかたを信じる者は、永遠の生命を受け、またさばかれることがなく、死から命に移っているのである」と、書かれている。それに対して、シルバー・バーチは「それは間違いです」と断じている。「人間は一人の例外もなく死後も生き続ける」のが霊的真理だからである。人間は、「何かの教義や信条、あるいはドグマを信じることによって永遠の生命を授かるのではなく、不変の自然法則によって生き続けるのです。それ自体は宗教とは何の関係もありません。因果律と同じ一つの法則なのです」とシルバー・バーチは言う。そのうえで、こう続けた。「この文句は地上に大きな混乱のタネを蒔き人類を分裂させてきた言葉の一つです。一冊の書物、それも宗教の書、聖なる書が、普通の書が起こそうにも起こせないほどの流血の原因となってきたということは、何という酷い矛盾でしょうか。宗教の目的は人類を不変の霊的関係による同胞性において一体ならしめることにあるはずです。」(シルバー・バーチの霊訓 (10)』潮文社、1988、pp. 182-183)
シルバー・バーチは、このように、現在のキリスト教に批判的であり、聖書の教えは、イエスの本来の教えからしばしば逸脱してしまっていることを幾度も指摘している。何故こうなってしまったのか。シルバー・バーチによれば、聖書の原典は、あのバチカン宮殿に仕舞い込まれて以来一度も外に出されたことがないらしい。「あなた方がバイブルと呼んでいるものは、その原典の写しの写しの、そのまた写しなのです。おまけに原典にないものまでいろいろと書き加えられております。初期のキリスト教徒はイエスが遠からず再臨するものと信じて、イエスの地上生活のことは細かく記録しなかったのです。ところが、いつになっても再臨しないので、ついにあきらめて記憶をたどりながら書きました。イエス曰く・・・・と書いてあっても、実際にそう言ったかどうかは書いた本人も確かでなかったのです」と、シルバー・バーチは言っている。(「霊訓(5)」p.184)
いうまでもなく、キリスト教は現代社会では最大の宗教で、イスラム教、仏教とともに世界宗教とよばれ、人種や民族、文化圏の枠を超え広範な人々に広まっている。その信者の数は世界中で約20億人以上ともいわれている。特に近代文明の中心であった欧米社会は、キリスト教文化に強く彩られているだけに、キリスト教は世界中に、宗教界のみならず、社会的、政治的にも強い影響を及ぼしてきた。そのキリスト教が、批判されるようなことがあれば、当然、それに対する反発も強くなる。スピリチュアリズムが、キリスト教会から白眼視されるのもそのためであろう。
しかし、現在のキリスト教を批判しているシルバー・バーチは、おそらく20億人のキリスト教信者の誰よりも、イエスの教えとイエス自身に近いところに存在している。ロンドンでの交霊会に出ていた頃でも、シルバー・バーチは、毎年2度、クリスマス(冬至)とイースター(夏至)に、この地上から引き上げて、イエスが主催される大集会に参列し、イエスに何度も直接に逢ったりしていた。(「霊訓 (11)」p. 96) イエスを最もよく知っているそのシルバー・バーチのことばに耳を傾けることは、それゆえに、キリスト教信者であるなしに関わらず、聖書に関心のある者にとっては充分に意味のあることといえるであろう。
本稿では、真実のイエスの姿を教えようとするシルバー・バーチのことばをいくつかまとめていきたい。霊的真理は一つであるはずだから、そのことを確認していくためにも、このような資料の検討は蔑ろにはできない。そのシルバー・バーチのことばの基本的なものを抜き出して資料Aとする。また、『霊訓』第5巻、11章のキリスト教牧師との論争で、牧師が「神は地球人類を愛するがゆえに唯一の息子を授けたのです」と言ったのに対して、シルバー・バーチは「イエスはそんなことは言っておりません。イエスの死後何年も経ってから、例のニケーア会議でそんなことが聖書に書き加えられたのです」と答えているように、西暦325年に開かれた「ニケーア会議」が聖書を歪めてきた主体として極めて重要である。そのニケーア会議を資料Bとして、記録の一端にも触れていくことにしたい。さらに、「処女懐胎」として言い伝えられているイエスの誕生の真実を取り上げた一つの文献を資料Cとして付け加えておくことにする。
資料A シルバー・バーチのことば
A-1(イエスの教えとスピリチュアリズムについて)
この問題の取り扱いには私もいささか慎重にならざるを得ません。なるべくなら人の心を傷つけたり気を悪くさせたくはないからです。が、私の知るかぎりを、そして又、私が代表している霊団が理解しているかぎりの真実を有りのままを述べましょう。それにはまずイエスにまつわる数多くの間違った伝説を排除しなければなりません。それがあまりに永いあいだ事実とごたまぜにされてきたために、真実と虚偽の見分けがつかなくなっているのです。
まず歴史的事実から申しましょう。インスピレーションというものはいつの時代にも変わらぬ顕と幽とをつなぐ通路です。人類の自我意識が芽生え成長しはじめた頭初から、人類の宿命の成就へ向けて大衆を指導する者へインスピレーションの形で指導と援助が届けられて来ました。地上の歴史には予言者、聖人、指導者、先駆者、改革者、夢想家、賢者等々と呼ばれる大人物が数多く存在しますが、そのすべてが、内在する霊的な天賦の才能を活用していたのです。それによってそれぞれの時代に不滅の光輝を付加してきました。霊の威力に反応して精神的高揚を体験し、その人を通じて無限の宝庫からの叡知が地上へ注がれたのです。
その一連の系譜の中の最後を飾ったのがイエスと呼ばれた人物です。(第一巻の解説"霊的啓示の系譜″参照)ユダヤ人を両親として生まれ、天賦の霊能に素朴な弁舌を兼ね具え、ユダヤの大衆の中で使命を成就することによって人類の永い歴史に不減の金字塔を残しました。地上の人間はイエスの真実の使命についてはほとんど知りません。わずかながら伝えられている記録も汚染されています。数々の出来事も、ありのままに記述されておりません。増え続けるイエスの信奉者を権力者の都合のよい方へ誘導するために、教会や国家の政策上の必要性に合わせた捏造と改ざんが施され、神話と民話を適当に取り入れることをしました。イエスは(神ではなく)人間でした。物理的心霊現象を支配している霊的法則に精通した大霊能者でした。今日でいう精神的心霊現象にも精通していました。イエスには使命がありました。それは当時の民衆が陥っていた物質中心の生き方の間違いを説き、真理と悟りを求める生活へ立ち戻らせ、霊的法則の存在を教え、自己に内在する永遠の霊的資質についての理解を深めさせることでした。
では "バイブルの記録はどの程度まで真実なのか″とお聞きになることでしょう。福音書(マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの四書)の中には真実の記述もあるにはあります。たとえばイエスがパレスチナで生活したのは本当です。低い階級の家に生まれた名もなき青年が聖霊の力ゆえに威厳をもって訓えを説いたことも事実です。病人を霊的に治癒したことも事実です。心の邪な人間に取りついていた憑依霊を追い出した話も本当です。しかし同時に、そうしたことがすべて霊的自然法則に従って行われたものであることも事実です。自然法則を無視して発生したものは一つもありません。なんびといえども自然法則から逸脱することは絶対にできないからです。イエスは当時の聖職者階級から自分たちと取って代ることを企む者、職権を犯す者、社会の権威をないがしろにし、悪魔の声としか思えない教説を説く者として敵視される身となりました。そして彼らの奸計によってご存知の通りの最期を遂げ、天界へ帰ったあとすぐに物質化して姿を現わし、伝道中から見せていたのと同じ霊的法則を証明してみせました。臆病にして小胆な弟子たちは、ついに死んでしまったと思っていた師の蘇りを見て勇気を新たにしました。そのあとはご承知の通りです。一時はイエスの説いた真理が広がり始めますが、またぞろ聖職権を振り回す者たちによってその真理が虚偽の下敷きとなって埋もれてしまいました。
その後、霊の威力は散発的に顕現するだけとなりました。イエスの説いた真理はほぼ完全に埋もれてしまい、古い神話と民話が混入し、その中から、のちに二千年近くにわたって説かれる新しいキリスト教が生まれました。それはもはやイエスの教えではありません。その背後にはイエスが伝道中に見せた霊の威力はありません。主教たちは病気治療をしません。肉親を失った者を慰める言葉を知りません。憑依霊を除霊する霊能を持ち合わせません。彼らはもはや霊の道具ではないのです。
さて、以上、いたって大ざっぱながら、キリスト教誕生の経緯を述べたのは、イエス・キリストを私がどう位置づけるかというご質問にお答えする上で必要だったからです。ある人は神と同じ位に置き、神とはすなわちイエス・キリストであると主張します。それは宇宙の創造主、大自然を生んだ人間の想像を絶するエネルギーと、二千年前にパレスチナで三十年ばかりの短い生涯を送った一人の人間とを区別しないことになり、これは明らかに間違いです。相も変わらず古い民話や太古からの神話を御生大事にしている人の考えです。
ではイエスをどう評価すべきか。人間としての生き方の偉大な模範、偉大な師、人間でありながら神の如き存在、ということです。霊の威力を見せつけると同時に人生の大原則---愛と親切と奉仕という基本原則を強調しました。それはいつの時代にも神の使徒によって強調されてきていることです。もしもイエスを神に祭り上げ、近づき難き存在とし、イエスの為せる業は実は人間ではなく神がやったのだということにしてしまえば、それはイエスの使命そのものを全面的に否定することであり、結局はイエス自身への不忠を働くことになります。イエスの遺した偉大な徳、偉大な教訓は、人間としての模範的な生きざまです。
私たち霊界の者から見ればイエスは、地上人類の指導者のながい霊的系譜の最後を飾る人物---それまでのどの霊覚者にもまして大きな霊の威力を顕現させた人物です。だからと言って私どもはイエスという人物を崇拝の対称とするつもりはありません。イエスが地上に遺した功績を誇りに思うだけです。イエスはその後も私たちの世界に存在し続けております。イエス直じきの激励にあずかることもあります。ナザレのイエスが手がけた仕事の延長ともいうべきこの(ズピリチュアリズムの名のもとの)大事業の総指揮に当っておられるのが他ならぬイエスであることも知っております。そして当時のイエスと同じように、同種の精神構造の人間からの敵対行為に遭遇しております。しかしスピリチュアリズムは証明可能な真理に立脚している以上、きっと成功するでしょうし、またぜひとも成功させなければなりません。イエス・キリストを真実の視点で捉えなくてはいけません。すなわちイエスも一人間であり、霊の道具であり、神の僕であったということです。あなた方もイエスの為せる業のすべてを、あるいはそれ以上のことを、為そうと思えば為せるのです。そうすることによって真理の光と悟りの道へ人類を導いて来た幾多の霊格者と同じ霊力を発揮することになるのです。(「霊訓(3)」pp.100-105)
A-2(人間イエスとイエス・キリストはどう違うのか)
ナザレのイエスは地上へ降誕した一連の予言者ないし霊的指導者の系譜の最後を飾る人物でした。そのイエスにおいて霊の力が空前絶後の顕現をしたのでした。
イエスの誕生には何のミステリーもありません。その死にも何のミステリーもありません。他のすべての人間と変らぬ一人の人間であり、大自然の法則にしたがってこの物質の世界にやって来て、そして去って行きました。が、イエスの時代ほど霊界からのインスピレーションが地上に流入したことは前にも後にもありません。イエスには使命がありました。それは、当時のユダヤ教の教義や儀式や慣習、あるいは神話や伝説の瓦れきの下敷きとなっていた基本的な真理のいくつかを掘り起こすことでした。
そのために彼はまず自分へ注目を惹くことをしました。片腕となってくれる一団の弟子を選んだあと、持ちまえの霊的能力を駆使して心霊現象を起こしてみせました。イエスは霊能者だったのです。今日の霊能者が使っているのとまったく同じ霊的能力を駆使したのです。彼は一度たりともそれを邪なことに使ったことはありませんでした。
またその心霊能力は法則どおりに活用されました。奇跡も、法則の停止も廃止も干渉もありませんでした。心霊法則にのっとって演出されていたのです。そうした現象が人々の関心を惹くようになりました。そこでイエスは、人間が地球という惑星上で生きてきた全世紀を通じて数々の霊覚者が説いてきたのと同じ、単純で永遠に不変で基本的な霊の真理を説くことを始めたのです。
それから後のことはよく知られている通りです。世襲と伝統を守ろうとする一派の憤怒と不快を買うことになりました。が、ここでぜひともご注意申し上げておきたいのは、イエスに関する乏しい記録に大へんな改ざんがなされていることです。ずいぶん多くのことが書き加えられています。ですから聖書に書かれていることにはマユツバものが多いということです。出来すぎた話はぜんぶ割り引いて読まれて結構です。実際とは違うのですから。
もう一つのご質問のことですが、ナザレのイエスと同じ霊、同じ存在が今なお地上に働きかけているのです。死後いっそう開発された霊力を駆使して、愛する人類のために働いておられるのです。イエスは神ではありません。全生命を創造し人類にその神性を賦与した宇宙の大霊そのものではありません。
いくら立派な位であっても、本来まったく関係のない位にイエスを祭り上げることは、イエスに忠義を尽くすゆえんではありません。父なる神の右に座しているとか、“イエス”と“大霊”とは同一義であって置きかえられるものであるなどと主張しても、イエスは少しも喜ばれません。
イエスを信仰の対象とする必要はないのです。イエスの前にヒザを折り平身低頭して仕える必要はないのです。それよりもイエスの生涯を人間の生き方の手本として、さらにそれ以上のことをするように努力することです。(「霊訓(9)」pp.138-140)
A-3 (イエスの教えと間違いを犯している信奉者を混同してはならない)
愛を最高のものとした教えは立派です。それに異議を唱える人間はおりません。愛を最高のものとして位置づけ、ゆえに愛はかならず勝つと説いたイエスは、今日の指導者が説いている霊的真理と同じことを説いていたことになります。教えそのものと、その教えを取り違えしかもその熱烈信仰によってかえってイエスを何度もはりつけにするような間違いを犯している信奉者とを混同しないようにしなければなりません。
イエスの生涯をみて私はそこに、物質界の人間として最高の人生を送ったという意味での完全な人間ではなくて、霊力との調和が完全で、かりそめにも利己的な目的のためにそれを利用することがなかった---自分を地上に派遣した神の意志に背くようなことは絶対にしなかった、という意味での完全な人間を見るのです。イエスは一度たりとも自ら課した使命を汚すようなことはしませんでした。強力な霊力を利己的な目的に使用しようとしたことは一度もありませんでした。霊的摂理に完全にのっとった生涯を送りました。
どうもうまく説明できないのですが、イエスも生を受けた時代とその環境に合わせた生活を送らねばならなかったのです。その意味で完全では有り得なかったと言っているのです。そうでなかったら、自分よりもっと立派なそして大きな仕事ができる時代が来ると述べた意味がなくなります。
イエスという人物を指さして“ごらんなさい。霊力が豊かに発現した時はあれほどのことが出来るのですよ”と言える、そういう人間だったと考えればいいのです。信奉者の誰もが見習うことのできる手本なのです。しかもそのイエスは私たちの世界においても、私の知るかぎりでの最高の霊格を具えた霊であり、自分を映す鏡としてイエスに代わる者はいないと私は考えております。
私がこうしてイエスについて語る時、私はいつも“イエス崇拝”を煽ることにならなければよいがという思いがあります。それは私が“指導霊崇拝”に警告を発しているのと同じ理由からです(8巻p.18参照)。あなたは為すべき用事があってこの地上にいるのです。みんな永遠の行進を続ける永遠の巡礼者です。その巡礼に必要な身支度は理性と常識と知性をもって行わないといけません。書物からも得られますし、伝記からでも学べます。ですから、他人が良いと言ったから、賢明だと言ったから、あるいは聖なる教えだからということではなく、自分の旅にとって有益であると自分で判断したものを選ぶべきなのです。それがあなたにとって唯一採用すべき判断基準です。
たとえその後一段と明るい知識に照らし出された時にあっさり打ち棄てられるかも知れなくても、今の時点でこれだと思うものを採用すべきです。たった一冊の本、一人の師、一人の指導霊ないしは支配霊に盲従すべきではありません。
私とて決して無限の叡智の所有者ではありません。霊の世界のことを私が一手販売しているわけではありません。地上世界のために仕事をしている他の大勢の霊の一人にすぎません。私は完全であるとか絶対に間違ったことは言わないなどとは申しません。あなた方と同様、私もいたって人間的な存在です。私はただ皆さんより人生の道のほんの二、三歩先を歩んでいるというだけのことです。その二、三歩が私に少しばかり広い視野を与えてくれたので、こうして後戻りしてきて、もしも私の言うことを聞く意志がおありなら、その新しい地平線を私といっしょに眺めませんかとお誘いしているわけです。(「霊訓(9)」pp.144-147)
A-4 (イエスも人間として立腹したことがあった)
(イエスが両替商人を教会堂から追い出した話を持ち出して)私が言いたかったのはそのことです。あの時イエスは教会堂という神聖な場所を汚す者どもに腹を立てたのです。ムチをもって追い払ったのです。それは怒りそのものでした。それが良いとか悪いとかは別の問題です。イエスは怒ったのです。怒るということは人間的感情です。私が言いたいのは、イエスも人間的感情をそなえていたということです。イエスを人間の模範として仰ぐとき、イエスもまた一個の人間であった----ただ普通の人間より神の心をより多く体現した人だった、というふうに考えることが大切です。
・・・・・ 誰の手も届かないところに祭りあげたらイエスさまがよろこばれると思うのは大間違いです。イエスもやはりわれわれと同じ人の子だったと見る方がよほどよろこばれるはずです。自分だけ超然とした位置に留まることはイエスはよろこばれません。人類とともによろこび、ともに苦しむことを望まれます。一つの生き方の手本を示しておられるのです。イエスが行ったことは誰にでもできることばかりなのです。誰もついていけないような人物だったら、せっかく地上へ降りたことが無駄だったことになります。(霊訓(5)pp.193-194)
A-5 (キリスト教の「回心の教義」をどう思うか)
よくご存知のはずの文句をあなた方の本から引用しましょう。〃たとえ全世界を得ようと己れの魂を失わば何の益かあらん〃(マルコ8-36) 〃まず神の国とその義を求めよ。しからばこれらのものすべて汝らのものとならん″(マタイ6-33)この文句はあなた方はよくご存知ですが、はたして理解していらっしゃるでしょうか。それが真実であること、本当にそうなること、それが神の摂理であることを悟っていらっしゃいますか。〃神を侮るべからず。己れの蒔きしものは己れが刈り取るべし″(ガラテア6-7) これもよくご存知でしょう。
神の摂理は絶対にごまかせません。傍若無人の人生を送った人間が死に際の改心でいっぺんに立派な霊になれるとお思いですか。魂の奥深くまで染み込んだ汚れが、それくらいのことで一度に洗い落せると思われますか。無欲と滅私の奉仕的生活を送ってきた人間と、わがままで心の修養を一切おろそかにしてきた人間とを同列に並べて論じられるとお考えですか。“すみませんでした”の一言ですべてが赦されるとしたら、はたして神は公正であるといえるでしょうか。(「霊訓(5)」p.199)
A-6 (キリストの赦しを受け容れることが愛の施しにはならないか)
神は人間に理性という神性の一部を植えつけられました。あなた方もぜひその理性を使用していただきたい。大きな過ちを犯し、それを神妙に告白する----それは心の安らぎにはなるかも知れませんが、罪を犯したという事実そのものはいささかも変りません。神の理法に照らしてその歪みを正すまでは、罪は相変わらず罪として残っております。いいですか、それが神の摂理なのです。イエスが言ったとおっしゃる言葉を聖書からいくら引用しても、その摂理は絶対に変えることはできないのです。
前にも言ったことですが、聖書に書かれている言葉を全部イエスが実際に言ったとはかぎらないのです。そのうちの多くはのちの人が書き加えたものなのです。イエスがこうおっしゃったとあなた方が言う時、それは
“そう言ったと思う”という程度のものでしかありません。そんないい加減なことをするよりも、あの二千年前のイエスを導いてあれほどの偉大な人物にしたのと同じ霊、同じインスピレーション、同じエネルギーが、二千年後の今の世にも働いていることを知ってほしいのです。
あなた自身も神の一部なのです。その神の温かき愛、深遠なる叡智、無限なる知識、崇高なる真理がいつもあなたを待ち受けている。なにも、神を求めて二千年前まも遡ることはないのです。今ここに在しますのです。二千年前とまったく同じ神が今ここに在しますのです。その神の真理とエネルギーの通路となるべき人物(霊媒・霊能者)は今もけっして多くはありません。しかし何ゆえにあなた方キリスト者は二千年前のたった一人の霊能者にばかりすがろうとなさるのです。なぜそんな昔のインスピレーションだけを大切になさるのです。なぜイエス一人の言ったことに戻ろうとなさるのです。(「霊訓(5)」pp.203-204)
資料B ニケーア会議について
ニケーア(ニカイアとも表記)は小アジア西部の地名で、現在はトルコ領の小都市イスニックである。この会議は、325年、コンスタンティヌス帝が主催したキリスト教教義を決する最高会議で、一般に宗教会議とも言われるが、公会議と呼ばれることもある。これ以後、この会議は何度も開催されてきた。
その前年の324年、コンスタンティヌス帝は自らキリスト教徒であることを宣言、翌325年にニケーアに約300人の司教を集め、コンスタンティヌス帝自ら黄金の椅子に座り議長を努めた。ここでは、イエスの神性を否定するアリウス派と、イエスの神性を認めるアタナシウス派の両派が激しく論争を展開した。
2世紀以降、キリスト教の教義が確立されていく中で、キリスト論や三位一体論の解釈においてさまざまな立場が現れたが、その中で正統的でないとみなされたものを支持するものもおり、彼らは異端とみなされて排斥された。このような場合、ある思想が正統か異端かということを判断する場合、主教(司教)一人の手におえなければニカイア公会議以前ではそれぞれの地方教会において会議を開いて解決するのが一般的になっていた。
しかし、3世紀にアリウス派の思想が論議になるにいたって、地域の主教(司教)や地方教会会議だけでは解決が難しい事態となった。これは放置すればキリスト教の分裂を招きかねず、当時キリスト教をローマ帝国の民心統一に利用しようと考えていたローマ皇帝コンスタンティヌス1世にとっても頭の痛い問題だった。ここにおいて皇帝の指導と庇護の下に初めて全教会の代表者を集めて会議が開かれることになったのである。
会議は一連の問題の議決およびアリウスとその一派の追放を決定して閉会した。しかし、この後も政治的な意図と神学論争を含んだ争いによって一度はアリウスの名誉回復がおこなわれ、アタナシオスたちが弾劾されるなど状況は二転三転、三位一体論争の解決にはなお多くの時間がかかることになる。見過ごすことができないのは、この公会議で、コンスタンティヌスに都合のいいように、聖書にいろいろな改ざんが為されたことである。それを示す資料の一つとして、D.ダドレー『第一回ニケーア公会議の真相』(近藤千雄訳編)から、その一部を抜粋しておきたい。原著名は次のとおりである。
History of the First Council of Nice
A World’s Chiristian Convention in 325 A.D. (The 7th edition)
By Dean Duddley, attorney-at-law
Published
in 1925 by Peter Ecker Publishing Co., New York
B-1 ( 「序論」から)
英語のCouncil, Synod,Conventionはいずれも「会議」を意味する同義語である。有名な『ニケーア公会議』の前にもキリスト教界の会議はいくつも開かれているのであるが、それらはEcumenicalでなかった、つまり全キリスト教界的なものではなかった。多分、初期の頃は指折り数えるほどの教会から司教Bishopが出席するだけだったのが次第に影響力を伸ばし、代表する地域が広がっていったのであろう。
イエスの使徒たちが伝道していた時代においては、その使徒たちが司教を選んでいたが、やがてその使徒の門弟たちが選んだ上でその教区の信者たちの認可を得るようになった。さらに時代が進むと、広い教区の代表が集まって新しい司教を指名するようになったが、それでもやはり住民の認可が必要だった。それが『ニケーア公会議』において大きく改められた。その具体的内容は本文で扱うとして――
その『公会議』の経緯を見ていくことによって、われわれは当時のローマにおけるキリスト教界の特殊事情を垣間見ることになる。即ち、「大帝」と呼ばれたコンスタンティヌスConstantine
the Greatの存在が圧倒的な影響を及ぼしていたことである。残念なことに、見てくれも勇猛さにおいても大帝の称号に相応しかった男が、晩年にいたってライバルや血縁者に残虐非道の限りを尽くして、その歴史に拭いきれない汚点を残してしまった。
彼自身、洗礼の儀式を行なったくらいでその罪が洗い流され魂が清められると本気で信じたとは思えないが、彼の周りにはおべんちゃらの上手な取り巻き連中がいて、正義にかこつけてそういう教義をこしらえ、彼にひそむ醜悪きわまる人間性を操ったのである。
ただ彼も、臣下の者たちに自分が天国に行きたいという願望を持っていることを意思表示していたことは間違いない。というのは、大きな金貨の片面に部分的にヴェールのかかった自分の姿を刻ませ、裏面には自分が乗ったチヤリオツト[二ないし四頭立ての古代ローマの戦車]が天翔けり、それを受け止めようとする手が天上から差し出されている光景を刻ませているからである。
私は一六〇四年に英語に翻訳されロンドンで出版されたメヒーアMexiaというスペイン人の書物を読んで、著者がコンスタンティヌスの生涯についての叙述の最後の部分で妙なことを言っているのに興味を抱いた。それは、彼の姿格好が悪逆非道の行為と似つかわしくないと述べている部分で、しかし「それらの行為は過ってはいなかったのであろう」と
一転して弁護し、なぜならば聖ヒエロニムスSt.Jerome[五世紀初頭のキリスト教を代表する修道士でラテン語聖書の完成者]を初めとする聖人や教皇が彼のことを立派なクリスチャンであり永遠なる至福の継承者であると明言しているから、と述べているのである。
近代のプロテスタント系の書物での評価はそんな甘いものではない。アリウス派Arians[四世紀のアレキサンドリアの神学者Ariusの一派で“三位一体説”を否定した。そもそも「ニケーア公会議」の目的は“三位一体説”を論ずることにあった]の書物が一冊も存在しないのは一体なぜなのか?“三位一体論者”たちが一冊残らず焼き棄ててしまったのである。
当時は、キリスト教の慣例として異端の信者は懲らしめ、異端の書物は焼き棄てていた。政治制度の大きな側面を担うものとしては、当時の宗教はまだまだ幼稚なもので、為政者がその戒律その他を好きなように改めていた。その目的は自分たちの見栄と欲望を満たすことでしかなく、しかもそれが「イエス・キリスト」の名のもとに行なわれた。もしイエス自身がその場にいれば、恥ずかしくかつ嘆かわしい思いをしたことであろう。
《復活祭》Easter Festivalも本来ならユダヤ教の最大の祝日である《過ぎ越しの祭》Passoverの日にするのが最もふさわしいはずであったが、これもコンスタンティヌスの気まぐれな思いつきで変更された。彼は神がユダヤ民族を最も愛されたというユダヤの言い伝えを認めざるを得ない立場に追い込まれながらも、それまでローマが嫌い迫害してきたユダヤ民族そのものへの嫌悪感が捨てきれなかったのである。
《安息日》Sabbathの変更も同じく理不尽な偏見からだった。ユダヤ人にとっては土曜日が安息日であり、ローマ人のキリスト教徒にとってもそれで何の不都合もなかったのであるが、日曜日が聖なる日だと言い張って、それ以外は頑として許さなかった。イエス自身も日曜日が聖なる日だとは言っていない。
その日曜日の祈りをする時に膝を折ることを禁じている戒律もある。スタンレー博士Dr.A.P.Stanleyによると、これはイエスの使徒たちが説教しながら立ったまま祈ったからだと言う。しかし私は、ひざまずくということは卑下することであるという考えから、勝利と喜びの日である日曜日にひざまずくことを禁じたのではないかと推察している。
キリストが死者から甦って死と地獄に打ち勝った日は日曜日だったと信じられている。となると、ひざまずくことは敵に屈することであるから、祈る時に膝を屈することはふさわしくないとされたのであろう。ちなみに、ニケーアにおける会議で祈りの儀式がいっさい行なわれなかったのも不思議である。
さらには去勢された者が司教の職につくことを禁じた戒律もある。かつては男性としての機能を削ぎ落とすことが宗教性を高揚すると見なされた時代があったのである。そうした愚かさを止めさせるためには、司教職を剥奪するという、さらに強硬な手段に訴えたのである。
コンスタンティヌスは証聖者(迫害に屈しないで信仰を守った者)や禁欲に徹する修道士には最大限の敬意を表し、拷問で受けた傷痕に口づけをすることで神の資質を授かると信じていた。多分これは敬虔な司教たちの心をつかむ意図もあったと思われるが、コンスタンティヌスが言い出す教義のウラには必ず狡猾な打算があった。修道士、修道女、隠遁者、その他、人間的安楽や快楽を拒否した生活を送っている者を賞賛し、恩着せがましく保護した。ぼろを着て不潔な環境で動物のように草類を食べて生きるということが、初期のキリスト教の教父たちにとっては、もっとも神聖な生き方とされたのである。
キリストの生きざまに倣おうとすれば、およそそうした生き方は生まれて来ない。にもかかわらず、そうしたクリスチャンが殉教者とともに「列福者」(奇跡を行なった人)として賞賛されてきたのである。
「偉大にして聖なる会議」と呼ばれるニケーア会議において聖書の文句が一節でも朗読されたという記事が見られないのも不思議である。聖ヒエロニムスの記録によると、プロテスタントの外典とされている『ユデテ書Book
of Judith』がその公会議において真正なる書として承認されたことを教父たちから聞いたというのであるが、それ以外の初期の記録にはそういう記述は見られない。
歴史家がたびたび述べていることであるが、その当時の教父たちはいわゆる「聖典」の記述を今日とは違った解釈をしていたようで、例えばコンスタンティヌスはかの有名な『聖人に贈る式辞Oration
to the Saints』の中で「エデンの東」はどこかの別世界にあるかの表現をしており、テルトウリアヌスTertullianを始め、タティアノスTatian、アレキサンドリアのクレメンテClement、その弟子のオリゲネスOrigen、聖ヒエロニムス等々のキリスト教神学者も同じである。
三二五年の公会議で採択された新しい宗教の支持者に回ったギリシャの神学者の中にも、すぐにそれらしき文書を書いて有名な弟子や殉教者の名前を付し、掘り出し物でも発見したかのように装って提出した者がいたようである。その種の神学者の魂胆は軽蔑して余りあるものがあるが、いかにもそれらしき体裁をしているので真正なものとして認可されているものがあるのである。
例えば『ヘブル人への手紙The Epistle to the Hebrews』がその良い例で、パウロの署名が入ってはいるが、これはいわゆる『ロマ書The
Epistle of Paul to the Romans』 に倣って誰かが書いたもので、確かにパウロの思想が入ってはいても、これをパウロ自身が書いたと信じる専門家は今はいない。
『ヨハネ黙示録』も怪しい文書であり、四つの福音書についても、近代の聖書学者の研究によって原文にはなかったはずと断定されている箇所がいくつも指摘されている。例えば『ヨハネ福音書』の冒頭の文句、即ち「初めに言があった。言は神とともにあった。言は神であった」は用語も表現もプラトン哲学とそっくりであるが、ガリラヤの湖で兄のヤコブとともに漁師をしていたヨハネが、いくら学問好きだったとは言え、その一文で文書を書き始め、しかも、それが『ニケーア信条』の根幹をなす思想となっていることを弁護できる人がいるであろうか。
初期の時代に、真面目で信心深いクリスチャンの間でよく読まれた文書に『ハーマスの羊飼いShepherd of Hermas』というのがあったが、著者は不明で、読んでみるとなるほど敬虞な用語を用いているが、文章は稚拙である。
いわゆる『ニケーア信条』を支持した教父たちは、反対派の文書は詩文で書かれているから詩人が書いたものであり、したがって神の啓示ではないと論駁した。しかし、そうなると旧約聖書はほとんどが詩文で書かれているという事実をどう弁護するのであろうか。また、世界各地の宗教を見ても、太古の宗教的文献は大半が神聖な雰囲気をもった詩文で書かれている事実を見落としてはならないであろう。
私が思うに、宗教の根幹を占める信仰と憧れは一種独特の詩的テーマであって、決して科学的推論や歴史的事実から生まれたものではない。だからこそ誰にでも親しめるのである。もしも神学上の教理の論理的根拠や証拠を検討しなければならないとしたら、それができるほどの知的能力をそなえた者はまずいないであろう。
となると、必然的に信仰というものは、誰かが述べたことや実体験したことに基盤を置くことになる。詩文で書かれていても散文で書かれていても、それが代々の慣習であり先祖から受け継いだものであれば、その中に自分が良いと思うもの、あるいは自分にとって都合が良いものを見つけて、それを自分の信仰としていく傾向がある。「暗黒時代」と呼ばれたあの身の毛もよだつ悪逆非道の時代から引き継がれた信仰が、今日なお残っている事実がそれを雄弁に物語っている。
これを改め理不尽な教理をなくしていくのは科学の責任である。ハックスレーThomas HuxleyやティンダルJohn Tyndall(いずれも十九世紀末の英国の科学者)のような大学者が伝統の誤謬や教説の不条理を指摘しているのは当然のことである。
コンスタンティヌスは、知性の深さと洞察力においては“大帝”の名にふさわしい人物ではなく、ただ抜け目がなく、機を見るに敏で、何ごとにつけてエネルギッシュで、その上際限のない野心に駆られて行動したからこそ、彼よりも偉大な人物でも克服できなかったであろうほどの困難を凌いで行ったまでのことである。
彼は自然科学については基本的原理すら知らなかった。そこから生まれる軽信性と迷信性が、唯一、彼の邪悪な性向を抑制する働きをしていた。が、ある時期から“国の王”たる自分と“天の王”たる神とを同等に考えるようになり、勝手に法律をこしらえ、好きなように臣下を殺し、敵に対しては剣でも火でも使って徹底的に報復してよいと思い込むようになった。そして、勝てばそれは神が許したことの証しである――正しくなかったらその行為を許されなかったはずだ、という都合の良い論理で押し通した。
司教たちも彼におもねて勝手な教えを説いた。例えば神は「一人息子のイエスを人類の贖い主として地上へ送り十字架にかけられた。だから、国王たる者は国のためであれば我が子を犠牲にしてもよろしいのです、と。
こんな気違いじみた教えを真に受けたコンスタンティヌスは、その極悪性を感じぬまま数々の血なまぐさい犯罪を重ねていった。その性格と行為とが、彼みずからでっち上げたキリスト教に暗い影を落とすことになる。
『ニケーア公会議』は信仰というものを強制的に押しつけようとした政治的暴挙の最たるもので、これほど理不尽なやり方は、偉大なる知性に恵まれた人間のやったこととしては世界の歴史でも類を見ないものである。近代英国の知性を代表するミルJohn
Stuart Millは名著『自由論』の中でこう述べている。
キリスト教を容認した最初のローマ皇帝がマルクス・アウレリウスでなくコンスタンティヌスだったことは、世界のあらゆる歴史の中でも最大の悲劇の一つであろう。もしもそれがコンスタンティヌスの治世下ではなくマルクス・アウレリウスの治世下であったなら、世界のキリスト教はどれほど違ったものとなっていただろうかと思うと、胸の痛む思いがする。
イエス・キリストが永遠の煉獄という教理を説いたか否かは神学者の間でも疑問とされている。ローマ・カトリック教会では神話でいうシーオールSheol、タルタロスTarutarus、ハデスHades等に倣って地獄説を取り入れたが、この手法はその他の教理や形式や儀式についても同じであって、多くのものが古い宗教からの借用である。
イエスの説いていることを読む限りでは、日常生活で人のためになることを心がけた生き方こそ、神 Godへの真実の信仰の道であるように思えるのだが……
B-2 (「第1章 会議の目的と結末」から)
『ニケーア公会議』の最大の目的はイエスの神性と、物的宇宙を創造した根源的エネルギーとキリスト神との明確な関係を、堅固な基盤のもとに討議し決着をつけることにあった。というのは、いわゆる「アリウス論争the
Arian contoroversy」によって教会のみならず社会一般の人たちも思想・信仰に混乱をきたしていたからであるが、実はそれ以外にも教義や規律にもさまざまな問題点があった。その中でも重要だったのはメレティウス派Meletiansが打ち出した新しいドグマと、同じくノヴァティアヌス派Novatiansのドグマ、それに「過ぎ越しの祭」を祝う最も適切な日はいつかという問題もあったのである。
キリスト教学者のモスハイム博士 Dr. Mosheimによると、コンスタンティヌスはもともと宗教というものに無関心だったのが、紀元三一三年頃からキリスト教に好感を抱くようになった。それはどうやらエジプト人の司教―多分スペインのコルドバの司教ホシウスHosiusであろう―
がローマまでやって来て、皇帝にキリスト教を説いたから、というのが歴史家ゾシムスZosimusの推察である。
しかし皇帝自身は他の宗教も人類にとって有用なものと考えていた。なのに急に公会議を召集してキリスト教だけを公認し、在来の宗教をすべて廃棄するようにとの勅令を出した、その理由をみずから述べたのは、それから数年後、他界する少し前である。これについては英国国教会の前出のスタンレー神学博士が、的を射た決定的な観測を述べている。
それは、マクセンティウスMaxentiusを征服した頃に彼は家族や親族に対して身の毛もよだつ残虐行為を行ない、その事実をひた隠しにしようとしたが、世間に漏れていた。そんな時にパレスチナにいたコンスタンティヌスは、次のようなローマの奢侈と悪逆非道を揶揄した詩文が刻印されているのを見た。
サトゥルヌスの黄金時代を取り戻すのは一体だれか?
いま宝石で輝いてはいるが、またネロが支配するのか?
[サトウルヌスは黄金時代を支配したローマ神話の神]
これにショックを受けて沈み込んでいる大帝のもとに母親のヘレナを連れてホシウスが訪れ、キリスト教を信ずる者に許されないことは何もないのです、と説いて慰めたという。が、コンスタンティヌスが犯した罪悪でれっきとした証拠のあるものだけでも数かぎりないが、嫌疑のあるものや伝説的に伝えられているものを数え上げたらキリがない。そうした罪悪への死後の報いに恐れをなしたコンスタンティヌスはキリスト教を国教とすることを考え始める。
相談を持ちかけられた当時の有力な司教たちは、すでに政敵をことごとく制圧したコンスタンティヌスに取り入るために、大帝にとって都合の良い宗教思想や教義・信条をもっともらしくでっち上げ、それを発表し国教とするための公的会議を開催することにする。それが『ニケーア公会議』の開催にいたる真相である。
開かれた会議は、正確な日数は定かでないが、100日以上の日数を費やしながら、最後は強引な採決によって、最大の論的であるアリウス派を退けて、予定していた通りの目的を果たす。
しかし、時とともにアリウス派が再び息を吹き返し皇帝派を慌てさせる。が、アリウスを暗殺するなどの強引とも悪辣ともいえる手段で、ついにアリウス派をキリスト教界から抹殺してしまう。
かくして『ニケーア公会議』は“第一回”という由緒と、“総会”という公的性格とその華々しさ、それに討議の重厚さも加わって、キリスト教界に前例がないだけでなく、宗教の歴史にもこれに比肩しうるものはないであろう。
B-3 (「第3章 公会議を開催せざるを得なくなった要因」から)
シリア生まれのキリスト教史家で司祭でもあったセオドレットTheodoretによると、悪名高い暴君たち、即ちマクセンティウスMaxentius、マクシミンMaximin、リシニウスLiciniusが他界した後は、教会に対して猛威をふるった悪逆非道の嵐も収まった。教会への敵意の風も凪ぎ、静寂が訪れた。
それを推進したのが、ほかならぬコンスタンティヌスである。当時はまだ王子だった。人間によって召されたのではない、人間を通して召されたのでもない、神によって召された、まさしく「神の申し子」として最高の賞賛をもって迎えられた。
彼は偶像崇拝とそれへの生贅を禁じる法律を制定し、教会の設立を奨励した。その教区の役人の職にはキリスト教信者を任命し、司教には敬虔なる敬意を表するように命じ、侮辱するような行為を働いた者は死刑に処するとまで定めた。
一方、前皇帝たちが破壊した教会を建て直し、しかも、前より広くかつ豪華にした。教会関係の行事は晴れやかに、また賑々しく行なわれ、キリスト教反対派の行事は不人気で没落していった。偶像を祭った寺院は閉鎖され、他方、教会ではしばしば行事が催され、祝祭が行われるようになって行った。
ローマで暴君たちが悪逆無道をほしいままにしていた頃、アレクサンドリアはエジプトの首都であることは無論のこと、隣接するテーベやリビアの首都的な役割を果たしていて、その地域で宗教的にもっとも大きな影響力をもっていた教父はペテロPeterであったが、ローマの圧制はエジプトまで及び、ついに殉教した。
ペテロの跡を継いでアキラスAchillasが司祭となったが、あまり長続きせず、三二一年にはアレクサンドルAlexanderが司祭となった。このアレクサンドルはキリスト教神学の大の信奉者で、当時同じアレクサンドリア教会の所属でボーカリスBaucalisと呼ばれる教区の司祭だったアリウスと対立することになる。
アリウス神学の中心的存在だったアリウスは厳しい禁欲主義者で、神学についてのみならず人間的にも尊敬を集めていた。宗教史家のソクラテスはアリウス神学について次のように述べている。
アレクサンドリアのペテロが三一一年に殉教し、その跡を継いだのはアキラスであったが、さらにその跡を継いだのがアレクサンドルで、ある日、司教としての権限のもとに、問題のドグマである《三位一体説》を教会の長老を初めとする全司教の前で説いた。それは、多分、よほど哲学的な内容のものであったものと思われる。
その出席者の中にアリウスという名の司教がいた。同じ管区に所属しているので当然アレクサンドルの教説は三世紀のサベリウスSabelliusというリビア大司教の教説、即ち神性を帯びた存在は宇宙に一人しかいないという説に立脚したものとばかり思っていたので、その意外な変節に黙っていられなくなった。
アリウスはその点を指摘して痛烈に反駁した。彼はこう指摘した―「無始無終の存在である“父”なる存在によって生み出された“子”なる存在には“始まり”がある。となると、その“子”には“存在しなかった時”があることになる。従ってその“子”は“無”から生じたという理屈になる」
これはまったく新しい発想で、居合わせた若い司教たちに斬新な思考の糧を与え、それによって点火された小さな炎が瞬く間に大きく燃え上がることになる。
このアリウスという人物についてエピファニウスEpiphaniusはこう描写している。
目立って背の高い男で、太く長い眉毛をし、その風貌には禁欲生活から生まれる厳しさがあった。衣服にもそれが反映していて、チュニック[膝の上まで届く上着]には袖がなく、ベスト[下着]も普通の半分の長さしかなかった。が、話しぶりは穏やかで、聞く者に好感を与え魅了するものがあった。
アリウスはコンスタチノープルで急死している。西暦三三六年のことで、多分彼の存在を疎ましく思う一派の者によって毒殺されたとされている。彼の死を喜ぶ者が多かったという。
そもそも《三位一体論》はプラトンに発し、プラトン学派が引き継いで説いてきたもので、哲学的な要素をもつものである。これに引きかえ、アレクサンドルの説はあくまでもキリスト教という一宗教の教説にすぎない。しかも子が父と同等で、資質も同一であるというのは矛盾している―神の御子はあくまでも創造物であり、こしらえられたものであり、従って存在しなかった時があることになり、それが無始無終の絶対神と同一であるはずがないわけである。
アリウスはその矛盾を、他の誤った教義とともに、教会だけでなく、あらゆる集会や総会で説き、時には個人の家に出向いて説くこともあった。
これに手を焼いたアレクサンドルは、諌言と議論でアリウスの間違いを説得しようとしたが収まらず、ついに地位を利用した強権でアリウスを“不敬”のかどで告発し、司教の職から追放するという愚挙に出た。その時の言い訳として引用したのがマタイ伝のイエスの言葉 ―「もしも右目が罪を犯したならば、その目を抉り出して捨てるがよい」であった。
コンスタンチノープルの弁護士ソクラテスの記述によると、アレクサンドルはアリウスを罷免したのち、まずアレクサンドリアでの集会における司教との交流を禁じ、さらに三二一年には、エジプトとリビアの長老一〇〇人が出席する長老会への出席も禁じた。しかし、この集会では賛否両論が噴出して、かえって紛糾した。
B-4 (「第5章 エウセビウス宛てのアリウスの書簡」から)
エウセビウス殿へ
貴兄も支持してくださっている「イエス人間説」を否定せんとして、監督アレクサンドル司教からの不当な仕打ちに遭っているアリウスより、一筆啓上申し上げます。
私の父アンモニウスはこれからニコメディア[古代小アジア北西部の都市]へ向けて出発するところですが、あなたにくれぐれも宜しくとのことです。同時に私は、貴兄が神Godと主イエスとの関係のことで同志たちに対して抱いておられる心情に、深甚なる敬意を表するものです。アレクサンドル司教は我々に対する圧力を強めており、その仕打ちは酷いものです。我々も大いに難儀しているところです。
私に加担する者は無神論者として国外へ退去させられました。彼の説くところ、即ち、”父”は無限の過去から存在し、“御子”もまた無限の過去から存在している、という説に同調しないからです。“父”と“御子は同じである/“父”が創造されたものでないように、“御子”もまた創造されたものではない/常に存在し、いつから存在が始まったということがない/観念的にも時間的にも、神がイエスに先立って存在したわけではない/神とイエスは常に存在していたのである/それでいて、イエスは神から出でたのである、と。
ご兄弟のカエサレアのエウセビウス司教を初めとして、テオドティオスTheodotius、ポーリヌスPaulinus、アタナシオスAthanasius、グレゴリーGregory、イーティオスEtius、その他、東洋の司教のすべてが、神は御子に先立って存在していたとの説に賛同したために、大変な非難を受けております。フィロゴニウスPhilogonius、ヘラニカスHellanicus、それにマカリオスMacariusは、もともと自説というものを持たない無教養の連中で、アレクサンドルの説に賛同しております。
そのうちの一人は“御子”は“父”から吐き出された“ことば”であると言い、また一人は“父”から放たれた“光”であると言い、また、“父”と同じく“始まりのない存在”であると言います。我々に言わせれば聞くに値しない不敬この上ない説ですが、彼らに言わせれば我々の説こそ万死に値する冒涜だそうです。
我々の説は、“御子”は始まりのない存在ではない/が、いかなる意味においても、部分的にせよ、被創造物でもない/その存在はいかなる物質にも依存していない/が、固有の意志と意図をもって、完全なる神として、時を超越して存続してきた/肉体をまとって出現し、それでいて変わることのない唯一の存在である/存在を与えられる、あるいは創造されるといった次元の存在ではない/我々はそう主張し、そう信じ、そう説いてきたし、今もそう説いています。
この説が非難されるのは、“御子”には始まりがあるが、“父”には始まりがないとしている点です。我々への迫害は要するにその一点なのです。その存在をいかなる物質にも依存していないとする点も、彼らが非難するところです。イエスは神の一部ではないし、いかなる物質もまとっていないというのが我々の主張であり、それを不敬として彼らは我々に迫害を加えるのです。後は推して知るべしです。
資料C イエス誕生の真実について
イエスは神ではなく一人の人間であったということは、シルバー・バーチも何度も述べているが、そのような「イエス人間説」について書かれた一冊の本がある。フロリゼル・フォン・ロイター『イエス・キリスト――失われた物語』(近藤千雄訳、ハート出版、2002年)[Florizel von Reuter: The Master From Afar ; Psychic Press Ltd, London, 1973]である。
現著者のロイターは、ウイーン国立音楽院のバイオリン科教授を長年務めた人物である。イギリスやドイツでスピリチュアリズムについての講演を行ったりして、コナン・ドイルとも親交があった。彼には自動書記の能力があって、ある日、いつものように机に向かっていると、いわく言い難い衝動に駆られて鉛筆を握り、書き始めた、というよりは書かされたのがこの本である。物語が進むにつれて、彼は「通信霊」の存在も感じ取ることができるようになる。その霊は、イエスについてバイブルとは異なる実像を掲示する使命を帯びていることを霊感的に伝えてきたという。こうして、書き上げられてみると400ページにもなる物語になっていた、というのが本書である。ここでは、そのうちの一部、イエスの誕生にまつわる部分だけを引用しておきたい。
C (同書、第一幕[6]より)
マグダラの町近くにテントを張り終えた時、ペテロが安堵の気持をこう述べた。
「どうやらこれまでは神も我々に味方をしてくださってるようだ。ナザレの不穏分子に捕まらなかっただけでも、もっけの幸いと感謝しなくては……」
「ナザレの住民のすべてが先生を憎んでいるわけではあるまい。中には仲間たちの態度に疑問を抱いている者もいるだろうに……」とネーサンが言うと、イエスがしみじみと言う。
「そうとばかりも言えないのではないかと思っているところだ。ナザレの町から数百人もの赤子が虐殺されたのだ。私は心の底からナザレ人に詫びたい気持だ。ただ、私の両親のヨセフとマリアについての噂には誤解があるようだ。
ちょうど良い機会なので、私の生い立ちについて、その真実を隠すことなく二人に話しておこうと思う。エスターも長旅で疲れて寝てしまったようなので、都合が良い。私の悲しい身の上話は若いエスターにはきつ過ぎるかも知れないからね」
「先生が聞かせたいと思われるのであれば、私たちはどんなことでも聞かせていただきましょう。しかし、先生の胸の痛むことまでお話いただかなくても結構です」
「いや、私は率直に話したいのだ。母に何一つやましいことがないことが分かっていただけるので、なおのことすべてを語らせてもらいたのだ」そう言ってイエスは真剣なまなざしで語りはじめた。
「母はナザレ近郊の羊飼いの娘だった。十三歳になろうとする頃に、酪農家のお手伝いとしてナザレの町へ働きに出かけるようになった。仕事といっても朝と夕方に村はずれの井戸から水を汲んでくるような、ラクなものだったらしい。母が私の実の父と出会ったのは、その井戸のところだったのだ」
「実のお父さん? ヨセフですか?」と、ヤイロがけげんな顔で聞く。
「違うのだ。ヨセフは義理の父親なのだ。本当の父親はユダヤ人ではない。カナンで生まれたのは事実だが、両親はヒッタイト[紀元前十九~十二世紀に大帝国を築いた小アジアの古代民族]の末裔で、よそ者だった。
父が成人に達した頃はヒッタイトもすでにローマの支配下にあった。名をハンデラといい、召し使いとしてローマ兵に仕えていて、そのローマ兵の任地がナザレになったことに伴い、父もナザレへやって来た。そこで母を見初めたわけだ。
井戸は昔から多くの者が集う場所だ。母はその中でも朝いちばんに水を汲みに来たらしいが、ある日からハンサムな若者を見かけるようになる。父も朝いちばんの仕事が水汲みだったらしい。聞くところによると、母は今でも大変な美人らしいから、当時はよほどの美少女だったのだろう。一週間あまりも毎日のように顔を合わせているうちに互いに恋心が芽生え、好き合うようになった。
この初恋は母にとっては神聖と言えるほど清らかな思い出だったらしく、自分の口からは一度も聞かされたことはなかった。いま話したことはすべて義理の父であるヨセフが、私が理解できる年齢になってから語ってくれたことだ。こんな美しい話があるだろうか? が、これが思いもよらない方向へ発展してしまう。父の主人であるローマ兵が本国への帰還を命ぜられたのだ。
父の身分は、奴隷のように拘束はされていなかったが、常に主人と行動を共にしなければならない。ということはローマへ行かなければならないわけだ。が、恋人を連れて行くなどということはとんでもないことで、そこで別れたら永久の別れとなることは明らかだった。そこで二人は脱走を考えた。
いま私は“脱走”という言い方をしたが、いわれもなく拘束された者が自由を求めても、それは脱走ではないと思う。しかし、ローマの側に言わせれば文句なしに脱走だ。許し難い脱走だ。ハンデラがいつになっても姿を見せないので、ローマ兵は一人で本国へ帰ってその旨を報告する。本部はこれに追随する者が出ることを恐れて、さっそく騎馬隊をナザレに送って徹底した捜索を始める。
その時父は、母とともに母の実家に逃げ込んでいた。母の両親は二人から事情を聞かされその愛が真実のものであることを確認すると、親しくしているラビ[ユダヤ教の聖職者]を呼んで形ばかりの結婚式を執り行なってもらい、ハンデラではその夜のうちにエジプトへ向かわせ、ほとぼりが冷めた頃を見計らってマリアに跡を追わせることにした。その夜二人は初めて結ばれたのだった。
しかし、悲劇が待っていた。真夜中に出立した父は、エジプトとの国境線を越えようとしているところをローマ兵に発見されて取っ組み合いとなり、奪った刀がそのローマ兵に刺さってしまった。多勢に無勢で逮捕された父は本部に連行され、脱走と殺人の罪で礫刑に処せられ、見せしめのために、その事実を書いた立て札がユダヤ全土に立てられた。
それを見た母が何と書いてあるのかを通りかかった人に尋ねてその事実を知り、その場に卒倒した。初め村人たちは刑のむごさに気を失ったものと思ったらしいが、その後すべての事実が明るみになって態度が変わったらしい。
その母にはすでに小さな生命が宿っていた。この私だ。次第にお腹が目立ってきたために、噂が気になり始めた。が、両親もラビも事実を語る勇気はなかった。そこへ天の助けがあった。最近になってナザレの町にヨセフという名の独り身の大工が店を出し、お手伝いを募集していることが分かった。また、その男は母親がエジプト人で、言葉もアラム地方の方言を話しているために、ナザレの人間からは今ひとつ親しみをもたれていないことも分かった。
窮地にあった母はその大工のところへ行って事実をありのままに話し、お手伝いとして働らかせてほしいと頼んだ。ユセフも事情を理解して母を雇うことにした。するとその夜のことだ。ユセフの夢に天使が現われ、昨日訪れた娘に宿っている子はユダヤ民族を解放する使命を帯びて生まれてくる……お手伝いとしてではなく妻として娶り、その子の生育をそなたが見守ってやってほしい、と告げた。
その生々しさにユセフは感動し、翌朝すぐに母の両親を訪ねて、マリアをお手伝いとしてではなく妻として正式に娶りたいと申し出た。これから先のことは一々述べるまでもないだろう」
「素晴らしい愛情物語ではありませんか。それに、ヨセフの夢のお告げが先生の使命を告げております」とヤイロが感慨深げに言う。「先生の誕生後の話はすでにお聞きしております。エジプトへ行かれたとのことですが、エジプトのどこですか?」
「ヨセフの母方の親戚が何人かコプトスにいるというので、我々はまずそれを頼りに赴いたのだが、その辺りもローマの目が行き届いていて危険だというので、我々は小船を雇ってイタケ島へ向かったのだった。ギリシャ西岸沖にあるイオニア諸島の中のいちばん小さい島だ。これは正解だったと思う。穀類とオリーブオイルとワインと干しぶどうを主な産物とする貧しい島で、それだけにローマは目もくれず、贅沢を言わなければのんびりと暮らせる、いい島だった。
島の住民はみんな大らかで、新参者の我々を気持よく受け入れてくれて、父の大工の仕事を次々と持ってきてくれたようだ。私も子供なりに父の手伝いをし、技術を身につけていった。そういう生活が十二歳まで続き、それまでは一歩も島から出たことはなかった。
その間に母は四人の男の子と一人の女の子を生んでいる。が、両親は最初の子である私をいちばん大事にしてくれた。どこの家でも同じだといえば確かにそうだが、ヨセフにとって私は義理の子だ。なのに父はそういう態度を片鱗も見せず、私を実の子のように育ててくれた。そういう父を母は心から尊敬していた」
「故郷へ帰りたいと思われたことは一度もなかったのですか? とくにヘロデ王が死んだ後とかに……」
「そのことを両親は何度か話し合ったようだが、ヨセフにはこれといって縁はないし、そのうちへロデの後継者のアルケラオスが反乱を鎮圧するために三千人ものユダヤ人を虐殺したとの話を耳にして、やはりその島がいちばん安全だということになったようだ。
私にとって大きな精神的転換期となったのは、十二歳の時に家族みんなでギリシャ本土へ旅行した時だった。ローマの操り人形のアルケラオスによる“ユダヤの王”抹殺の恐怖が両親の脳裏からすっかり消えたのであろう。我々は二、三週間にわたって島を離れ、のんびりと旅行を楽しんだのだった。
私がギリシャ建築と彫刻の素晴らしさに触れたのはその時だった。オクタビアヌス〔アウグストウス皇帝〕によって建設されたエピルス地方の首都ニコポリスの至るところにある豪華な寺院、同じく皇帝アウグストウスがアントニウスとクレオパトラを破った記念として海神ポセイドンに捧げた円形劇場に、私はただただ庄倒されるばかりだった。こうしてギリシャ精神の真髄に初めて触れた時が、私が生涯でもっとも大きな幸せを味わった時だったように思う」
「伸び盛りの少年にとって、それは計り知れない貴重な体験だったことでしょう」とネーサンが言う。「ギリシャ語もすでに幾らかは話せたのでしょう?」
「小さいとはいえギリシャの島に十年以上もいたわけだから、言葉には不自由しなかった。芸術的な美の裏に託されたギリシャ人の宗教的な概念が理解できるようになったのは、そのお蔭だ。ギリシャ人は何よりも“美”から宗教的インスピレーションを感得しており、彼らが崇拝する神々は芸術と詩歌の勝利の象徴でもあるわけだ。
それは当然多神教であるわけだが、基本的な唯一絶対神の概念も変わることなく残っていた。それをゼウスと呼び、その神性を細かく分けて小さな神々としているわけだ。我々ユダヤ人は絶対神をヤハウェ[エホバ]と呼び、これを唯一の全知全能の神として崇拝している。どちらが真実だろうかと思いあぐねているうちに、こんな体験をした。
ある日エコポリスで友だちと遊んでいるうちに、シナゴーグ[ユダヤ教の礼拝堂]の前を通りかかった。何となく入りたい衝動に駆られて覗いてみると奥で数人のラビが真剣な面持ちで討議し合っていた。私に気づくと、こちらへいらっしゃいと手招きしてくれた。
近づくと、一人のラビが私の手を取って自分の膝の上に抱き、お父さんはどういう信仰をもっているのかな、と尋ねた。信仰については義父のヨセフからいろいろ聞かされていたので、それを大まかに話してから、ギリシャには女神アフロディーテ[ビーナス]や海神ポセイドンに捧げた神殿があり、エジプトにはまた別の神々がいるという話をした。
すると長老のラビが、そうしたことを君はどう思うか、と尋ねた。私は、日ごろ敬虔な気持で眺めていたラビが気さくな態度で接してくれることに気を良くして、唯一の神を別々の名前で呼んでいるだけではないかと思う、と生意気な意見を述べた。すると長老が、自分もそう思うが、ユダヤの大予言者の一人であるモーセが呼んだ“ヤハウェ”という名前が“真の天国の王”という意味なのでいちばん良い、という意見を述べた。ラビたちの打ち解けた雰囲気に気を良くして、私は小生意気にもこんなことを言ってしまった――ボクが大きくなったらそうした違いを全部改めて、世界中の人間が一つの神を信じるようにします、と。
そこへ母が現われた。まだ家族で旅行している最中で、私だけがいつまでも姿を見せないので、近くの少年たちに尋ねてみると、シナゴーグへ入るところを見かけたと聞いて入ってきたらしい。私がラビたちの邪魔をしていると思った母は、厳しい口調で責めた。するとラビの一人が、これこれ、この子を叱ってはいけない。どうやらお子さんはただの子供ではなさそうだ。この年でよく宗教の奥義を理解している。他の宗教の神々への寛容心もそなえている。どうやって教育されたのかな? と尋ねた。私どもが教えたわけではございませんと母が答えると、ではこの子からあなた方が教わりなさい。この幼い年齢でこれほどの叡智をそなえているところをみると、この子は神の使命を帯びているとしか思えない。どうかこの子がやりたいと思うことをやめさせたり、親の手の届くところに留めておこうなどという狭い了見は持たないでほしい。この子の将来については神に一存がおありのようだ、と述べた。
このエピソードを述べたのは、これが若い私の心に強烈な印象を与えたからだ。母の民族、つまりユダヤ民族のことが妙に気がかりになり、母にいろいろと質問を浴びせるようになった。受難の歴史が一通り分かったとき、私の心に何とかして屈従の束縛から解き放たねばという思いが湧いてきたのだ。
長期の旅行から島へ帰って、私はまた学校へ通い始めた。が、正直言って、学校で学んだことよりも義理の父から教わったことの方が多かった。父は実に博学で、言葉も古代シリアの言語であるアラム語を初め、ユダヤで使われているヘブライ語、さらにはエジプト人だった母親から学んだエジプト語も堪能で、それらをすべて教えてもらった。
しかし、エジプトもシリアもユダヤもギリシャも、今やことごとくローマの手に落ちている現実を知って、私は民族解放の先頭に立つ者の必要性を痛感せざるを得なかった。そこで十六歳になった時に、船乗りになりたいとの希望を両親に打ち明けた。シナゴーグでのラビの予言めいた話を父も母から開いていたのであろう。二人とも素直に許してくれた。運良くイタケ島に立ち寄った貨物船に欠員が出て、新たに船員を募集していることが分かり、すぐに応募した。
こうして私の第二の人生が始まったわけだ。お蔭で私はそれまでまったく未知だった外国を訪れ、そこの慣習や道徳を知り、人類というものについての認識を広めることができた。たまにイタケ島に便のある時に帰宅することもあり、手紙を書き送って心配をかけないようにはしたが、二十歳を過ぎてからは一度も帰っていない。
その後家族はエジプトへ移住し、さらに五年後にはガリラヤに帰ったと聞いている。
おや、外がにぎやかになってきたな。馬車がやって来たようだ。新しく同志がやってきたのだろう。行ってみよう」 (同書、pp.28-34)
(2017.08.01)
人はどのようにしてあの世へ還っていくか (身辺雑記 No.114)
1. 死とは何か
死とは何か。人は死んだら、どうなるのか。人類は、有史以来ずっと、いろいろと想像力を掻き立てて、このことを考え、さまざまな宗教をも生み出してきた。現代でも、この問いは、いくら科学が進んでも解けない永遠の謎とされている。いったん完全に死んだ人が、もう一度甦ってきて、死んだ後のことを話してくれない限り、死後のことは決してわかるはずがないと思われているのが世間一般の常識である。
しかし、現実には、「完全に死んだ人が、死後の生を証明してくれている」例は、いくつもある。ただ、人々は、そういうことはあり得ないと、はじめから思い込んでいるし、知ろうとはしないだけのことである。かつての私もそうであったが、長年の迷いと苦しみ、それからの学びと霊的体験を経て、いまでは、死後の生に対する確信は揺るぎないものになっている。そして、それを教えてくれたのが、3千年前に「死んだ」といわれる高位霊のシルバー・バーチであった。
シルバー・バーチについては、いままでも何度も触れてきたので、ここでは繰り返さない。その膨大な霊言は世界中で読まれ、人類の至宝と言っていいと思うが、シルバー・バーチは、「理性で判断してください。私の言っていることに、なるほどと納得がいったら真理として信じてください。そんな馬鹿な、と思われたら、どうぞ信じないでください。それでいいのです」と言っていたことだけを、ここでも付言しておきたい。
そのシルバー・バーチは、「死とは何か」について、こう述べている。
《死とは物的身体から脱出して霊的身体をまとう過程のことです。少しも苦痛を伴いません。ただ、病気または何らかの異状による死にはいろいろと反応が伴うことがあります。それがもし簡単にいかない場合には霊界の医師が付き添います。そして、先に他界している縁者たちがその人の〝玉の緒″が自然に切れて肉体との分離がスムーズに行われるように世話をしているのを、すぐそばに付き添って援助します。》(『シルバー・バーチの霊訓 (8)』潮文社 1986, p.103)
世間では、「脳死が人の死である」などと医者が言ったりするが、本当の死とは、ここでいう“玉の緒”(シルバー・コード)が切れることで、肉眼で見ることはできない。このことについても、シルバー・バーチは、「霊視能力者が見れば、霊体と肉体とをつないでいるコードが伸びて行きながら、ついにぷっつりと切れるのが分かります。その時に両者は永久に分離します。その分離の瞬間に死が発生します。そうなったら最後、地上のいかなる手段をもってしても肉体を生き返らせることはできません」と、述べている。(『霊訓 (11)』pp. 206-207)
シルバー・コードが切断されて、肉体から離れると、やがて私たちは意識を回復する。その時の私たちは、今までと同じく手足を備えた身体のままである。ただし、その身体は霊体である。私たちは、もともと、肉体を伴った霊であって、霊を伴った肉体なのではない。だから、この場合も、死によって、本来の姿である霊体に戻ったというべきかもしれない。私たちは、死ぬ前も霊であったし、死んでからも霊である。つまり、霊として生き続けている。この意味でも、私たちにはいわゆる「死」はないといってよいであろう。本当は、私たちの生命である霊は永遠で、「死のうにも死ねない」存在なのである。
2. シルバー・コード
このように、いわゆる「死」という現象は、シルバー・コードの切断をもって完結する。シルバー・コードが切れないうちは、私たちは死んだことにはならない。世に伝わる多くの臨死体験は、一旦は「死んで」霊界をかいま見ることができても、シルバー・コードが切れなかったからこの世に戻ってくることができた事例である。
このシルバー・コードは、肉眼では見えないから、臨終に立ち会う病院の医師たちにも付き添いの家族たちにも認識されることはない。しかし、霊界からの極めて貴重な報告として、『新樹の通信』により、私たちはそれをうかがい知ることができる。『新樹の通信』には、浅野和三郎先生の次男で霊界にいる新樹氏が、父上の臨終に際して、そばに付き添い、シルバー・コードが切れていく様子も見守っていた状況が記されている。
浅野和三郎先生(1874-1937) は、いうまでもなく、心霊研究に大きな業績を残した日本での先駆者である。旧制一高、東大英文科を卒業後、海軍機関学校の英語教授になったが、後に官職を辞して(その後任が芥川龍之介であった)、心霊研究に生涯を捧げた。1937年(昭和12年)2月、62歳の時に急性肺炎で急死する。霊界で新樹氏は、心霊研究における父の功績を訴えて、神さまに父の延命をお願いしたが、それは叶わなかった。
しかし、新樹氏が病床で瀕死の父上を見ると、ほとんど苦痛もなさそうなので、こんなことでこちらの世界へ来るのだろうかと不審に思ったりする。そこで、或いは、回復の期待が持てるのではないかと神さまにお伺いすると、神さまは、「そうではない、こちらで守護しているから、そう見えるだけだ。これは最大の幸福である」と告げられたという。
浅野和三郎先生の臨終の席には、兄上の正恭氏(海軍中将)も立ち会っていた。正恭氏は、浅野先生の多慶子夫人を霊媒として、霊界の新樹氏とは、伯父と甥の間の自然な対話をそれまでも何度も続けていた。その正恭氏に、新樹氏は、自分が霊視で見た父上の臨終の模様をつぎのように知らせている。
《父が起き上がると、幽体は足の方から上の方へと離れ始めました。幽体と肉体とは、無数の紐で繋がっていますが臍の紐が一番太く、足にも紐があります。脱け出たところを見ると、父は白っぽいような着物を着ておりました。僕は足の方から幽体が脱けかけ、頭の方へと申しましたが、それはほとんど同時といってもよい位です。そして無数の紐で繋がれながら、肉体から離れた幽体は、しばらく自分の肉体の上に、同じような姿で浮いているのです。そして間もなくそれらの紐がぷつぷつと裁断されていきました。これが人生の死、いわゆる玉の緒が切れることなのです。》 (浅野和三郎『新樹の通信』潮文社、2010、pp. 36-44 現代文訳 武本昌三)
この後、正恭氏は、「どの紐から切れ始めたか」と新樹氏に訊いている。新樹氏は、「臍のが一番先で、次が足、頭部の紐が最後でした。紐の色は白ですが、少し灰色がかっております。そして抜け出た幽体は、薄い紫がかった色です」と答えた。
紐は音もなく切れたが、「その切れるさまは実に鮮やかで、何か鋭利な刃物ででも切られたのではないかと思われるほどでした」とも、新樹氏は答えている。そして、「僕はまのあたりに父の幽体の離れ行くさまを見て、実に何ともいえぬ感慨に満たされました。この離れた幽体は、しばらくそのままでおりましたが、やがて一つの白い塊となって、いずこへか行ってしまいました」と付け加えた。
3. 霊界への移行
シルバー・コードが切れて、霊界へ移行するときの模様は、かつてイギリスのユニテリアン派の牧師であったジョン・ピアボントによっても報告されている。ピアボンドは、自他共に認めたスピリチユアリストとしても著名であった。
彼は、「みずから死を体験し、また何十人もの人間の死の現場に臨んで実地に観察した者として、更にまたその『死』の問題について数えきれないほど先輩霊の証言を聞いてきた者として、通信者である私は、肉体から離れて行く時の感じはどんなものか、という重大な質問に答える十分な資格があると信じる」と自負している。そのピアボンドが、ロングリー夫人を霊媒として、死の瞬間についてつぎのように伝えている。(以下、各引用は近藤千雄『シルバー・バーチに最敬礼』コスモス・ライブラリー、2006、pp.84-87:同書[資料]:ジョン・レナード『スピリチュアリズムの真髄』より)
《いよいよ死期が近づいた人間が断末魔の発作に見舞われるのを目のあたりにして、さぞ痛かろう、さぞ苦しかろうと思われるかも知れないが、霊そのものはむしろ平静で落ち着き、身体はラクな感じを覚えているものである。もちろん例外はある。が、永年病床にあって他界する場合、あるいは老衰によって他界する場合、そのほか大抵の場合は、その死に至るまでに肉体的な機能を使い果たしているために、大した苦痛を感じることなく、同時に霊そのものも恐怖心や苦痛をある程度超越するまでに進化をとげているものである。》
このように、苦悩にうちひしがれ、精神的暗黒の中で死を迎えた人でも、その死の過程の間だけは苦悩も、そして自分が死につつある事実も意識しないものであるらしい。断末魔の苦しみの中で、未知の世界へ落ち行く恐怖におののきながら「助けてくれ」と叫びつつ息を引き取っていくシーンなどは、ドラマとフィクションの世界だけの話のようである。
中には自分が死につつあることを意識する人もいるかも知れないが、たとえ意識しても、一般的に言ってそのことに無関心であって、恐れたり慌てたりすることはないらしい。ピアボンドは、それを、死の過程の中ではそうした感情が薄ぼんやりとしているからである、という。意識の中枢である霊的本性はむしろ喜びに満ちあふれ、苦痛も恐怖心も超越してしまっている、とも言っている。そして、ピアボンドは、自分自身が「死んだ」ときの体験についても、こう語った。
《自分が老いた身体から脱け出る時の感じは喜びと無限の静けさであることをここで付け加えたい。家族の者は私があたかも深い眠りに落ちたような表情で冷たくなっているのを発見した。事実私は睡眠中に他界したのである。肉体と霊体を結ぶ磁気性のコードが既にやせ細っていたために、霊体を肉体へ引き戻すことができなかったのである。が、その時私は無感覚だったわけでもなく、その場にいなかったわけでもない。私はすぐそばにいて美しい死の過程を観察しながら、その感じを味わった。》
このなかの、「肉体と霊体を結ぶ磁気性のコード」がシルバー・コードである。「既にやせ細っていた」というのは、シルバー・コードが切れかかっていたということであろう。ピアボンドは、自分が死んでいくとき、自分が住み慣れたアパートにいること、お気に入りの安楽椅子に静かに横たわっていること、そして、いよいよ死期が到来したということを十分に意識していた。そして、自分自身のシルバー・コードが切れていく様子についても、詳細に、つぎのように観察していた。
《私の注意は、いまだに私を肉体につないでいるコードに、しばし、引きつけられた。私自身は既に霊体の中にいた。脱け出た肉体にどこか似ている。が、肉体よりも強そうだし、軽くて若々しくて居心地がよい。が、細いコードはもはや霊体を肉体へ引き戻す力を失ってしまっていた。私の目には光の紐のように見えた。私は、これはもはや霊体の一部となるべきエーテル的要素だけになってしまったのだと直感した。そう見ているうちに、そのコードが急に活気を帯びてきたように見えた。というのは、それがキラメキを増し始め、奮い立つように私の方へ向けて脈打ち始めたのである。そして、その勢いでついに肉体から分離し、一つの光の玉のように丸く縮まって、やがて、既に私が宿っている霊体の中に吸い込まれてしまった。これで私の死の全過程が終了した。私は肉体という名の身体から永遠に解放されたのである。》
このようにして、霊がすっかり肉体から離脱し、眠りから覚めたように新しい環境を正常に意識するようになると、霊界での新しい生活が始まることになる。しかし、死後の生を知らず、霊的に無知であった人の場合は、ここで大いに戸惑うことになるようである。シルバー・バーチは、それを、こう言っている。
《こちらへ来た当初は霊的環境に戸惑いを感じます。十分な用意ができていなかったからです。そこで当然の成り行きとして地上的な引力に引きずられて戻ってきます。しばらくは懐しい環境―我が家・仕事場など―をうろつきます。そして大ていは自分がいわゆる〝死者″であることを自覚していないために、そこにいる人たちが自分の存在に気づいてくれないこと、物体にさわっても何の感触もないことに戸惑い、わけが分からなくなります。しかしそれも当分の間の話です。やがて自覚の芽生えとともに別の意識の世界にいるのだということを理解します。》(『霊訓 (12)』p.35)
4. 霊界での生活
霊界とはどのようなところか。私たちは、あの世へ還った時、どのような環境で暮らすことになるのか。この霊界での生活は、たとえば、仏典の「仏説阿弥陀経」を読んだりして私たちは微かに想像することはできる。しかしそれは、西の彼方の十万億土を過ぎたところに極楽という世界があると説いている夢のような話である。そんな雲を掴むようなレベルの話に頼らなくても、現実には、霊界からのメッセージで、私たちにはかなり具体的で詳しい生活の実況が様々な形で伝えられている。私自身にも、霊界の妻や長男からの数多くの通信記録がある。その一端は、私のホームページや『天国からの手紙』(学研パブリッシング、2011)などでも紹介してきた。
まず、霊界は階層社会で、そこに住む者の進化の程度に応じて、住む場所に段階的な階層の差ができている。私たちが他界後に落着く先は、私たちがこの世で身につけた霊的成長に似合った界層であり、それより高いところへは行けない。それより低い階層には、行こうと思えば行けるが、何らかの使命を自発的に望む者は別として、好んで行く者はいないらしい。それをシルバー・バーチは、つぎのように述べている。
《死後あなたが赴く界層は地上で培われた霊性にふさわしいところです。使命を帯びて一時的に低い界層に降りることはあっても、降りてみたいという気にはなりません。と言ってそれより高い界層へは行こうにも行けません。感応する波長が地上で培われた霊性によって一定しており、それ以上のものは感知できないからです。結局あなたが接触するのは同じレベルの霊性、同じ精神構造の者にかぎられるわけです。》(『霊訓 (12)』p.34)
私たちが正しい霊的認識をもち、すでに地上時代から死後の世界についての理解を深めていた場合は、すんなりと新しい環境に馴染んでいくといわれる。しかし、この世に生きている間、死後の生を知らず、或いは死についての間違った固定観念に固執していた者は、霊界ではその矯正の期間が設けられる。各自の必要性に応じて適当な指導霊が付けられ、いわば霊界でのオリエンテーションを受けることになるのである。
ただし、それぞれの霊格に応じた階層に落ち着いた後も、実は、難しい問題が無くなってしまうわけではない。解決すべき問題が次から次へと現われ、それを解決することによって魂がさらに成長を続けていくのである。何の課題もなくなったら、“生きている”意味がない。この世と同じく、霊界でも、魂は陽光の中ではなく嵐の中にあってこそ、その中でもまれて霊的成長が見込まれることになる。
霊界で、霊的意識が深まるにつれて、自分に無限の可能性があること、完全への道は果てしない道程であることを認識するようになる。と同時に、それまでに犯した自分の過ち、為すべきでありながら怠った義務、他人に及ぼした害悪等が強烈に意識されるようになり、その償いをするための行ないに励むことになる。「埋め合わせと懲罰の法則があり、行為の一つ一つに例外なく働くことも知るようになります。その法則は完全無欠です。誰一人としてそれから逃れられる者はいない。見せかけはすぐに剥ぎ取られてしまいます。霊界では何一つ隠しおおせることはなく、すべてが知れてしまいますが、それは、正直に生きている人間にとっては何一つ恐れるものはないということです」と、シルバー・バーチは言っている。(『霊訓 (10)』pp. 82-84)
私たちが霊界へ移行した後、そのような霊界の厳しい摂理のなかで、具体的にどのように暮らしていくかということについては、『新樹の通信』にも、詳しい報告がある。それによると、新樹氏は、東京あたりの郊外などによく見られるような平屋建ての3室ほどの家に住んでいるらしい。その家の見取り図も、母上である多慶子夫人の霊視によって描かれている。
新樹氏は、訪問で出かけるときは洋服を着るが、自宅でくつろいでいる時には和服で過ごしているという。家の中の書斎には、新樹氏が霊界へ来てから描いた絵のうちで、一番お気に入りの絵を壁にかけている。「庭は割合に広々ととり、一面の芝生にしてあります。これでも自分のものだと思いますから、敷地の境界を生垣にしてあります。だいたい僕ははでなことが嫌いですから、家屋の外回りなどもねずみ色がかった、地味な色で塗ってあります」などと新樹氏は伝えている。
このように、新樹氏は霊界で自分の好きな家に住み、絵を描いたり、水泳をしたり、散歩や山登りをしたり、乃木希典元大将と一緒に霊界の伊勢神宮に参拝したりもしている。極めつけは、この『新樹の通信』を出版するにあたって、和三郎先生の序文に新樹氏が挨拶のことばを書き添えていることである。
「このたび父から、僕がこれまでに送った通信の一部を一冊の書物にとりまとめて上梓するから、お前も何かひとつ序文を書くようにとのことで、未熟の僕には特にこれというよい考えも浮びませんが、ほんの申し訳に、少し所感を述べさせていただくことにいたします・・・・・」と書き出された新樹氏の挨拶文には、新樹氏が今もこの世に生きていて、日本の何処かから原稿を送ってきているような錯覚をさえ感じさせられる。
新樹氏の霊界での生活ぶりについては、ここではさらに詳述する余裕はないが、このような新樹氏の生活からもうかがえることは、私たちは、もともと、霊界で生きる存在であって、この世は仮の宿であるにすぎないということである。肉体に包まれて感覚が鈍っている間は、そのことが意識にのぼらず、なかなか理解し難いだけなのであろう。
私たちは、この世に生き、やがて年老いて死んでいく。それが世間の常識だが、本当は、死んでから、はじめて私たちは本来のいのちを生き続けるといえるのかもしれない。そのような命の真実を理解できずに、霊的真理に無知のまま霊界へ移行する者が極めて多いことに霊界では手を焼いているともいう。なかには、その無知頑迷が後遺症となって新しい霊的環境に適応できない者もいるらしい。シルバー・バーチも、そのような霊界の生活の一端を、つぎのように述べたことがある。
《霊界にも庭園もあれば家もあり、湖もあれば海もあります。なぜかと言えば、もともとこちらこそが実在の世界だからです。私たちは形のない世界で暮らしているのではありません。私たちもあい変わらず人間的存在です。ただ肉体をもたないというだけです。大自然の美しさを味わうこともできます。言葉では表現できない光輝あふれる生活があります。お伝えしようにも言葉がないのです・・・・・・・。
霊的に病んでいる場合はこちらにある病院へ行って必要な手当てを受けます。両親がまだ地上にいるために霊界での孤児となっている子供には、ちゃんと育ての親が付き添います。血縁関係のある霊である場合もありますが、霊的な近親関係によって引かれてくる霊もいます。このように、あらゆる事態に備えてあらゆる配慮がなされます。それは自然の摂理が何一つ、誰一人見捨てないようにできているからです。》(『霊訓 (8)』pp. 115-117)
終わりに
生と死については、私はいままで随分多くのことを書いてきた。「人は死なない、生命は永遠である」というようなことを口にするのは、大学教授としてはあるまじきことであるというのが、いまでも世間に根強くはびこる「常識」だが、そのような世間の無知と偏見のなかで、またこのような小文を書くのは孤独な作業である。本稿では、一般にはあまり知られていない、シルバー・コードのことなども取り上げてみた。
最後に、ここで一つのエピソードを付け加えておきたい。アメリカのシカゴ大学精神医学部教授で『死ぬ瞬間』を書いたエリザベス・キューブラー・ロス博士(1926-2004)は、ターミナル・ケアの世界的な権威として有名であった。彼女は、患者の臨死体験の例を2万件も集めて、生命は不滅であり、人間は「死んでも」永遠に生き続けることを人々に説いてまわった。このような言動に対する世間の無知と偏見は、アメリカでも同じである。彼女は反撥と非難に包まれ、自宅を焼かれたりもした。
やがて、彼女は悟るようになる。人間は死後も生き続ける、本来、死というものはないのだということは、聞く耳を持った人なら彼女の話を聞かなくてもわかっている。しかしその一方で、その事実を信じようとしない人たちには、2万はおろか100万の実例を示しても、臨死体験などというものは脳のなかの酸素欠乏が生み出した幻想にすぎない、と言い張るのである。そこで彼女は、臨死体験の例を集めて「死後の生」を証明しようとする努力をついに2万件でやめてしまった。その彼女は、「わかろうとしない人が信じてくれなくても、もうそんなことはどうでもよいのです。どうせ彼らだって、死ねばわかることですから」と、少し自嘲気味に言い放っている。(『死ぬ瞬間と臨死体験』 読売新聞社、1997、p.129)
(2017.10.01)
このHPで伝えておきたかったこと (身辺雑記 No.115)
― HP公開終了の予定について ―
このホームページ「ともしび」を開設したのは、2003年3月のことでした。私の講演会の主催者や出席者の方々のお勧めとご尽力があって、私にとっては思いがけないことでしたが、ホームページを開設する運びになりました。ホームページの作成やプロバイダーへの事務手続き等は、すべて、パソコンに詳しい溝口祭典の佐々木薫さんがしてくれました。はじめの頃は、毎日のように入力・更新を続けながら、私も忙しくパソコンに向かっていましたが、それからもう14年が過ぎていきました。私が伝えるべきことはほぼすべて伝えてきたという思いもありますので、来年3月に15年目になるのを機会に、このホームページは閉じさせていただきたいと思っています。毎月1日に交互に公開してきた「随想」と「身辺雑記」も、今日が本年最後になりますので、この機会に、改めて、このホームページで私が伝えたかったことの主旨をまとめておきたいと思います。
私は、このホームページの「はじめに」のところで、「最愛のご家族を失って深い悲しみに沈んでおられる方々や、さまざまな人生の試練のなかで、迷ったり苦しんだり悩んだりしながら生きる意味と幸せを求めて重い足取りで歩んでおられる方々の、足許を導くささやかな
『ともしび』 になることができれば、たいへん有難いことだと思っています」と書いています。かつての私は、自分自身が「死後の生」や「霊界の存在」などについて何もわからず、1983年の事件で妻と子を亡くして以来、長い間、悲嘆と絶望に陥っていましたから、このようなことを将来の自分が書くようになるとは、全く予想もできませんでした。その私が変わり始めたのは、1991年の春から、ロンドン大学客員教授としてロンドンに住むようになってからのことです。私は、ロンドンでシルバー・バーチを読み始めるようになり、1992年に入ってからは、頻繁に大英心霊協会へ通うようになりました。そこで、私はアン・ターナーやその他の大勢の優れた霊能者に出会い、霊界の妻と子にも「再会」して、死後の生を十分に納得し確信するようになったのです。
大英心霊協会では、ある男性霊能者から、「あなたはこれからは教師になる」と言われたことがあります。彼は、私のことは名前も国籍も職業も何も知りません。私が、実は私の今の職業は教師なのだと言いますと、彼は、「私が言っているのはその教師ではない。社会を導く教師だ」と答えました。ほかの女性の霊能者からも、あなたはこれから、「多くの人々を導いていくようになる」と言われたこともあります。その頃はまだ、それがどういうことを意味するのかわかっていませんでしたが、日本に帰国してからは、私は霊的真理の学びを深めていきながら、「死後の生」について本を書き、講演会で話し、講演集なども発行していくようになりました。それが私の「教師になる」と言われた意味であったかもしれません。私の『天国からの手紙』の「はじめに」には、次のように書いているところがあります。
・・・・・・・愛する家族を失って、悲嘆に暮れるのは人の常である。
私も随分長い間、嘆き悲しんだ。死をどうしても受け容れることができず、妻と息子の葬式をすることも自分では考えることができなかった。
「時が癒してくれる」などという言葉には、強く反発した。失った家族のいのちが返ってこない以上、まわりの人たちの、どのような慰めのことばも耳には入らなかった。
心理カウンセラーなどの、もっともらしいタイトルの本の数々も、まったく受けつける気持ちにはならなかった。
だから、私は、何年も何年も苦しんだ。
それでは、愛する家族を失えば、もう、救われることはないのか。いつまでも、今度は自分が死ぬまで、悲しみつづけなければならないのか。
そうではない。
救いへの道は確かに存在する。
とはいえ、救われたい一心で、迷信にすがるのは論外である。何かにつけてカネのかかる新興宗教に凝って、幻想のなかで生きるのは惨めである。豪華に着飾って権威を印象づけようとする「教主」や「救世主」たちの、あやしげな法力に縋るつもりも、さらさら、ない。
では、どうすればいいか。
愛する家族のいのちを失ったのであれば、そのいのちを、取り戻せばよい。
それしか、絶望と悲嘆から逃れるすべはない。
愛する家族が死んでしまったから悲しいのであって、生きているのであれば、決して悲しむことはないはずであろう。
それならば、自分で自分の愛する家族のいのちを取り戻すべきである。
それも、真実のいのちを、愛する家族の生きている姿を、しっかりと、自分で見極め、取り戻すのである。
それしか、ない。
それが、自分を救い、亡くなった家族を救う、ただひとつの道である・・・・・・・
「愛する家族を失えば、もう、救われることはないのか。いつまでも、今度は自分が死ぬまで、悲しみつづけなければならないのか」というのは、長い間、私に付き纏っていた深刻な悩みでした。それが、実は、妻も子も「死んではいなかった」ことを知るに及んで、私の人生は180度の転換を遂げたのです。だから、「それならば、自分で自分の愛する家族のいのちを取り戻すべきである」と書くこともできました。人は死ぬと、焼かれて灰になり無に帰すると考えるのは、無知にほかなりません。愛する家族が亡くなって、もう決して逢うことも話し合うこともできないと思い込むのも、大きな間違いです。そういうことも臆することなく口にするようになりました。自分で考えても、大きな変化であったと思います。と同時に、私自身が、その無知と勘違いの中で苦しんできただけに、その無知と勘違いの恐ろしさを痛いほどに思いしらされてもいました。『天国からの手紙』のなかでは、こうも書いています。
人は死なない。というより、死ぬことができない。愛する家族も死んではいない。いまも生き続けている。話し合えないことも決してない。
ただ、そのことを知らずに、死んだらすべては終わったと諦めて、愛する家族をみずから忘却の彼方へ押し流し、話し合おうとはしない人たちが、おびただしくまわりにはいるだけである。
確かに、その姿は目の前には見えないかもしれない。
しかし、もう永遠に会えない、となぜ思い込むのか。話し合うこともできないと、誰がそう言ったのか。「死んで」しまったのだから、本当にもう会うことも話し合うこともできないのか。それを自分で確かめたのか。
いまでは、私は、溢れるような思いを抑えて、そう問いかけることができる。(pp.310-311)
私は、妻や子が「生きている」ことを知り、何十回となく「対話」を重ねてきて、その生存の事実を「自分で確かめて」きたのです。だから、私には「溢れるような思い」がありました。それを自分の胸にだけ秘めておくことはできません。それが重大な生と死の真実であるだけに、一人でも多くの方々に伝えなければならないと思いました。それで、このホームページの開設の機会に、まず、『シルバー・バーチの霊訓』を紹介することから始めたのです。
訳者の近藤千雄さんと連絡を取りながら、『霊訓』11冊(12冊目は「総集編」)と『古代霊は語る』などを、内容により「生と死」「霊・魂・肉体」「霊界での再会」「偶然、必然」「霊界の生活」「人生の目的」「霊的真理」「心霊能力」等々、80の項目に分類して、その要点を抜粋し、「学びの栞」(A)として入力する作業を続けていきました。近藤さんの訳されていないA.W.Austen編集のTeachings of Silver Birch も私が和訳して、原文でも読めるように英和対訳の形で付け加えました。それが「霊訓原文」です。さらに、シルバー・バーチの膨大な教えの中から、要点になる言葉を100にまとめて「叡智の言葉」としました。これらが、シルバー・バーチの教えを紹介した私のホームページの主要部分です。
この「学びの栞」(A) に対して、シルバー・バーチ以外の高位霊、霊能者、宗教家、学者、知識人等のことばから、各項目に対応するように選んできたのが「学びの栞」(B)です。これらも(A)と同じ項目別に並列させることによって、シルバー・バーチが言っていることを、他の霊能者や学者・宗教家などがどう言っているか、を較べてみることもできるように意図したものです。例えば、「学びの栞」(A)の項目(2)は、「死」についてまとめたものです。人間の最大の問題であり恐怖の対象でありつづけてきた「死」についてシルバー・バーチは、こう言っています。
(2-a)すでに地上にもたらされている証拠を理性的に判断なされば、生命は本質が霊的なものであるが故に、肉体に死が訪れても決して滅びることはありえないことを得心なさるはずです。物質はただの殻に過ぎません。霊こそ実在です。物質は霊が活力を与えているから存在しているに過ぎません。その生命源である霊が引っ込めば、物質は瓦解してチリに戻ります。が、真の自我である霊は滅びません。霊は永遠です。死ぬということはありえないのです。死は霊の第二の誕生です。第一の誕生は地上へ生をうけて肉体を通して表現しはじめた時です。第二の誕生はその肉体に別れを告げて霊界へおもむき、無限の進化へ向けての永遠の道を途切れることなく歩み始めた時です。あなたは死のうにも死ねないのです。生命に死はないのです。(サイキック・プレス編『シルバーバーチは語る』ハート出版、pp.13-15から)
シルバー・バーチは、このように、「生命に死はない」と断言していますが、それに対して、シルバー・バーチ以外の高位霊や、霊能者、学者たちはどのように言っているでしょうか。それを「学びの栞」(B)の同じ項目(2)では、エリザベス・キュブラー・ロス、ラムサ、五井昌久、コナン・ドイル、エマニュエル・スウェデンボルグ、ジェームズ・ヴァン・プラグ、ジュディー・ラドン、ニール・ドナルド・ウォルシュ、M.H.テスター、ゴードン・スミス等のことばを、抜粋して対置させています。そのうちの一つとして、例えば、高位霊ラムサは、死について、つぎのように言っているのがわかります。
(2-c)・・・ひとつ偉大な真実を話しますから、これだけは絶対に忘れないようにしてください。生命はけっして終わることがありません。確かに身体に危害をおよぼすことはできます。首を斬ることだろうが、内臓をえぐり出すことだろうが、どんなひどいことでも可能です。でも、その化身の内に生きる人格=自己は、絶対に滅ぼすことはできません。思考や感情をいったいどうやったら破壊できるか、ちょっと考えてみてください。思考を爆破できるのか、刃物で刺すのか、それともそれに戦いをしかけるとでもいうのでしょうか? それは不可能です。人間でも動物でも、ここに生息するすべての生き物の生命力は、身体という仮面の影に生きている人格=自己、つまり目に見えない思考と感情の集合体なのです。
死は大いなる幻影です。なぜなら、いちど創造されたものはけっして消滅させられないからです。死とは、肉体だけの死なのです。肉体の内に宿り、それを操る本質の部分は(もしそれが望むのなら)、すぐにこの場所に戻り、もうひとつ別の化身と統合されるのです。肉体の壁の内に生きる生命力は、生き続けていくからです。それを覚えておきなさい。(『ラムサ―真・聖なる預言』(川瀬勝訳)角川春樹事務所、1996、p. 86)
このように、「学びの栞」(A)で、シルバー・バーチの教えを80項目に分類し、それらに「学びの栞」(B)でそれぞれに対応する教えやことばを対置させました。これにより、シルバー・バーチのことばの真実性をより深く理解することができるようになるかもしれません。ただ、この80の項目の設定は、楽ではありませんでした。シルバー・バーチを読みながら、項目を決めていきましたので、80全部に分類が終わった段階では、項目名を改めたり、順序を入れ替えた方がいいような場合も出てきましたが、項目の各抜粋には、それぞれに引用箇所を明記していて、これを入れ替えるのは大変な作業になってしまいます。仕方なく、項目名や順序はそのままにして、「学びの栞」(B)のほうも、分類はその順序に従うことにしました。
「死後の生」の真実を知るということは極めて大切で私たちの生き方にも重大な影響を与えると思いますが、「学びの栞」(A)のシルバー・バーチのことばを補完する意味でも、「霊界通信集」をもこのホームページに取り入れています。このうち「霊界通信A」は、『新樹の通信』を私が現代文に訳したもの全文を掲げ、「霊界通信B」では、それ以外の様々な霊界通信を載せています。私個人の「霊界からのメッセージ」も、ご参考までに付け加えておきました。そのうえで、「メール交歓」欄では、ホームページの読者の方々からの様々な質問に私なりの答え方をしてきました。それ以外にも、「プロフィール」、「教育活動」、「家族の想い出」などを付け加えていますが、それは、霊的真理について無知頑迷であった頃からの私のすべてを曝け出したうえで、私が書いているものを判断していただきたいと思っていたからです。
このようにして、2003年3月以来、最初のうちは土、日曜日を除いてほぼ毎日、5年前に大腸癌と動脈瘤の手術を受けて以来は、週3~4回、このホームページの更新に取り組んでいるうちに、いつのまにか14年以上の歳月が流れていきました。ホームページに入力してきた内容量も本にすれば数十冊分くらいになっているかもしれません。私には、書いておくべきことは、私なりに、すべて書いてきたという思いがあります。年齢も87歳になり、冒頭でも申し上げましたが、来年の3月に開設15年目を迎える頃には、このホームページを閉じさせていただくことにしました。今年の12月末までは、今まで通りの更新を続けて、来年に入ってからは、週1~2回に更新を減らしながら、徐々に終了に向けての準備をしていきたいと思っています。このホームページをご覧いただいている皆様には、どうかよろしくご了承くださいますようお願い申し上げます。
(2017.12.01)
[付記]
私の著作の中で、このHPに含まれている未公刊の著書、訳書等は次の通りです。
これらは、ご希望があれば、自由に全文または一部を抜粋、コピーしていただいても
差し支えありません。
『天国の家族との対話』
『新樹の通信』
『霊訓原文』(Teachings of Silver Birch edited by A.W.Austen)
『講演集』(1~9)
『叡知の言葉』
森鴎外の「高瀬舟」を読み返す (身辺雑記 No.116)
高瀬舟というのは、京都の高瀬川を上下する小舟のことである。
徳川時代に、京都の罪人が遠島を申し渡されると、罪人は高瀬舟に乗せられて、大坂(現在の大阪)へ回されることになっていた。それを護送するのが、京都町奉行の配下で同心と呼ばれた下級役人であった。
江戸で松平定信(1758-1829)が政権を握っていた寛政のころ、弟殺しの罪名で、喜助という名の30歳ばかりになる住所不定の男が高瀬舟に乗せられていた。
通常、罪人が遠島に送られる時には、京都と大坂間だけ、罪人と共に、親類でただ一人だけ同乗することが許されており、そこで今生の別れをする習わしであった。
罪人と親類の者は、たいてい哀しい身の上話や、悔やんでも返らぬ繰り言で涙ながらの一夜を過ごすことになる。しかし、喜助には親類はなく、一人であった。同心の羽田庄兵衛が護送を命じられて一緒に船に乗り込んでいた。
庄兵衛は、役目もあって、罪人の喜助の様子をそれとなく眺めていたが、不思議なことに、喜助は罪人とは思えない穏やかな明るい表情であった。
罪人は、船の中では横になることも許されているのに、喜助は横になろうともせず、黙って月を仰いでいる。その額は晴れやかで、目はかすかに輝いているようにさえ見えた。
同心の庄兵衛は喜助が弟殺しの罪を犯したことを知っている。
罪人は、普通、こうして島流しにされる場合には目も当てられぬほどに取り乱したりするものだが、この青白い顔をした痩せ男は、そのような気配は全くない。人の情というものがないのであろうか、と庄兵衛は思ったりした。
思い余った庄兵衛は、「喜助、どうもお前は、島流しが苦にはなっていないようだ。いったい何を思っているのか」と問い質した。それに対して、鴎外の原文では、喜助はこう答えている。
「ご親切におっしゃって下すって、ありがとうございます。なるほど島へ往くということは、ほかの人には悲しいことでございましょう。その心持ちはわたくしにも思いやってみることが出来ます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまでわたくしのいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で、命を助けて島へやって下さいます。島はよしやつらい所でも、鬼の栖む所ではございますまい。わたくしはこれまで、どこといって自分のいていい所というものがございませんでした。こん度お上で島にいろとおっしゃって下さいます。そのいろとおっしゃる所に落ち着いていることが出来ますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それにわたくしはこんなにかよわい体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ往ってから、どんなつらい仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それからこん度島へおやり下さるにつきまして、二百文の鳥目をいただきました。それをここに持っております」
喜助はそれまで一か所に定住して暮したことがなかった。京の町で苦労ばかりの毎日であった。島がどれほど住みにくい、厳しい場所であろうと、住むところを与えられるというだけでも、今よりはましであると喜助は思っているのである。
それに、罪人に遠島の際、手当として与えられる二百文もこうしてここに持っている。
二百文というのは、今なら数千円というところであろうか。しかし、喜助は、それだけのカネさえ、それまでに手にしたことはなかった。
骨身を削り働き、僅かばかりの賃金は借りた金を返し、また別の金を借りる。ほんのわずかの蓄えもなかった自分が、捕まってからというもの、牢屋という住む場所を与えられ、食事さえお上が用意してくれた。その上で、この二百文ももらって、これで、島での仕事の元手にしようと思うと、楽しみでしょうがない、というのである。
庄兵衛は、喜助の話がことごとくあまりに意外であったので、しばらく何も言うことができなかった。
庄兵衛は、そろそろ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子どもを4人産ませている。それに老婆も生きているので、家は7人暮らしであった。下級役人として奉行所から僅かばかりの扶持米を得ていたが、生活は決して楽ではない。
庄兵衛は、いま喜助の話を聞いて、喜助の身の上をわが身の上に引き比べてみた。その庄兵衛の気持ちを、著者はこう書いている。
「喜助は、仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな、気の毒な境界である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に、はたしてどれほどの差があるか。自分も上からもらう扶持米を、右から左へ人手に渡して暮しているに過ぎぬではないか。彼と我との相違は、いわば算盤の桁が違っているだけで、喜助のありがたがる二百文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。」
喜助は世間で仕事を見つけるのにいつも苦しんでいた。仕事を見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようやく口を糊することの出来るだけで満足した。
牢に入れられてからは、今まで得がたかった食事が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、感謝さえしている。
庄兵衛は自分と喜助には、大きな違いがあることを感じざるを得なかった。
自分の扶持米で生活をやりくりしていくのは決して楽ではないが、それでも、飢えることもなく7人家族で暮らしている。しかし、そのことに満足を覚えたことはほとんどない。普段は、幸いとも不幸とも感じずに日々を過しているだけである。
しかし心の奥には、こうして暮していて、ふと、お役が御免になったらどうしよう、大病にでもなったらどうしようという危惧がひそんでいて、折り折りに妻が里方から金をもらってきて生活費の穴埋めをしたりすることがあるのが分かったりすると、そのような危惧が、不意に頭をもたげてきたりする。
どうも、自分は、喜助のような気持にはなれそうもない、と庄兵衛は思う。家族が有る無しに関わらず、武士と町人の身分の差にも関係なく、自分と喜助との間には、何か深い根底からの違いがあるようであった。
庄兵衛はただ漠然と、人の一生というようなことを考えてみる。そして、考えているうちに、つぎのように、一つのことに気がつくのである。
「人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。かくのごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで往って踏み止まることが出来るものやらわからない。それを今目の前で踏み止まって見せてくれるのがこの喜助だと、庄兵衛は気がついた。」
「庄兵衛は今さらのように驚異の目をみはって喜助を見た」と著者は書いている。このとき庄兵衛は、空を仰いでいる喜助の頭から後光がさすようにさえ思われた。
庄兵衛は喜助の顔を見まもりつつ、「喜助さん」と呼びかけた。今度は「さん」づけであったが、これは意識して呼称を改めたわけではない。その声が自分の口から自然に出てきたのである。すぐに庄兵衛はこの呼称の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出たことばを取り返すことも出来なかった。
庄兵衛は少し間の悪いのをこらえて言った。「いろいろのことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは、人を殺めたからだということだ。おれについでにそのわけを話して聞かせてくれぬか。」
それに対して、喜助は次のように答えた。
――幼い頃に両親を亡くし、自分は弟と常に一緒に暮らしていたが、その弟が、去年の秋に病に倒れた。弟は、ひとり仕事へ出る兄に、いつも申し訳ないと言っていた。弟の病は癒えることなく、ある日家に戻ると、血まみれの弟が布団に伏せっていた。兄を早く楽にさせようと、自分で喉を剃刀で掻き切ったのである。
弟はまだ息絶えておらず、死に切れぬ激しい苦しさに、自分では引き抜くことができなかった剃刀を、兄に早く抜いてほしいと身振りで頼んだ。
最初はためらっていた喜助も、見るに見かねてやがて覚悟を決め、弟の喉元に刺さる剃刀を引き抜いた。その瞬間を近所の老婆に見られ、奉行所へと連れられて行くことになったのである。
それが原文では、こう書かれている。
「このとき近所の婆さんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、わたくしの頼んでおいた婆さんなのでございます。もう大分内のなかが暗くなっていましたから、わたくしには婆さんがどれだけのことを見たのだがわかりませんでしたが、婆さんはあっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。・・・・・わたくしは剃刀を握ったまま、婆さんの入って来てまた駆け出して行ったのを、ぼんやりして見ておりました。婆さんが行ってしまってから、気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。創口からは大そうな血が出ておりました。それから年寄衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで、わたくしは剃刀をそばに置いて、目を半分あいたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます」
喜助の話はよく筋が通っている。町奉行所でも、取り調べのたびに、そのように何度も述べてきた。
庄兵衛はその場の様子を目のあたりに見るような思いをして聞いていたが、これがはたして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いたときから起って来ていた。聞いてしまっても、その疑いを解くことが出来なかった。
弟は剃刀を抜いてくれたら死ねるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって、それで死なせたのだ、殺したのだと言われる。しかしそのままにしておいても、死ぬはずの弟であった。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えられなかったからである。
喜助はその苦しみを見るに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。
人を殺すというのは、罪には相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても庄兵衛にはわかりかねるのである。
答えはない。ただ、庄兵衛には、喜助が罪人であるという気持ちはもう消えてしまっていたであろう。あたたかい血の通った人間同士の、親しみと同情を感じさせられていたかもしれない。
このあと、「次第にふけて行く朧ろ夜に、沈黙の人二人を載せた高瀬舟は、黒い水の面をすべって行った」とあって、この鴎外の短編「高瀬舟」は終わっている。
この「高瀬舟」の初出は、大正5年(1916年)である。「中央公論」一月号に掲載された。中学校の教科書「新版中学国語3」(教育出版、1978年)にも採録されている。
原著は寛政3年に出た『翁草』で、明治38年に池辺義象が出版した校定本のなかに「流人の話」として紹介された。それを読んだ森鴎外は、「財産というものの観念」と「安楽死」の二つの問題に興味を持ち、この作品を書いたと「高瀬舟縁起」のなかで、述べている。
財産の問題は、「足ることを知る」ということの大切さを改めて考えさせられる。いまの世の中でも、この際限のない人間の物的金銭的欲望は、厳しい現実である。カネが少なければ、少しでも多くを望み、その望みが叶って多くを持っても、それで満足することは決してない。隣人に分け与えるなどとは考えもせず、さらに多くのカネを求めて血眼になったりする。
牢屋に入れられても食事と居所が保証されていることに感謝し、遠島での生活資金二百文で満足する喜助の生き方は、鴎外が、私たちに欲望の追求から離れて、「留まること」の幸せを考えさせようとしたのかもしれない。
安楽死については、鴎外は、医学者として早くから関心を持っていた。長女の茉莉が、明治41年に重病にかかったとき、森家ではこの問題を真剣に考えた体験もあった。いまでは、少しは理解が進んではいるといえないことはないが、やはり依然として、この安楽死は重い課題であることには変わりがない。
(2018.02.01)
コナン・ドイルの心霊研究 (身辺雑記 No.117)
コナン・ドイル(Conan Doyle)はいうまでもなくイギリスの推理作家で、あの名探偵シャーロック・ホームズの創作者である。推理小説というジャンルに初めて手を染めたのはエドガー・アラン・ポー(Edgar
Allan Poe)であるといわれるが、それを確立させたのはコナン・ドイルであった。彼が打ち立てた推理小説のスタイルは、アガサ・クリスティー(Agatha
Christie)を始めとするその後の作家にも受け継がれ、今日に至っている。
コナン・ドイルは1859年5月2日にエディンバラに生まれ、エディンバラ大学の医学部で学んだ。1882年にポーツマスで医師を開業したが、患者が少なく暇であったことが、小説の執筆に力を入れるきっかけになったといわれている。
しかし彼には、もうひとつ、熱心な心霊研究者としての顔があった。晩年には文字通り文筆家としての栄光に満ちた経歴さえ捨てて、数多くの国々へ講演旅行に出かけたり、論文を書いたりして心霊研究の普及のために献身した。彼は1930年7月7日に71才でこの世を去ったが、「死んだ」後も、霊界通信で個性存続の証言を行ってきた。
この彼の心霊研究とはどういうものであったか。それについては、いま私の手許に、むかし大英博物館の正門近くの書店で手に入れた何冊かの本がある。そのうちの、The New Revelation and the Vital Message(新しき啓示と重大なるメッセージ)とThe Return of Arthur Conan Doyle(邦訳:『コナン・ドイル 人類へのスーパメッセージ』大内博訳、講談社、1994)という二冊の本をもとに、その心霊研究の足跡をたどってみることにしたい。
コナン・ドイルは1882年に医学生としての課程を終えた。その頃の彼は、他の若い医者と同じく、肉体や生命に関しては確信に満ちた唯物主義的概念を抱いていた。しかしその一方で、信仰的には神の存在を否定することはできなかった。彼の頭の中には、あのナポレオンのエピソードのひとつが消えないで残っていた。かつてナポレオンは、エジプトへの航海中、お供をしていた数名の無神論者の学者たちと夕食後の会話を楽しんでいた。夜空には降るような星が無数に瞬いている。その星を指さしてナポレオンは、「ところで諸君、あの星はいったい誰が作ったのかね」と尋ねたというのである。
夜空に瞬く星を見て、大宇宙の神秘に思いを馳せ、神の存在を考える。これは多くの人が経験することであろう。たとえば内村鑑三も、かつて神の存在に疑念を持った時、「しかしてもし神なしとせば真理なし、真理なしとせば宇宙を支える法則なし、ゆえに我自身の存する限りは、この天この地の我が目前に存する限りは、余は神なしと信ずる能わず」と『基督教徒のなぐさめ』(岩波文庫)の中に書いている。
この大宇宙が不変の法則によって作られている、というのはわかるような気もする。しかしそれなら、その不変の法則は誰が作ったのかと問われると、それには無神論者の誰もが答えられないであろう。そのことはコナン・ドイルにもよくわかっていた。それでもまだ彼は、人間的な容姿をした神の存在などというものを信じ切ることはできなかった。大自然の背後にはおそらく知性を備えた巨大エネルギーが存在する。しかし、それはあまりにも巨大かつ複雑で、ただ存在するということ以上には説明のしようがない。それがその当時の彼にとっての、神なるものに対する理解の限界であった。
その頃、多分1886年に、彼は偶然、The Reminiscences of Jugde Edmunds (エドマンズ判事の回想録)という本を手に入れた。著者のエドマンズ判事は、当時、ニューヨーク州最高裁判所の判事で、高い人望を得ていたが、同時に心霊現象の解明に意欲を燃やしていた心霊研究家でもあった。
彼は当初、心霊現象をトリックとみなして、それを暴く目的で交霊会に参加したのであるらしい。しかし、どのように考えても真実としか思えない現象を体験させられて、その真相解明に乗り出したのが心霊研究に深入りするきっかけとなった。だが、判事という仕事がら、世間の眼はやがて批判的になり、「エドマンズ判事は、裁判の判決のことまで霊能者にお伺いをたてている」という噂まで聞かれるようになる。彼はそれを弁明するために、”Appeal
to the Public” (「世に訴える」)という釈明文を新聞紙上に掲げたりもしたが、批判はおさまらず、結局、法曹界から身を引いて自由な立場で心霊研究の普及に努めたという人物である。
その本を読んでコナン・ドイルは、しかし、と考えた。そもそも、エドマンズ氏のいうところの霊とは、いったい人体のどこにあるというのであろうか。交通事故で頭蓋骨を強打すると、性格が一変してしまうことがある。才気渙発だった人が急に愚鈍になったりもする。またアルコールや麻薬などに中毒すると、性格そのものも一変する。このように霊的なものはやはり物質に左右されてしまうのだ。初めのうちは、コナン・ドイルもそのように割り切っていた。実際に変わるのは霊ではなくて、その霊が操っている肉体器官なのだという認識は彼にはまだなかったようである。たとえば、バイオリンの名器も、弦が切れてしまえばいかなる名手も音が出せなくなる。それをもってその名手も死んでしまったことにならないのと同様なのであろう。
それでも彼は、なにものかに憑かれたように、心霊研究関係の本を次から次へと読み始めるようになった。そして彼が驚いたのは、実に多くの学者、特に科学界で権威を持った人たちが、霊と肉体とは別個の存在であり、死後にも霊は存在し続けることを完全に信じ切っているのを知ったことである。
無教育な人間が信じているというのであれば、それこそ無教育のなせる業であると冷笑してもおられよう。しかし、英国第一級の化学者であるクルークス(William
Crookes)、ダーウィン(Charls Darwin)のライバルである博物学者のウォーレス(Alfred Wallace)、世界的な天文学者のフラマリオン(Camille
Flammarion)などといったそうそうたる学者によって支持されているとなると、簡単に見過ごしてしまうわけにはいかなかった。
これらの高名な学者の心霊についての調査研究や著作に、コナン・ドイルが大きな関心を抱いたのは当然のことであったろう。しかしそれでもなお、それらがいくら著名な学者による徹底した研究の末の結論であるとはいえ、「気の毒に、こんな偉い人たちにもその脳の一部には弱いところがあるのだな」などと考えたりして、彼はまだ信じる気持ちにはなれなかった。彼はまだしばらくの間は、心霊研究を否定する立場の学者たち、たとえば、ダーウィン、ハックスレイ(Thomas
Huxley)、ティンダル(John Tyndall)、スペンサー(Herbert Spencer)などがいるのを口実にしては、懐疑的立場をとり続けていた。
ところが彼がさらに調べてみると、実はそうした否定論者は、ただ心霊研究を嫌っているだけで、まるで調査も研究もしたことがないことがわかってくる。スペンサーはいわゆる常識論で否定しているにすぎないこと、そして、ハックスレイに至っては、興味がないというだけの理由しか持ち合わせていなかったことがわかったのである。
コナン・ドイルは、こんな態度こそまさに非科学的であると思わざるを得なかった。非難は受けていても、みずから調査に乗り出し、あくまでも研究者としての真理追究の手をゆるめなかった人たちこそ正しい学者の態度であると、当然のことながら考えた。この時点で彼は、心霊研究に一歩近づいたといえる。そして彼の心霊に対する懐疑的態度は、以前ほど頑固なものでなくなっていた。
その後彼は、心霊研究協会の会員になる。会員になってからの彼は、協会が所有する調査研究の報告書を片っ端から読んでいった。やがて1914年に第一次世界大戦が始まり、それが1918年に終わる頃まで、コナン・ドイルは心霊現象の研究に余暇のすべてをつぎ込んでいった。交霊会にもしばしば参加して、驚異的な現象をいくつも見ていくことになる。一方、巷では、戦争の悲劇に巻き込まれて嘆き悲しむ人々が増えていた。毎日のように、夢多き青春が次々に戦場で散らされていく現実の中で、それら若者の魂がどこへいってしまうのかもわからずに、泣き崩れている戦死者の妻や母親たちの姿を見ているうちに、彼の心霊研究に対する考え方は、さらに少しずつ変わっていった。
大切なことは、物質科学が未だに知らずにいるエネルギーが存在するのかしないのか、というような問題よりも、この世とあの世との間の壁を突き崩し、人類に向けられた霊界からの希望と導きの呼びかけに答えることである。そう考えるようになったコナン・ドイルの関心は、やがて次第に霊界からの啓示に向かっていった。
このような長い逡巡と懐疑の過程を経てコナン・ドイルは、霊界からの啓示により、死後の実相について次第に確信を持つようになっていく。死後の実相については、霊界からの通信にあまり矛盾はない。問題はそれがどこまで正確かということである。
コナン・ドイルは、自信を持って語り始めるようになった。太古から地球上の各地で語り伝えられてきた死後の世界の概念は、細かい点ではいろいろと相違しても、霊界からの通信とおおむね一致しており、そこに一貫性が認められる場合には、それを真実と受け取ってよい。たとえば彼自身が個人的に受け取った通信の数は二十種類ほどであるが、それらがことごとく同じことを言っているのに、それがすべて間違っているとは考えにくい。それらの通信の中には、この地上時代のことに言及したものが少なくなく、それらは調査の結果、間違いなく正確であると証明されているものも多い。その場合、過去の地上生活に関する通信は正確であっても、現在の霊界からの通信だけは虚偽である、とするには無理がある、と彼は考えるのである。
そして、彼は確信を持って死後の世界の実相を次のように描き始めた。
《死ぬという現象には痛みを伴わず、いたって簡単である。そしてそのあとでは、想像もしなかったやすらぎと自由を覚える。やがて肉体とそっくりの霊的身体をまとっていることに気付く。しかも地上時代の病気も障害も完全に消えてしまっている。その身体で、抜け殻の肉体の側に立っていたり浮揚していたりする。そして、肉体と霊体の双方が意識される。それは、その時点ではまだ物的波動の世界にいるからで、その後急速に物的波動が薄れて霊的波動を強く意識するようになる。》(The New Revelation and the Vital Messeage)
それからのコナン・ドイルは、心霊研究こそは人間が研究すべき最も重要な問題であることを確信し、生活のほとんどすべてを捧げて絶え間のない前進を続けた。そして、自分の確信していた心霊研究を証明するために、1930年に「死んで」からも、あの世から通信を送り続けるのである。彼は、霊界からつぎのようなメッセージを送ってきている。
《何度も繰り返しますが、私たちは死後の世界で今現在、生きています。これを本当に人類に理解してもらいたいのです。人間は死後も生き残るだけでなぐ、すべての生命の背後には普遍的かつ創造的な神の力が働いているということ、そして、人間がこの神の力を認識し、すべての生きとし生けるものとの同胞愛に生きる気持ちになるまでは、人間はけっして永続的な心の安らぎ・幸せ・調和を見いだせないということを証明したいのです。》
(アイヴァン・クック編 『コナン・ドイル 人類へのスーパーメッセージ』(大内博訳)講談社、1994年、p.244)
愛する人たちとの霊界での再会については、彼は、「今は亡き、父親、母親、夫、妻、兄弟、姉妹、子供と、再びこの世とあの世の障壁を越えて心を通わせられるということを知るほど、心を慰めてくれるものがあるでしょうか。それは本当のことなのです。素晴らしいことに本当なのです」と伝えてきている。(クック前掲書、p.246)そして、つぎのように霊界での体験者としての感慨を洩らした。
《魂が愛する者たちと再会したときに体験する愛の深さと喜びを、いったいどうすれば、私はあなた方に伝えられるのでしょうか。本当に悲しい別れであったものが、もはや、それは自分に与えられた運命ではないと悟るのはなんという喜びでしょうか。愛し合う魂は、ときにはそれぞれの任務を果たすために、やむをえず別な道を歩まなければならないとしても、それは別れではないのです。これまで考えていたような別れが、愛の腕の中で、永遠に消滅するのを知って、本当に胸をなでおろすのです。》(クック前掲書、pp.194-195)
興味深いのは、人がどのようにして生まれるかについてのコナン・ドイルのメッセージである。私たちは、人生の計画を立てたうえで、自分の環境を選び、自分で選んだ親の元にこの世に生まれてくる。こういう誕生のありかたについて、コナン・ドイルは、つぎのようにメーテルリンクの『青い鳥』に触れている。(HP「随想集」No.65「メーテルリンクの『青い鳥』」参照)
《こちらの世界から、著名な作家のインスピレーションがどこから来ているのかを見ていると、じつに興味深いものがあります。メーテルリンクの『青い鳥』を思い出します。その本の中に、子供たちが地球に戻るべく名前を呼ばれるのを待ちながら、みんなが集まっている場面があります。
それぞれの子供は袋を持っていて、その袋には、地球に持ってかえる贈物や知識だけでなく、自分が患うことになる百日咳や狸紅熱といった病気も、きちんと包まれて入っています。子供たちは、星の海を“父なる時”の船に乗って渡り、地球で待っている母親のところに帰ろうとしているのです。
ただのおとぎ話だと言う人もいるでしょう。しかし、ここには、大変な真実が述べられているのです。それはおそらく、宇宙存在から降りてきたか、作者の自我の前意識のレベルから出てきたものでありましょう。》(クック前掲書、pp.264-265)
「ここには、大変な真実が述べられている」とコナン・ドイルは言っているが、この真実については、ラムサをはじめ多くの霊能者たちの証言がある。ブライアン・ワイス博士も、退行催眠で、このことを証明してきた。親を選んで生まれてくるのは実の親だけではない。「養父母もまた、産みの親と同じように生まれて来る前に選ばれているのです。すべてのことには理由があり、運命の道には何一つ、偶然はありません」とも博士は述べている。(ブライアン・ワイス『魂の療法』(山川紘矢・亜希子訳) PHP研究所、2001年、pp.70-71)
コナン・ドイルは、このような霊界の真実を数多く伝えてきたが、その彼の「死後」の通信を仲介したのが、アメリカのミネスタ(Minesta)と呼ばれる著名な心霊主義者である。彼女は女流作家でもあった。彼女は生まれながらの超能力者で、透視や、未来を予見する能力のほか、病気を癒す才能なども身につけていたらしい。
そのミネスタは、実は生前のコナン・ドイルには会っていなかった。1930年の夏、しきりに、ミネスタに会いたがっていたコナン・ドイルは彼女を自宅に招待していたが、その面会が実現する直前の7月7日に、彼女はコナン・ドイルの計報を受け取ってしまったのである。これは二人にとっても心残りであったに違いない。彼が、この世では会うことのできなかったミネスタを、後に自分の霊界通信の仲介者として選んだのも、決して意味のないわけではなかったのであろう。
ともあれ、コナン・ドイルは自分に与えられた人類に対する使命を自覚して、その生涯を心霊研究に捧げた。この使命のために、彼は自分の得たもののすべてを、富、安逸な生活、世間の承認と名声をも投げ打とうとした。貴族の地位を提供しようという申し出も拒否した。この人気のない、たったひとつの信念のためにである。その彼は、生きて心霊研究の真実を説き、「死んで」もなお、霊界から霊的真理を説き続けている。
彼が死んで、その遺体が、イギリスのサセックス州のクロゥバラー(Crowborough)に近い自宅の庭に横たえられた時、世界中の彼の作品愛読者、友人、知人らからの美しい花々が特別仕立ての列車で運ばれてきた。それらの花々は広い庭をいっぱいに覆い尽くしたという。
コナン・ドイルの葬儀は盛大であったが、それは一般的な意味での葬儀とは違っていた。しめった雰囲気とは無縁の、明るく静かな大規模の「ガーデン・パーティ」であった。数多くの参列者は、ほとんど喪服も着てはいなかった。
彼の良き理解者であったジョン・ディクソン・カー(John Dickson Carr)氏は自分の著書The Life of Sir Arthur Conan Doyle (アーサー・コナン・ドイル卿の生涯)を、次のことばでむすんでいる。
「彼の墓碑銘を書くなかれ。彼は死んではいない」
( 2018.04.01)
*コナン・ドイルについては、下記の小文でも触れている。
「随想集」No.46「コナン・ドイルの霊界からのメッセージ」
No.58「コナン・ドイルに導かれて」
学者たちの死生観の限界 (参考資料) (身辺雑記 No.118)
学者の本分は真理の探究にある。そして、その真理の探究はあくまでも科学的であらねばならない。だから、科学で検証できない霊的な問題は学問の対象にはならないし、学者で霊的真理などを口にすることは恥ずべきことである、というように考える風潮は昔も今も変わらない。私もかつては、そのようなアカデミズムの中で生きていた。死後の世界とか霊魂などについては、はじめから拒否反応を示してきた。私の魂がまだ霊的真理を受け容れる準備が出来ていなかったということであろう。
そのような私が、紆余曲折を経て霊的真理を理解するようになってからは、いわゆる知識人や学者たちが述べる死生観には、霊的真理から乖離しているということで、いつも隔靴搔痒の感をぬぐえないできた。真摯に生と死に向き合おうとしていることはわかっていても、私たちが本来霊的存在であることを抜きにしては、安心立命の死生観にはついに到達しえないのではないか。そのようなことを感じながら、ここで試みに、3人の学者たちの生と死についての考察を取り上げてみることにしたい。
1.正木晃氏の宗教と霊魂
正木 晃氏は、宗教学者である。1953年、神奈川県小田原市に生まれた。筑波大学卒業後、国際日本文化研究センター客員助教授、中京女子大学助教授、純真短期大学教授をへて、慶應義塾大学文学部・立正大学仏教学部非常勤講師を勤めている。日本密教・チベット密教を研究し、マンダラ研究を主な研究課題としているようである。氏は、「人は死んだらどうなるか」、この問いから、あらゆる宗教ははじまったのだという。氏の著書、『いま知っておきたい霊魂のこと』(NHK出版、2013)のなかで、以下 [A](pp.16‐20)と [B] ( pp.106‐111) を引用する。[A]では、冒頭で、「死んでよみがえってきた人が、報告してくれればいいのですが、現実には起こりえません」と述べている。氏は、霊魂の存在を肯定しているようだが、このことばが、すでに、学者としての氏の思考の限界を示唆しているといえるかもしれない。
*********
[ A ]
死んだら、どうなるのか。この問いは、文字どおり永遠の問いです。いくら科学が進んでも、解けない謎です。ほんとうは、いったん完全に死んで、もう一度よみがえってきた人が、こうだったと報告してくれればいいのですが、現実には起こりえません。だからこそ人類は、有史以来ずっと、想像力を総動員して、死後のことについて考えてきました。その成果を、まずは世界の事例から見てみましょう。
古代エジプトでは、死者は審判をうけなければなりませんでした。審判では死者の心臓が「真理の秤」にのせられ、死者が申告する生前のおこないと、心臓の重さが照らし合わされます。その結果がよければ、死者は至福の生活を保障されます。しかし、結果が悪ければ、天秤のかたわらにうずくまる怪物に食われて、一巻の終わりとなってしまいます。あの世の生活は、基本的にこの世の生活と変わりません。ただし、この世では整いがたい理想的な条件がすべてそなわっています。例をあげれば、つらい労働はロボットにあたる存在がみな片付けてくれるのです。
古代ギリシアでは、霊魂は不滅と考えられていました。死んで肉体が滅びると、霊魂はまず陸上に住む動物の肉体へ生まれ変わります。つぎに海中に住む動物に生まれ変わり、さらに空中に飛翔する鳥に生まれ変わります。このようにつぎつぎに生まれ変わっていって、三千年を一周期として、ふたたび人に生まれ変わると信じられていました。
キリスト教には、いろいろな説がありますが、伝統的な考え方では、お墓の中で最後の審判を待っています。そして、世界の終末において再臨したイエス・キリストが、すべての死者をよみがえらせ、最終の裁きをおこない、永遠の生命をあたえられる者と地獄におちる者とに分けるとされます。
イスラム教でもおおむね同じですが、最後の審判はアツラーによっておこなわれます。また、キリスト教よりも、最後の審判を強調する傾向があります。
いずれにしても、最後の審判では、死者は肉体を復活させられ、霊魂と合体させられます。肉体が復活させられる理由は、生前の善業にしろ悪業にしろ、霊魂と肉体がいっしょになっておこなったので、霊魂だけでなく、肉体も審判をうける必要があるからです。
したがって、キリスト教徒は復活にそなえて、肉体を残さなければなりませんから、土葬しか認められません。いいかえれば、火葬は認められません。この点、イスラム教はいまなお厳格です。しかし、キリスト教は近代合理主義の影響もあって、イスラム教ほど厳格ではありません。国や地域によっては、衛生面などから、火葬が主流になっている場合もあります。
仏教やヒンドゥー教をはじめ、インド生まれの宗教では、ありとあらゆる生命体は死ねません。死んだと思っても、なにかに生まれ変わってしまうのです。また、つぎの生のありかたは、前の生の行為によって決定されると考えられています。その結果、生きているうちに悟りを開いて、絶対安楽の境地にいたらないかぎり、永遠に生き返りまた死ぬのです。これを輪廻転生といいます。
たとえば、苦労ばかりの人生の果てに死を迎え、これでやっと苦労から解放されて安らかな眠りにつけると思っていたら、別のあまり上等ではない生命体に生まれ変わってしまい、前世よりももっと悪い状況におちいってしまうことだって、十分にありえるということです。
中国の儒教では、人は死ぬと、精神活動をつかさどる魂と肉体活動をつかさどる魄に分かれると考えます。逆にいうと、生きているとは魂と魄がともに活動している状態です。魂はいわば気体のような性質をもち、死後、天上に昇っていきます。魄は、遺体として、そのまま地上にとどまります。
魂は姿形がないので、木主(位牌)をつくって祀ります。魄はお墓をつくって祀ります。もちろん、遺体は土葬され、火葬は厳禁です。そして、子孫が敬意を込めてていねいに祀っていると、魂と魄はふたたびむすびついて、再生するとみなされてきました。
同じ中国でも、道教では、やり方次第で、永遠の生命を得ることも不可能ではないと考えて、特別な修行法や神秘的な薬剤の開発にとても熱心でした。しかし、最後には、肉体をたもったまま永遠の生命を得ることはできない、という結論に達したようです。すなわち、肉体を離脱して、精神だけの存在、つまり霊魂になってはじめて、永遠の生命は得られるということです。
「死んだら、どうなるのか」という問いは、宗教の起源にも深くかかわっています。仮に、ある集団のリーダーが死んだとします。のこされた人々は悲しみ、途方に暮れたことでしょう。そのとき、誰かが「いや、あの方はじつは死んでいない。この世とは別のどこかで、あいかわらず自分たちを導いてくれている」と主張すれば、大きな説得力をもったはずです。そして、さらに深く、死後の世界について考えるきっかけになったはずです。このようなプロセスから宗教が生まれた可能性は、十分にあります。
[ B ]
もしあなたが幽霊を見たとしましょう。あるいは、霊魂についてなにか知りたいと考えたとしましょう。そのとき、あなたはどこをたずねますか。
占い師や霊能者のところにいくという方もあるでしょう。お寺に足を運んで、お坊さんにたずねるという選択肢もあります。お坊さんはこの領域にとても詳しいはずだと信じられているからです。
ところが、現実は違います。たずねていっても、ほとんどのお坊さんは、相談や疑問に答えてくれません。そもそも、幽霊や霊魂にまつわる知識も経験ももちあわせていないのです。なかにはこの領域に詳しいお坊さんもいますが、全体から見れば、少数派にとどまります。なぜなら、お坊さんの教育を一手に引き受けている仏教系の大学では、霊魂はない、幽霊などいるはずがないと教えているからです。
明治維新までの日本仏教では、おおむね霊魂があるという立場でした。しかし、近代化とともに、ヨーロッパから、科学的な方法論にもとづく「仏教学」が導入されると、ブツダは霊魂の実在を否定したという学説が主流になりました。現在でも、大学の仏教学部ではたいがい、将来お坊さんになる学生たちに、そう教えています。
しかし、日本人の心の中には、あいかわらず霊魂はあるというおもいが、まだまだ濃厚にのこっています。ですから、現場では混乱してしまうのです。
たとえば、作家の藤本義一さんが、こういうことを書きのこしています。ある宗派の説教の集いに、講師としてまねかれたときの話です。
聴衆の大半は年配の信者さんたちでした。講演に先立ち、若いお坊さんが挨拶し、「霊魂なんてものはありません。仏教はもともと霊魂を認めておりません」と述べたのです。
若いお坊さんにすれば、大学で教わった学問仏教の見解を、そのまま述べたのかもしれません。あるいは、これぞ正しい仏教であり、自分は迷信にまみれた旧来のありかたを正していると考えたのかもしれません。
しかし、それを聞いて、善男善女は茫然自失。「じゃあ、死んだら、私らはどうなるんだ。ご先祖様たちはどうなってしまっているのか」。
その光景を目の当たりにした藤本さんは激怒したそうです。若いお坊さんが、善男善女が先祖代々つちかってきた信仰を、一瞬にしてぶち壊してしまったからです。
こういう話はなにも特殊な例ではありません。日本全国のお寺で、よく起こっています。その結果、葬儀の際に、霊魂はあるという一般人のおもいと、いや霊魂はないという学説が、ぶつかりあって、会葬者は釈然としないまま、儀式だけが粛々と進行することになりがちです。
お通夜では、昔から通夜説教といって、お坊さんが必ず説教する習慣があります。しかし、最近は、霊魂についてへたに説教すると面倒な事態になるのを見越して、「触らぬ神に祟りなし」といわんばかりに、けっしてふれようとしないお坊さんも少なくありません。
宗派によっても、霊魂にたいする考え方は異なります。例をあげれば、真言宗など密教系の宗派では、おおむね霊魂はあるという立場です。日蓮宗も同じです。曹洞宗は、約半数くらいのお坊さんが、霊魂はあるとみなしているという調査報告があります。それに比べ、浄土真宗は霊魂の存在について否定的です。
全体の傾向としては、ご祈祷をよくする宗派は、霊魂の存在にたいして肯定的です。逆に、ご祈祷をしない宗派は、否定的です。
また、霊魂の存在に肯定的な宗派は、葬儀に熱心にとりくむ傾向があります。否定的な宗派は、葬儀にさほど熱心ではありません。
さらに、葬儀にかんしても、意味付けが異なります。霊魂の存在に肯定的な宗派は、葬儀はまず第一義的に死者のためとみなしています。否定的な宗派は、あとにのこされた生者のためとみなしています。
以上の事柄は、それぞれの宗派がよって立つ教義にゆらいしていますから、良い悪いの問題ではありません。ただ、同じ日本仏教の宗派であっても、考え方には大きな違いがあることは、知っておいたほうがいいとおもいます。
では、肝心のブツダは霊魂について、どう考えていたのでしょうか。
すでに述べたとおり、仏教学の領域では近年まで、ブツダは霊魂の存在を認めていなかったという説が主流でした。ところが、最近、ブツダは霊魂の存在を必ずしも否定していないという説が台頭しています。
たしかに、もっとも成立が古い初期仏典(原始仏典)をひもといてみると、ブツダは、悟りを開かないかぎり、ヴィンニヤーナとよばれるなにかがのこると考えていたようです。このヴィンニヤーナは、かつては「霊魂のようなもの」と翻訳されていましたが、最近ははっきり「たましい」と翻訳するようになってきました。つまり、悟ってしまえば、死後になにものこりませんが、そうでなければ、やはり霊魂がのこると、ブツダは考えていた可能性が高いのです。
ブツダは霊魂の存在を認めていなかったという説は、「無我説」とか「非我説」とよばれるブツダの教えを、有力な根拠としてきました。しかし、ブツダが説いた「無我説」も「非我説」も、なんであれ、これが自分だとか、これが自分のものだとして、把握できるものはなにもないという意味であって、霊魂がないという意味ではなかったことがわかってきました。
ようするに、「無我説」や「非我説」は、霊魂の否定ではなく、我執をなくせという教えだったのです。それを、後世になって、論師(ろんじ)と称される宗教哲学者たちが、ブツダの教えを矛盾なく論理的に説明するために、霊魂の否定にまで拡大解釈してしまったのが真相のようです。
ブツダは霊魂の存在を認めなかったという学説は、キリスト教の霊魂は実在するという教義に、うんざりしていた近代合理主義に立脚する、ヨーロッパの仏教学にとって、まことに魅力的でした。ヨーロッパをモデルにひたすら近代化に邁進してきた近代日本にとっても、同じでした。
しかし、仏教を近代合理主義で把握することは、根本的に間違っています。霊魂にまつわる旧来の学説は、その典型例なのです。
2. 渡部昇一氏とスピリチュアリズム
渡部昇一氏は、1930年(昭和5年)生まれで、上智大学、ドイツのミュンスター大学で学び、長年上智大学教授を勤めた。英語文法史専攻の英語学者であったが、評論家としても著名であった。昨年(2017年)、心不全により享年86歳で死去した。氏の著書、『語源力』(海竜社、2009年)のなかで、氏は、「スピリチュアリズムとは哲学である」と言っている。そして、スピリチュアリズムについて以下の引用のように述べている。(pp. 178‐183) この場合も、書名が示すように霊的な考察を扱ったものではないにせよ、氏は、「スピリチュアリズム」を表面的に紹介するだけで、本質的な部分には触れていない。
**********
いつのころからか、スピリチュアルという言葉が流行りだした。週刊誌や単行本などにもスピリチュアリストと称する人物が登場する。テレビのバラエティー番組にもよく出演し、タレントたちの前世はどうだとか、背後霊はトラだブタだヤタガラスだといってびっくりさせ、あれこれ能書きを述べては関心を誘っている。だが、占い師や霊媒師とどこがどう違うのだろうと不思議に思っている人も多いだろうし、どこかいかがわしさを感じている人もいるだろう。
しかし実は、ヨーロッパやアメリカなど、キリスト教圏においては、「スピリチュアル」という言葉は、軽々しい言葉ではない。「霊的な」「神聖な」という意味だが、霊魂の不滅や死後の世界などとのかかわりで、非常に崇高な意味を持つ。スピリチュアルには、神や霊魂の存在を信じるか、信じないかが大きく関係するからだ。
もともとカトリックにおいては「ルルドの奇跡」などによって、霊魂の不滅、死後の世界の存在は信じられてきた。だが、プロテスタントにおいては、聖母マリアや聖人信仰を捨てた。そのため、聖母や聖人を媒介として「不滅の霊魂」や「死後の世界」が顕示されることはなくなる。ここから、プロテスタントの世界では、「霊魂観」が独得な形で発展することになる。これがスピリチュアリズム(Spiritualism)と呼ばれるものだ。
その出発点は、一八四八(嘉永元)年三月三十一日とされている。このころの日本は第十二代将軍家慶の時代で、日本周辺に欧米の黒船がしきりと出現し始めていた。その黒船の一つ、アメリカでの出来事だ。ニューヨーク州に住むフォックス家のドアをしきりに叩く霊が現れた。この霊が、実は、以前そこで殺された行商人の霊であることが、この家の十四歳の娘ケイトによってつきとめられ、大騒動となった。そしてその後、アメリカ各地やイギリス、またヨーロッパ大陸諸国においても、同じような超自然的な現象が、霊媒を通じて起こることが確認されるようになる。こうして、この流れは、十九世紀後半から二十世紀にかけての、欧米精神史の中でも注目すべき現象となっていった。『ブリタニカ百科事典』の第十一版にも、このために約三ページ、四百数十行を使って述べているくらいだ。
また、シャーロック・ホームズの物語で有名な著者のコナン・ドイル(Sir Arthur Conan Doyle,1850‐1930)も、熱心なスピリチュアリストであったことが知られている。
彼はその歴史について三百ページ以上もの大冊の本二巻を書いている。ドイルは、エジンバラ大学で医学を学び、開業もしたことのある科学者だ。自然科学についての知識も豊富で、合理的精神の持ち主だ。その彼が、自らの体験や観察、調査に基づいて、熱心なスピリチュアリストになった。ドイルは、当時のスピリチュアリズムの霊魂観について次のように明快に定義している。「個人たること(パーソナリティー)は死後も続いて存在し、死後もこの世の人たちと交信できる」と。
これは何を意味しているのかといえば、「霊魂」だけではなく、死者もその姿を現すことができるといっていることになる。だがもちろん、その現れた姿は、この世の物ではないから現実の人間とは構成要素が違う。骨や皮、あるいは蛋白質や脂肪などで成り立っているわけではない。
しかし、ドアや壁を叩いて音を出したり、テーブルを動かしたりといった、この世的な、いわゆる「物理的」な作用は行えると考えた。だから、物質的な存在ではないのに、「写真」に写ることはあり得る。
スピリチュアリストは、ドイルだけではなく、ほかにも大勢いる。ダーウィンに先駆けて、独創的な自然選択説による進化論を唱えたイギリスの大博物学者、A.R.ウォレス(Alfred
R. Wallace,1823‐1913)もその一人だ。あの動物分布に関する「ウォレス線」の提唱者となるこの人も、種々の体験や実験から、スピリチュアリストになった。そして、死んだ母親の死後の写真撮影に成功したと書いている。
さらに注目すべきなのは、天才的な化学者クルックス(Sir William Crookes,1832‐1919)もスピリチュアリストの仲間入りをしたことだろう。彼は二十九歳の時にタリウム元素を発見し、その後、ウラニウムから活性ウラニウムのⅩを分離し、それが次第に崩壊していくことをつきとめた人物だ。真空放電の実験で有名なクルックス管を初めて用いた化学者でもあり、これらの業績によって、サーの称号を与えられた。英国化学学会会長、王立協会(ロイヤル・ソサイェティー)会長、英国学術協会会長などを務めた、文字通り第一級の自然科学者だ。その彼もスピリチュアリストだった。日本の自称スピリチュアリストたちも、そこまでの科学的、合理的精神をもって、スピリチュアルを名乗っているのかどうかはわからないが、とにかく、十九世紀半ばから第二次世界大戦のころまで、欧米ではスピリチュアリストたちが活躍していた。
こういうエピソードもある。アメリカの大富豪スタンフォード夫妻が、息子をなくして悲観に暮れていた。それを知ったウォレスは、スピリチュアリストの立場から彼らを慰めた。そのことが、死んだ息子を記念するための大学設立の動機となる。
現在のスタンフォード大学がそうで、この大学は自然科学の殿堂ともいわれるくらい卓越した大学となっている。大学設立の方向が、精神的な方向ではなく、科学的な方向へ向かうというのが面白いと思う。
また、コナン・ドイルは第一次世界大戦中に、多くの心霊現象があったことを記録している。息子がフランス戦線で戦死したちょうどその時刻に、母親の枕元に息子の姿が現れたというような話だ。大戦中の日本にもよくあったようだが、このような心霊現象を信じることを、スピリチュアリズム(Spiritualism)、あるいはスピリティズム(Spiritism)といった。
ただスピリチュアリズムという語は、従来哲学で、物質界よりも精神界を重んじる立場に用いられてきたため、ウォレスなどの心霊現象信仰に対しては「近代的」という形容詞をつけて、モダン・スピリチュアリズムという場合もある。が、最近では、スピリチュアリズムが一般的になっている。
このような単語が文献上にいつから登場するかを調べてみると、スピリティズムが一八五六年、その信者を表すスピリチスト(Spiritist)が一八五八年。スピリチュアリズムが一八五三年で、その信者を表すスピリチュアリストが一八五二年となっている。
いずれも一八五〇年代ということになる。ダーウィンの『種の起源』の出版が一八五九年、サムュエル・スマイルズ(Samuel Smiles, 1812‐1904)の『セルフ・ヘルプ(自助論)』も同じ一八五九年に出版されているが、この十九世紀中ごろは、ヴィクトリア王朝が栄えた時代で、イギリスの物質文明が世界を制覇していたといってもいい時代だ。一説によれば、このころのイギリスの工業生産は世界の半分以上を占めていたといわれている。このような繁栄の中で、進化論的な思想が空気のように、思想界を包み始めていた。
近代への扉が開きつつあったまさにこのころ、カトリックの世界では、聖母マリアの無原罪懐胎が教義として打ち出され(一八五四年)、「ルルドの奇跡」が起こり始めた(一八五八年)。そしてプロテスタントの世界でも、アメリカのフォックス家への幽霊(心霊)現象が確認される(一八四八年)。
3. 岸本葉子氏の生と死についての考究
岸本葉子氏は1961年生まれで、1984年東京大学卒業後、中国の北京外国語学院に留学した。帰国後、文筆生活に入ったが、2001年には虫垂癌と診断され、その手術・治療体験を2003年に『がんから始まる』として著した。現在は、NHK中央放送番組審議会副委員長、淑徳大学客員教授などを勤めている。
岸本氏は、自分が癌にかかったときの経験からも、人間の力の限界を思い知り、人間の統御を超えたものに生と死は左右されていると自覚するようになった。そういったところで伝統的宗教は、一定の役割を果たしていると氏は考える。しかし、近代以降の人々は科学的、合理的な考え方にあまりに慣れ親しんできたために、伝統的な宗教をそのままではなかなか受け入れることができない。
そこで氏は、そうした「知」の人の苦しみとでもいうべきものを体現した人として、岸本英夫と頼藤和寛の実践を取り上げている。岸本英夫は、東京大学教授、東京大学図書館長などを歴任した著名な宗教学者である。頼藤和寛は、大阪大学医学部を卒業した精神科医で、大阪大学病院に勤務したあと、1997年からは神戸女学院大学人間科学部教授になった。以下は、岸本葉子『生と死をめぐる断想』(中央公論新社、2014)からの引用である。
**********
[A]
岸本英夫は一九〇三年に生まれ、一九六四年にがんで亡くなっている。宗教学者として古代エジプトの信仰から、イスラム教、キリスト教、仏教と、世界のさまざまな宗教を研究してきた。
ところが彼の立脚点を揺るがすほどの事態が、岸本の身に降りかかる。五一歳でのがんの告知。死生観を研究の対象としてきた彼はそのときはじめて我が事として、死生観の練り直しを迫られる。一九五四年、客員教授として滞在していたアメリカで左頸部に悪性腫瘍が発見された。
日本ではその頃はまだ、がんの本人への告知は行われていなかった。その意味で岸本英夫は今の日本人の多くが経験していることをひと足早く経験した、先駆例と言うことができる。
結果として彼は告知から十年を生きた。それはあくまで結果であり、告知のとき本人に示された予後は余命半年という、非常に厳しいものだった。
愕然とするのは、死とは突きつめれば「この、今、意識している自分」が消滅することだと気づいたときだったと、彼は述べる。
《これは恐ろしい。何よりも恐ろしいことである。身の毛がよだつほどおそろしい。死後の生命の存続ということが、煎じつめると、その一点にかかっている。何とかして、「この自分」はいつまでもその個体意識をもちつづけうるということを確かめられればとねがう。これが近代的来世観である。》(『死を見つめる心』)
世界じゅうの宗教を研究することを専門としてきた岸本は、それらがこの間題をどう解決しようとしているか、さまざまな宗教を調べ直した。すると伝統的な宗教のとる解決法は、多少の例外はあるにせよ概ねひとつの型に落ち着くことがわかったという。説明の仕方は異なるが、人間の生命が何らかの形で死後も続くと主張するところが共通する。それによって死の恐怖を乗り越えようとするものだと言う。
岸本はそうした解決法を否定しない。よい悪いを言うものではけっしてなく、むしろそのような教えを信じて死んでいく人生はそれでよいのだと、伝統的宗教の果たす役割を肯定する。
しかし彼自身は、そうした主張に安らぎを見いだせなかった。
さきに引いた文章では、「死後の生命の存続」が「この自分」の「個体意識」の存続とすぐさま言い換えられている。「近代的来世観」といみじくも言うように、デカルト的な自我の意識になじんだ私たちの多くが持つ感覚ではないだろうか。
同時に私たちは、「わたし」の首座は脳であること、脳も肉体の一部であり脂質やたんばく質といった有機物から成ることを知っている。
「わたし」の存続を切に願いながらも岸本は、科学的な見地から、願いの妥当性に疑問を投げかける。死によって肉体が崩壊すれば、脳細胞も自然要素に分解される。生理的構造がなくなった後で「この自分」の意識だけが存続するのが可能と考えるのは、相当に無理があるのではないかと。
《そのような考え方はどうも、私の心の中にある合理性が納得しない。それが、たとい、身の毛がよだつほど恐ろしいことであるとしても、私の心の中の知性は、そう考える。私には、死とともに、すなわち、肉体の崩壊とともに、「この自分の意識」も消滅するものとしか思われない。私自身は死によって、この私自身というものは、その個体的意識とともに消滅するものと考えている。》(『死を見つめる心』)
死後の存続の可能性を打ち消すのは苦しみを伴う。「私の心は、生への執着ではりさけるようであった。私は、もし、自分が死後の理想世界を信じることができれば、どれほど楽だろうと思った」。伝統的宗教が差し出している解決法を採用しない彼は、素手で死に立ち向かったも同然だった。
煩悶の末に、岸本は死に対しどのような態度をとったか。ひとことで言えば、どこへ行くかを問わない、というものだ。私は團十郎の「時なき世へ」の句をきっかけに自らを振り返り、どこから来てどこへ行くのかを、漠然とながら考えてきたとさきに述べた。それに即して整理するなら、岸本英夫が示したのは、その問いを問わないという生き方である。
死後のことはわからないが、死後の生はないものと決める。人間に与えられているのは今営んでいるこの命だけと思い定めて、「この自分」がたしかに存在している生の期間に集中する。身の毛がよだつと繰り返し書いた死の恐怖も、充実感に溢れる生き方をしていけば克服できるのではないか、と彼は言う。
死を前にして大いに生きるというのが、彼の新しい出発点となった。そうして残された生の期間、仕事に邁進していく。
その後岸本英夫は、死は「別れのとき」だという考えに到達する。人間が折ふしに経験して、そのつど耐えることのできてきた別れの、より大きく全体的なものなのだと。そうとらえるに至って、心の平穏を得る。
死は別れのときとは、それだけを言ってしまえばめあたらしいことは何もないようだが「生命飢餓状態」に置かれた彼が煩悶の末つかみとったものだと思うと、重みがある。
そう受け止めた上でなお、死が目前までは迫らずにいた私にとって印象的だったのは、死は別れのときとの結論にたどり着く前の彼の葛藤だ。
私もまた科学的、合理的な思考になじんだ者として、肉体の滅んだ後も生が続くとは考えにくかった。同じような思考の習慣を持ち、かつ私よりはるかに厳しい状況で死と向き合った岸本英夫の実践に、深い感銘を受けた。彼の意志力を見倣いたいと思った。
誕生と死との二点に区切られた、「この生」だけに集中して生きる。それが病に際してまず私のとった態度である。(pp.24‐29)
[B]
岸本英夫同様、近代人の知を背負い、その指し示すところに忠実であろうとした人に精神科医の頼藤和寛がいる。一九四七年生まれ、二〇〇〇年に直腸がんと診断され二〇〇一年に死去。岸本のときよりも時代は下り、日本でも本人告知が原則となっており、その上彼は医師であるから自分でⅩ線写真を見てまぎれもない進行がんであると知るという、待ったなしの遭遇となった。
頼藤もまた、死がもうひとつの生のはじまりであるとする解決法を採用しない。その理由を彼は、岸本英夫より踏み込んで述べている。死後の生の存続を期待するのは、科学的にあり得ないから間違い、なのではない。それを信じてしまえば、死という人間にとっての最大の問題が「原理的に成立しなくなるから許されないのだ」とする。(頼藤和寛『わたし、ガンです ある精神科医の耐病記』文春新書)
許されないとは、他者に向けては酷な言葉に聞こえるが、自らへの戒めとも意志表明ともとれる。その先はない断崖絶壁としての死を措定することで、そこからの逆照射の中で生を直視しようとするのである。
願望に基づく世界観の構築を、彼は拒む。自らの避けられない死に際してもその立場を徹底する。その姿は、認識の鬼とでも形容したくなるような、ある種の凄みを持っている。
医師を続けてきて頼藤は患者から、何も悪いことをしていないのにどうしてこんな病になったのかという抗議を幾度も聞いてきた。彼は述べる。科学的に研究をすれば、善人と悪人とで罷患率や平均余命などに有意の差はないと、証明されてしまうだろう。心理学は、善悪に関して死後の因果応報を信じがちな人ほど願望充足的な推論や希望的観測を多用する、という実験結果をつきつけてくるかもしれないと。「自然現象に人間的な道理は通用せず、来世で辻褄を合わせようとする世界観は心理的な自慰にすぎないことを強く示唆しているのである」。(頼藤和寛『人みな骨になるならば』時事通信社)
おそらく世界の実相は、人間の都合とは無関係にある。「このことを、実は、何千年ものあいだ人類は怖れてきた。われわれは幸福がなにかの恩寵によるもので、耐え難い災厄ですらなんらかの意味をもつと信じたがった」。(pp.29-30)
(2018.06.01)
思い出の旅(1)―1974年夏 ヨーロッパ (身辺雑記 No.119)
1.バンクーバーからロンドンへ
私たち家族4人を乗せたロンドン行きのエアー・カナダのチャーター機は、8月25日午後8時半、定刻通りにバンクーバー国際空港を離陸した。私たちにとって初めての、約1か月に及ぶヨーロッパ旅行の始まりであった。機種はボーイング727型機で、ほぼ満席である。1時間ほど北東へ向かって飛んだあと、エドモントン空港に着地して給油のあと、ロンドンへ向かった。ロンドンまでの飛行時間は約9時間、時差が8時間あるので、ヒースロー空港には、26日の午後3時過ぎに到着の予定であった。
その前年、1973年の暮れから、私は文部省在外研究員としてオレゴン州のオレゴン大学(University of Oregon)に在籍していた。妻・富子と現地の小学校パターソン(Patterson)に通っている6年生の由香利と5年生の潔典も一緒で、前日の24日に、住んでいたアパートから旅行用のスーツケースなどを乗りなれた中古車のシボレーに積み込み、その大学町ユジーン(Eugene)を出発したのは、朝の9時である。約500キロ北上したところで、マウント・バーノン(Mt.Vernon)のモテルで一泊した。ここからは、バンクーバーの街も一時間ほどのドライブである。
私は、1959年3月、オレゴン大学の大学院を終えて、このバンクーバーの港から帰国している。その15年ぶりのバンクーバーの街を車で一巡した後、空港へ行って荷物を預け、車は空港の片隅にある広大なエアー・カナダの専用駐車場に駐車して、チャーター機のロンドン行きに乗り込んだのである。
エアー・カナダ機は、北米大陸を西から東へ飛び越え、グリーンランドを横断し、アイスランドの南端を掠めて、26日午後4時、ほぼ予定通りにヒースロー空港に着陸した。入国検査は簡単で、ほとんど税関の検査もなく、私たち親子4人は、空港から2階建てのバスに乗って1時間ほど走り、ヴィクトリア駅に隣接する英国海外航空(British
Overseas Airways Corporation, BOAC)の空港ターミナルへ 向かった。窓外に広がる景観は、だだっ広い感じのアメリカやカナダの街の雰囲気とはやはりかなり違う。マッチ箱のような長屋の家並みが印象深かった。
BOACは、当時存在していたイギリスの国営航空会社で、現在の英国航空(British Airways)の前身である。BOAC空港ターミナルのすぐ裏側が、Belgrave
通りで、その通りに沿って安い2つ星、3つ星のホテルがいくつも並んでいる。アメリカにいる間に調べておいたそのうちの一つ、「ヘンゼルとグレーテル」(Hanzel
& Gretel)に、空港カウンターで問い合わせてもらったら、家族用の部屋が空いているという。私たち4人は、それぞれのスーツケースをゴロゴロと引きずりながら10分ほど歩いて、ホテルに辿り着いた。時差の関係で疲れて、その日はみんな早くベッドにもぐりこんだ。
翌日7時半、ホテルの食堂で朝食を取る。ハムと卵、トースト、オレンジジュースと紅茶などのBritish Breakfastである。スペイン人の若い女性がサービスしてくれた。ここからはバッキンガム宮殿もそう遠くないので、歩いて行ける。外へ出てみると、夏だというのにうすら寒いくらいである。ロンドンの8月の最高気温は、東京よりも、平均で、10度ほど低い。時には、晩秋をおもわせるように気温が低下することもある。私たちは、それぞれに薄手のセーターを着たりして、バッキンガム宮殿では衛兵交代を見た。その時の写真も残っているが子どもたちは、寒そうな顔をしている。
そのあと、ウェストミンスター寺院、国会議事堂、トラファルガー広場などを訪れる。トラファルガー広場には、ナショナル・ギャラリー(National
Gallery)がある。この美術館には、ヘンリー七世の曽孫にあたるレディー・ジェーン(Lady Jane Grey)の処刑の絵があった。彼女は16歳のとき、たった9日間、イギリス女王の椅子に座らされただけで、反逆罪に問われて、1554年に、夫のダッドレーと共に、ロンドン塔で処刑されてしまったのである。その絵が、可憐で美しく、衝撃的で、私は後年、ロンドンへ行くたびに、この絵の前にたたずむようになった。
翌日28日も、一日中、ロンドン観光である。朝ホテルを出て、ヴィクトリア駅から地下鉄でロンドン橋駅(London Bridge)で降り、そこからテムズ川を渡ってロンドン塔へ行った。ロンドン塔は1000年も前からの城塞であるだけに古色蒼然としていて、血なまぐさい歴史にまみれているから陰気な印象を与える。かつては牢獄であり、処刑場でもあった。レディー・ジェーンが幽閉されていた監房も残されているはずであるが、その時は見過ごした。
奥にある宝物館に入ってみると、戴冠式などで使われた王冠や金糸のマントなどが展示されていた。その豪華な煌びやかさがロンドン塔の陰気さをいくらかでも救っているような気がした。中でも「アフリカの星」という世界最大のダイヤモンドは有名である。しかし、厚いガラスの壁越しに見ている私には、大きなガラスの玉とあまり変わらないように思えた。
ロンドン塔を出て、近くのレストランに入り、昼食を取った。何を食べたか忘れたが、代金が高いばかりで美味しくはない。子どもたちも食べ残した。アメリカを思い出してコカ・コーラを注文したら、氷なしの生ぬるいコカ・コーラを持ってきたのにはちょっと驚ろかされる。ビールを冷やさないのはイギリス流だが、コーラまで冷やさないのは知らなかった。
地下鉄で、エロス象で名高いピカデリー・サーカスへ引き返して、周辺の商店街を散策する。「サーカス」とは、円形広場のことである。このあたりには、リージェント・ストリート、オックスフォード・ストリート、ボンド・ストレートなどの商店街が集まっていて、ロンドンでも最も賑やかなエリアである。店頭で、面白おかしく女売り子が通行人に呼びかけたりしていた。子どもたちは、アメリカの小学校でもう半年も英語の生活を送ってきたから、アメリカ英語の会話にはほとんど不自由しないようになっていた。しかし、イギリス英語には独特の抑揚がある。その女売り子の、ロンドン英語のアクセントを口真似して笑い転げる気持ちの余裕も彼らにはあった。
ピカデリー・サーカスからは、中華街も近い。数多くの中華レストランも軒を連ねていて、料理も美味でしかも安い。私たちは、中華街を見て回った後、ここで中華料理の夕食を楽しんで、ホテルへ帰った。
2.ロンドンの街を歩く
ロンドンに着いて3日目。予約の都合で11時に「ヘンゼルとグレーテル」をチェックアウトして、すぐ近くのコロナ・ホテルへ移った。ここでアメリカのコロラドから来たというアメリカ人夫妻に会った。ヨーロッパ各国を見て回って、明日はアメリカへ帰るのだという。ヨーロッパ各国のホテル事情などを訊いておく。パリやローマのホテルの予約を取るのも、夫妻の話では、思ったより楽なようであった。
この日は、午後、バスでラッセル・スクェア―へ行き、大英博物館に入った。イギリスは、主要な博物館や美術館が無料で入れるのが有り難い。正面入り口のゲートから壮大重厚な建物の全容を眺めて、これがあの世界最大の博物館か、とちょっと興奮する。私は小学校の時に読んだ本で、ロゼッタ・ストーンのことが忘れられずに頭にあった。入ったら1階西側の部屋の一角にすぐそのロゼッタ・ストーンが目についた。床上のケースに無造作に置かれている感じで、私はしばらくその前に立ち尽くした。
近くの広い展示室に並べられているアテネのパルテノン神殿の彫刻群は美しい。子どもたちも感動して見入っていた。感動は、次から次へと続いた。2階北側へ行くと、何室かが古代エジプトの展示室になっている。古代エジプト壁画やミイラの実物は圧巻であった。なかでも紀元前3100年に埋葬されたという赤毛の女性のミイラは、それが目の前にあることさえ奇跡のように思える。
マグナ・カルタ(Magna Carta)のオリジナルも見た。この博物館の収蔵品は膨大で、一日や二日ではとても廻りきれない。私たちは、3時間くらいで切り上げて、博物館のすぐ裏手に広がるロンドン大学を訪れた。私はその15年後には、この大学の客員教授として単身で赴任するのだが、当時はそのようなことは予想も出来なかった。
ラッセル・スクェアの地下鉄駅の近くで、インド料理の昼食を取って、セント・ポール大聖堂へ向かう。この大聖堂は604年の創建だというが、1666年の大火で焼け落ちてしまった。それを時の大建築家クリストファー・レンが35年かけて1710年に再建したものだという。その雄大さは世界三位だそうで、完全なバロック建築の傑作として有名である。地下の納骨堂には、そのクリストファー・レンの棺のほか、トラファルガー海戦でフランス・スペイン連合艦隊に勝利したネルソン提督やワーテルローの戦いでナポレオンを破ったウェリングトン公爵の棺も置かれている。
大聖堂を出てからは、すぐ前の通りの旅行社、Miki Travel Service に寄った。私たちは、その二日後、ロンドンからアムステルダムへ行って、そこからはレンタ・カーで南下しながらローマまで下る予定をたてていた。アムステルダムへ行くためには、ロンドンから北東のハリッジ(Harwich)まで行って、そこから連絡船でドーバー海峡を渡らなければならない。そのための列車や連絡船2等寝台の予約をしてもらった。
次の日の午前中は、ゆっくりコロナ・ホテルで休んだ。ロンドンに着いて5日目だが、毎日歩き回って少し疲れていたかもしれない。昼頃ホテルを出て、地下鉄でベイカー・ストリート駅まで行き、マダム・タッソー蠟人形館に入った。マダム・タッソー(Madame
Tussaud)は、フランス革命当時に、獄中生活を送りながら蠟人形作りを覚えたという人である。歴史上の有名人を本物そっくりに蝋人形で再現して注目されるようになり、その後人気俳優やスポーツ選手、政治家などが加えられて、この人形館はロンドンの観光名所の一つになった。
少し薄暗い館内には、チャーチル首相、エリザベス二世をはじめ、アドルフ・ヒトラー、マハトマ・ガンディー、チャールズ・チャップリン、マリリン・モンロー、エリザベス・テイラーなどが勢ぞろいしている。日本の吉田茂元首相の人形もあった。イギリスやフランスの歴史上の血なまぐさい事件の現場を再現させたものなども非常によくできていて興味深かった。館内では、人形の真似をして不動の姿勢で立っている館員が急に動き出して、観光客を驚かせたりもしていた。
外へ出てみると、天気は相変わらず曇りがちで、時折小雨が降ったりした。しかし、雨は、東京のように激しく降ることはない。ロンドンの夏は、日本と違って、乾期なのである。
セント・ポール大聖堂前の Miki Travel Serviceへ行って、前日に予約しておいたアムステルダム行きの4人分の切符を受け取る。それからバスでオックスフォード・サーカスへ行った。ここは、ヨーロッパ最大の商業地区といわれるウエスト・エンドの中心地で、一年中人通りが絶えない。ロンドンでも有数のショッピング街の一つである。富子は、デパートでお目当てのバーバリー・コートを探し求めたが、結局、気に入ったのが見つからず買えなかった。
夜8時過ぎに、ヴィクトリア駅に戻る。ここから Belgrave 通りのコロナ・ホテルまでは、歩いて10分くらいだが、その途中に、中華料理のテイクアウト専門の店がある。この店の料理は安くて美味しい。何度か利用したが、その日の夕食も、ここのテイクアウトですませた。ロンドンで取った食事の中では、あるいは、ここのテイクアウトの中華料理が一番美味であったかもしれない。子どもたちは、このテイクアウトの中華料理を、後々までも懐かしんだ。
3.ロンドンからアムステルダムへ
8月31日、土曜日、午前11時にコロナ・ホテルをチェックアウトした。私たちはそれぞれにスーツケースを転がしてヴィクトリア駅から地下鉄に乗り、リバプール・ストリート駅まで行った。ハリッジ(Harwich)へ向かう列車はここから出る。ハリッジからは、フェリーで約200キロのドーバー海峡を渡り、オランダのフク・ファン・ホラント(Hoek
van Holland)に着く。そこからまた列車に乗り換えて、アムステルダムへ向かうことになる。
リバプール・ストリート駅からハリッジ行きの列車は、午後8時発である。予定通り出ることを確認し、スーツケースを預けて身軽になったうえで、街の散策に出た。また、オックスフォード・サーカスへも行って、Marks
& Spencrでみんなの分のセーターを一枚ずつ買う。ぶらぶらとウインドウ・ショッピングなどをして、リバプール・ストリート駅に戻ったのは、午後6時過ぎである。
ハリッジ行きの列車は、8時10分にリバプール・ストリート駅を出発した。2等の座席指定で、6人用のコンパートメントになっている。同室は、ドイツへ行くという若いイギリス人の兵士と、ミニスカートの学生風のオランダ人女性である。列車は2時間ほど走って、ハリッジに着き、フク・ファン・ホラント行きのフェリー・ウイルヘルミナ号(Wilhelmina)に乗った。2等寝台で眠って、オランダのフク・ファン・ホラントに着いたのは午前6時である。
簡単な入国審査を経て、ここからアムステルダム行きの列車に乗り、1時間ほどでアムステルダム中央駅に8時半に着いた。車窓からは、いくつか水車が見えていたが、それがオランダへ来たという印象を強くした。アムステルダムの緯度は北緯52度で、樺太の北端に相当するから、夏でもかなり涼しい。朝のうちは少し寒いくらいである。日中でも気温は20度くらいにしかならない。
駅に着いて先ずしなければならないのは、観光案内所でホテルを探してもらうことであった。私はフロマー『ヨーロッパ一日10ドル旅行』(Arthur
Frommer『Europe on $10 A Day』)というガイドブックを持っていた。1970年代のアメリカでは、まだヨーロッパは誰でも簡単に行けるところではなかった。富裕層だけではなく一般の人々にもヨーロッパ旅行が身近なものになるように企画されたのがこの本で、アメリカでは、ヨーロッパ旅行の「バイブル」と言われていた。私はこの本で、アムステルダムのホテルも大体の見当はつけていた。観光案内所で、そのホテルの名前を言って、問い合わせてもらったら、家族部屋が空いているという。3泊の予約をしてもらった。
アムステルダムの街は歩きやすい。荷物があるから、中央駅(Centraal Station)から路面電車に乗ったのだが、南西に真っ直ぐ伸びているダムラーク(Damrak)大通りを、歩いても10分ほどで、右手に街の中心のダム広場が見えてくる。大通りを隔てて、その左手には、3階建てくらいの商店街の建物が並んでいて、そのなかに予約したHotel
Ronnyがあった。二つ星クラスだが、3階の屋根裏部屋のような室内は清潔で、洗面所にはシャワーもついているのが有り難かった。私たちは、2時間ほど部屋で休んだ後、すぐ近くの「アンネの家」(Anne
Frankhuis)へ出かけた。
ダム広場を横切って、アンネの日記にも出てくる西教会(Westerkerk)まで来ると、その裏がアンネの家である。前には幅広い運河が通っている。いまとは違って、当時は観光客はそう多くはなかった。まばらな人々に交じって、ゆっくりと家の中を見ることが出来た。
入り口から入って、表側の建物の奥にある回転式本棚を押すと、そこが開いて裏側のアンネたちの部屋に通ずるようになっている。子どもたちも、映画で見てこの構造を知っていたので、現実にその情景を目の前にして感動しているようであった。アンネ達は、1944年8月4日、ここでドイツの官憲ゲシュタボに発見され、アウシュビッツの収容所へ送られたのである。
西教会の前には、当時はなかったが、いまはアンネの像が建てられている。来た道をダム広場まで戻り、王宮の前まで来た。これは、もともと1655年にタウンホールとして建てられたものである。19世紀のはじめに、時のフランス皇帝であったナポレオンの弟、ルイ・ボナパルトによって王宮として接収されたが、その後アムステルダム市に返還され、オランダの新王家の宮殿として使われていた。いまは迎賓館となっている。王宮の周辺を散策した後、夜は近くの繁華街に出て食事をとり、ウィンドウ・ショッピングを楽しんだ。
アムステルダム滞在二日目、9月2日には、ベルグマン社の運河めぐりに出かけた。アムステルダムは、中央駅を中心に、幾重にも運河が放射線状に張り巡らされているから、一時間半ほどのこの遊覧船による運河めぐりで、街の様子がよくわかる。アンネの家の前も通った。
私たちの乗った遊覧船では、ボートの観光客に向かって、若い案内嬢が早口で次々と運河の両側に開けていく建物や風景を説明していた。初めは、オランダ語で、次に英語で、そしてドイツが続いた。ボートはかなりのスピードで走っているから、3か国語での説明もかなり早口にならざるをえない。その見事な説明ぶりに感銘を受けた。この3か国語は、同じ印欧語のゲルマン系言語だから、お互いに親戚のようなものだが、それでも、日本語のような、いわば「孤立語」の世界から見ると、この案内嬢の説明ぶりは極めて特異な早業のように目に映る。
運河めぐりの後は、ダウンタウンのHerz のレンタカー事務所へ行って、明後日から2週間の予定で V.W1300を借りる予約をする。これも、アメリカにいる時から、フロマーの『ヨーロッパ一日10ドル旅行』でいろいろと検討してきた。無事に予約が出来て、それから、国立美術館(Eijksmuseum)を訪れた。
これは、1885年に国王の命により建造されたオランダ最大の美術館である。レンブラントの「夜警」やフェルメールの「台所の女中」など、貴重な作品が多く、デルフト焼きや、オランダ特有の美術品も多数収納されている。なかでも、レンブラントの「夜警」(Nachtwatch)は圧巻で、3.63
m×4.37 mの大画面の前では、しばらくは身動きも出来ずに立ちすくんだ。
外へ出ると、小雨が降っていた。小雨の中の運河のたたずまいは風情がある。しばらく小雨の中を歩き回った後、中華料理店に入り、ゆっくり夕食を楽しんだ。やはり中華料理は、どこでも、安心して食べられる。
その翌日も、天気はよくなかった。風もやや強く、うすら寒い。晴れたり曇ったりしたが、曇っている時には冬のコートでも着ていたくなるほどだ。昼前に、ゴッホ美術館(Van
Gogh Museum)に入る。この美術館は、私たちが訪れた前年の1973年に、ゴッホの遺族の寄贈で開館されたというから、私たちは最も早い方の入館者になるかもしれない。館内には、ゴッホの油絵約200点、素描約500点、書簡約700点、それにファン・ゴッホとテオが収集した浮世絵約500点などを中心にして、同時代のポール・ゴーギャン、ロートレックらの作品、ファン・ゴッホが盛んに模写をしたミレーの作品なども展示されている。
ゴッホの作品は、強烈な色彩感覚と独特のタッチを見慣れてきただけに親しみ深く、私はここで、レコード解説付きのスライド写真を買った。美術に趣味がある富子も、この美術館が気に入ったようであった。解説書や絵葉書などを買っていた。
この美術館の近くには、私立近代美術館や世界的に著名な交響楽団「コンセルトヘボウ」もあるが、それらは外観を眺めただけで、私たちは、ダム広場の周辺を歩き回ったり、のみの市をのぞいたりして、夕方まで過ごした。少し疲れて、一旦ホテルに帰ったあと、近くのレストランへ出かけて、オランダ風の夕食をとった。
翌日、9月4日は、アムステルダムを去る日である。朝、ホテルでの朝食後、潔典を連れてタクシーでダウンタウンの Herz のオフィスへレンタカーを受け取りに行った。ところがオフィスでは、事務的な手違いで、予約していたでV.W.1300
は昼過ぎにならなければ用意できないという。代わりに 少し大きいサイズの Ford Escort を準備するからと言われて、それを了承した。
一旦またタクシーで引き返し、11時にホテルのチェックアウトをすませて、今度はみんなでタクシーに荷物を積み込み、Herz のオフィスへ行った。そこでスーツケースをレンタカーに積み込み、私が運転して、南に向かって下り始めた。イギリスと違って、ヨーロッパ諸国はアメリカと同じ右ハンドルだから、ドライブの感覚に違和感はなかった。
まもなく、ヨーロッパ・ハイウエイ9号に入る。ハイウエイはアメリカのように縦横に網の目のように走っていて、ドライブが楽であった。欧米諸国では、第二次世界大戦以前から高速道路が走っていたが、欧米に比べ自動車の普及が遅れた日本では、高速道路の建設自体が相当に遅れて始まった。1964年の東京オリンピックで高速道路の建設も進み、1965年には名神高速道路が全線開通したが、東名高速道路が全線開通したのは、1971年12月である。
ヨーロッパ・ハイウエイ9号は、いまでは A2 となっている。30分ほど南下すると、ユトレヒトの町が見えてくる。そこからハイウエイ36号(現在の
A12)に入って、東南へ向かう。1時間ほど走ってアルンヘム(Arnhem)あたりまで来ると、もうドイツとの国境が近い。ドイツに入る前に、国境近くの小さな町で、遅い昼食を取り、手持ちのオランダ通貨ギルダーをドイツのマルクに変えた。
4.ハイデルベルグの思い出
ドイツ入国は、国境の検問所で係員がパスポートをちょっと見ただけであった。引き続きハイウエイ36号を疾走する。ドイツのハイウエイを走る車のスピードは、アメリカの高速道路に較べても明らかに速い。ドイツは、ヒットラーが作らせたアウトバーンでも知られているように、高速道路の先進国であるが、制限速度も当時は無制限であった。私は常時コンスタントに時速120キロくらいのスピードで走っていたが、多くの車がすいすいと私たちのフォード車を追い抜いて走り去っていった。
ヨーロッパ・ハイウエイ36号は、ドイツに入ってからは、ライン川の流れに沿って南下する。工業都市として知られるデュースブルク(Duisburg)を通り、さらに南下して金融やファッション、世界的な見本市の中心都市の一つであるデュッセルドルフ(Düsseldorf)も通り過ぎると、やがてドイツではベルリン、ハンブルク、ミュンヘンに次いで4番目に大きな都市であるケルン(Köln)の大聖堂が遠望できるようになる。そのケルンも素通りして、20キロほど走り、午後5時ごろ、ボン(Bonn)に着いた。アムステルダムから280キロほど走ったことになる。
ボンは、当時はドイツ分断時代の首都であった。1990年に東西ドイツが統合されてからも首都機能を分担している。ボンに着いた頃には、小雨が降っていた。ガソリンスタンドでガソリンを入れ、フロマーの『ヨーロッパ一日10ドル旅行』で調べておいた
モテル・バーデン(Motel Baden)の場所を聞く。ベートーベン・ホール(Beethovenhalle)のすぐ近くだからわかりやすいはずであった。私は片言のドイツ語交じりの英語でしゃべり、店員はドイツ語で答える。それでもなんとか意味が通じて、まもなくライン川に面したそのモテルに辿り着くことが出来た。
ドイツで最初の一夜を明かして、9月5日、木曜日になった。モテルの朝食は、いわゆる「コンチネンタル」で、バターやジャム、マーマレードなどを添えたトーストやロール、クロワッサンなどと、ミルクやジュース、コーヒーや紅茶などが出されるだけである。朝食後は、荷物を車に積み、観光に出かけた。
ベートーベン・ホールはライン川沿いにあって、巨大な円形の丸屋根が特徴である。同じく川沿いにオペラハウスがあって、その近くに3階建てのベートーベンの家(Beethoven
Haus)がある。ベートーベンはここで生まれて、22歳でウイーンに活躍するようになるまで、この家に住んだ。中に入ってみると、ベートーベンが使用したピアノや、直筆の楽譜、補聴器、家具などが展示されている。3階の生誕の部屋には、ベートーベンが赤ん坊の時に使ったという揺り籠と大理石の胸像が置かれてあった。
街のなかを車で見てまわる。ドイツ連邦議事堂、市庁舎、ボン大学なども車窓から見たあと、ライン川に沿って南下を続ける。ローレライ付近を通り、マインツからはライン川支流のマインツ川に沿って東方30キロのフランクフルトを目指した。
フランクフルトは、よく知られているように、ドイツの商業、金融の中心地である。一方ではこの町には古い歴史があり、中世、神聖ローマ帝国皇帝の選挙や戴冠式はこの町で行われてきた。戦後は近代的に生まれ変わったとはいえ、かつての栄華を偲ばせる大聖堂、旧市庁舎などがある。ここは、ドイツを代表する文豪で、詩人、劇作家、小説家、自然科学者、政治家、法律家でもあるゲーテ(Johann
Wolfgang von Goethe)の生まれた町でもあり、中心部には、5階建ての大きなゲーテの家も残されている。
ゲーテの家(Goethe Haus)は、第二次世界大戦で一度破壊されたが、市民たちが瓦礫を拾い集め、疎開させてあった家具類を戻して復元したものだという。中に入ってみると、2階にゲーテが誕生したと伝えられている「誕生の間」があるほか、3階には、書斎があって、ここでゲーテは、『ファウスト』などの多くの作品のほか、ヨーロッパ中でベストセラーになった小説『若きウェルテルの悩み』を書いたといわれる。この本は、学生時代に私が感動して、ドイツ語の原文ででも読んでいただけに、その本の原稿が書かれたであろう重厚な机を目の前にした時には感慨深いものがあった。
その日は、ゲーテの家を出て、市内を一巡したあと、ハイウエイ4号(現在の5号)で一路南下してハイデルベルクへ向かった。途中のマンハイムは素通りして、80キロほど走り、ハイデルベルクに着いたのは、午後7時過ぎである。フロマーのガイドブックで紹介されているネッか川のほとりのホテルを探し出して、一泊の予約をすませ、遅い夕食を近くのレストランで取った。
ハイデルベルクは、子どもの時からハイデルベルク大学(正式名称はハイデルベルク・ルプレヒト=カール大学 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)の名前で親しんできた。この大学は1386年に創設されたドイツ連邦共和国の中で最も古い大学である。日本では、金閣寺を建てた足利義満が第3代将軍であった頃である。マイヤー・フェルスターの戯曲『アルト・ハイデルベルク』(Alt-Heidelberg) などでも知られており、むかし、杉村春子などが築地座でこの戯曲に出演したことがあった。
「ハイデルベルク」は、私にとっても、何かしら懐かしい響きがあった。その時に買った金色の獅子のハイデルベルグ市の紋章の小さなレプリカは、今も私は持っている。後年、私は、ハイデルベルクの「国際応用言語学学会」研究誌(『IRAL』Vol.
20 No.4)に、「日本語と英語の相違の比較文化論的研究」(Cultural Implications of Language Contrasts
between Japanese and English)という論文を掲載することになるが、これが1982年からのフルブライト上級研究員に選ばれる一つのきっかけになった。そして、それが、私の運命を変える大事件に遭遇するきっかけにもなるのだが、そんなことは当時の私には、想像すらできなかった。
翌日の早朝、私は一人部屋を抜け出して、目の前のネッカ川(Neckar)を散歩した。ネッカ川にかかるカール・テオドール橋(Karl Theodor
Brucke)の上からは、すぐ近くの山の上にハイデルベル城もよく見える。その麓に広がる街の佇まいも、中世の世界が再現されているような趣がある。たまたま橋の上を歩いてきた優しそうな顔つきの若い女性に、英語で、「ハイデルベルク大学はどの辺にあるのですか」と訊いてみた。その女性は、ぽっと顔を赤らめて、戸惑いの色をみせた。英語がわからないようであった。ドイツ語の単語を並べてゆっくり聞き直すと、今度は笑顔で答えてくれた。
ホテルで朝食をすませて、私たちは車に荷物を積み込み、旧市街を車で見て回った。当時は、ヨーロッパでも、いまほど車の数は多くはなかったから、ハイデルベルグでも、街の中でかなり自由に駐車することができた。ハイデルベルク大学は旧市街の一部に広がって大学街を形成している。イギリスのケンブリッジ大学のようなものだが、やはり古色蒼然としていて、古い歴史を感じさせる。有名な「学生牢」も見た。学生達は、この牢に入れられると、記念に自分の似顔絵を描き、自分の名前も落書きとして書き添えた。それがそのまま残されていた。
5.インスブルックからローマへ
ハイデルベルグからは、ハイウエイ11号(現8号)でミュンヘンへ向かった。途中で小雨が降り出し3時間ほど走ってミュンヘンに着いた頃には、雨は少し強くなってきていた。街角のパン屋で、ソーセージとパンを買い、車内で遅い昼食を取った。ミュンヘンはバイエルン州の州都で、何世紀も昔の建物や数多くの博物館、美術館がある。しかし、ここでは、郊外のオリンピック施設の一部を見て市内を一巡しただけで、また1時間ほどハイウエイ6号(現11号)を南下してオーストリアに入る。山を越え、谷を渡ったりして、あたりの風景も急に山国らしくなってくる。インスブルックには、午後5時ごろに着いた。
オーストリアは、国土面積が日本の北海道とほぼ同じ大きさでしかない。そのうち、アルプス山脈が国土の62パーセントを占めるといわれるが、インスブルックもアルプス山脈の中の町といってよい。家々の窓は、たいてい彩り豊かな花々で飾られている。その日は雨であったが、晴れていれば、アルプスの山々がすぐ近くに聳えているはずであった。1974年当時は、人口も10万人くらいの小都市で、旧市街のすぐ近くまでまだ空き地が広がっていた。
ゆっくりと車を走らせていると、“Zimmer”(部屋)と書かれた小さな看板を出している家が何軒か並んでいた。いまでいう民宿であろう。そのうちの一軒の前に車を停めて、4人が泊めてもらえるかと英語で聞くと、その家の奥さんらしい人は、英語がわからないようであった。すぐ隣の家に声をかけてくれて、愛想いい奥さんが片言の英語で私たちの宿泊を引き受けてくれた。二間続きの部屋で、室内は隅々まで塵一つなくきれいで、ベッドには純白の羽根布団がかけられている。美味しい夕食も用意してくれた。私たちは満足して、安らかな一夜を過ごした。
翌朝、目を覚まして窓のカーテンを開けると、アルプスの山々が雄大に連なっているのが見えた。素晴らしい眺めである。雲は多いが空は晴れている。朝食のあと、奥さんとご主人から、ドイツ語交じりのたどたどしい英語で、インスブルックの観光スポットのことなど聞いた後、私たちは車にスーツケースを積んで、市内へ向かった。
旧市街に入るところで、道端の空き地に車を停め、後は歩いて観光スポットの一つである「黄金の小屋根」(Goldenes Dachl)の建物を見に行った。これは、1496年に当時のマクシミリアン1世がチロル公国を継承後建造したという建物で、屋根には2,657枚の金の瓦が使用され、当時のチロルの富と繁栄の象徴となったといわれる建物である。そこからは、南にマリア・テレジア通りが伸びている。この通りがインスブルックの中心で、両側には中世の町並みが続き、アルプスの美しい山並みが通りからもよく展望できる。
しばらく歩くと、聖アンナ記念塔(St. Anna's Column)が、道の真ん中に立っているのが見えてくる。大理石のコリント様式の柱の上には聖母マリア像が市内を見下ろしている。この塔は、1703年のスペイン継承戦争のとき、町を侵略してきたバイエルン軍を撃退した記念として建てられたもので、その名前はその日が聖アンナの日であったことに由来するという。
この旧市街を散策するのは楽しかった。私たちは、それぞれに記念の小物や絵葉書などを買い、車に戻ってからも、街を一巡して、昼前にイタリアとの国境を目指して走り始めた。
ブレンナー峠に至るアルプス山脈のなかの有料道路182号からの風景は絶景であった。雄大な山々の連なり、谷間の上にかけられた高い陸橋から眺める山の麓のおもちゃのような家々、山の斜面の緑に放牧されている牛の群れ、こころが洗われるような美しい風景がどこまでも続くのである。
インスブルックからブレンナー峠までは、直線距離では30キロほどだが、山の中の道で屈折しているから1時間以上もかかる。ブレンナー峠を超えると、国境の検問所でパスポートを見せてイタリアに入り、イタリア側の同名の町ブレンナーで、ガソリンの補給をした。ただ、その当時のイタリアはガソリンが配給制で、パスポートをみせてガソリン購買のクーポンを出してもらうのに、30分も待たされてしまった。
ブレンナーを出てからは、ハイウエイ6号(現A22号)で、一路南下する。ビピテノ(Vipiteno)、ボルツァーノ(Bolzano)、トレント(Trento)、ロベレト(Rovereto)まで、2時間ほど走って、そこからは、ガルダ湖(Lago
di Garda)の西側で出る。地方道路45bで、屈折が多くスピードはあまり出せないが、しばらくは美しいガルダ湖の風景を堪能した。
サロー(Salo)を通り、ガルダ湖の底部を東に向けて走り、ベローナ(Verona)近くまで来て、またハイウエイに乗り、あとは一路南下を続けた。途中で夕食をとり、モデナ(Modena)に着いた時には午後10を過ぎていた。イタリアに入ってからも300キロ以上走ったことになる。しばらく街の中をドライブしながら、モテルを見つけて、やっとくつろぐことが出来た。
モデナは、州都ボローニャから西北西へ約40キロにあって、中世においては北イタリアの学問の中心であった、12世紀初期ロマネスク時代を代表する大聖堂やグランデ広場などがよく知られている。しかし、翌朝、街を一巡しただけで、ハイウエイ6号に乗り、南東約40キロの州都ボローニャも通過して、1時間ほどで、フィレンツェに着いた。
フィレンツェは、街全体が美術館といわれるほどで、歴史的建築物として注目されている大聖堂や礼拝堂のほか、世界的にも有名な作品を展示している美術館など、見ておきたい場所が数多くある。ところが、その日、9月8日はちょうど日曜日で、商店街はほどんど休業し、美術館なども一斉に休館ということであった。仕方なく、そのままハイウエイ6号で、ローマへ向かって走った。フィレンツェからローマまでは、直線距離で約220キロである。2
時間半で着いた。
地図を頼りに、市内中心部に入っていく。ここまで南下すると、気温もかなり高く、喉がやたらに乾いた。ホテルは、フロマーのガイドブックを頼りに、テルミニ駅の近くのペンションを探して、やっと見つけた。子どもたちは、私がイタリア語やフランス語が出来ないことを知っているので、ホテルを予約するのも心配のようであったが、身振り手振りで英語をしゃべっていると何とか通じるものである。私たちは無事に2泊の部屋を確保し、室内に荷物を運びこんで2時間ほど休み、その後、夕闇のなかを外出して、レストランでスパゲッティなどの夕食を取った。
翌日から 2日間、私たちは、朝ペンションで食事を終えた後は、車でローマ観光に出かけた。1日目は、まず市内を一巡して、大体の地理的感覚を掴もうとした。名所、旧跡の近くの駐車場または路上に駐車して、見学、観光が終わればまた次へ移る。いまでは、車が多すぎて、こんなことはできないが、当時はローマでも車でまわれたのである。
私たちは、まず、フォロ・ロマーノ(Foro Romano)へ行って見た。ここは、東西約300m、南北約100mの古代ローマの中心部の遺跡である。この整備は紀元前6世紀頃に始まったといわれるが、現在の輪郭になったのは、ガイウス・ユリウス・カエサルによる西側の大改装の結果であるという。古代の歴史をまざまざと目の前に見る思いで、この遺跡は圧巻である。
近くのコロッセオ(Colosseo)にも感動させられた。長径188メートル、短径156メートルの楕円形で、高さは48メートル、約5万人を収容できたというこの巨大な建造物のことは、学生時代に、あのノーベル賞作家
シェンキェヴィチの『クォ・ヴァディス』(Quo Vadis)を読んで以来、強く印象に残っている。ネロの治世下のキリスト教徒たちが、ここで虐殺されたことなどが思い出されてくる。
サン・ピエトロ大聖堂を見たあと訪れたバチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂(Cappella Sistina)では、子どもたちも衝撃を受けたようだ。ミケランジェロ、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ピントゥリッキオら、盛期ルネサンスを代表する芸術家たちが内装に描いた数々の装飾絵画作品は世界的に有名であるが、特に、ミケランジェロが描いた天井画と、『最後の審判』には圧倒されてしまう。
6.ローマから北上してピサへ
9月10日、ローマに着いて3日目の朝、ペンションをチェックアウトして、車に荷物を積んだまま、カラカラ浴場(Terme di Caracalla)へ行ってみた。ローマの緯度は41.9度で日本の函館とほぼ同じだが、夏の気温は東京とよく似ていてかなり高い。西欧諸国の人々と違って、古来、ローマ人が風呂好きであったのは、おそらくそのためであろう。
この浴場は、ローマ帝国第22代皇帝カラカラがローマ市街の南端付近に造営した世界最大級の大浴場である。名が横225メートル、縦185メートルの建物の内部には、2,000から3,000の浴槽があって、1,600人が同時に入浴できたという。2000年以上も経って、廃墟になっていたが、廃墟の中を歩いているうちに、潔典は、浴槽の床の一部と思われるはげ落ちた小さなタイルのかけらを拾って、彼の思い出の品にしていた。
ローマ市内を、またしばらく走り回って、広場や寺院、博物館などを車窓から見たあと、私たちはまたハイウエイ6号で、フィレンツェへ向かった。2時間半のドライブの後、フィレンツェに着いたのは、午後3時過ぎである。まず、フロマーのガイドブックを参考に、フィレンツェ中央駅付近のペンションを見つけて2泊の予約をした。
部屋へスーツケースを運び入れて、少し休んだ後、私たちは車で外出した。市内の狭い道をドゥオーモ広場の近くの路上に車を停め、花の聖母教会(Santa
Maria del Fiore)と呼ばれるドゥオーモ大聖堂へ歩いて行った。
ここは、大聖堂、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ジョットの鐘楼の三つの建築物で構成されるフィレンツェの信仰の中心である。1296年の着工から175年の歳月をかけて完成させた典型的なイタリアン・ゴシック建築であるといわれている。1時間ほど内部を見て、車を駐車しておいた場所へ戻ろうとしたら、道に迷って少し慌てた。やっと車を見つけて、少し周辺をドライブしたあと、ホテルに帰り、近くのレストランで夕食を取った。
次の日も、やはり車で観光にでかけた。英語と手振り身振りで地名を告げて道を訊いたりしながら、先ず、サンタ・クローチェ教会(Santa Croce)へ行った。この教会には、ミケランジェロ、マキャベリ、ロッシーニ、ガリレイなど、フィレンツェを代表する多くの文化人が眠っていて、276の棺が納められているという。歴史の重みをずっしりと支えているような教会であった。
つぎに、アルノ川沿いのウッフィツィ美術館(Galleria degli Uffizi)へ行った。ルネッサンス美術の集大成といわれるメディチ家の膨大なコレクションの展示は、じっくり鑑賞するためには1日や2日では足りない。画集や教科書などで見慣れたボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」、ミケランジェロの「聖家族」、マルティーニの「受胎告知」、ダヴィンチの「三賢王の礼拝」、カラヴァッジョの「イサクの犠牲」等々、私も富子も、心を奪われて食い入るように見入っていた。2、3時間も経つと、小学校5年生の潔典は疲れてきたらしい。「絵を見るのは飽きた」と言い出した。カフェで簡単な昼食を取り、アルノ川にかかる屋根付きのヴェッキョ橋のあたりを少し歩いたのち、一旦ペンションへ引き返した。
部屋で少し休んで、近くのマーケットへ歩いて出かけてみた。付近には、路上にも革製品などを広げて売っている業者が沢山いる。値段は高くはない。それを、買い物客は、いちいち値切って買っていた。そのやり取りが面白く、私たちもやってみた。英語と日本語でしゃべり、相手はイタリア語で返してくる。身振り手振りも加えて、それでも何とか、富子のショルダーバック、由香利の革ジャンパー、潔典の靴、それに土産用の財布などを買い込んだ。結構時間がかかったが、私たちは楽しみ、満足して、その日一日を終えた。
翌日の9月12日、車に荷物を積み込んで、ペンションを出たのは午前10時である。一路西へ、ピサへ向かって走った。ピサまで直線距離でおよそ70キロである。ハイウエイ55号に乗って、1時間ほどで着いた。
ピサは科学者ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)の生誕地である。彼は1564年にこの町で生まれた。落体の法則を発見するために、ピサの斜塔の頂上から大小2種類の球を同時に落とし、両者が同時に着地するのを見せたという故事は有名である。ただし、これは弟子ヴィヴィアーニ
(Viviani) の創作で、実際には行われていないとする説もある。
ピサは小さな町だが、中心部に近づくとドゥオモ広場があって、大聖堂の前に建つ斜塔が見えてくる。近くの駐車場に車を停め、斜塔の前に立つ。堂々たる重量感があって思っていたよりずっと大きかった。高さは55.86メートルで、296段の階段で上へ登れるようになっている。私たちが行ったとき(1974年)には、5.5度傾いているといわれていたが、その後、1990年から2001年の間に行われた工事によって、現在は約3.99度に是正されているらしい。
斜塔の前に建つ大聖堂にも入ってみた。ガリレイは、この大聖堂で揺れるシャンデリアを見て、振り子の等時性を発見したといわれている。暑い日差しのなかを歩き回り、洗礼堂、カンポサント(墓所回廊)なども見て、土産物店をのぞいたりする。その時買った斜塔の小さな置物は、44年後のいまも私の手許にある。
ピサからはリグリア海が近い。かつてのピサはこのリグリア海に面し、貿易によって財を成したイタリア最古の海洋都市であった。アルノ川が運ぶ土砂により、現在のピサは内陸の町になってしまったのである。その日は、ピサを出てからは、海岸に沿って通っているハイウエイ1号線で、ジェノバへ(Genova)向かった。2時間ほどでジェノバに着いてからは、右折して、ハイウエイ9号(現A7)でミラノへの進路をとった。
ミラノでも、大聖堂を車窓から遠望しながら素通りし、さらに北上してコモ湖南端のコモ(Como)を通った。そこからスイス領に入って、ルガノ湖北岸のルガノ(Lugano)に着いたのは午後4時過ぎであった。美しい湖を背景にしたリゾート地のような感じである。ルガノ西端のルガノ駅前にホテル予約センターがあったので、一泊の予約をする。80フラン、約25ドルで、当時としては安くはなかった。しばらく湖畔の美しい風景のなかをドライブして、予約したベーハ・ホテル(Beha
Hotel)に着き、一休みしてから、近くのレストランで夕食を取った。魚料理は美味であったが、値段も高級料理店並みであった。
7.アルプス山脈・ゴッタルド峠のカウベル
翌日、9月13日、ホテルを出て、真っ直ぐにハイウエイ9号を北上した。アルプス山脈の中に入り込んで、周辺には、高く低く、山々が連なっている。道路も屈折を繰り返しながら、昇り勾配が続くようになった。ところどころに目につく谷間へ傾斜する緑の草原には、牛の群れが放牧されていたりする。カウベルのカランカランと鳴る響きが耳に心地よかった。
1時間半ほどゆっくりドライブして、ゴッタルド峠(独Sankt Gotthard、伊San Gottardo にさしかかった。標高2108メートルで、この峠からのアルプス山脈は絶景であった。峠には軽食堂や売店もあって、ここで土産物なども買う。いまでは、1980年に開通したゴッタルド道路トンネルを通ることが多いから、この峠をトコトコと越えていった経験は貴重な思い出である。
それからの道路は下り坂になって、ゆっくり周辺の風景を楽しみながら2時間近く走って午後2時過ぎ、ルツェルンに着いた。ルツェルン(独Luzern、英Lucerne)は、ルツェルン湖のほとりにあって、周囲はアルプスの山々で囲まれている。中世からの建築が多く、湖の景観とよく調和して、絵のように美しい街である。
湖から流れ出ているロイス川には、花で飾られた屋根つきの橋、カペル橋がかかっていて、その北側にはやはり花々で飾られた美しい家々が建ち並ぶ旧市街がひろがっている。メンデルスゾーン、チャイコフスキー、ゲーテなど、多くの芸術家たちからも愛されてきた街だという。このカペル橋と旧市街の明るく品のよい佇まいは、その後も長く、私の胸の中に忘れがたい印象として残った。
ルツェルンは、また、時計の町でもある。当時は、スイス製時計は高級品のイメージがあった。潔典は、スイスで時計を買うことを目標にして、日ごろから小遣いを貯めていた。フロマーのガイドブックで紹介されている時計屋を見つけて入り、気に入ったデザインの腕時計を
50ドルで買うことができて彼は嬉しそうであった。
ルツェルンからは、スイス国道4号(現8号)で西南に下り、ブリエンツヴィラー(Brienzwiler)からは、ブリエンツ湖(Brienzersee)の南側の湖畔に沿って30分ほどドライブして、インターラーケン(Interlaken)に着いた。12世紀に建てられた修道院を起源とする小さな街だが、ユングフラウ登山などへ向かう際の拠点になっている。街を通りながらも、ユングフラウの雪を頂いた山容がくっきりと遠望できて、壮麗であった。
インターラーケンからは、国道6号(現8号)でトゥーン湖(Thunersee)の西岸を北上して1時間ほどでスイスの首都ベルン(Bern)に着いた。U字型に流れるアーレ川(Aare)に三方を囲まれた田園都市のような感じの街である。中心部を一巡しただけで、国道12号(現在も12号)を西南に下ってレマン湖のほとりにあるローザンヌ(
Lausanne)を目指す。途中、地図に名前も載っていないような小さな村を通ったら、あのインスブルックの民宿のように“Zimmer”の看板が出ている家があった。Zimmer(部屋)は、もちろんドイツ語だが、イタリアでもこの地方では、「民宿」の代名詞になっているらしい。
4人が泊まれる部屋があるというので、ここで一泊することにした。その日は、朝、イタリアのルガノを出て、ゴッタルド峠を越えてスイスに入り、ルツェルン、インターラーケン、ベルンを経て、ここまで来るのに330キロほども走ったことになる。時間も午後6時を過ぎていた。
その家の近くに村のレストランがあるというので行ってみると、十人ほどの男女の村人たちが、ワインやビールを飲みながら賑やかに談笑していた。突然、見も知らぬアジア人一家が入ってきて、みんなはちょっと驚いたようであったが、すぐに打ち解けて、私たちを歓待してくれた。彼らはフランス語かイタリア語で話しかけてくる。よくわからないなりに、私と子供たちは英語で受け答えする。彼らの中にも英語が少しわかる人がいて、なんとか話も少しは通じたようであった。楽しい雰囲気であったし、食事のビフテキも、美味しかった。
翌朝、Zimmer で、朝食をとったあと、国道9号でレマン湖北岸のローザンヌまで走り、街の中心部を素通りして、そこから南西約50キロのジュネーブ(Geneve)へ向かった。レマン湖の北岸を通るヨーロッパ・ハイウエイ4号(現スイス国道1号)からは、湖の彼方に聳え立つアルプスの山々がよく見える。モルジュ、ロール、ニヨン、コペなどの湖畔の町を通過して、ジュネーブには1時間ほどで着いた。
ジュネーヴには、国連ヨーロッパ本部、国際赤十字本部など、多くの国際機関の事務所があり、外交や銀行の国際的な中心地でもある。車でレマン湖の大噴水、ルソー島、サン・ピエール大聖堂、ジュネーブ大学などを見て回った後、歩いて、宗教改革記念碑、イギリス公園の花時計なども見て写真に収めた。晴れていれば、ヨーロッパ・アルプスの最高峰
4,810メートルのモンブランもよく見えるはずなのだが、生憎その日は薄曇りの天気で、折角の偉容が霞んでしか見えないのがちょっと残念であった。
8.ジュネーブからパリへ
昼食を取った後、ジュネーブから北へ向かうと、すぐに小さなフェルネ・ヴォルテール (Ferney-Voltaire)の町に着く。ここからはフランス領である。ここでも、国境の検問では、車に座ったままパスポートを見せるだけであった。ここから屈折の多い山道を通り、北西のロン・ル・ソニエ(Lons
le Saunier)までは、100キロくらいだが、2時間以上もかかった。くねくねした山道を下っていきながら、パリへ向かっているという実感があった。さらに1時間ほど北へ走って、ディジョン(Dijon)に至り、ここでガソリンを入れる。50ドルを渡して、お釣りをフランでもらった。
ディジョンから西北に約150キロ走るとフランス中央部のオーセール(Auxerre)の町に着く。人口2、3万人の小さな町だが、ここでホテルを探したが見つからない。さらに30キロほど走って、ジョワニー(Joigny)へ向かう途中、やっとモテルを見つけて、泊ることが出来た。その日は、ローザンヌの手前の小さな村から走り始めて、500キロほども走ったことになる。少し疲れた。
翌日は9月15日で、日曜日である。モテルで朝食を取った後、ジョワニーからは、国道6号線で北上する。この近くからヨーロッパ・ハイウエイ1号(現在A6)に乗れば、北西のパリまで一直線に約150キロで、1時間半で行けるが、時間がかかっても国道の方が、通っていく街の様子や周辺の風景などを身近に見ることが出来る。国道6号は、マロニエの並木が続いて美しかった。田園風景のなかを時折通り抜ける街の佇まいも、スイスとはまた違い、趣きがあるような気がした。
サンス(Sens)を通り、モントロー(Montereau)、リュザン(Lieusaint)を通って、クレテイユ(Creteil)まで来ると、もう市街地らしくなり左側にセーヌ川も見えてくる。セーヌ川の右岸に沿ってしばらく進むと、やがて午後1時過ぎに、シテ島のノートルダム大聖堂(Cathédrale
Notre-Dame)の前に辿り着いた。全長127メートル、高さ63メートルの壮大なゴシック建築で、1804年には、帝政を宣言したナポレオン・ボナパルトの戴冠式がここで行われた。日本でも、ヴィクトル・ユゴーの『ノートルダムのせむし男』などで、子どもたちにもよく知られている。
近くの駐車場に車を停めて、大聖堂の中に入る。ゆっくりと一巡したが内部は広い。9000人も収容できるそうである。バラ窓のステンドグラスから差し込んでくる光が神々しく感じられた。売店でパリの地図を買い、セーヌ川に沿ってしばらくドライブする。ルーブル美術館の前を通り、エッフェル塔を眺めて、オペラ座の近くで「うなぎ定食」のメニューを掲げた日本食レストラン「さくら」を見つけて中に入った。
日本でも、1964年から海外渡航が自由化され、長い間1ドル360円であった為替相場もその前年の1973年から変動相場になっていたが、まだ海外へ出かけられるのは富裕層に限られていた。「さくら」もおそらく、そのような富裕層の日本人旅行客向けレストランのようであった。いまでは、寿司店からラーメン店に至るまで、パリには数多くの日本食レストランがあるが、当時はまだ、「日本食」の店は珍しかった。
「さくら」の店員は、横柄であった。うなぎ定食を注文したら、ない、という。代わりに「串かつ定食」を4人分頼むと、2人分は「餃子定食」にしてはどうか、という。私たちは少し気分を悪くして、不満足な食事を早々に切り上げ、店を出た。
まず、フロマーのガイドブックを参考にホテル探しをする。ナポレオンの墓があるアンヴァリッド(廃兵院、Les Invalides)を訪れ、教会の内部中央に置かれた巨大な大理石の石棺を見る。この中でナポレオンは眠っているのである。そのアンヴァリッドの近くに、ガイドブックに書かれた安いホテルがあった。行ってみると、インド人経営のホテルで、部屋はあるという。見てから決めよ、といわれて部屋を見に行くと、乱雑で不潔な感じがした。諦めて、また少し車で動き回り、エミール・ゾラやヴィクトル・ユーゴ、ジャンジャック・ルソーなどが埋葬されているというパンテオン(Panthéon)の近くで、何とか気に入った部屋を見つけて2泊の予約をとることが出来た。
ホテルの前に駐車して、部屋で少し休んだ後、ホテルの周辺を散歩する。街角のパン屋で、サンドイッチとオレンジジュース、ミルクなどを買って帰った。フランスでも、ことばにはあまり不自由した記憶はない。いまはそれほどでもないが、当時のフランス人は、英語に対する優越感のようなものがあったかもしれない。こちらの英語の意味が分かっても、フランス語でしか返事をしない傾向があった。私たちは、相変わらずの手振り身振りを交えての英語でなんとか意志の疎通をはかってきた。一旦ホテルへ戻って、サンドイッチで夕食をすませた後、また外出して、リュクサンブール公園やモンパルナス界隈を散策した。
翌日は、ホテルでの朝食後、地下鉄でルーブル美術館へ行った。いまは世界で最も入場者数の多い美術館といわれていて、毎年800万人を超える入場者に対応するために、美術館前の広場にガラスの大きなピラミッド型の建物があるが、当時は、ピラミッドはなく、あまり混雑もなかった。先史時代から19世紀までの様々な美術品35,000点近くが、総面積60,600平方メートルの展示場所で公開されているだけに、3時間ほど見て回っても、ほんの一部しか鑑賞できなかったが、やはり、「モナリザ」の前では、しばらく動けなかった。写真も何枚も撮ったが、いまは人だかりがして、撮影も禁止されているようである。
ルーブルを出てからは、エッフェル塔(La tour Eiffel)へ行った。放送用アンテナの部分を含めると、塔の高さは324メートルで、3つある展望台のうち、最も高い276.1メートルの第3展望台へエレベーターで上がってみると、パリの市街が一望できる。セーヌ川の西の彼方にはブローニュの森が見え、北の方向にはエトワール凱旋門が見える。2キロ東には、コンコルド広場の緑も目に入った。
エッフェル塔を降りてからは、モンマルトルへ行った。モンマルトル(Montmartre) は、パリでは一番高い丘である。パブロ・ピカソやアメデオ・モディリアーニなどのかつての貧乏画家達がモンマルトルの「洗濯船(Le
Bateau-Lavoir)」と呼ばれる安アパートに住み、アトリエを構え、ジャン・コクトー、アンリ・マティスらも出入りして活発な芸術活動の拠点になっていたといわれるが、1914年以後は多くはモンパルナスなどへ移転した。キャバレー「ムーラン・ルージュ」の傍のゆるやかな坂を上っていくと、丘の上にロマネスク様式の壮麗なサクレ・クール寺院
(Basilique du Sacré-Cœur)が建っている。私は後年、何度かこの坂を上り、サクレ・クール寺院のクリスマス・ミサに参列したこともあったが、このときは寺院のなかには入らなかった。
モンマルトルからは、凱旋門へ出て、シャンゼリゼの大通りを歩いた。グランパレ(Grand Palais)、コンコルド広場(Place de la
Concorde)、マドレーヌ寺院(Église de la Madeleine)などを見て、モンパルナスへ戻り、中華料理店で遅い夕食をとってホテルへ帰ったのは午後10過ぎであった。朝から随分歩き回って、みんなも疲れたような顔をしていた。
9.パリからブリュッセルへ
翌日、9月17日は、ベルギーのブリュッセルへ向かう日である。朝9時半、ホテルを出て、車でオペラ座やトリニティ教会の前を通って北へ向かい、ヨーロッパ・ハイウエイ3号(現A1号)に乗った。ここからは道路地図の距離表では、ベルギーのブリュッセルまで301キロである。一路、北へ向かって走れば3時間で着く距離で、アメリカを走り回った経験からは、やはりヨーロッパは広くはない。ブリュッセルで、その日の夕方、レンタカーを返す予定にしていたが、充分に時間の余裕はあった。
2時間近く走って、コンブル(Combles)を過ぎたあたりで、ハイウエイ 3号線から北東へ逸れてハイウエイ10号線(現A2号)に入った。スカルプ・エスコー自然公園(Parc
Naturel Regional Scarpe Escaut)の東側を通り過ぎたところで、フランス・ベルギーの国境線に到達する。車の中からパスポートを見せただけで簡単に検問を通過した。ヨーロッパ・ハイウエイ10号線はまだ続くが、ベルギー側では、現在はここからハイウエイE19に変わったいる。ニヴェル(Nivelles)あたりから国道に入り、15キロほど走ってワーテルロー(Waterloo)に着いた。
ここは、ナポレオン戦争最後の戦闘となった「ワーテルローの戦い」(仏: Bataille de Waterloo、英: Battle of Waterloo)の現場である。1815年6月18日、ここで、イギリス・オランダをはじめとする連合軍およびプロイセン軍と、フランス皇帝ナポレオン1世(ナポレオン・ボナパルト)率いるフランス軍との間で戦闘がおこなわれて、フランス軍が敗北した。「ライオンの丘」と名付けられた小高い円錐形の丘が築かれていて、周辺には、土産物店、レストラン、ホテル、民間の博物館が散らばっているだけである。「ライオンの丘」に登り、小さな記念の土産物を買って、ブリュッセルへ向かった。
30分ほど走って、ブリュッセルに着いてからは、まずホテルを探した。少し道に迷ったりしたが、翌日、ロンドンへ発つことを考えて、ブリュッセル南駅(Gare
de Bruxelles-Midi )の近くのクレマンソー・ホテル(Residence Clemenceau)を見つけて、一泊の予約を取ることが出来た。
スーツケースを部屋に運び込んで少し休んだ後、車で市内のあちらこちらをドライブする。サン・カトリーヌ教会、王宮、王立美術館などを、車窓から見た。走り回りながら、Herz
のブリュッセル支店を探し、2週間生活を共にしてくれたフォード・エスコート(Ford Escort)を返却した。アムステルダムでドライブを始めて以来、2週間で、4,500キロほど走ったことになるが、それも無事に終えることが出来て、この車にも感謝したい気持ちであった。
あとは、歩いて街の観光を続けた。「小便小僧」の像は見たが、その近くにあるグラン・プラス(Grand Place)を見過ごしてしまった。ここは、ヴィクトル・ユーゴーが
“世界で最も美しい広場”と絶賛したという、ブリュッセルでも一番の見どころである。私は、後年、数回ここを訪れているが、最初の旅行でグラン・プラスを家族に見せてやれなかったことを、いつも辛い気持ちで思い出していた。その9年後、富子と潔典は、アメリカから帰国の途中、事件に巻きこまれてサハリン沖で亡くなってしまったからである。
翌日、9月18日、ブリュッセル南駅発、12時36分の列車に乗って、西へ110キロのオーストエンデ(Oostende)へ向かう。ドイツあたりからイギリスへ修学旅行に出かけるらしい高校生の一団と一緒になってしまったため、列車は少し混んでいた。オーストエンデで、フェリーに乗り換えて、ドーバー海峡を渡った。ドーバー駅からロンドン・ヴィクトリア駅まで列車は、がらがらに空いていた。
窓外に広がる久しぶりのイギリスの田園風景がなつかしかった。列車は少し遅れて、午後8時半、ヴィクトリア駅に着いた。子どもたちは、見慣れた駅に帰ってきて、はしゃいだ。何よりも、英語で自由に話せるのが気持ちを和ませた。
10.ロンドンからアメリカへ帰る
ヴィクトリア駅のホテル予約センターで、コロナ・ホテルに問い合わせてもらうと、満員だという。「ヘンゼルとグレーテル」も満員で、しばらくは予約できないといわれて、アールズコート(Earls
Court)まで行き、少し高めのジョージ・ホテル(Hotel George)を予約した。とにかく泊まるところが見つかって有難かった。明日また、安いホテルを探すことにして、その日は、ゆっくりと休んだ。
翌日、9月19日の朝、ヴィクトリア駅裏のコロナ・ホテルへ電話してみたら、家族部屋がとれるという。3泊の予約をして、ジョージ・ホテルから、タクシーで荷物をコロナ・ホテルへ運んだ。これで、9月22日にアメリカへ帰る飛行機に乗るまでのホテルの部屋は確保できて一安心である。
その日は、ヴィクトリア駅の隣のBOAC空港ターミナルからバスでヒースロー空港まで行ってみた。私たちの乗る予定のカナダ・バンクーバー行きのチャーター機は、午前8時15分の離陸予定である。当時は、今ほど搭乗手続きに時間はかからなかったが、それでも、遅くとも出発1時間前までには、ヒースロー空港に着いていなければならない。バスの運行時間を調べ、出発手続きカウンターの場所を確認し、チェックインの手順などもよく聞いておいたうえで、私たちはまた、ヴィクトリア駅へ引き返した。
バスターミナル(Victoria Coach Station)で、翌日のストラットフォード(Stratford-upon Avon)行きの予約をとろうとしたら、満席であることがわかって、列車で行くことにした。Miki
Travel Service へ電話して、パディントン駅(Paddington Station)から出る列車の時間などを訊いておく。後は、ヴィクトリア駅の周辺を散歩し、夕食をとってホテルへ戻った。
翌日の朝、ヴィクトリア駅から地下鉄でパディントン駅へ行き、ストラットフォードへ向かった。ロンドンからの直線距離は約140キロだが、2時間近くで、ストラットフォードに着いた。
駅前から、オルスターロード通り(Alcester Road)を西へ10分も歩くと、シェイクスピアの生家に着く。中に入ると、シェイクスピが生まれたという部屋には、天蓋つきの小さなベッドなどが置かれ、食堂には、食卓の上に、食事に用いた木製のトレイが置かれていた。そのトレイには片隅に小さな塩を入れる窪みがある。塩というのはサラリー(給料、salary)が塩(salt)からきているように、金銭のように貴重であった。これを自由に使えるというのは、豊かさを示す象徴であった。
シェイクスピが 33歳という若さで購入したという地元で2番目に大きな邸宅「ニュー・プレイス」、シェイクスピア劇場、トリニティ教会なども見て回る。トリニティ教会(Holy
Trinity Church)は、シェイクスピアが洗礼を受け、晩年まで通った教会である。シェイクスピアは妻アン・ハサウェイと共にこの教会の内陣に埋葬されている。シェイクスピアの墓に刻まれている「この墓を暴くなかれ」ということばを拓本に取っている教会の人がいたので、頼み込んで一枚分けてもらった。いまでは貴重であるかもしれない。そう思って、その拓本を額縁に入れ、東京外国語大学文書館に寄付しておいた。
帰途、オックスフォードで下車して、オックスフォード大学を見学した。この大学は、英語圏では最古の大学で、現存する大学としては世界で3番目に古い。39のカレッジを持つ総合大学で、広範囲に学舎は分散しているから、短時間ではまわれない。途中でタクシーを拾って、タクシーで一まわりしてもらった。
オックスフォードからの列車は、鈍行に乗ってしまったので、パディントン着は、午後8時過ぎになってしまった。ヴィクトリア駅からうすら寒い夜道を歩いて帰る途中、馴染みになっている中華料理のテイクアウト店に立ち寄り、美味で安い料理を沢山仕入れて、ホテルで遅い夕食を取った。
翌日は、ロンドン観光最後の日である。ヴィクトリア駅の隣のバスターミナルから、6時間のロンドン周遊観光バスに乗った。ロンドン見物の総復習である。まだ行っていなかったハイドパークなどを含めて、主な観光箇所は全部見ることが出来た。大英博物館の図書館閲覧室の内部とデュビーン美術館(Duveen Gallery)などを見る。ロンドン大学もまた訪れて写真を撮ったりした。
午後4時過ぎに、バスツアーが終わった後は、オックスフォード・サーカス(Oxford Circus)やマーブルアーチ(Marble Arch)のあたりを歩いて、最後の買い物をする。夕方、ヴィクトリア駅を出て、BOACバスターミナルで、明朝のバスを確認したうえで、ホテルに帰る。中華料理のテイクアウトで夕食をすませてからは、明日の出発に備えて、みんな早めに寝た。
9月22日、日曜日、5時に起きて、荷物をまとめ、5時半にホテルを出たら、ちょうどタクシーが走ってきた。BOACバスターミナルまでは近いが、チップを余分にはずんで、ターミナル前まで行ってもらう。ヒースロー空港行きのバスも予定通り出発して、空港には、7時前に着いた。カナダ・バンクーバー行きチャーター機のチェックインをすませて、私は免税店でウイスキーなどを買い、チャーター機に乗り込んだ。チャーター機は30分遅れて8時45分に離陸した。とうとうイギリスともお別れだが、無事に帰りの飛行機にも乗れたということで、深い安ど感があった。
チャーター機は、スコットランドの上を飛び、アイスランド、グリーンランドの上空を飛び続ける。時折、眼下に展開する氷の世界をカメラに収めたりした。チャーター機は、約10時間の飛行の後、午後7時ごろ、バンクーバー空港に着陸した。時差が8時間あるので、カナダ時間では、午前11時であった。
入国審査は簡単で、税関の検査もほとんどなく、私たちは、1 か月近く駐車場に停めておいたシボレーに乗り込んで、真っ直ぐに南下し始めた。30分も走ると、もうアメリカに入る。安いガソリンを入れ、みんなで安いハンバーガーを食べ、よく冷えたて安いコーラを飲む。アメリカはいいなと思った。高速道路も無料だし、乗っているシボレーも年季が入った中古車だが、ヨーロッパで乗っていたフォード・エスコートよりも一回りも二回りも大きい大型車である。それに、もうホテルを探すのに気を遣うこともない。ユジーンには「わが家」が待っているのである。
私たちは、インターステイト・ハイウエイ 5号線を真っ直ぐに下って、途中2度ほど、サービスエリアで休憩を取りながら、オレゴン州ユジーンまでの約550キロの距離を6時間ほどで走った。1か月留守をしていたわが家に辿り着いたのは、午後8時である。これで、私たちの初めてのヨーロッパ旅行も無事に終わった。
私たちは、その年1974年の夏休み3か月の間に、アメリカとヨーロッパの旅行を企画し、子どもたちと一緒に旅行先の地理や歴史を勉強したりして、周到に準備していた。アメリカ旅行の方は、6月中旬から1か月半、車にテントと寝具、米や水などを積み込んで、アメリカ一周17,000キロの旅を終えていた。2週間休んで、出かけたのがこのヨーロッパ旅行であった。
それも終わって、その 2日後の 9月25日からは、新学年が始まった。由香利は中学校Jeffersonに進学して1年生になり、潔典は同じ小学校
Pattesonの 6年生に進級した。私もまた、大学の自分の研究室へ通うようになった。もう44年前の話である。いまでは、うたかたの淡い夢のように思い出される。
老いぬれば残れる春の花なるか
世に荘厳(おごそけ)き遊ぶ文章 ― 円空
(2018.08.01)
思い出の旅(2)―1974年夏 アメリカ (身辺雑記 No.120)
1.諦めかけていた8週間の旅
1973年の暮れから私は文部省在外研究員として渡米し、オレゴン州ユジーンのオレゴン大学(University of Oregon)に在籍していた。妻の富子と長女・由香利、長男・潔典も一緒であった。私たちは、ユジーンの大学宿舎に住み、子どもたち二人は、近くのパターソン小学校(Patterson)の6年生と5年生として通学していた。
アメリカの学校は、大学も小学校も、6月の中旬から3か月の夏休みに入る。この夏休み中に、出来れば車でアメリカを一まわりしてみたいと考えていた。ユジーンの私たちの家の壁には、大きな世界地図と、それと同じくらい大きなアメリカ地図が、はりつけられていた。このアメリカ地図の方には、かつて私が大学院時代に、車とバスで走り回ったアメリカ一周の足跡を、太い赤線で示してあった。私たちは、この同じ地図の上に、もう一本のアメリカ一周の線を、何度か、書いては消し、消しては書いたりして、アメリカ一周のプランを練っていた。
車は61年型シボレーであった。大型でよく手入れされて外観も美しく、エンジンの調子もよかったとはいえ、13年間にすでに、20数万キロメートルも走った老朽車であった。クーラーもついていなかった。オレゴンでは、クーラーがない車が多かったが、オレゴンを出てこれだけの大きな旅行をするとなると、いささかの不安がなかったわけではない。
だいたいこの車を買った時は、例のオイルショックで、オレゴン州ではガソリン不足が特にひどかった。10ガロンのガソリンを求めて、朝5時からスタンドの前に並んだり、160キロ離れたポートランドへさえも、帰りのガソリンが心配で行けなかったくらいである。大学へ通う足として、やむなく買ったものの、その時は、この車でアメリカを一回りするなどということは、私自身、全く予想はできなかった。
そのオイルショックによるガソリン不足が、春先から急に改善され始めた。やがて、ガソリンはいつでも買える元の状態に戻った。そこで私たちはまた、アメリカ一周旅行を真剣に考え始めたのである。車を買い替える余裕はなかったから、行くとすればこの車に頼るしかなかった。
車の故障のかなり高い可能性を含めて、この広大な大陸の地表を、アリのように這っていくには、はじめからいろいろな困難が予想されていた。「自殺行為だ」と脅かした大学の同僚もいたくらいである。いろいろと考えた末、結局、私たちは決行することにした。テントと寝具、米と水、食料品なども積んで、私たちは、アメリカ大陸を横断して東海岸まで行って戻ってくる来るという8週間の旅に出かけたのである。
2.ユジーンを出発する
6月19日、水曜日、出発の日である。オレゴン大学の客員教授で同僚の増田さんの家を訪ねて出発の挨拶をした。増田さんは、夏休み中、ボルチモアへ行く予定をたてていた。私たちも、途中でボルチモアを通過するときに、再会することを話し合っていた。
ユジーン市外へ出て、インターステイト・ハイウエイ5号で南下し始める(インターステイト・ハイウエイとは、いうまでもなく全米を網羅する高速道路の大動脈である。以下、「インターステイト」と略記する。つぎに「ステイト・ハイウエイ」、「ハイウエイ」がある)。ローズバーグ(Roseburg
)を過ぎ、グランツ・パス(Grants Pass )を経て、2時間ほど走った後で州立公園(Rogue River State Park )に着いた。
州立公園には、たいていキャンプ場の設備があって、安い料金で泊まれる。トイレ、シャワー室、売店などがあり、キャンプ用敷地(camping lot)には、数人が座れる木製の椅子付きテーブルと、煮炊きができる炉と水道がついているのが普通である。ここの公園には、22
のテント用敷地があったが、午後1時頃であったのに、もうすでに大半が埋まっていた。事務所で1泊の予約をして、テントをはり、寝転んで少し休む。出発前までは、いろいろと準備で忙しかったが、ここで一息つくことが出来た。
翌朝、午前9時、朝食を終え、テントをたたんだ後で、インターステイト5号に乗り、東南に向かって走り続ける。メドフォード(Medford)、アッシランド(Ashland)を通って、1時間足らずで、カリフォルニア州に入る。さらに南下してレッディング(Redding)で5号線から降り、ステイト・ハイウエイ44号に乗り換えて、東へ向かった。そこからは、約50キロ走れば、ラッセン国立公園(Lassen
National Park)のキャンプ場に着くはずであった。
ここで、くねくねと曲がっている山道を上がっているうちに、車のエンジンの微かな不調和音を感じる。平地を走っている間は問題ないのだが、急勾配の坂道を登り続けると
61年型車であるだけにエンジンに過重負担がかかって圧縮漏れを起こしているのかもしれなかった。それでも、なんとかキャンプ場入口に辿り着くと、通行止め(Road
Closed)のサインが出ている。がっかりして、近くの キャンプ場(Hat Creek Camping Area)へ行き、ここで1泊することになった。
このキャンプ場には水道がないので、すぐ下の別のキャンプ場からポリ容器で水を運ばなければならなかったが、キャンプ場そのものは、山の中の静かな環境で気持ちが安らいだ。氷のように冷たいHat
Creekのせせらぎの音が快かった。
6月21日、金曜日。Hat Creek Camping Area からスーザンビル(Susanville )へ出て、ハイウエイ395号で Reno
へ向かう。ホニー湖(Honey Lake)のほとりを東南に下り、ドイル(Doyle)を通ってコールド・スプリングス(Cold Springs)まで来たところで、ネバダ州に入った。Susanvilleからは105キロほどの距離である。
州境から30分ほど走ればリノ(Reno)に着くはずであったが、道を間違えたらしく、Reno の街外れに出てしまった。ネバダ州は賭博公認の州である。Reno
も州内の規模はラスベガスに次ぐカジノ・シティとしても名高く、“The Biggest Little City In The World”(世界で一番大きい小都市)という愛称がある。
Reno を過ぎて、さらに40分ほど南下し、カーソン・シティ(Carson City)でマクドナルドに入り、ハンバーガーの昼食をとる。この町にもカジノがあり、見学のために入ってみた。スロットマシンでしばらく遊ぶ。日本のパチンコと同じようなもので、景品の玉が出る代わりに、お金がじゃらじゃら出てくるので刺激は強い。3ドルほど「出資」した後で、カジノを出て、近くの州立博物館で1時間ほど館内を見て回った。
カーソン・シティからはタホー湖(Lake Tahoe)が近い。タホー湖は、カリフォルニア州とネバダ州の州境のシエラネヴァダ山中にある北米で最大の高山湖(湖面の標高1,898メートル)である。面積は496平方キロもあって、湖岸線の
3分の2はカリフォルニア州に属している。夏の避暑地として有名で、その自然美は、世界有数といわれている。湖畔を半周し、カリフォルニア側の キャンプ場(General
Creek Camping Ground)に午後4時過ぎに到着した。
このキャンプ場は、売店のほかトイレやシャワーの設備もよく、閑静で快適な環境であった。ここで3日間休養することにした。朝はゆっくり朝寝坊し、昼間は散歩したり、テーブルに座って本を読んだり、フリスビーなどで遊んだりする。たまには車で湖のまわりをドライブした。湖の色が実に美しく、見ていて飽きなかった。
6月24日、月曜日。General Creek Camping Ground を朝9時に出発する。Lake Tahoeを半周して、もとの Carson
City へ戻った。富子のズボン、子どもたちのサンダルを買い、食料品などを仕入れた後、ハイウエイ50 号でシルバー・スプリング(Silver
Spring)に着く。
このあたりは広漠とした一面の荒野で、外はすさまじい熱気である。クーラーがない車内では、耐え難かった。この暑さでは、このまま南へ下がることはできない。進路を変更して、そこからはユタ州を通ってコロラド州へ向かうことにした。ハイウエイ95号を北上してインターステイト80号に乗る。
ハイウエイの周辺には、走っても走っても、荒涼とした灰色の荒れ地が続いた。カーソン・シティから1時間半ほど走ったところで、 道路地図の上では砂漠のオアシスのような森林と湖の州管理地域(Humboldt
State Wildlife Management Area)がある。そこにキャンプ場もあることになっていたが、行ってみるとそれはなかった。
そのままさらにインターステイト80号を1時間半ほど北東に進んで、荒れ地の中の小さなウィネマッカ(Winnemucca)の町のモテルに泊まる。室内はクーラーで冷やされて、快適である。ダブルベッド一つの部屋しかなかったので、子どもたちは床のカーペットの上にスリーピングバッグを広げて、はしゃぎながらもぐりこんだ。
翌日、ウィネマッカのモテルを朝9時に出発する。インターステイト80号を東へ3時間ほど走って、ウェルズ(Wells)付近でキャンプ場を見つけるつもりでいたのだが、相変わらずの荒涼たる荒れ地が一面に広がっているだけで、キャンプ場もありそうもない。
そのまま東へ走り続けて、ウエスト・エンドーバー(West Wendover)でユタ州に入り、200キロ近くのドライブでソールト・レイク(Salt
Lake)に着いた時には、午後5時近くになっていた。ユタ州は、アメリカの4つの標準時のうち、山岳部標準時になる。太平洋標準時の午後5時は、ここでは、午後6時である。時計の針を1時間進ませる。
この湖は塩分が濃く、手足を動かさなくても体は沈まない。湖畔に車を停めて、潔典と30分ほど水に浮かんでみたりした。その日は、Salt Lake
City市中のモテル(Motel Chateau)に泊まった。ダブルベッド二つの広めの部屋で12ドル。冷房もよく利いて、清潔ないい部屋であった。
3.ロッキー山脈を越える
モテルで朝食をとり、10時に車でSalt Lake Cityの市内観光に出た。ユタ州議事堂、パイオニア博物館、モルモン教の総本山(Temple Square)などを見て回った。6つの尖塔をもつ神殿、大聖堂などは壮観である。街は整然と碁盤の目のように区画されていて、清潔で美しい。
ユタ州立大学を見学し、そこから私の留学生時代にも訪れたことがある郊外の “This is the Place”記念塔まで車を走らせた。ここが
Salt Lake City発祥の地である。
モルモン教徒たちは、周辺の住民からの迫害や抵抗を受け、1844年には教祖のジョセフ・スミスが暴徒に殺害されている。あとを引き継いだブリガム・ヤングが、1万5000人の信徒、ワゴン3000台、牛3万頭を引き連れてアメリカ大陸を西へ西へと移動し、1年がかりで2,100キロを踏破して辿り着いたのが、このSalt
Lake Cityであった。この記念碑のある丘の上から前面に広がる緑の大地を見下ろして、「この場所に決めよう」(This is the Place)とブリガム・ヤングが言った言葉が、この記念碑の由来である。
私たちは、この記念碑を見た後、そのままハイウエイ40号を東に向かって走り続けた。周辺は緑が目立って濃くなり山の中を走っている感じである。長い上り坂が続くと、やはり車の馬力は十分に出ないようであった。老馬に鞭打って走るような気持ちになる。ダッチェス(Dutchesne)、ヴァーナル(Vernal)を経て、ダイナサウル(Dinosaur)でコロラド州に入った。
ダイナサウル国定公園(Dinosaur National Monument)の南側をしばらく走っても、適当なキャンプ場は見当たらない。時々小休止をとりながら、さらに走り続けて、午後8時、クレイグ(Craig)
という小さな町に着く。ここで夕食を取って、モテルに泊まった。ダブルベッド二つの部屋で18ドル。暑いのに冷房がよく利かず、あまりいい部屋ではなかった。この日は、朝から約450キロ走ったことになる。
6月27日、木曜日。モテルを午前10時に出発して、ハイウエイ40号を一路東に向かって走り続ける。ハイウエイの周辺は緑がだんだん濃くなっていって田園風景が美しい。1時間ほど走って、スティームボート・スプリングス(Steamboat
Springs)でハイウエイは 国有林(Medicine Bow Routt National Forests)の山塊にぶつかるのを避けて右折し、20キロほど南下する。そのあと東に向きを変えて、いよいよロッキー山脈を越えていくことになる。二つの峠を越えなければならないが、最初の峠が、20キロほど坂道を登ったところにある
高度 2,873 メートルのラビット・イアーズ峠(Rabbit Ears Pass)である。
Rabbit Ears Pass は何とか越えた。峠には、ロッキー山脈分水嶺(Continental Divide)のサインがあった。降った雨は、ここから西側が太平洋に向かって流れ、東側が大西洋へ流れることになる。
やがてハイウエイ40号は右折して南下し、1時間ほど走って着いたクレムリング(Kremmling)で東に向きを変える。そこから約20キロのところにグランビイ(Granby)という町があった。ロッキー山脈のなかの小さな町だが、周囲は広々した平地になっていて、往復4車線のメインストリートには、レストラン、食料品店、雑貨店、自動車修理工場などもある。
この町の東側には、ロッキー山脈の山塊が連なり、国立公園(Rocky Mountain National Park)になっている。町から北東20
キロには湖(Grand Lake)があって、その湖畔のキャンプ場(Grand Lake Camping Ground)に辿り着き、ここで2泊することにした。湖を見下ろす広々としたキャンプ場の1区画に、車を停め、テントを張り、ゆっくりと手足を伸ばして休んだ。
美しい自然のなかのキャンプ場は、トイレやシャワーの設備もよく快適であったが、夜は寒いくらいであった。この湖では、鮭の子が釣れるらしい。なぜか無性に、ゴムボートを浮かべて釣りをしてみたい気持ちがした。
午後、車で、潔典と二人でグランビィ( Granby) の町へ下りて行って、自動車修理工場へ行き、翌朝、自動車を点検してもらう予約をした。食料品店にも寄って、バーベキューの食材などを買う。夜は、キャンプ場の集会室で、ロッキー山脈の四季を撮ったスライドショーを行うというので、みんなで観に行った。
翌朝 8時。潔典と二人で、車の点検をしてもらうためにグランビィへ行った。このあたりは夏でも気温は低い。潔典は車のヒーターをつけたがったくらいである。修理工場では、結局、1時間ほどかけてキャブレターの掃除とディストリビューターの配線を替えただけであったが、それでも30ドル取られた。キャンプ場へ引き返し、テントや寝具類を車に積み込んで、昼前にキャンプ場を離れた。
Granby からまたハイウエイ40号に乗って、南東へ向かう。いよいよロッキー山脈越えである。往復2車線のハイウエイは、くねくね曲がりながら上り勾配が続く。50キロ近くも上り続けて、私たちにとっては、第二の関門であるバーサッド峠(Berthoud
Pass)に行き着くのだが、この峠は、高度が 3,446メートルもあって、富士山(3,776メートル)の高さに近い。喘ぎ喘ぎ走り続けていた車は、峠まであと10分というところで、とうとうエンジンが止まってしまった。さすがに青くなった。
道路の右端に停まったまま、ボンネットを開けてみたが、白い煙が出ていて、エンジンが過熱しているようであった。もしオーバーヒートであるなら、しばらくエンジンが冷えるの待つしかない。私はまた、ボンネットを下ろして、運転席に座り込んだ。
すると潔典が、「お父さん、ボンネットは上げておいたほうがいいと思うよ。事故であることがわかるようにして、誰かに助けてもらわなければならないから」と言った。その通りかもしれない。ハイウエイ・パトロールを呼ぶにしても、誰かに頼まなければならないのである。私は、また外に出て、ボンネットを上にあげた。
しばらくエンジンが冷えるまで待ってみてもエンジンがかからなければ、やはりハイウエイ・パトロールを頼まなければならない。すると、2,3分も経たないうちに、車が一台近づいてきて、中年の男性が下りてきた。「何かお手伝いできることはありませんか」と訊く。私は、お礼を言って、事情を説明し、エンジンが冷えるのを待っているところだと答えた。
その男性が立ち去ると、すぐまた、別の一台がやってきて停まった。今度は若い学生風の男性が、同じように、「何かお役に立つことがありませんか」と尋ねる。私はまた、お礼を言って、同じように答えた。次から次へと、5台くらいが停まってくれた段階で、私はボンネットを下ろして、途中で小休止している様子を装った。人々の親切が身に染みて有難かった。
30分近く経ったであろうか、私は祈るような気持ちで、エンジンをかけてみた。エンジンはすぐにかかった。車が動くこともわかった。私たちは、なんとか無事に、高度 3,446メートルのバーサッド峠を越えた。
ハイウエイ40号は4,5度大きく折れ曲がりながら、徐々に高度を下げていく。バーサッド・フォールズ(Berthoud Falls)でもう一度大きく折れ曲がって、あとは真っ直ぐに東へ向かい始めた。下り勾配だから、車は楽に走り続ける。
30分近く走って、エンパイア(Empire)を過ぎたところで、インターステイト70号に入った。アイダホ・スプリングス(Idaho Springs)を過ぎて間もなくステイト・ハイウエイ
6号に乗り換え、40分ほど走って、ゴールデン(Golden)に着く。ここはもう、デンバーの郊外である。ゴールデンのガソリン・スタンドでガソリンを入れたら、タイヤの1本がすり減っていて危険だという。言われるままに1本、新品に取り換えたが、走り出すと、タイヤが少しガタガタするような感じである。
デンバー市内に入ったところで、モテルを見つけて1泊の手続きをした。車から荷物を部屋へ運び込んだ後、近くのガソリンスタンドで、タイヤを見てもらったら、ゴールデンで入れ替えたタイヤがチューブレスでリムとうまく適合していないらしい。タイヤのリムを修理するか交換しなければならないという。これは日ごろから感じさせられていたが、アメリカ人の修理工は、もちろん全部ではないにしても、どうも仕事ぶりが杜撰である。
仕方なく、買ったばかりのタイヤを預けて、スペアタイヤを使うことにした。翌日は日曜日なので月曜日の午後1時までに修理してもらうことにする。最後までトラブルが続き、ちょっと大変な一日であった。それでも、何よりも車が動き続けてくれたのは有り難かった。
翌日、6月30日の日曜日、みんなで少し朝寝坊する。昼前に、モテルをチェックアウトし、昨日、タイヤを預けたガソリンスタンドのジョイ(Joy)から紹介された新しい別のモテル(Motel
Westerner)へ移った。午後、車でデンバー市内を見てまわる。
デンバーは大都会である。海抜1,607メートルの高地にあるので “The Mile High City” と呼ばれて、夏でも気候は爽やかで暑くはない。避暑地のようなもので、アメリカ人の住みたがる街の一つである。ダウンタウンには高層ビルが立ち並び、街並みは整然と碁盤の目のように区画されて、清潔で美しい。コロラド州議事堂、デンバー美術館、デンバー大学(University
of Denver)などを訪れた。
7月1日、車に荷物を積み、モテルを10時過ぎに出て、市内観光を続ける。市立公園(City Park )へも行ってみた。緑が広がる広大な敷地の中に湖があり、動物園やデンバー自然科学博物館などがある。自然科学博物館は、動植物から鉱物にいたるまで、珍しい標本などがふんだんに金をかけて豊富に展示されているような趣がある。
午後1時、タイヤを預けておいたガソリンスタンドへ行った。店主のジョイの努力にもかかわらず、タイヤのリムは私の車に合うのは見つからなかったらしい。結局、スペアタイヤのリムをチュウブレスタイヤに転用して間に合わせることになった。街のレストランで昼食を取った後、午後3時半、やっとデンバーから抜け出して、東へ向かって進み始めた。
4.ネブラスカの夜半の嵐
インターステイト76号に乗る。ハイウエイはバーレイク州立公園の西端を掠めて北東に進み、ロックビー(Lochbuie)、ハドソン(Hudson)、フォート・モーガン(Fort
Morgan)、ブラッシ(Brush)、スターリング(Sterling)を経て、ジュールスバーグ(Julesburg)を過ぎたところでネブラスカ州に入った。
ここから50キロほど東にオガラーラ(Ogallala)の町がある。その近くにオガラーラ湖(Lake Ogallala)があって、その湖畔のオガラーラキャンプ場にテントを張って泊った。その日は、デンバーから約350キロ走ったことになる。
その翌日は、オガラーラからインターステイト80号で東進する。230キロほど荒涼とした荒れ地を走ったところで、カーニー(Kearney)という小さな町に着いた。市内には、グッド・サマリタン病院とネブラスカ大学カーニー校があるが、周辺に僅かに農地の緑が広がるだけの砂漠の中の町という感じである。もともとここは、アメリカ陸軍の砦(fort)が1848年に築かれたところであるらしい。
街の南側にプラット川が流れていて、その川べりの緑地(Fort Kearney State Recreational Area)に キャンプ場がある。一泊したが、あまりいいキャンプ場ではなかった。おまけに、真夜中、突然に猛烈な強風が吹いてきて、テントが吹き飛ばされそうになった。子どもたちも一緒になって、みんなでテントの中から必死になってポールを支えているうちに、30分ほどで嵐は通り過ぎて、あとは嘘のように静かになった。
翌朝、カーニー砦(Fort Kearney)の遺跡を見た後、インターステイト80号に戻り、東へ向かった。約200キロ走ったところで、ネブラスカ州の首都リンカーン(Lincoln)に着いて、ここで昼食をとる。
ここでは、ネブラスカ州議事堂を見ただけで、南東に40分ほど車を走らせて、ステージコーチ湖(Stage Coach Lake)に着いた。この湖の周辺が州立保養地(Stage
Coach Lake State Recreational Area)になっており、ここのキャンプ場で 2泊してゆっくり休んだ。ここで記憶に残っているのは、潔典と湖で泳いだことくらいである。
7月5日、金曜日。みんな朝寝坊して、遅い朝食を取り、テントを畳んでキャンプ場を出たとのは11時過ぎであった。しばらく田舎道を走る。パナマ(Panama)、アダムス(Adams)、セント・メアリー(St.
Mary)を通って、アーバーン(Auburn)を過ぎたところでインターステイト29 号に乗る。一路南下して2時間近く走った後、カンザス・シティ(Kansas
City)に着いた。ここはすでにミズーリ州である。時間も中部標準時で、時計の針を1時間進める。
カンザス・シティは市街を通りながら周辺を眺めただけで、さらにインターステイト70号に乗って東へ進む。2時間ほど走ってコロンビア(Columbia)の近くまで来たところで、Texaco
のキャンプ場(Safari Camp Ground)を見つけて一泊する。一日5ドルで割高だが、トイレ、シャワー、洗濯室、食堂などのほか、プールもついていて快適であった。
翌日は、このキャンプ場のプールで泳いだり、広々とした芝生の上でフレスビーなどをしてゆっくり過ごし、昼食を取ったうえで、午後1時過ぎに出発した。ここからセント・ルイス(St.
Louis)までは車で2時間ほどである。
セント・ルイスに着いて、市内を車で一巡する。市の南にあるゲートウェイ・アーチは、高さは192メートルで最大幅は192メートルもある。セント・ルイスでは最も高い建築物で遠くからもよく見える。1965年に完成したセント・ルイス市のシンボルである。
この日は、市内の観光は翌日に延ばして、セント・ルイスのイリノイ州側、East St. Louisのカホキア・マウンド州立公園(Cahokia
Mounds State Psrk)のキャンプ場に早めに入った。州立公園というのはたいてい広々とした森林の中にあって環境も設備もよい。料金も1泊2ドル前後が普通だが、ここは1ドルであった。
7月7日、日曜日。テントの横のテーブルで遅い朝食をとった後、州立公園のなかの博物館に行ってみた。小さな博物館だが、ここが北米最古の村落跡ということで、原住民の住居の復元や生活用具などの展示品などにも厳粛といっていいような歴史の重みを感じさせられる。
テントはそのままにして、セント・ルイスへ引き返す。ダウンタウンの西7キロのフォレスト公園(Forest Park)へ行ってみた。ここは、1904年の万国博覧会の会場であったところで、敷地はニューヨークのセントラル・パークよりも広いという。
この公園のミズーリ歴史博物館は貴重な歴史的展示物が満載されている感じだが、次に訪れたセント・ルイス美術館は圧巻であった。モネ、ゴッホ、ルノアール等々、世界有数のコレクションといわれているだけに、数多くの名作がふんだんに目の前に次々と現れてくる。絢爛豪華なルネッサンスの絵画なども、鑑賞眼のない私のような者にさえ強く心に迫ってくるものがあった。
プラネタリウムに入り、動物園もちょっと覗いてみる。ダウンタウンを一まわりして、午後6時過ぎに、カホキア・マウンドのキャンプ場へ戻った。
翌日、月曜日の朝9時、キャンプ場を出て、一路、インターステイト70号を東に向かって走る。途中、サービスエリアで 2度休憩しただけで 360キロ走ってインディアナポリス(Indianapolis)に着いた。ここはもうインディアナ州である。時間も東部標準時で、また時計の針を1時間進める。
インディアナポリスは州都だけあって、高層建築が立ち並ぶアメリカでは有数の大都市である。車で市街をひと回りする。世界で最大規模を誇るという子供博物館(Indianapolis
Children’s Museum)が目当てであったが、行ってみると休館であった。恐竜が建物に首を突っ込んでいるという奇想天外な外観を見ただけで、また、インターステイト70号に戻り、東進を続ける。
リッチモンド(Richmond)を過ぎたところでオハイオ州に入り、150キロほど走り続けて、午後8時過ぎ、コロンバス(Columbus)郊外のモテル(Motel
40)に着いた。この日は、朝から約 670キロ走ったことになる。
5.ピッツバーグのフォスターの家
翌日、7月9日、ゆっくり朝寝坊して、コロンバス郊外のMotel 40を11時過ぎに出た。コロンバスはオハイオ州立大学がある学術都市で、当時の人口で約55万人の大都会である。「コロンバス」はアメリカに到達したクリストファー・コロンブスに由来するらしい。ダウンタウンを一巡して、科学博物館に入り、そのあとインターステイト70号に戻って東進を続ける。
車内では、たいてい、ラジオで常時放送されているクラシック音楽が流れていたが、子どもたちが好きであったジョン・デンバーのテープを聴いたりもしていた。歌詞で歌われている「天国のようなウエスト・バージニア」は、すぐ真下にある。
「カントリー・ロード」(Country Road)の歌も忘れがたい。“Country road, take me home. To the
place where I belong.”(この田舎道よ、故郷のわが家へ連れて行っておくれ)のメロディーを、私たちは身につまされるような思いで、何度も聴いた。私たちのユジーンの家は、もう何千キロも彼方である。しかも私たちはさらに、東海岸に向かってオレゴンから遠ざかりつつあった。
ケンブリッジ(Cambridge)を通り、コロンバスから 220キロ走ったところでペンシルベニア州に入った。遅い昼食を レストラン(Howard
Jonson’s)でとり、さらに車を東に走らせて、人口 2万人ほどの小さな町ワシントンで小休止する。 Dairy Queen でアイスクリームを食べたあと、ハイウエイ19号に乗り換え、北東に進路を変えて、30分ほどでピッツバーグ(Pittsburgh)に着いた。
ピッツバーグは、ペンシルベニア州では、フィラデルフィアに次ぐ第二の都市である。鉄鋼業をはじめとする製造業に支えられて発展してきただけに、工業都市のイメージが強い。ダウンタウンを走っていると、レンガ作りの古色蒼然としたビルが立ち並んでいる。
アメリカは、西から東へ行けば行くほど、街の古さが目立つようになる。このピッツバーグは、特に建物の古さが印象的であった。車を走らせながらも、大都市特有の喧騒に巻き込まれて、ひどく神経が疲れるような気がした。やっと郊外に抜け出し、モテルを見つけて泊った。
翌日、7月10日、水曜日。ピッツバーグ市内に戻って、フォスターの家を探す。スティーブン・コリンズ・フォスター(Stephen Collins
Foster)は、いうまでもなく19世紀半ばのアメリカ合衆国を代表する歌曲作曲家である。
彼は、このピッツバーグの隣町ルイスヴィルで1826年に生まれている。戦後、空襲で焼け野原になった大阪で、中学生の私は、英語の勉強を兼ねて、このフォスターの歌をよく歌っていた。「ケンタッキーの我が家」、「故郷の人々」(「スワニー河」)、「金髪のジェニー」、「オールド・ブラック・ジョー」などは、日本でもひろく知られていた。
フォスターの家は、なかなか見つからなかった。いろいろな人に訊いてみたが、ほとんど誰も知らない。やっと一人の老人に教えられて見つけた家は、白い3階建ての小奇麗な葬儀社になっていた。
次いで、街の東側にあるオークランドのピッツバーグ大学(University of Pittsburgh)を訪れる。広大な敷地である。46階の校舎(Cathedral
of Learning)を中心に壮大で華麗な校舎が散在している。そのうちの一つ、Cathedral of Learning の International
Rooms を見学した。一つ一つの教室が芸術品のように品格があり、入口中央部のラウンジは、中世の僧院を思わせるような荘厳さである。まったく“豪い”大学もあったものだと、感心させられた。
ここで、大学付属のフォスター記念館(Stephen Foster Memorial)を見る。500人が入れる堂々とした劇場の隣に、記念館はあった。フォスターの原稿、著書、楽譜、レコード、プログラム等のほかフォスターが使っていたピアノも置かれていた。
ピッツバーグ大学を出て、しばらく一般道を通って南下する。ユニオンタウン(Uniontown)でステイト・ハイウエイ40 号に入り、アディソン(Addison)を通ってインターステイト68号に乗った。このあたりは、もうメリーランド州で、アパラチア山脈に入り込んでいる。小雨が降っていた。
アパラチア山脈はロッキー山脈のように高くはない。車も何事もなく 2時間ほど走り続けて山脈を越えた。ヘイガーズタウン(Hagerstown)まで来て、インターステイト
68号は東南に向きを変える。68号はここから 70号に変わった。
30分ほど走ったところで、ワシントン・モニュメント州立公園(Washington Monument State Park)に着き、キャンプ場で一泊した。その日は、300キロほど走ったことになる。ここまで来ると、ワシントンD.Cも近い。車で1時間ほどの距離である。
6.ワシントンD.C からボルチモアへ
7月11日、木曜日。ワシントン・モニュメント州立公園のキャンプ場を10時過ぎに出て、インターステイト70号を東南に下る。フレデリック(Frederick)で270号に乗り換え、昼前にワシントンD.Cに着いた。
私が初めてここへ来たのは、留学生の時の1958年だが、その時とは様子が大分変わっているように見えた。16年の間に、随分観光客が増えている。かつては、ホワイトハウスの中にも入って見学できたのに、もう簡単に入れないようになっていた。車も増えて、空いている駐車場を探すのに一苦労する。リンカーン記念堂の裏にやっと駐車できて、巡回バス(Town
Mobile)のチケットを買い、主なところをバスで見てまわった。
ホワイトハウス、国会議事堂、ワシントン記念塔、トマス・ジェファソン記念館、アーリントン墓地等を見て、スミソニアン博物館に入った。ここで、月ロケットやリンドバーグの愛機(Spirit
of St.Louis)も目前に眺めた。
国立絵画館(National Gallery of Art)は、大理石造りの建物そのものの豪華さと、13~20世紀のヨーロッパとアメリカの絵画のコレクション約12万点という膨大さに圧倒される。世界の名画がふんだんに展示されているのに、ただ心を奪われるだけであった。
夕方、ワシントンD.Cを離れ、郊外に出たところで、インターステイト95号で北東のボルチモアを目指して走る。1時間ほどでボルチモアに着き、街の中心部でステイト・ハイウエイ40号に入り、郊外に出たところでハイウエイ沿いのモテルに泊まる。もう午後10時過ぎになっていた。ボルチモアでは、その翌日、オレゴン大学の同僚の増田さんと会うことになっていた。
すでに連絡はしてあったが、翌日11時ごろ、レイクサイト(Lakesite) の増田さんの寄宿先 Clark氏の家へ車で訪ね、久しぶりに歓談した。増田さんは、心理学が専門で、Clark氏とは共同研究の打ち合わせか何かでボルチモアに来ていた。明るく話し上手で、子どもたちにも人気がある。近くのレストランで昼食をご馳走になり、私たちの車で一緒に市内見物をする。
ボルチモアは、アメリカでも最も古い都市の一つで、街全体が古くくすんでいるような感じを受ける。まず、ボルチモア美術館に入った。この美術館は、世界最大というフランス人画家アンリ・マチスのコレクションで有名である。ルノアールやマチス、モネ、ファン・ゴッホ、ピカソ等の巨匠のすばらしい傑作を見てまわった。収蔵作品は 9万点を超えるらしい。
フォート・マクヘンリー(Fort McHenry)にも行ってみた。ここは、米英戦争中の1814年、チェサピーク湾に侵入したイギリス海軍の艦隊がボルティモア港を攻撃して来たときに、防衛に成功した星形要塞の遺跡である。フランシス・スコット・キーが詩「星の煌く旗」(The
Star-Spangled Banner)を作ったのがこの砦に対する艦砲射撃の時のことであり、これがアメリカ合衆国の国歌になった。
ボルチモアはまた、「野球の神様」といわれたベーブ・ルースが生まれたところでもある。野球の好きな潔典の希望で、ベーブ・ルースの生家と野球場をも訪れた。富子の希望で、エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe)が眠っているというボルティモア最古の墓地にも行ってみた。
このあと、アメリカの最難関校の一つで数多くのノーベル賞受賞者を出しているジョン・ホップキンス大学(Johns Hopkins University)を訪れる。緑の多い広大なキャンパスを歩いて、大学のカフェテリアで夕食を取った。一旦、増田さんを寄宿先へ送り、Clark氏ともちょっと話し合ったあとで、一路フィラデルフィアへ向かった。もう夜の 8時になっていた。
フィラデルフィアまでは、160キロほどの距離である。途中でモテルを見つけるつもりで、インターステイトには乗らず、ハイウエイ40号でゆっくり走っていくことにする。1時間ほど走って、そろそろモテルを見つけようと探しているうちに金曜日のせいであろうか、なかなか空いている部屋のサイン”Vacancy”
が目につかなかった。
エルクトン(Elcton)あたりでフィラデルフィア州に入り、そのまま走っているうちに、とうとうフィラデルフィアまで来てしまった。ダウンタウンまで入り込んで、あちらこちら、探したが、やはり見つからない。やっと郊外のホリデイ・インで部屋を見つけて、休んだ時には、午前一時近くになっていた。
翌日は、7月13日の土曜日である。暑い日であった。ホリデイ・インで朝寝坊して、遅い朝食をすませ、ホテルを出たのは午前11時である。フィラデルフィアはペンシルベニア州最大の都市で、自由の鐘や、独立宣言と憲法の宣言が署名された独立記念館などをはじめとするアメリカ革命にちなむ名所、旧跡が多い。
独立記念館(Independence Hall)、自由の鐘(Liberty Bell Center)、フランクリン博物館(Franklin
Museum)、ベンジャミン・フランクリンの墓、フィラデルフィア美術館などを見て、ペンシルベニア大学(University of Pennsylvania)へ行った。
この大学は、1740年にベンジャミン・フランクリンによって創立され、全米で初めて"University"と名付けられた名門大学である。この大学付属の有名な考古学人類学博物館へ行ってみたが、午後5時の閉館に間に合わず、入れなかった。
ペンシルベニア大学から東へ進み、フィラデルフィアの街の中心部を横断してデラウェア川を渡ると、そこはもう、ニュー・ジャージー州である。前日、モテルを見つけるのに苦労したのに懲りて、その日は、ニュー・ジャージー州に入ったところでモテルを見つけて早めに投宿する。モテルはプールもあって、潔典と二人で
30分ほど泳いだ。
7.アメリカの大西洋岸に到達する
7月14日、日曜日。モテルを10時に出発して、ニュー・ジャージーの州都であるトレントン(Trenton)へ行った。州都といっても人口5万人くらいの小さな町である。1679年、故国イングランドを追われ、新大陸にやってきたクエーカー教徒たちがここで植民地を建設したのが町の起源であるといわれている。
その日は日曜日なので、トレントンの街全体が静まり返っていた。商店街の店もほとんど店を閉じている。宗教の影響だろうか、近頃こういう街は珍しいと思った。ここで見るつもりであった博物館も閉館で、そのままプリンストンへ向かった。
ステイト・ハイウエイ1号線で北東に30分ほど走って、プリンストン大学(Princeton University)を訪れた。この大学は1746年設立のアメリカ屈指の名門校で、大学ランキングではハーバード大学と常に1,2位を争っている。アインシュタインも、かつてはこのプリンストンの町に住み、プリンストン高等研究所の教授であった。
私たちは、大学の正門前に駐車して、レストランで昼食を取ったあと、広いキャンパスのなかをゆっくりと歩いて見てまわった。大学のチャペル、学生寮、図書館、美術館などに入って、夕方まで過ごした。
プリンストンを出て30分ほど東へ走り、ハイツタウン(Hightstown)でモテルに入る。このモテルにも綺麗なプールがあって、潔典と二人で泳いだ。ここから、さらに1時間も東へ走れば、大西洋岸のアズベリパーク(Asbury
Park)に着くはずである。このアズベリパークは、1958年の夏、留学生時代の私が、ひと夏、アルバイトをしていたところである。
翌日、7月15日、月曜日、10時にモテルを出ようとしたのだが、車のバッテリーが上がってしまっているようでエンジンがかからず、困惑する。たまたま、モテルに居合わせたハーバードの学生だという黒人の若者が、自分の車のバッテリーに電線をつないで、エンジンを始動させてくれた。本当に救われた感じで有難いことであった。封筒に
5ドルを入れてお礼する。
一般道の33号をゆっくり東に進んで、昼前にアズベリパークに着いた。アズベリパークはニューヨーク都市圏の保養地である。大西洋を目の前にした砂浜には10メートルほどもあるような幅広いボードウォークが築かれ、周辺には土産物店、レストラン、劇場、コンベンション・ホール、カジノ・アリーナ、赤レンガ造りのパビリオンなどが、海に面して建ち並んでいる。
このボードウォークの北の端に、私がその16年前に働いていたホテルがある。オレゴンから、友人の学生たち4人で中古車に乗り、1週間かかって大陸を横断したのだが、この海辺に立った時、私には「遥々と来つるものかな」という感慨があった。今度も私は、4週間の旅路の末にここまで辿り着いて、同じような感慨にふけっていた。
私がアルバイトをしていたホテルは、バークレー・カートレット(Berkley Cartlet Hotel)といった。それが、「バークレー・オーシャンフロント」(Berkley
Oceanfront Hotel)と名前は変わっていた。
8階建ての建物は昔のままだが、やはり少し古ぼけて、かつての一流ホテルの品の良さは失われているような気がした。今度は家族4人で、昔の職場であったコーヒー・ショップで昼食を取ったが、ナイフとフォークはプラスチックで、料理も紙の皿で出されたことに今昔の感が深かった。
ボードウォークをしばらく歩いて、街の中をひと回りした後、ニューヨークへ向かう。ニューヨークまでは、80キロほどの距離である。アズベリパークから一般道35号を40キロ北上したところに、チーズクェイク州立公園(Cheesequake
State Park)があって、広大な森林が大西洋に接するようにして広がっている。そのなかにフックス・クリーク湖(Hooks Creek Lake)があり、湖畔には設備のよいキャンプ場があった。ここに数日滞在する予定にした。テントを張り、しばらく休んだ後、ニューヨークまでドライブした。
7月16日、火曜日。この日は、一日中、休息をとることにする。キャンプ場は森の中で空気も爽やかである。大西洋の風が吹き込んでくるらしく、暑くもなかった。私たちは、森の中を散歩したり、テントの横の椅子付きテーブルで本を読んだり、テントの中で寝転んだりして、長旅の疲れを癒した。夜、シャワーを浴びて、テントの中で横になりながら、私がアメリカの歴史の話をしていると、子どもたちもいつの間にか眠ってしまったようなこともある。
翌日は、朝から車でニューヨーク見物に出かけた。ゆっくり走っても、4,50分の距離である。ハドソン川の下を通るリンカーン・トンネルを経て、マンハッタンのミッドタウンに出る。
セントラルパークとニューヨーク市立美術館(The Museum of the City of New York)を見るところまではスムーズにいったが、路上の駐車メーターがついている場所の駐車は2時間がリミットである。エムパイアステイト・ビルに上がってみるためにやっと見つけた駐車場所は、建物から遠すぎて、歩いているうちに2時間では無理と判断してビルに上がるのは諦めたりした。
民間の駐車場では1時間 2ドル59セントで異常に高い。マンハッタンはほとんど車の中からの見物になってしまった。タイムズスクエア、ロックフェラー・センター、セントパトリック大聖堂などをゆっくり見てまわって、その日は、早めにキャンプ場に戻った。
ニューヨークには、私の知人で日本経済新聞の特派員をしている武田さんが家族と住んでいる。私たちがニューヨークに着いたら、電話をくれるように言われていた。夜、キャンプ場から電話して、明後日、武田さんの自宅に伺うことにする。
翌日は、長旅の疲れが出たからであろうか、富子が少し体調を崩しているので、終日テントで休養することにした。食料品などを仕入れに車で出かけたほかは、私もほとんど1日、キャンプ場で過ごした。
7月19日、金曜日、夕方には武田さんと会うことになっていた。テントは張ったままにして、昼頃ニューヨークへ向かう。夕方まで、また、マンハッタンを見て回るつもりにしていた。ところが、ホーランド・トンネル(Holland
Tunnel)を通りぬけてマンハッタンに入った途端に、車の底のシャフトのあたりがゴトゴト音を立て始めたのである。故障である。このまま放置することはできない。
バッテリー公園(Battery Park)へ向かってゆっくり走りながら、途中のガソリンスタンドで、少し離れた場所にある中国人経営の自動車修理工場を紹介してもらった。
「中国人経営」というのは悪いことではない。アジア人に対する差別意識が残るこのニューヨークのマンハッタンで、中国人や日本人が事業を経営していくのには、通常、白人たちに較べて、より優れた仕事ぶりを示し、サービスに努め、しかもより安価にしなければやっていけない。だから、修理技術もかえって信用できるのである。
私は、ゴトゴト小さな音を立てている車を慎重に運転しながら、やっとその修理工場を探し当てた。車を診てもらうと、ユニバーサル・ジョイントの部品を交換しなければならないという。結局、3時間かかって、部品を交換してもらった。車はまたもとのように調子よく走り出した。
オレゴンのわが家を出てから、すでに 5週目にかかろうとしている。ロッキー山脈越で車が止まってしまったり、ネブラスカでは真夜中の突然の嵐に、テントが吹き飛ばされそうになったりした。ハイツタウンのモテルで車が始動できなかったし、長旅の疲れが出て、富子も体調を崩している。そして今度は、このような故障である。オレゴンを出たばかりのはじめの頃はよくはしゃぎまわっていた由香利と潔典も、これが容易ならぬ旅行であることを、もう十分に、体で感じはじめていたようである。
子どもたちはワシントンの博物館で、リンドバークのスピリット・オブ・セントルイス号を見てからは、思い出したように大西洋横断飛行のことを話題にした。「翼よ、あれがパリの灯だ」には、実際、身につまされるものがあったらしい。もし、この車で無事ユジーンに帰れたら、このエンジンにキスする、と由香利が言ったりした。
なんとか車の故障の苦境を切り抜けて、武田さんとも予定通り会えるようになった。武田さんとは、ペンシルベニア駅前の大手出版社McGraw Hillで
6時半に待ち合わせる約束であった。リンカーン・トンネルを渡ってマンハッタンに入るとすぐ近くの所である。
まだ少し時間があったので、バッテリー公園から自由の女神を見たりした。それから北へ引き返して、6時半にMcGraw Hill のビルの入口で武田さんに会い、私たちの車に乗ってもらって武田さんのアパートへ向かった。
途中、武田さんの用事でちょっと国連に立ち寄る。そのあと、クイーンズボロ橋(Queensboro Bridge)でイースト川を渡って、クイーンズ通り(Queens
Blvd)を東に15分ほど走ると、エルムハースト(Elmhurst)に着く。そこのアパートに武田さんは奥さんと小学校のお嬢さんと3人で住んでいた。
久しぶりに武田さんの奥さん手作りの美味しい日本食をご馳走になり、子どもたちも一緒に賑やかに歓談した。アパートの一室にはテレタイプが置かれていて、東京の日経本社との交信の様子なども見せてもらった。午後10頃まで楽しく過ごして、夜のマンハッタンを一巡し、チーズクェイクのキャンプ場に帰った。
8.ニューヨークからボストンへ
チーズクェイク州立公園の朝は清々しい。小鳥のさえずりで目を覚ます。富子の体調はまだあまりよくない。長旅の疲れが取れないようだ。7月20日から23日まで、富子にはゆっくり休養を取ってもらうことにする。何度か、潔典と二人で食料の買い出しに車で出かけるほかは、私たちも、公園内を散歩したり、湖で泳いだり、テント横のテーブルに座って本を読んだりしてのんびりと過ごした。
7月24日、水曜日。この日は朝から小雨が降っていた。テントを畳み、車の中でおにぎりの朝食をとって、10時半、キャンプ場を後にする。ニューヨーク見物の予定を変更して、雨の中を、高速道路ニュージャージー・ターンパイク(現在はインターステイト95号)でボストンへ向かった。ニューヨークに着いてからは、ワシントン橋(Washington
Bridge)でハドソン川を越え、あとはインターステイト95号を走り続けるだけである。
すぐにコネチカット州に入り、ニュー・ヘブン(New Haven)を通って、ホプキントン(Hopkinton)の手前でロードアイランド州に入った。さらに北東へ進んでプロビデンス(Providence)を過ぎてマサチュウセッツ州に入る、ボストンに着いたのは午後5時ごろであった。ボストンの海岸に立って、眼の前にひろがる大西洋を眺めながら、私たちは、気が遠くなるくらいに遠く離れてしまった、小さなユジーンの町をなつかしんだ。
ボストンでは、ダウンタウンの一部と、マサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology)ハーバード大学(Harvard
University)などを見てまわって、郊外のレキシントン(Lexington)でホテルに泊まる。その日の朝からの走行距離は500キロを少し超えていた。
レキシントンは、アメリカ独立戦争の火ぶたが切られたところである。1775年4月19日、この町中央のバトル・グリーン(Battlegreen)と呼ばれる三角の緑地帯で、コンコードの植民地兵士群とイギリス軍とが初めて衝突した。私たちが泊ったホテルは、奇しくも、その緑地帯の前にあった。名前も、Battlegreen
Inn であった。
翌日、7月25日の朝食はホテルで取った。レキシントンという古戦場の歴史的遺跡の町だからであろうか、ホテルも品がよく、どこかよそとは違う感じである。人々の服装もきちんとしていて、互いに交わす朝の東部アクセントの挨拶も気持ちがいい。
ホテルの目の前の緑地には、独立戦争発端の記念碑である、銃を手にした独立戦争の農民兵士ミニットマンの像(Minute Man Statue)が立っている。私たちはそれを見てから、車でボストン市内へ向かった。
ハーバード大学、マサチュウセッツ工科大学をもう一度ゆっくり歩いて見てまわった後、ボストン交響楽団のシンフォニーホール、全米でもトップクラスのボストン美術館、ボストン虐殺地跡(Boston
Massacre Site)、旧州議事堂(Old State House)等も訪れた。ニューヨークなどと違って、どことなく落ち着きがあり、人が多い割にはこせこせしていない。街全体が何となく好ましい印象を与える。それまで見てきた都市の中では、もっとも好感がもてた。
午後2時ごろ、ボストンを出て、インターステイト 93号で北上する。間もなくニューハンプシャー州に入り、コンコードまで来てインターステイト 89号に乗り換えた。レバノンを過ぎたところでバーモント州に入った。
この辺から周辺に山々が目立つようになってきた。アパラチア山脈の一部になるのであろうか、グリーン山脈(Green Mountains)が前方に迫ってきているのである。1,200~1,300メートル級の山々の間を縫うようにして北西に進む。高度はあまり高くないが、上り勾配が続く時には、車のエンジンはやはり少し喘いでいるようであった。
ボストンから 320キロほど走ったところで、シャンプレーン湖(Lake Champlain)に面するバーリントン(Burlington)に辿り着いた。静かな美しい町である。ここで民間のキャンプ場を見つけて一泊した。
9.国境を越えてカナダへ
7月26日、金曜日。キャンプ場でゆっくり休んで、11時頃出発する。車のエンジンが一発でかかったときには子どもたちが歓声をあげた。やはりエンジンの調子を心配していたのであろう。バーリントンの街を一巡して、湖畔の道を北上する。1時間半くらいのドライブでカナダとの国境に着いた。入国手続きは簡単で、パスポートを見せるだけである。
国境からモントリオールに向かって北上する。道路も家も周囲の風景も、アメリカと同じようであって、どこか違う感じもする。1時間ほど走って着いたモントリオールでは、まず、ことばがフランス語であった。こちらが英語で答えると英語が返ってくる。バイリンガルの都市なのである。石造りの歴史的な建物と近代的な高層ビルが混在する街並みは、ヨーロッパの都市のようでもある。
ダウンタウンの中心部には巨大なマリア大聖堂(Mary Queen of the World Cathedral)がある。マッコード博物館やモントリオール美術館もあるが、ここでは中には入らなかった。重厚なバロック調のモントリオール市庁舎やセント・ローレンス川沿いの港の風景などを見てまわった後、モントリオールを出て私たちは初めて西に向かって走り始めた。オレゴンのユジーンを出発してから、その日でもう 1か月を超え、38日目である。
西に向かうということは、私たちにとっては素晴らしいことであった。やっと帰路につくのである。エンジンの音さえ、こころなしか快調に聞こえる。ここまで来ると、この車にも執念みたいなものが出てきて、もとの古巣へ辿り着くまでは、決して挫折しまいと奮起しているかのようであった。「人間でいえば、もう 80歳というところなんでしょうにね」と富子は同情し、私たちの車に対する労わりと感謝の気持ちも日ましにふくらんでいった。
モントリオールの南に位置するセントルイス湖(Lac St. Louis)は、西南に流れる長大なセント・ローレンス川でオンタリオ湖と繋がっている。そのセント・ローレンス川の川沿いの一般道路401号を280キロほど走って、オンタリオ湖畔のキングストン(Kingston)に着いた。
キングストンは、かつて(1841-1844年)は、カナダ連邦の首都が置かれた古都である。白亜の石灰岩を用いた歴史的建造物が多く残されていることから”Limestone(石灰岩)City”
とも呼ばれているらしい。古い街並みを一巡した後、食料品などを買入れて、湖畔の小さなモテルに泊まった。
アメリカドルがカナダドルに対して弱く、1ドルについて5セントずつ取られる。物価もアメリカに較べて高い。その日のモテルも小さくて古い割には、26ドルと安くはなかった。
翌日の朝、モテルでチーズのサンドイッチを食べ終わった頃から、時々、刺すような腹痛があった。薬を飲んで西へ西へと走り続ける。まだ前途は長いが、オレゴンへ近づいているということが励みになった。途中に立ち寄ったガソリンスタンドの店員が、私たちの車を見て感心する。オレゴンのナンバーをつけてこんなところを走っている
61年型シボレーがよほど珍しかったのかもしれない。
250キロほど走って、トロントに着き、市内を見てまわる。旧市庁舎(Old City Hall)と斬新な新なデザインの新市庁舎、美しいロマネスク様式のオンタリオ州議事堂、博覧会公園(Expo
Park)、世界最大級の大学といわれるトロント大学(University of Toronto)などを見たあと、オンタリオ湖の西端を半円状にまわって、ナイアガラの滝へ向かった。
トロントから 2時間ほどのドライブでナイアガラの滝に着いた。その日は7月27日の土曜日で、夏休み中の観光客も多く、車の駐車がちょっと心配であったが、運よく、空いている駐車場を見つけた。ナイアガラ公園に出て、しばらく、カナダ滝、アメリカ滝の景観を楽しむ。私は16年ぶりであったが、この雄大な景観には子供たちも圧倒されているようであった。
その後、もと来た道を引き返していく途中のナイアガラの滝キャンプ場(Niagara Fall Camping Site)で1泊することにした。民間のキャンプ場で、広々として芝生の美しいキャンプ場であった。
翌朝、Niagara Fall Camping Siteからハミルトンへ出て、その後は一路、西へ走り続ける。ロンドン(London)から南下してハイウエイ401号に乗り、ウェストローン(West
Lorne)、レイクショア―(Lakeshore)を通って、午後5時ごろ、ウインザー(Windsor)でセントクレア湖と繋がるデトロイト川に到達する。この川がアメリカとカナダの国境で、対岸がアメリカ・ミシガン州のデトロイトである。
デトロイトの街の中を通り抜けて、インターステイト94号に乗り、アナーバー(Ann Arbor)まで行った。ミシガン大学(University
of Michigan)の所在地である。この大学は、日本では、英語教育で有名である。私は中学生の時からこの名前を覚えていて、憧れの大学であった。
ミシガン大学に立ち寄り、キャンパスを見てまわった後、また、インターステイト94号に乗った。一路、西に進んで、ジャクソン(Jackson)を通り、カラマズー(Kalamazoo)を過ぎ、ミシガン湖の湖畔の町セント・ジョーゼフ(St.
Joseph)に午後8時過ぎに辿り着いた。このミシガン湖の対岸はシカゴである。ここで、民間のキャンプ場 KOA に一泊した。設備はよいのだが、蚊が少しうるさかった。この日の走行距離は約560キロである。
キャンプ場の公衆電話で、シカゴに住んでいるという Mrs. Knipe に電話する。私の母方の遠い親戚にあたるらしいのだが、私はよく知らない。母から聞いたのであろうか、ユジーンの私たちの住所へ、夏休みの旅行の際には是非立ち寄ってくれるよう手紙が来ていた。シカゴへ着くおよその日程はすでに知らせていたが、明日の夕方訪問することを伝えた。
10.遠い親戚と知人からの歓待
7月29日、月曜日。午前4時、激しい雷雨の音で目を覚ます。雨が漏れるわけではないが、テントは雨には弱い。テントを叩きつけるような雨の音も耳障りであった。子どもたちを車に移して、車の中で眠らせた。
雨は8時ごろにはほとんど止んでいた。9時過ぎに KOAを出発する。目の前には、ミシガン湖の砂浜が美しく広がっていた。ミシガン湖の底辺を半円状にまわって、2時間ほどでシカゴに着く。シカゴは、アメリカでは、ニューヨーク、ロザンゼルスに次ぐ第三の大都会である。ダウンタウンの摩天楼の景観は圧巻であった。
ミシガン湖畔のグラント公園(Grant Park)へ行ってみる。広大な敷地の一隅にフィールド博物館(Field Museum)がある。入館すると、天上の高い広々としたホールには、アフリカ象や恐竜の骨格が置かれている。2階のネイティブ・アメリカン文明の展示は、全米の先住民の生活様式を地域ごとに見ることが出来て興味が尽きなかった。
公園の北端には、シンフォニー・センターの隣に、シカゴ美術館もある。メトロポリタン美術館、ボストン美術館と並んで、アメリカでは三大美術館の一つといわれている。ゴッホの自画像、セザンヌの「リンゴの篭」、エル・グレコの「聖母被昇天」などのほか、モネの収蔵作品は、フランス国外では最多であるらしい。美術の好きな富子は飽かずに見ていたが、展示作品はあまりにも膨大である。小学生の子どもたちは、いささか食傷気味であったかもしれない。
近代的で賑やかなダウンタウンを車で見てまわったあと、Mrs. Knipeに電話して道順を聞き、午後5時過ぎに彼女の自宅へ伺った。初対面である。ご主人のEdwardはドイツ系のアメリカ人で、鉄鋼会社に勤めている中堅社員のようである。利発そうな顔つきの小学生の女の子が一人いる。自宅の2台分車庫には、キャンピング・カーもあって、生活も豊かなようであった。
小奇麗な家の食堂で、大きなビフテキをご馳走になった。子どもたちも久しぶりの家庭料理で満足したようである。Mrs. Knipeは、Terry
といった。彼女も女の子の Alice もなつかしそうにいろいろと子どもたちにも話しかけてくる。遠い親戚でも、温かみが伝わってきて有難いものである。その夜は、大きな寝室を使わせてもらってゆっくり休むことが出来た。
翌日は、10時ごろMrs. Knipe宅を出る。Edward は7時過ぎにはもう出勤していて居なかったが、会社から電話をかけてきて、私たちの旅行の無事を祈ると言った。思いがけないもてなしを夫妻に感謝しながら,私たちは、シカゴからハイウエイ20号で西へ向かった。
アイオワ州のウォータールー(Waterloo)に、ユジーンで親しくしているヘイゼル( Hazel) の弟さんが住んでいる。Hazelは、私が留学生時代に世話になった
International House のオーナーであった。日本にもやって来て、私たちのところに数日泊ったこともある。私たちが、またユジーンに住むようになってからも、彼女とは親しく付き合っていた。私たちが旅行でアイオワを通るときには、弟の家に寄るように言われていたのである。彼女の弟さんのWillard
にも、旅行の途中、アイオワ到着の予定などを連絡はしていた。
シカゴからハイウエイ20号を250キロほど走ると、ダビューク(Dubuque)のあたりでミシシッピ川にぶつかる。川を越えるとアイオワ州である。ダイアーズビル(Dyersville)、デラウェア(Delaware)を通って、ウォータールーには午後4時頃に着いた。
公衆電話で Willard に電話したら、迎えに行くからその場所で待っていてくれるように言われる。すぐWillard と奥さんの Ruth
がクライスラーの新車に乗ってやってきた。現在、息子夫婦とHazelの姉妹たちが泊りにきているので部屋に余裕がなく、私たちの宿泊はホテルを予約してあるという。
ラマダ・インまで案内してくれて私たちの部屋の鍵をもらったあと、私たち家族4人は夫妻のクライスラーに乗せられて、街を一巡したあと、Willardの家へ連れていかれた。
庭の広い高級住宅であった。高校教師をしているという息子のBob夫妻、Hazel の姉、妹さん夫婦に紹介され、賑やかな歓談が続いた。豪華な夕食をご馳走になって、ホテルへ送られたのは10時過ぎである。立派なホテルで、立派な部屋に泊まることが出来て、私たちはのびのびして甦ったような気がした。
翌日の昼前まで、ぐっすりと眠る。午後2時、Willard夫妻がホテルへやって来た。ホテルのカフェテリアでみんなで遅い昼食をとり、Willardのクライスラーでいろいろと街のなかを見物させてもらう。高級車クライスラーの新車であるだけに車内も広く快適である。奥さんのRuthは無類のお人好しで、由香利たちにもいろいろと優しく語りかけてくれていた。
Hazel が通ったという北アイオワ大学(University of Northern Iowa)を見学し、アイオワ州で一番古いというホープ・マーティン劇場を訪れ、歴史・科学博物館(Grout
Museum of History and Science)や中央図書館(Central Public Library)、ウォータールー美術館(Waterloo
Center for the Arts)なども見せてくれた。ガイド付きで贅沢な見物になった。
街の中では、あちらこちらに“Granger Association” という不動産の看板や事務所があった。Willard夫妻のもう一人の息子さんの経営で、ウォータールーには100エーカーの広大な土地も持っているらしい。今乗っているクライスラーの新車も、その息子さんからプレゼントされたものだとWillardは言った。
夕方になって、広いショッピングセンターのレストランで夕食をご馳走してくれたあと、午後8時過ぎ、Willard夫妻は、私たちをラマダ・インまで送り届けてくれた。念のためにロビーのカウンターで訊いてみたら、ホテル代はすべてWillard夫妻が支払ってくれているという。このウォータールーでは、随分お世話になって、恐縮のほかはなかった。
11.オレゴンに近づいていく旅
翌日は8月1日である。ユジーンを出てから 44日目であった。9時ごろホテルを出て、小雨の中をWillard夫妻の家へ行き、お礼とお別れの挨拶をした。ウォータールー市内のガソリンスタンドで、残りのタイヤ1本を新品に替え、オイル交換をすませて約50ドル支払う。あとは一路ステイト・ハイウエイ20号を西へ走り続けるだけである。
350キロほど走って、スー・シティ(Sioux City)に着き、ミズーリ川のほとりのキャンプ場で泊まろうとしたが、テントを広げてみると、先日のミシガンでの雨以来濡れたままであったので、ハエに似た虫が大量に発生していた。
テントをしばらく乾かし、薬を散布して虫退治をしただけで、ここは引き揚げることにした。空模様も少し怪しくなっている。すでに午後6時を過ぎていたが、その夜は走れるだけ走って、車で眠ることも覚悟する。
スー・シティからサウス・ダコタ州に入る。西に進むにつれて、だんだん緑が少なくなり、褐色の荒れ地の大平原が続くようになった。車の後方では、遠くで雷が鳴り雨の気配がする。雷の音は度々轟音を響かせながら近づいてくるようでもある。大平原の夕闇の中を雷に追われながら鬼ごっこをしているような形になった。子どもたちは面白がって、12時過ぎまで後部座席ではしゃいだりしていた。
午前2時、眠気がしてきて、ハイウエイのレストエリアで仮眠をとることにした。天気は晴れていた。レストエリアには、ほかにも沢山車が停まっていて、それぞれに仮眠しているようであった。レストエリアに入ってきたと思ったら、さっさとスリーピングバッグを芝生の上に広げて、そのまま眠ってしまうような勇ましい女性の一団もあった。
朝6時半、レストエリアを出てインターステイト90号を西進する。スー・シティからは 660キロほど走ったところで、ラピッド・シティ(Rapid
City)に着いた。
このあたりからは、砂漠の中のオアシスのように緑が目立つようになり、前方にはブラックヒルズ森林公園(Black Hills National
Forest)の低い山並みが連なっている。このラピッド・シティのレストランで遅い昼食をとり、近くの KOAキャンプ場でテントを張った。少し疲れて、テントの中でゆっくり休んだ。
このラピッド・シティから南西に約40キロにマウント・ラシュモア国定記念物(Mt. Rushmore National Monument)がある。ジョージ・ワシントン(初代)、トーマス・ジェファソン(3代)、セオドア・ルーズベルト(26代)、エイブラハム・リンカーン(16代)の 4人の大統領の顔が、左からこの順に花崗岩の岸壁に彫り込まれているのである。
是非見たかったのだが、その山自体の高さが1,745メートルなので、また坂道を上っていかねばならない。車のエンジンに無理がかかるのを避けて、見学は諦め、そのまま西へ走り続けた。
インターステイト90号は、ブラックヒルズ森林公園の山並みを避けて半円形に迂回してワイオミング州に入る。州境から 300キロ近く走ってシェリダン(Sheridan)に午後5時頃に着いた。ここでも民間のキャンプ場
KOAで一泊する。KOAはトイレやシャワーの設備もよく、きれいなプールもついている。潔典と二人で、ここでも少し泳いだ。
翌日は、8月4日で日曜日であった。シェリダンを朝9時半に出て、北に少し進むと、もうモンタナ州である。インターステイト90号は山並みを避けてしばらく北へ向かう。州境から約60キロのガリョーエン(Garryowen)には、カスター戦場博物館(Custer
Battlefield Museum)があり、その少し北にはカスター国立記念戦場(The Custer Battlefield National
Monument)がある。私たちは、その戦場の跡地を訪れた。
1876年6月25日、カスター将軍が率いる米軍第7騎兵隊が、宗教行事で集まっていた総勢約1,500名のダコタ族とラコタ族のスー族、シャイアン族、アラパホ族のインディアン同盟部族に戦いを仕掛けた。戦闘が始まると、カスター隊は
2時間も経たないうちに追い詰められて、カスターと部下225名が全員戦死した。インディアン側は、スー族だけで136人戦死し、160人が負傷したというのが、この「カスターの愚行」といわれる戦闘の概要である。
この戦闘は、ビグホーン川の周辺で行われたので、今では、ビグホーンの戦跡(Bighorn Battlefild)と呼ばれているらしい。
1時間ほど、戦跡やカスター将軍たちの墓地を見てまわり、子どもたちは絵葉書や本を買ったりした後、私たちはまた、インターステイト90号に戻った。この90号は、ハーディン(Hardin)からまた西へ進むようになる。
イエローストーン国立公園の北部、ビリングス(Billings)を過ぎるあたりからロッキー山脈の山々が見え始めた。ハイウエイ90号は、イエローストーン国立公園北側の山脈の山々の合間を縫うようにして通っている。このあたりのロッキー山脈はコロラド州で通過した高度
3,446メートルのバーサッド峠(Berthoud Pass)に較べれば、かなり低い。最初の峠を無事に越え、二つ目の峠の大陸分水嶺(Continental
Divide)約1,800メートルも何とか無事に越えた。
やがてリビングストン(Livingstone)、ボーズマン(Bozeman)を経てビュッテ(Butte)に着いた。かつて銅鉱山のブームに沸いた山の中の小さな町である。ここのキャンプ場
KOAでその夜は休んだ。
翌日の8月5日、月曜日、私たちはテントを畳んで、ビュッテの世界鉱山博物館(The World Museum of Mining)を観に行った。この銅鉱山には、”The
Richest Hill on the Earth” というサインが掲げられているが、巨大な銅採掘現場などを見ていると、なるほどと思わされる。お土産用に、銅製のスプーンをいくつか買う。
昼頃、インターステイト90号を西に進む。ロッキー山脈の山々がまだ続いていたが、それもこの辺ではあまり高くはない。ミズーラ(Missoula)を過ぎ、ロウロ国立森林公園(Lolo
National Forest)の中に入って、山の中の小さなセント・レジス(St. Regis)の町に着いた。この日も民間のキャンプ場 KOAで、テントを張ることにする。この日の走行距離は約300キロであった。
このキャンプ場は新設されて間もないらしく、トイレやシャワーなどの設備は清潔そのものであった。従業員たちもみんな親切で気持ちがよい。
セント・レジスを10時過ぎに出て、西へ向かって走って行くと1時間足らずで、モンタナ州からアイダホ州に入った。このあたりは、まだ低い山々の中を走っている感じである。ウォレス(Wallace)、ケロッグ(Kellogg)を経て、パインハースト(Pinehurst)まで来たところで、まだ昼前であったが、ここの
KOA で一泊することにした。ここのキャンプ場も設備がよい。
オフィスの新聞自動販売スタンドで、新聞を買おうとしたら、潔典がお金を入れるのを自分にやらせてほしいという。潔典が 25セントのコインを入れると、新聞と共に、お釣りがじゃらじゃらと、おそらく1ドル以上も出てきた。潔典は興奮してちょっとした騒動になった。アメリカの機械は、どうも少しいい加減なところがある。
ここから、隣のワシントン州スポケーンまでは約100キロのドライブである。私たちは、そのスポケーンで開催中の万国博覧会を観に行くことにしていた。その4年前の大阪万博にも私たちは出かけている。1962年にレイチェル・カーソンが『沈黙の春』を出版して以来、アメリカでも水質汚染や公害が広く注目されるようになっていたが、「汚染なき進歩」というテーマで開かれるアメリカの万博がどういうものか興味があった。
12.スポケーンの万国博覧会を観てオレゴンへ
8月7日、水曜日。朝7時半にパインハーストを出て、スポケーンに向かって走る。スポケーンの キャンプ場 KOA では、なんとかキャンプ・サイトが取れた。ここで2泊の予約をする。
KOAから万博会場までバスが出ている。12時半のバスで会場へ行ってみた。先ず日本館に入ってみたが、なかは随分質素な内容と飾りつけで驚いた。中国館(台湾)のほうが豪華で、ショーが終わった後も観客から大きな拍手を浴びていた。韓国館も華やかな舞踊で観客を盛り立てていた。
大阪万博では、1969年秋に宇宙船アポロが持ち帰った「月の石」がアメリカ館で展示されて人気を呼んだが、このスポケーンのアメリカ館では、特に評判になるような展示物は何もなかった。大きなパビリオンに農業機械などを含めて、ありふれた展示物だけが並べられているように見える。カリフォルニア州やオレゴン州の州博覧会とあまり変わらないような気がした。
どの国の出品も目覚ましいものはなく、極力予算を少なく抑えているようであった。大阪の万博のような華やかさは全くない。ただ、入場者が少ないのは大助かりであった。どこへでも並ばないですぐに入れた。
売店で土産物を見ていたら、偶然、ポートランドから来ていた武部さん一家に出会った。武部さんはポートランドの大学医学部で客員研究員をしている医師である。ポートランドで
5月下旬から開催されていたバラ祭りの時には、私たち家族4人は、ユジーンから出かけて行って、お宅に泊めていただいた時以来の再会であった。
その日は、会場のレストランで夕食を取り、ゆっくりと会場を歩き回って、10時のバスでキャンプ場に戻った。
翌日は、朝9時25分のバスでまた万博会場へ行く。前日の夜は少し雨が降ったが、朝には止んで晴天であった。前日とその日の二日間で、会場のほぼ全部を一通りまわってみることが出来た。
新聞などでは、1日の入場者数は約3万5千人と報道していたから、大阪万博の10分の1以下でしかない。大阪万博では会期中の全入場者は 6,400万人であったが、このスポケーンの万博では、5月4日から11月3日までの会期中の全入場者数は
480万人に留まったようである。
夕方6時のバスで、KOA へ引き返したが、一日中歩き回ってさすがに少し疲れた。ソ連館で買った小イワシの缶詰を開けてビールを飲み、早めに寝る。
8月9日、金曜日。スポケーンを10時半に出て、一路、西へ向かって走った。オレゴン州はすぐ隣である。ユジーンを出発してすでに52日目である。なんとかやっと無事に帰れそうである。西に向かって走り続けていると気持ちが和んだ。
途中のガソリンスタンドで、ガソリンを入れたついでにエアクリーナーを交換したら、急に車の加速が利くようになった。それまで、急な坂道を上がる度にエンジンがかすかな不調和音を出していたのは、エアクリーナーの汚れが一因であったのかもしれない。
カスケード山脈の1,000メートル級の山々の間を縫うようにしてインターステイト90号で上り下りを繰り返す。モーゼス・レイク(Moses Lake)を通り、エレンズバーグ(Ellensburg)で左折して(Yakima)に着き、そこからはステイト・ハイウエイ97号でトッぺニッシ(Toppenish)へ向かった。
トッぺニッシからはほぼ一直線に南下する。100キロ近く走ってメアリーヒル(Maryhill)に着いた。ここはワシントン州の最南端である。コロンビア川に面していて、この川を渡ればオレゴン州になる。川を渡って遂にオレゴン州に入った。
インターステイト84号に乗って、コロンビア川に沿って西へ向かう。ダレス(The Dalles)を通り、フッド・リバー(Hood River)を通る。そこからさらに50キロほど川沿いを走り続けてマルトノマの滝(Multonomah
Falls)に着いて小休止した。
この滝は、落差 165メートルの上部と 21 メートルの下部の二段に分かれ、間には 3 メートルのなだらかな滝があり、全体の落差は189 メートルである。私たちは以前にもここに来たことがあり、いよいよオレゴンに帰ってきたのだという実感が湧き上がってきた。
マルトノマの滝を出てポートランドを通り、インターステイト5号で南下して、セイラム(Salem)に着いた時には、午後10時近くになっていた。朝スポケーンを出てから、すでに
670キロも走っている。
セイラムはオレゴン州の州都である。その年の春休みのオレゴン州周遊旅行の時には、州議事堂に知事を表敬訪問したのだが、トム・マッコール知事(Tom
McCall)が由香利と潔典を抱きかかえるようにして一緒に写真に収まってくれた。子どもたちにとっても思い出の地である。
この日は、そのままユジーンまであと100キロを走り続けられないことはなかったが、さすがに疲れが溜まって眠気に襲われるようになった。無理を避けて、近くの
KOA でテントを張って眠ることにした。翌日、ゆっくり朝寝坊して、ユジーンのわが家に帰りついたのは昼頃である。こうして、とうとう、53日間、走行距離約17,000キロのアメリカ一周旅行は終わった。
* * * * *
この旅行では、私たちは「予想通り」、いろいろな困難に遭遇した。ロッキー山脈越えで、酸欠とオーバーヒートのためか車のエンジンが完全にストップしてしまったことは忘れられない。ネブラスカでは真夜中の突然の嵐に、テントが吹き飛ばされそうになった。子どもたちが小さな力をいっぱいに出して、テントの中から必死にポールを支えていた情景は、いまもありありと眼の前に浮かぶ。アパラチア山脈では、壮絶な雷に追いまわされ、ニュー・ジャージーの森の中では、旅の疲れで富子が寝込んだ。車もニューヨークのマンハッタンの真ん中で、二度目のトラブルを起こして立ち往生する・・・・・・。
モントリオールまで行って、初めて進路を西に向け帰路についた時には、子どもたちは歓声をあげた。西への道も、文字通り平坦ではなかったが、確実に一歩一歩、オレゴンに近づいているということは、大きな励みであり、慰めであった。アイオワの平原で、モンタナの山中で、あるいはワシントンの渓谷で、私たちは日焼けし、汗にまみれて、興奮や涙や、時には笑いのシンフォニーを奏でた。子供たちのこころの中には、それらの余韻がいつまでも尾を引いていたであろう。
数々の思い出を残して、無事ユジーンに辿り着くまで、こんな古い車で17,000キロも走り続けることができたのは、やはり、僥倖であったというほかはない。
私たちは、このあと、2週間休んで、ヨーロッパ旅行に出かけた。経費を切り詰めた貧乏旅行であったが、こういう旅行からは学ぶことが多い。それを「思い出の旅」(1)に書いた。
あれから、44年が過ぎた。いまは富子も潔典も亡く、私は思いがけずに長生きして、今年も「9月1日」を迎えた。事件から35年目の供養の日である。私は、そう遠くない将来、霊界で再会するであろう彼らとの歓談のためにも、この日に、この彼らとの共通の思い出話の一つを、こうして書き留めておくことにした。
(2018.09.01)
|